
なぜ用宗のしらすはおいしいのか? しずまえ鮮魚の魅力に迫る
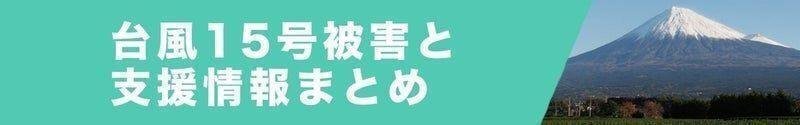
令和4年10月15日、静岡市の用宗魚港で「しずまえ用宗しらす漁丸ごと見学ツアー」が開催されました。
こちらは、子どもたちにしらす漁や競り、加工の様子を見学してもらい、静岡市の前浜、通称「しずまえ」で獲れる海産物を身近に感じてもらうためのイベントです。
▼ツアーの様子はこちらからご覧になれます▼
静岡みんなの広報は、用宗魚港の関係者の方々に、用宗のしらすがおいしい理由や漁港でおこなわれている取り組みについて伺いました。
(協力……経済局 農林水産部 水産漁港課 しずまえ振興係)
しらすの鮮度に隠された秘密

用宗のしらすは、とにかく鮮度がピカイチです。新鮮なしらすが一番おいしいですからね。「お客様の手元までいかに早く届けるか」ってところが重要です。
用宗港がどのようにしてしらすの鮮度を保っているかというと、その作業工程に秘密があります。
まずは、なんといっても港と漁場の近さ。しらすの漁場は用宗港の目と鼻の先なんです。そのため、獲れたしらすを港まですぐ持ち帰ることができます。
しらす漁の仕方にも工夫があります。
用宗ではしらす漁を漁船三隻でやっています。じつのところ漁をするだけなら二隻で足りてしまいます。なのになぜ三隻でやっているかといえば、作業スピードを上げるためです。

二隻で網を曳いてしらすを獲り、残りの一隻で水揚げしたしらすを急いで港に運ぶんです。一隻は運搬専門の船ということですね。漁船の役割を分けることで、しらすが傷む前に港まで持ち帰ることができます。
持ち帰ったしらすはすぐ競りにかけられ、出荷準備が進みます。箱詰めしたり、釜揚げしらすにするものを煮たりするわけです。

この工程では、なるべくしらすに人の手が触れないように気を遣っています。空調の管理されたルートをしらすが通ることで、熱や雑菌でしらすの鮮度が落ちることを防いでいます。
今では瞬間冷却する技術が発達して、無凍結のままの生しらすを届けることもできるようになりました。

しらすはその日のうちに全国に向けて出荷されます。こうして用宗のしらすは、北は北海道、南は九州まで、みなさんの食卓を賑わせています。
鮮度の良い用宗のしらすを、ぜひ食べてみてください。
恵まれた自然が育む静岡のしらす

静岡は魚がおいしく育つための環境が整っています。そのように言える理由は主に三つですね。
一つ目は黒潮の影響です。
黒潮とは日本列島に沿って太平洋を流れる暖かな海流のことです。黒潮は多くの魚を静岡の海に運んできます。その中にはしらすの親となるイワシの仲間たちもたくさん含まれているんです。
二つ目は、大きな川が近くを流れていることです。
用宗は安倍川、富士は富士川、浜松は天竜川が港のすぐそばにあります。川の水には山の栄養分がたくさん溶け込んでいて、魚のエサとなるプランクトンを育ててくれます。

三つ目は静岡が日本一深い湾、駿河湾を擁していることです。
その最深部は2,500メートルもあると言われています。その深い海の底から、栄養満点の海水が昇流によって運ばれてきます。
栄養のある水でエサになるプランクトンが増え、そのプランクトンを食べて、しらすもおいしくなるわけですね。
海を守る用宗漁港の取り組み
しらす漁には禁漁期間というものがあります。簡単に言えば、「魚を獲っちゃいけない期間」ってことですね。
そんなわけで、3月21日から翌年の1月15日まで、僕らは海に出ることができません。

なぜ一ヶ月以上も漁をしてはいけない期間があるかというと、海の生態系を守るためです。漁師がしらすを獲りすぎてしまうと、海の環境が崩れ、魚たちが住めなくなってしまいます。
すると近い将来、漁師たちも漁ができなくなってしまう。そうならないためにも漁師は海の環境を気にしながら漁をする必要があるんです。
ただ、しらす漁に出られない漁師たちは、その間、仕事を失ってしまいます。仕事ができないと、それはそれで困ったことになりますよね。
そこで用宗魚港では禁漁期間中、ワカメやアカモクといった海藻を育てる取り組みをしています。種から育てた海藻は、ちょうど3月ごろに収穫ができるようになり、禁漁期間中の収入源として漁師たちの生活を支えてくれています。

とくにアカモクは昨今、栄養価の高いスーパーフードとして注目を集めています。ダイエットやアンチエイジングにも効果があると、若い方たちの間で話題になっているそうですよ。
こういった漁港の小さな取り組みも知ってもらえると嬉しいですね。
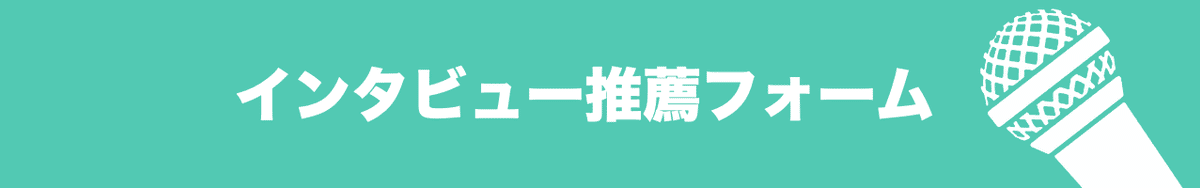

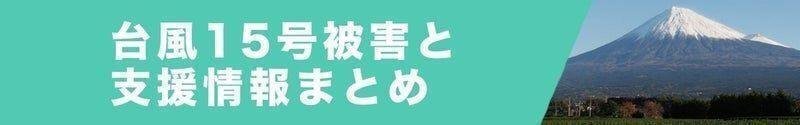

いいなと思ったら応援しよう!

