
【質問箱】 誰のために書くのか
素晴らしい質問をいただきました。
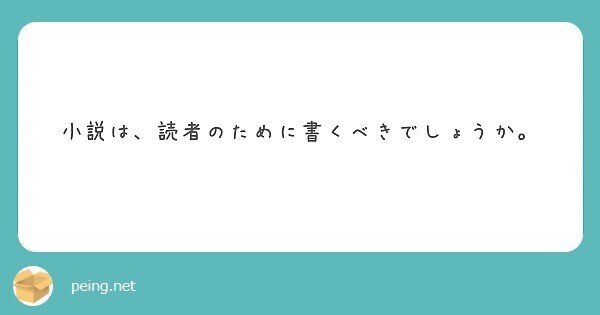
小説は、読者のために書くべきでしょうか。
難しい質問です。奥が深い質問でもあります。
編集とか関係なく、一創作人として私見を書き留めておきます。
あくまで私なりの答えとして言いきりますが、
読者のためだと思います。
もちろん、小説――とりわけ私小説には、少なからずプライベートな性質があることは事実です。内省の記録であったり、自己治療の一環であったり。小説を書くこと自体が「癒し」になったりもするんですね。
自分が面白いと思うものを書くのだから、そりゃ心の底から面白いはずです。他人の誰よりもいちばん自分が楽しめる、最高のエンターテインメントです。
いやいや、書いている最中は苦しい、ひたすら苦しいよという人もいらっしゃるかもしれません。しかしそれも「産みの苦しみ」というやつです。なぜわざわざ苦しみながらも、長い時間を割いてまで、私たちは書こうとするのか。それはやっぱり、出来上がったものがメチャクチャ面白いからです。少なくとも、メチャクチャ面白いものを目指して書いているはず。ときには理想とする文章表現に辿り着けず、悔しい想いをすることもあるでしょう。もどかしく、絶望することもあるでしょう。しかし、頭のなかには「メチャクチャ面白いもの」のイデアがあるはずです。でなければ、小説の1行目を書き出すゴーサインが出るはずはありませんから。
プロの作家にも、
「自分の作品がいちばん面白い」
「普段は自分の書いた本しか読まない」
と豪語して憚らない先生が複数いることを、私は知っています。
何千部、何万部もの出版経験があるプロでさえ「もっぱら自分の楽しみのために」という原点を忘れないでいる人がいる。そういう生きかたは、とても幸福だなぁと思います。
かように小説創作とはごくごく私的で個人的な側面のある行動なのですが、それでもなお、私は読まれるために書くものだと思っています。
なぜか。
それは「なぜ文章でなければならなかったのか」という問いに対する答えでもあります。
音楽や朗読ならば、耳で聴いた音の情報そのものが伝わります。
絵画や工芸やダンスならば、目で見た光の情報そのものが伝わります。
ドラマや映画ならば、光と音の情報そのものが伝わります。
ゲームならば、コントローラーでの操作感をプレイヤーの手許で再現させることができるでしょう。
しかし、小説が読者に喚起するものは、決して均質ではありません。
読者ひとりひとりによって、喚起させられる情景は多かれ少なかれ異なるはずです。
なぜなら、この質問箱シリーズでも何度か書いてきたとおり、言葉が借りものでしかないからです。文章とは、所詮は代替物、記号の羅列でしかありません。小説が頼るのは、ひとえに読者の記憶です。文章を通じて、読者はそれぞれ異なる記憶を喚起され、情景を思い浮かべます。
なぜ言葉は借りものなのか。
取りも直さず言葉が徹頭徹尾、伝達手段だからです。
(ジョン・ケージの『4分33秒』は芸術作品として成立していますが、白紙の本は『小説』とは決して認められないでしょう。ただのメモ帳です)
情報を伝える媒体として成立させるためには、著者と読者のあいだに共通認識がないことには始まりません。
著者が「犬」と書いた動物について、読者が「ニャアと鳴く肉球のある愛らしい動物」を思い浮かべたら、ディスコミュニケーションとなってしまいます。その時点で、著者が意図した表現は失敗に終わってしまいます。
音楽でもイラストでも芝居でも、表現形態はなんでもよかったはずなのに、なぜ文章でなければならなかったのか。なぜ私たちは小説を書かずにはいられないのか。
それはもう、誰かに読んでもらうためでしょう。
でなければ、借りものの共通認識を使う必要はありません。
もっぱら自分の楽しみのためにだけ書く小説ならば、作中に「犬」と書いた部分から、自分の認識世界でだけ「ニャアと鳴く肉球のある愛らしい動物」を想起しても一向に構いません。しかし、そんな面倒なことをする人はいないはず。
小説とは異なりますが「日記」だって、非常に個人的なものであるはずなのに、学校の先生に読ませるために書いたりしますよね。
そもそも大昔の紀貫之さんが「男もすなる日記というものを、女もしてみんとて、するなり」って書いてるんですよ。
男の紀貫之さんがですよ。
「男の人たちが書いている日記ってやつをぉ~、アタシも書いてみよっかなぁ~なんて思って、書きます☆」
とか性別を偽って書いてるんですよ。
ただただ自分の備忘や癒しために書いているんだとしたら、ヤベェやつじゃないですか。
未来永劫、国語の教科書に晒され続けるんですよ?
そんで「日記文学」とか呼ばれて、価値あるものとして有難がられるんですよ?
とんでもねぇ恥じゃないですか。
しかし、紀貫之さんはおそらく、最初から他人に読まれることを想定し、なにひとつ恥じる顔せずに書いていたと思われます。当時、女たちの専有物だったひらがなを使って、女性の筆に仮託して「男のもの」だったはずの日記を、やわらかく表現しようとした。とんでもなく挑戦的で、かつスマートな試みです。
なぜか?
他人に伝えるためです。
おかげで『土佐日記』は、日本文学はおろか、日本の言語文化全般に多大な影響を与えたわけですから、この伝達は世紀の大成功でした。
まさか紀貫之さんも、自分の書いた文章が未来のnoteの片隅でネタにされるとは、思ってもみなかったことでしょう。
以前も書きましたが『壇蜜日記』も、あれは正しく読まれることを想定した文芸の一形態ですよ。「壇蜜」というペルソナを演じている美女の日記。
エッセイ/随筆/日記には「話の筋道が整合的な体系に回収されてしまうことを何より忌避して、複数の論理や断片的な思考に積極的に身を任せ、脱線や逸脱や逡巡をいとわない。安直な全体化に執拗に抵抗する、そんな自由な思考の『試み』にこそ、エッセイというジャンルの本質がある」という解説がありました。
なぜそんな迂遠な試みをせねばならぬのか。
やっぱり、誰かになにかを伝えるためです。
いやほんと、伝わらねーのよ。
小説を書いていると。
でも書かずにはいられない。
「なにかを伝えることの難しさ」を身をもって痛感しているからこそ、必死に足掻きたいのです。
足掻きましょう、書きましょう。
そしたら読ませてください。読みます。
いいなと思ったら応援しよう!

