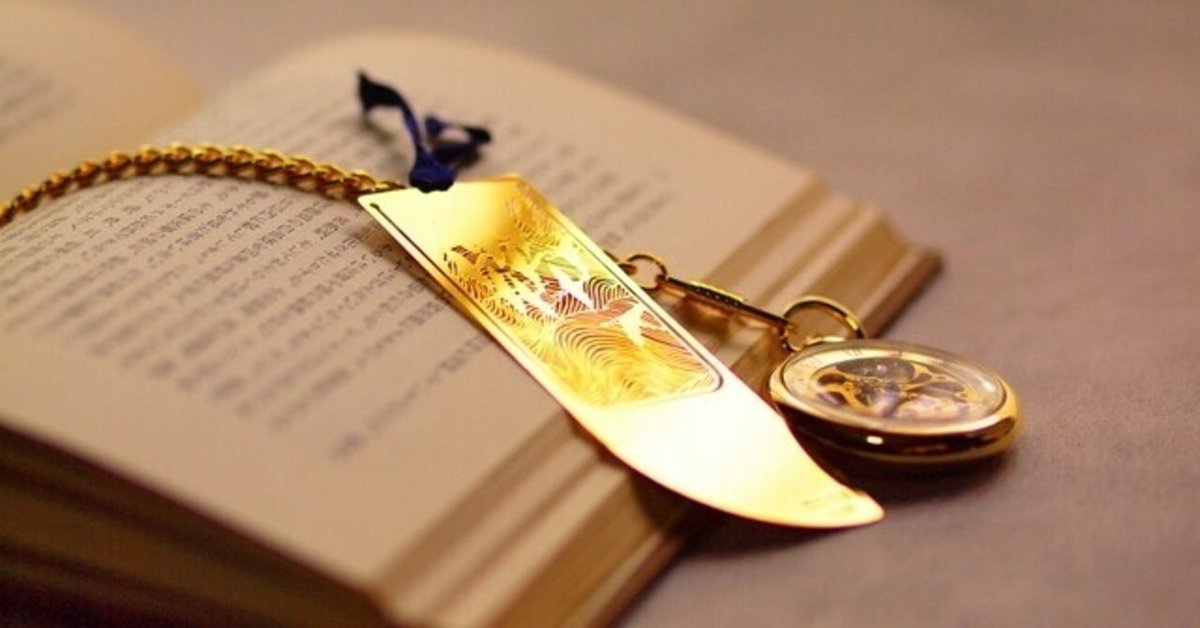
【質問箱】 スカウト
今年のプロ野球では、ルーキーの活躍が目立ちますね。
阪神の佐藤輝明選手、中野拓夢選手。
広島の栗林良吏選手。
横浜の牧秀悟選手。
ヤクルトの元山飛優選手。
楽天の早川隆久選手。
オリックスの宮城大弥選手。
日本ハムの五十幡亮汰選手。
西武の若林楽人選手。
パッと思いつくだけでも、目覚ましい成績を残している選手がこんなにいる。打てる、抑える、それから「速い」の選手もだいぶ多い印象です。ほかにヤクルトの並木選手とか。
ここまで豊作の年も珍しいんじゃないでしょうか。
逆にいうと、ここで名前が挙がらないような失敗ドラフトをここ数年ずっと続け、他チームからの移籍に頼った高齢の外人部隊となっているどこかの球団にはスカウトの眼力がないんだろうと思う。
金本監督時代から数年越しの構想で花開いた阪神は、本当に見事ですね。ちょっと前の広島を見ているかのようです。
前置きが長くなりましたが、ご質問にお答えします。
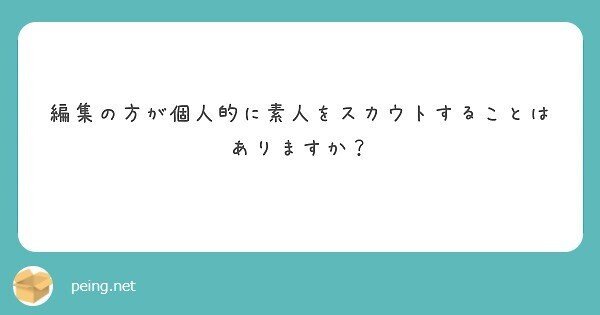
結論からいうと、可能性がゼロではありませんが、滅多にありません。
ずいぶん前のnoteに書きましたが、商業誌主催の文学賞に投稿して受賞することが、プロになるための正攻法にして最短ルートです。
押しの強い作家志望者に対し、昔の上司はよく言っていました。
――まずは賞に応募されることを強くおすすめします。なぜなら、受賞して初めて、作家としてのスタートラインに立てるからです。あなたはまだスタートラインにすら立っていない。
出版社によっては、持ち込み原稿はすべて賞への応募と見做すところもあるようです。
受賞して初めてスタートラインに立てるものであって、受賞することすら通過点なのです。
とはいえ、出版社も「待ち」の姿勢でばかりいては、頭打ち・縮小傾向に入ってしまうことは間違いありません。編集者たるもの、ウェブに限らず文学フリマなどいろいろなところにアンテナを張って、才能の原石がないかどうか探しているはずです。
それでも、敏腕編集者によって発掘された無名の新人が、誰もが熱狂するくらい面白がって文句なしにバカ売れする大ベストセラー作家となった例が、ここ10年20年でどれだけあったというのでしょう。持ち込みから成功した例として京極夏彦先生のエピソードはあまりにも有名ですが、それをきっかけとしてメフィスト賞という、持ち込みに極めて近い形態の文学賞が設立されました。受け皿がなかったから、作る。真っ当な理屈です。
各書店のベストセラーランキングに名を連ねる著者の経歴を見てみてください。ほぼすべての人のデビュー作に受賞歴があるはずです。無冠の(否、つい近年まで無冠だった)帝王というと、島田荘司先生や佐伯泰英先生くらいじゃないですかね。
もし無冠の新人をデビューさせるとなれば、出版社だってビジネスとして売らねばならないわけですから、それなりにコストをかけ、大々的に宣伝することになります。
「10年に1度の大型新人」
いや、
「100年に1度の超大型新人」
くらいは豪語するかもしれません。
そうでもしないと凄さは伝わらないし、一般読者の目に留まらない。
しかし、毎年毎年「100年に1度の超大型新人」「1000年に1度の超新星」が出てきたら、どうでしょう。
「またか」
って、うんざりしません?
「超新星」に至っては人ですらない。
爆発四散する天体ですよ?
「ここ数年で一番出来が良い」
「10年に1度の逸品」
「近年まれにみる出来で過去10年間でトップクラス」
「10年に1度の当たり年」
「過去10年で最高と言われた2001年を上回る出来栄え」
「100年に1度の出来、近年にない良い出来」
「今も語り継がれる1976年や2005年に近い出来」
「過去最高と言われた2005年に匹敵する50年に1度の出来栄え」
「100年に1度の出来とされた2003年を超す21世紀最高の出来栄え」
ボジョレー・ヌーヴォーかよ。
書店に「無名の超大型新人」が乱立していないのは、そういうわけです。
まったく無名の新人に箔をつけるために、各社は文学賞というブランドを少しずつ少しずつ、大切に育てているわけです。
デビューするのは誰もが1度きりですが、その1度きりのチャンスに、過去10年、20年、連綿と続いてきた文学賞の「ブランド」「箔」を使わせてもらえるんですよ。しかも応募するにあたっては無料で。仕事上、現時点で文学賞に関わっていない私の身から客観的に見て、こんなに贅沢なことはなかろうと思います。
「受賞して初めてスタートラインに立てる」とは、そういうことです。
仮に受賞歴がなかったとしても、たとえば「なろう」「カクヨム」などで「ランキング1位」となったことを売り文句にしたりするでしょう。その場合、まずは世間一般の広い市場ではなく、「なろう」「カクヨム」が好きな特定の購買層を当て込んでいることが多いと思われる。市場をそこでいったん完結させようという想定のもと、ビジネスを展開しているわけです。
一般文芸のプロの作品であっても、書店で帯を見渡してみてください。「読書メーター読みたい本ランキング第1位」みたいな「箔」をつけて、なんとか売ろうとしているのが現状です。
どこもかしこも、
「1」
「1」
「1」
この数字ばかりが並んでいる光景、見たことありません?
毎回失点する防御率6~7点台の先発投手かよ。
甲子園、大学野球、都市対抗などさまざまな大会が開かれ、打率や防御率、球速といった明確な数字でもって衆人環視のもとに評価され、鳴り物入りで選抜されるプロ野球選手でさえ、先述したように全員が全員、活躍するわけではありません。成功するのは、ほんのひと握りの天才たちだけです。
ましてや、明確な数字で測れるわけではない「面白さ」を武器に勝負する小説家という職業が、どれだけ大変なことか。また、それを編集者が査定し、抜擢し、売り出し、ベストセラーにつなげることの、どれだけ途方もなく難しいギャンブルであることか。
そのことをご理解なさったうえで、文学賞を目指すかスカウトの目に留まるのを望むか、それは各自の判断になろうかと思われます。
【こちらも参考記事】
いいなと思ったら応援しよう!

