
【質問箱】 JとE
Jun BungakuとEntertainment。
永遠の課題ですね。
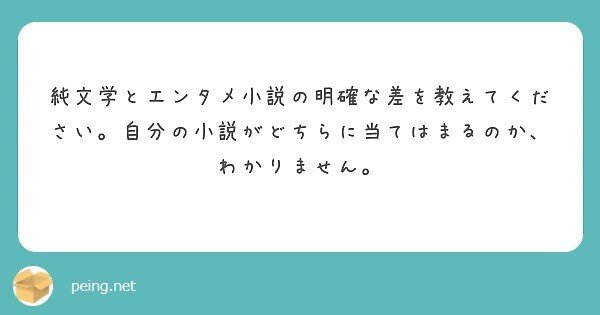
じつは、この問題については過去に書いてあるので、詳しくはそちらをご参照ください。
そのうえで、おとといの質問箱の内容と関連してくるのですが、
純文学かエンタメかを最終的に規定するのは書き手の自分ではなく、他者であるところの読者なんですよね。分けること自体にそもそも意味はないけれど、読者が知的興味を覚えるなら純文学、頭からっぽにしてでも強い刺激を得て楽しめるならエンタメ。もちろんすっぱり二分できるわけでもなくて、純文学にエンタメ的な要素があってもいい(いや、あるべきだ)し、逆もまた然りです。だから両者の「明確な差」は明示できそうにありません。
純文学を志向する書き手は「凡庸な表現」を極力排し、誰も読んだことのない表現に挑戦するかもしれません。しかしそのためには「伝わらなさ」に対する絶望がちゃんと念頭になければいけない。いわば「純文学の言葉」で書きたいことを読者に100%伝えることは、まあ大変なのです。となれば、どこかでエンタメ的な「凡庸な表現」を援用したっていい。そのエンタメ的なストーリーテリングによって、なんらかの新しい知的刺激が生まれることだってありえます。
一方でエンタメでは、ある種の記号化された「凡庸な表現」がしばしば役に立ちます。より効率よく読者に物語を伝えるため、先達が試行錯誤しながら連綿と積み上げてきた一種の定石のような表現です。それに乗っからない手はない。私がよく「小説とは拡大再生産されるものである」と書いているのは、そういうことでもあります。ただし、文章が金太郎飴化されればされるほど、そこに乗っかるストーリーそれ自体が目新しさを含んでいないと、ただの「凡庸」になってしまうおそれがある。エンタメはエンタメで非常に難しいのです。だから、エンタメ小説においても社会派の重厚なテーマを扱ったり、警句や箴言めいたキラーフレーズをどこかに潜ませたりするのは、有効なテクニックです。エンタメ小説の巻頭に、たまにエピグラフが載っていたりしますよね。短い詩や格言が引用される、あれです。あれは、エンタメ的なストーリーの裏に潜ませたテーマを提示していることが多いのです。
自分の書いているものが純文学かエンタメか。たしかに難しい問題ですが、どちらかに振り切る必要はないと思います。どちらの要素も書けているのであればそれはむしろ健全なことですし、その最適なバランスを試行錯誤しながら探っていけばいいのだろうと思います。
いいなと思ったら応援しよう!

