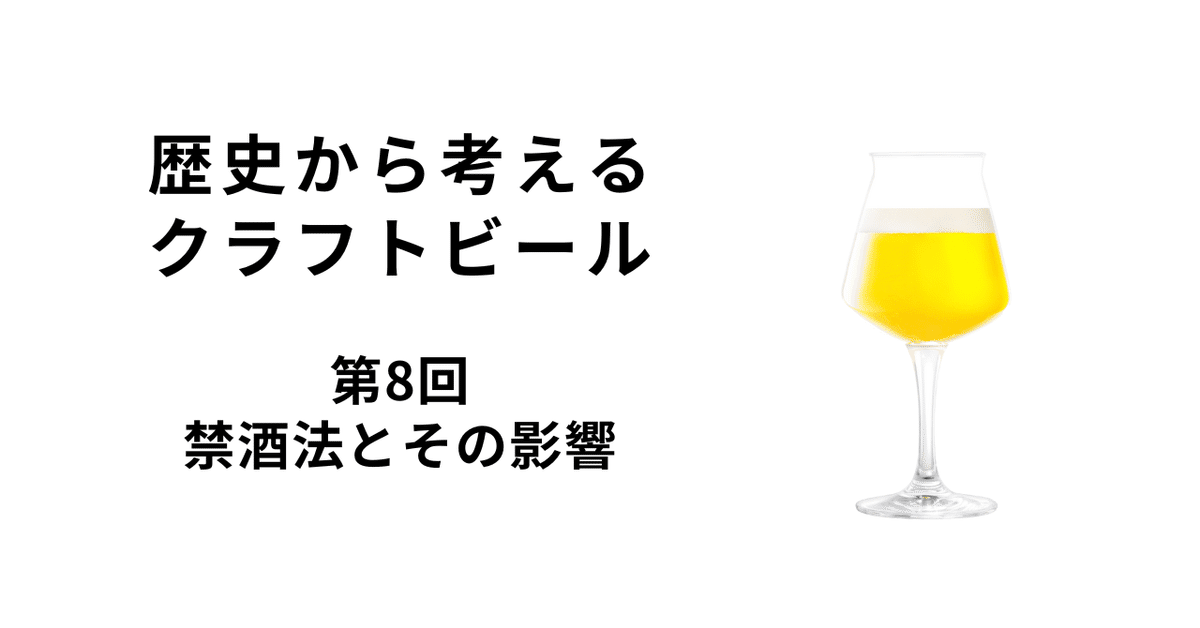
歴史から考えるクラフトビール〜⑧禁酒法とその影響
前回からの続き
前回は禁酒運動の盛り上がりから禁酒法の成立までを見てきました。社会の風紀を乱す酒場が標的となって成立した禁酒法は、現代の健康志向の高まりによるアルコール規制とはいくぶん背景が異なります。今回は1920年から実施された禁酒法の中身とその後世への影響を考察してみたいと思います。
禁酒法の本質
法律としての禁酒法
法律としての禁酒法は、アメリカ合衆国憲法修正第18条とその憲法規定の詳細を定めるボルステッド法によって構成されています。
第1節 本条の承認から1年を経た後は、合衆国及びその管轄権に従属するすべての領土において、飲用の目的で酔いをもたらす飲料を醸造、販売若しくは運搬し、又はその輸入若しくは輸出を行うことを禁止する。
第2節 連邦議会と各州とは、適当な法律の制定によって、本条を施行する権限を共に有する。
憲法は上記のとおりいたってシンプルです。(第3節は停止条件なので割愛しました)禁止されているのは、製造、販売、運搬、輸出入であり、実は個人がお酒を所持したり飲んだりするのは違法ではありません。そしてその対象は酔いをもたらす飲料(Intoxicating Drinks)です。「酒類」ではなく酔いをもたらす飲料という少々曖昧な言葉が使われていることに注目です。この用語を使った理由は、憲法改正には両院で3分の2を超える議員の発議という非常に高いハードルがあるので、規制対象となるお酒の定義をなるべく曖昧にしておきたかったためと言われています。
憲法改正とボルステッド法にいたる流れは、民主主義国家において人々の生活を大きく変える法律がどのように合意形成されるかを考えるうえで非常に興味深い事例です。前回の投稿で見たとおり、禁酒法の流れを決定づけたのは反酒場連盟でした。彼らは酒場と酒場を牛耳る酒造メーカーを標的にした活動を展開していました。なので一般の人の自由を奪うというより、お酒を提供する側を処罰する方向で法制化されているのです。また、ドライ派と言われる禁酒法推進派の議員の中にも温度差がありました。徹底した禁酒を求める急進派は骨までカラカラということでボーンドライ派と呼ばれていました。一方でドライ派の中でも「ビールくらいだったらいいんじゃないか」などと考える(ある意味穏健な)人たちは、ボーンドライ派から見ると中途半端なのでモイスト派。対して禁酒法に反対する人たちはウエット派です。憲法改正のためには、モイスト派も含めた合意形成が必要なので、広く納得性が得られるようにIntoxicating Drinksという玉虫色の用語を使いました。憲法改正の発議当初はモイスト派議員は、ビール(中でも比較的低アルコールなもの)はこの規制に該当しないと考えていました。ところが、蓋を開けてみるとボルステッド法ではIntoxicating Drinksの定義は0.5%以上のアルコール飲料となりました。これはボーンドライ派の目論見どおりの結果でした。
禁酒法の実際
禁酒法がはじまったのは正式には1920年1月からですが、実際には2.75%以上の酒類の製造を禁止する戦時禁酒法が1919年5月から施行されており、また酒類の販売も1919年7月から禁止されていました。さらに各州には独自の禁酒法や酒類の規制があったため、1920年1月を境にくっきりと禁酒法時代に突入したというよりは、段階的にアメリカ全土が禁酒法下に移行したというのが実際です。
禁酒法時代には、スピークイージーと呼ばれる酒の密売をする無許可バーが横行しました。このようなアンダーグラウンドの取引はギャングの資金源になり社会問題化しました。取締官の汚職も頻発していましたが、そんな中でも買収されずに厳正に取締をしていた人たちもいて、その有名な事例が酒類取締局の捜査官エリオット・ネスです。ケビン・コスナー主演の映画「アンタッチャブル」で描かれています。
一方で、1920年代は空前の好景気の時代でした。第一次大戦後、アメリカはイギリスに代わって「世界の工場」となり大量生産・大量消費により経済が膨張しました。「狂騒の20年代」、またはフィッツジェラルドの小説のタイトルから「ジャズ・エイジ」と言われています。20年代を舞台にしたフィッツジェラルドの小説「グレート・ギャツビー」では華やかなパーティーで人々がお酒を楽しんでいる様子が描かれています。そうです、製造も運搬もできないはずの禁酒法時代にもお酒はたくさん飲まれていました。禁止されているにも関わらず、密輸、密造している人たちがだくさんいたということですね。
禁酒法の影響
1933年に成立した憲法修正第21条によって修正第18条は廃止されました。これをもって禁酒法時代は終わりとなります。ですが、はじまった時と同じように、この日を境にスパッと酒が解禁されたというわけではありません。酒類の制限は州によってはしばらく残り、徐々に変化したというのが実情のようです。さらに禁酒法の後遺症とも言える影響がアメリカのビール業界に大きなインパクトを与えました。主なインパクトを4つを紹介しますが、いずれも反動エネルギーとして作用し、クラフトビールがその反動を利用して勢いよく普及する構造を作っていると考えられます。
ブルワリー数の減少と寡占化
禁酒法前には全米に2000ほどだったブルワリー数は激減しました。小さなブルワリーが廃業し、その空白地帯をアンハイザー・ブッシュのような巨大ビール会社が埋めていきました。前々回の投稿で紹介したような多様なビール文化は失われ、巨大ビール会社による過度に産業化されたラガービールがモノトーンなビールシーンを作りました。ただし、この現象は禁酒法そのもの、つまり禁酒法が実際に施行された14年間が真の原因というわけではなさそうです。下のグラフを見てみましょう。

1920年と1933年(禁酒法期間)に点線で橋を渡してみました。これを見ると実はブルワリー数は禁酒法の施行に関係なく長期的に減少トレンドだったことが分かります。ブルワリー数が減ったのは禁酒法が直接の理由というよりおそらく複合的な要因です。そもそも西欧と同じように「近代ビールの三大発明」をきっかけにしたビールの過度の産業化の影響が根本にあります。禁酒運動と禁酒法がどの程度市場の寡占化に影響したかを正確に把握することは難しいですが、禁酒法によって多くの中小ブルワリーが廃業に追い込まれたのは事実です。そして結果としてアメリカのビール市場はヨーロッパ以上に寡占化され、そこに反動的なエネルギーが生まれる余地ができました。
ちなみに完全に脱線ですが、過去のブルワリー数のピークは1873年で、その年を起点にした2015年までのグラフが下記です。(何が1870年代からの急激な減少をもたらしたのか興味深いところです)

流通三層構造
アメリカの酒類業界には3 Tier System(流通三層構造)という原則があります。これは禁酒法が廃止された1933年に、禁酒法に代わって酒類業界を統制するために作られた法律に基づいています。特に酒類メーカーが特約酒場(タイドハウス)を通じて、市場をコントロールするのを防ぐ目的がありました。州によって運用が違ったり、実際にアンハイザー・ブッシュなどの大手メーカーは優越的で支配的な立場を保持できていたので、この流通三層構造が当初の目的を果たしているかどうかは大いに疑問があります。ただし、禁酒法がきっかけで「政府が酒類業界を強力に規制する流れ」が醸成されたことは間違いないでしょう。
ホームブルーイングの禁止
禁酒法とともにホームブルーイングも禁止されました。1978年に解禁されるまで、ずっとホームブルワーたちの「ビールを造りたい!」という欲求をマグマのように溜め込む結果になりました。つまりホームブルーイングの禁止は構造的に反動エネルギーの源泉になっていると思います。
業界の一致団結
禁酒法成立過程において禁酒法支持者たちが着々とロビー活動を進めている間、当時のビールの業界団体であるUSBA(USブルワーズ・アソシエーション)は内部抗争状態にあり、一丸となって対抗することができませんでした。この機能不全への反省から、クラフトビール業界は団結してロビー活動をすることで現在の繁栄を築きあげました。日本のクラフトビール業界も見習いところですが、日本では禁酒法のような過去の手痛い失敗がないので実感がわかないのかもしれません。
次回へと続く
2回にわたって禁酒法の影響を見てきました。禁酒法の影響はその後のクラフトビールの勃興に大きなインパクトを与えます。禁酒運動と禁酒法を通じてある種の反動エネルギーが形成されて、それがクラフトビールを勢いづけたと考えられるのです。
さて、お待たせしました、次回からようやくクラフトビールの話になります。
宣伝
お読みくださりありがとうございます。この記事を読んで面白かったと思った方、なんだか喉が乾いてビールが飲みたくなった方、よろしけばこちらへどうぞ。
受賞のお知らせ。Japan Brewers Cup 2025において、Far Yeast Whiteが小麦部門2位、Far Yeast Blondeがライトエール部門2位に輝きました!定番ビールで受賞できたことは大変うれしく思います。
受賞速報はこちら。


