
美容室が公立大学と連携して地元学生とコラボした話
シローの店は美容室です。美容室が大学とコラボでものを作るという企画をしました。美容室というと専門学校とのコラボが多い印象があります。ですが、ワタクシが今回の企画でピンときたのは大学。
「なんで大学と?」というわれるその動機やなんのプロジェクトなのか、そしてそのプロジェクトのキックオフ後の成果物の作成過程などを少し述べてみようと思います。
ちなみにこのコラボの話は12月2日の河北新報朝刊にも掲載されました。
なぜ大学とコラボを考えたのか。
なんで宮城大学という教育機関に頼んだのか。
常々、ワタクシは「何かをやりきる」ことが大事、といっています。何かをやり切るにはプロジェクトベースのなんらかが必要。大学の場合は卒論というプロジェクトがありますが、それ以外にもなにか「やりきった」感が生まれるものがあってもいいんじゃない?と思っていました。
「やりきった」ことの重要性
その「やりきった」という感覚は「自信」という宝物になる。なんでもいいんです。上記の卒論でもいいし、部活でも、なんでもいい。とにかくなんでもいいから「やりきった自信」という宝物を若いうちから持ってほしいと思っています。
そのやりきった自信は社会に出て多少のことがあっても
「あのときあんだけやったんだから、だから今回も乗り切れる」
というバックボーンになる。
だから地元の大学に依頼して学生に「こういうことをやり切りました!」と胸を張っていえる経験のきっかけを作り、地元貢献をしたいと思っていたのです。もちろんそれは、シローの店のスタッフにも、いっていることではあるのですが、誰に対しても思っています。「やりきったという自信」は人が成長するには必要なことだと考えています。

きっかけ
きっかけは1年前のビジネスマッチです。宮城大学が出展していて、伊藤先生のプロジェクトを展示していました。50周年という節目のプロジェクト。頼めばシローの店のスタッフのみならず、宮城大学の学生も胸を張れるプロジェクトができそう、という感覚がありました。
もちろん、ある種の公共機関に頼むわけだから適当にやってよ、とも言えない。1から10までピシっとやる。依頼しているシローの店側もそれなりの準備が必要で、相互にいい影響を与えると思ったところがあります。
なんのプロジェクトをしたのか
シローの店が50周年ということで、1年間だけの期限付きロゴを作成、さらにその派生販促物などの提案をしてもらうのがプロジェクト。そのロゴを使って50周年記念のブランディングをしていくのがこちらのその成果物の利用方法です。実際にSNSやシールなどに利用したり、式典で大々的に使ったりしています。
作るまでの過程
普通のデザイン会社では、案外と忖度をしてくれるので、「こんな感じでやっといてね、あとよろしく」といえばある程度進む事があります。これはこれで楽ちん。ところが、相手は大学の先生とその学生。しっかり腰を据えてやらねばいかんことも多々ありました。
ディスカッションは数時間にも及び、どうでもいい話もしつつ、思いというものを汲み取ってもらいました。会長を含めたセッションを設けたりもしています。
やはり最初の提案は「うーん」というもの。そこから何度も事務所に足を運んでもらい、こーだあーだ、ワタクシはこう思う、などのやり取りをしました。さらに、「いや、それはダサい」、「んじゃ、そもそもどう思っているの?」などなど結構ガツガツとやり取りをしています。
(伊藤先生はもっとケンケンガクガクのディスカッションをしたかった、とお聞きしました。)

他に中心となる学生数人だけが来て、提案を出してくれたときは「もう少しひねりがほしい」と突き返したりもしています。一発OKはめったにない、という社会の世知辛さを経験した、と落ち込まずポジティブにとらえてほしいです。実際、WEBから取ってきたものではなく、脳汗かいて考えた上での提案が欲しかったところもあります。
結果
いいものができていると思っています。案外とロゴに込められた思いをスタッフが知っているとそのロゴの方向に動いていくものなのだなぁ、と思ったりもしました。気づくことも多かった、違う方向からの知見が得られたいい機会でした。
ロゴの解説はお店に来てスタッフから聞いて下さい。
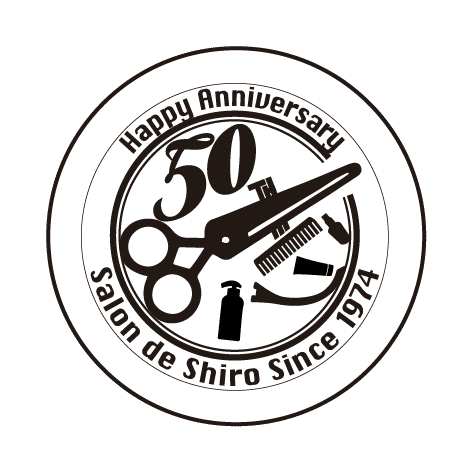
個人的に
久しぶりにアカデミアと話ができたのはワタクシにとって非常に新鮮で、面白いことだらけ。ケンケンガクガクのディスカッションもコンサルタントだった頃以来で、個人的にはもっと早くから関わりたかったと思うと同時に、さらに関われるものたくさんあるぞ、とも思っていたりするのでした。
