
国別ウィスキング文化の比較(5カ国)
こんにちは!しらかばスポーツです。

今回は前回の続きで、国別のウィスキングの特徴(5カ国)をご紹介したいと思います。
私見も多いと思いますが、参考までに。
お時間あれば是非読んでみてくださいませ。
フィンランドにおけるウィスキング
前回の記事にも書きましたが、「フィンランドのサウナ文化」は日本のサウナ文化に大きな影響があります。
サウナ、ロウリュウ、ヴィヒタは全てフィンランド語です。
特にヴィヒタは「白樺のサウナウィスク(サウナほうき)」を表していて、フィンランドでは「白樺」しか使わないから「それ以外の植物」を表現する必要がない?ようです。
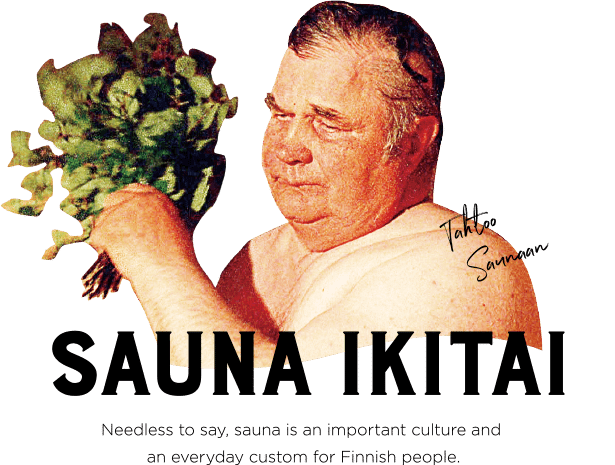
上記画像、フィンランド映画の「サウナのあるところ」でもヴィヒタは出てきますが、フィンランドでは「ヴィヒタを使ったセルフウィスキング」が基本のようです。
余談ですが、マグ万平さんがフィンランドに行った際、サウナ小屋のおばちゃんに【ウィスキング】をしてあげたら「なんじゃこりゃ?最高!」みたいに喜んでもらえたという話があります。
「フィンランドはヴィヒタでセルフウィスキング」
が基本であることを示すエピソードですね。
ロシアにおけるウィスキング
ロシアでは「ウィスキング」は「プロにやってもらうサービス」で、日本で言えば「アカスリ」や「マッサージ」のようなイメージが分かりやすいと思います。

ロシアではサウナのことを「バーニャ」(バニャ):Баня と呼びます。
※「サウナ」:Саунаと発声すると「サウナ付きラブホ?」みたいなものになるようですので注意。
また、ウィスキング道具=サウナウィスクにも違いがあります。
フィンランドでは「ヴィヒタ」=「白樺のサウナウィスク」がメインですが
ロシアでは「オークのサウナウィスク」がメインで振られます。

オークはヴィヒタに比べてとってもタフで、熱もよくはらみます。
嗅いだことがある人はわかると思いますが、日本のカシワに似た香りです。
※柏餅の香りを想像してください。
またロシアのウィスキングではたくさんの種類のサウナウィスクを使います。

ロシアでは「公衆バーニャ」(=日本でいう銭湯)や、「貸切バーニャ」(=日本でいう貸切サウナ)があり、「施設付きのウィスキングマイスター」や「フリーランスのウィスキングマイスター」に依頼してウィスキングを受けることができます。
ウィスキングマイスターがサウナ施設を所有しており、そこに受けにいくスタイルもあります。
ウィスキングマイスターによって個性があるのも面白いです。
コチラの記事も是非読んでみてください。
「ロシアはオークがメインで、プロにウィスキングしてもらう」
と言えると思います。
バルト三国におけるウィスキング

バルト三国=エストニア、ラトビア、リトアニアの3つの国。
旧ソヴィエト連邦でもあり、1918年〜1920年にかけて独立した歴史があります。
正直まだあまり詳しくありませんが、聞いた話(うろ覚え)だと
リトアニア=ロシア寄りのサウナ文化。
ラトビア=少しスピリチュアル寄りのサウナ文化。
エストニア=伝統医学との融合など挑戦的なサウナ文化。
と言われているようです。
さらに実はフィンランドもロシア占領下だった歴史もあり、いい悪いは別にして「文化的な接点はある」と思います。
実はしらかばスポーツが振るサウナウィスクは、ラトビアのオーガニック農家さんと協業で作っています。

しらかばスポーツのサウナウィスクのこだわりの記事はコチラ
サウナにまつわる歴史と、ハーブの知識から生まれる多様なサウナウィスクは、僕たちのウィスキングを支える「なくてなはらない」道具です。

この縁を活かしてバルト三国サウナ視察も行こうと思ってます。ヨーロッパでのコロナがヤバくて全然目処が立ちません。。。(まじでベラルーシちゃんとして!)
話が少しそれましたが、歴史的な背景も込みで乱暴にまとめると
「バルト三国では、ロシア的なウィスキングをベースに新たな独自のウィスキング文化を模索中」と言えるかと思います。
さて、いかがでしたでしょうか?
まだまだリサーチ不足ですが、ふんわりしたイメージの違いはお伝えできたかと思います。
次回は、【しらかばスポーツのウィスキング活動(2017-2019)】をご紹介できればと思っています。
最後まで読んでくださりありがとうございました🌿

ウィスキングに興味がある方は是非フォローをお願いします↓↓↓
