
アフターデジタル時代に求められるメカニズム解明型ユーザー理解 #UXグロースモデル 1枚まとめ4
アフターデジタルの第3弾「UXグロースモデル アフターデジタルを生き抜く実践方法論」が2021年9月16日に発売となりました。本書では、UX(ユーザーエクスペリエンス)企画の秘伝である、方法論、プロセス、その裏にある考え方を詳説するといいます。今回は本書の「第3章 人間心理の探求から、メカニズムの解明へ(ユーザー理解を再定義する)」についての学びをまとめます。
本書の構成
「UXグロースモデル」の章立ては以下のようになっています。今回の記事は、★のところとなります。
はじめに
→UX型DXでのUXの定義とは #UXグロースモデル まとめ1
第1章 アフターデジタル時代に求められるバリュージャーニー型への転換
→1枚まとめ #UXグロースモデル まとめ2
第2章 UXグロースモデルの概要
→アフターデジタル時代に求められるUXグロースモデルの全体像まとめ3
★第3章 人間心理の探求から、メカニズムの解明へ(ユーザー理解を再定義する)
第4章 ボトムアップ型UXグロースの方法論1/2(既存サービスの抜本改善)
第5章 ボトムアップ型UXグロースの方法論2/2(既存サービスの高速改善)
第6章 トップダウン型UXグロースの方法論1/2(事業変革の推進)
第7章 トップダウン型UXグロースの方法論2/2(全社変革の推進)
第1章のまとめ(再掲)
第1章:アフターデジタル時代に求められるバリュージャーニー型への転換顧客の成功をバリューチェーン横断で支援するプラットフォーマーと価値要素特化の機能提供者にプレーヤーが分かれる。競争力の源泉は顧客成功を継続支援する中でLTVを高めるビジネスモデルへ移行。その実現には使用価値を運用・成長・進化させるグロースチームの構築が経営に求められる。
第2章 UXグロースモデルの概要(再掲)
UXグロースモデルとは中長期×経営目線のトップダウン型と、既存サービス改善のボトムアップ型のUXグロース活動の相互連携でバリュージャーニーを成長・進化させ企業変革を推進すること。2つの型では目指すゴール、ケイパビリティが異なるため組織・チームを分ける一方で、人材交流・ローテなど連携・循環を促すことで互いの創造性を尊重し高めあう文化を作ることが重要
第3章 人間心理の探求から、メカニズムの解明へ(ユーザー理解を再定義する)
本章で説明されているメカニズム解明型のユーザー理解を一言でいうと普及版「ジョブ理論」です。実際に、本章中のコラムでも、ジョブ理論の民主化という表現をしています。ジョブ理論に関しては、私の過去のnoteでも紹介しているので、最後にそちらは紹介するとして、本書の提唱するメカニズム解明型のユーザー理解をまとめたいと思います。
一般に普及している心理探究型ユーザー理解の課題

一般に普及しているユーザー理解(顧客理解)の定義・枠組みを「心理探究型ユーザー理解」と呼称し、このアプローチの課題を説明します。このアプローチでは、以下のような人間観を前提とします。
心理探究型ユーザー理解の前提となる人間観
1. 心・深層心理:ユーザーは価値観・信念にもとづいて
2. 願い・欲求:xxxという願い・欲求をいだき
3. 行動・選択:xxxという行動を選択する
この人間観にもとづくユーザー理解には以下の課題があります。
心理探究型ユーザー理解の課題
人間の行動は、純粋な心の産物ではなく、状況・文脈によって変わることを考慮しづらい
また、このアプローチは、UXの改善・進化においても以下のような課題があります。(書籍からかなり意訳してます。)
UXの改善・進化における課題
・主観の壁:心理の推定がセンス&分析者の主観に頼りがち
・UX企画化の壁:製品・サービスのUXの改善・進化の施策検討で発想の飛躍が必要
本章には書かれていませんが、上記のようにして導き出された企画はPDCAを回して改善することも難しくなりそうだと思います。
メカニズム解明型のユーザー理解
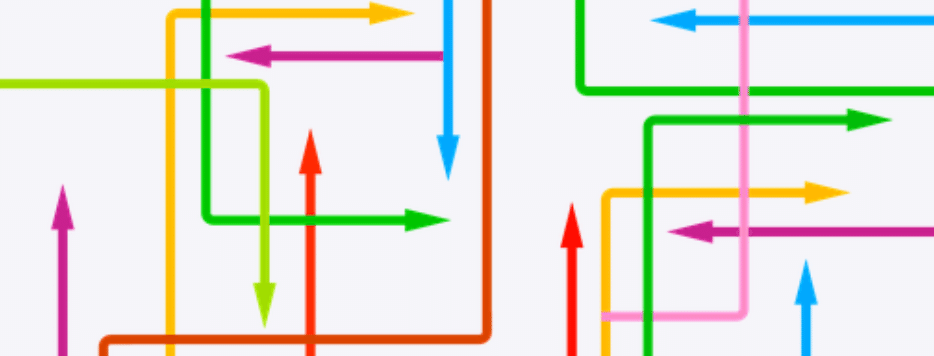
ユーザーの体験を改善・進化させるために、深層心理・性格・価値観といったものを理解するアプローチは課題があります。そのため、ユーザーが行動を選択するメカニズムに着目してUX企画を考える「メカニズム解明型のユーザー理解」のアプローチへの転換が必要だ、というのが本書の提案となっています。
メカニズム解明型のユーザー理解のアプローチ
1. ユーザーが目指す成功を確認する
2. 成功に至るまでの行動フローを特定する
3. 一連の行動フローにおけるペインポイントを抽出する
4. ペインポイントの発生メカニズムを解明する
ぼやき

本章は、新規事業開発の業務をやりながら、先にジョブ理論に触れていて、むしろ、「一般に普及している心理探究型ユーザー理解」自体があまりピンとこなかった自分はなんか不思議なこと言ってるなぁ、と思って本章の前半を読みました。
私は、基準がジョブ理論の考え方になっていて、本書のコラムで説明されているジョブ理論の説明もしっくりこない部分がありました。自分の中では、以下のジョブ理論のオリジナルの考え方がしっくりきます。
概説「ジョブ理論」
ジョブ理論は究極的には以下の質問に答えることに集約されます。
「 顧客はどんな状況で、どんな進歩もしくは問題の解決を雇用したいのか?」
顧客が欲しいのはProduct(製品)ではなく、Progress(進歩)なのだ、というのも印象的でした。これはこのままUXグロースでいうところの、顧客が欲しいのはUXの進化なのだ、ともいえるでしょう。
いずれにせよ、ここで特に重要なのは、「状況」だということですね。その状況を描くのにJOBSフレームワークが有効で、個人的にはこっちのほうが、UXグロースモデルで言っている定義より語呂合わせにもなっているし覚えやすいと思います。
<JOBSフレームワーク>
Job:顧客が本当に成し遂げたいことはなんなのか?
Objectives:その目的、理由はなんなのか?
Barriers:何がその障害になっているのか?
Solutions:現状の(代替の)解決手段として何をどうしているのか?
そのうえで、ジョブ理論の中で、Barrier(障害)とSolutions(代替手段)を特定するためにストーリーボードをつくることを上げます。以下のStep2ですね。
メカニズム解明型のユーザー理解のアプローチ
1. ユーザーが目指す成功を確認する
2. 成功に至るまでの行動フローを特定する★
3. 一連の行動フローにおけるペインポイントを抽出する
4. ペインポイントの発生メカニズムを解明する
第3章のまとめ
いつも通り、一枚まとめを作ってみました。

ユーザーの行動が、その人の性格や価値観などの深層心理から選択されるという心理探求型ユーザー理解のアプローチは、インサイト獲得の主観依存とUX企画化を複雑にする課題がある。UXの改善・進化にはユーザーが行動を起こすメカニズムを解明しようとする以下のアプローチが有効
メカニズム解明型のユーザー理解のアプローチ
1. ユーザーが目指す成功を確認する
2. 成功に至るまでの行動フローを特定する
3. 一連の行動フローにおけるペインポイントを抽出する
4. ペインポイントの発生メカニズムを解明する
おわりに
DXについての記事は以下の「マガジン」にストックしてますので、併せて覗いてみてください。フォローや「スキ」を押してもらえると励みになります。
ということで「形のあるアウトプットを出す、を習慣化する」を目標に更新していきます。よろしくお願いします。
しのジャッキーでした。
Twitter: shinojackie
