
学校では習わない「僧帽筋」

どーも。水曜日の薬師寺です\(^o^)/
以前のPhysio365のゲストライターの肩さんが紹介していた「OIKOSヨーグルト」が脂質ゼロでなおかつタンパク質10グラム入ってることを知ってからOIKOSヨーグルトの全種類を制覇しようと試みてる最中です。
全種類制覇とか言ってますが、何種類あるのかそもそも知りませんww
ゲストライターの肩さんの栄養指導にも活用出来るコラムです⬇⬇
では、切り替えて本題へ。
前回の「広背筋コラム」が有り難いことにまあまあ見てくれる人がいたので、予定変更をします。
前回の広背筋コラムに引き続いて「僧帽筋」に絞ったコラム。
前回の広背筋コラム↓↓
では、、
「僧帽筋コラム」をどうぞ↓↓
僧帽筋の機能解剖学
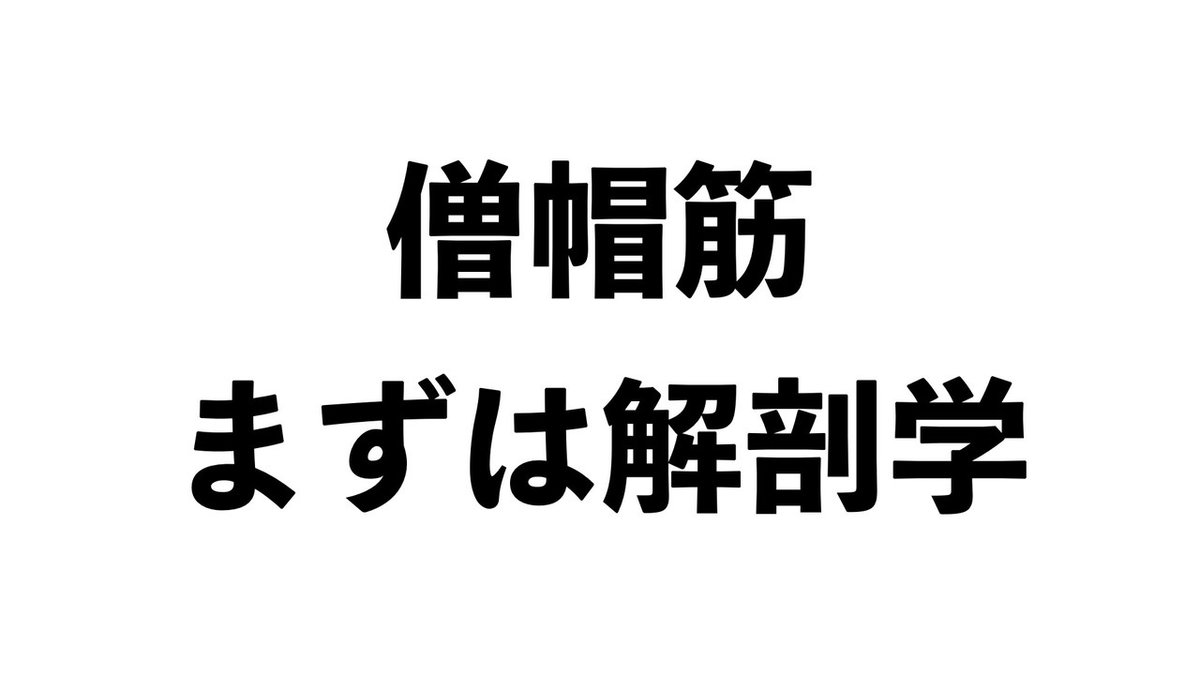
僧帽筋の話を深堀りしていく前に…
入りは基礎から。
解剖学の知識からスタートです。

まずは僧帽筋の機能解剖学。
これは学校でも習う内容ですが、基本が大事と言われるようにもう一度復習がてら目を通してもらえたらと思います。
僧帽筋は背部にある広く付着する筋肉。

基本的な僧帽筋の解剖学の知識です。
基本的な学生が使用する参考書には僧帽筋の起始停止はザックリと起始がどこで停止がどこまでと記載しているものが多いですが…
僧帽筋を理解する上で、絶対に欠かせないことが「上部線維・中部線維・下部線維」を分けて捉えることです。
・上部線維:肩甲骨挙上・上方回旋・頸部伸展、側屈
・中部線維:肩甲骨挙上・肩甲骨内転
・下部線維:肩甲骨下制・上方回旋
こういった作用があるわけであって…
上部線維・中部線維・下部線維によって作用が異なるわけです。
臨床では、僧帽筋の起始停止をまとめて暗記していることにはほとんど意味はなく、その3つの線維を別々に分けて考えることが重要になってきます。
ここから先は

臨床マガジン【現場で使える機能解剖学・運動療法・ピラティス】
業界最大規模の購読者数700名以上●「現場でしっかり結果を出したい」セラピスト・トレーナー・インストラクターのためのマガジン●"臨床で本当…
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
