
歯科と医科が別のメリット・デメリット【④Another view 医療システムの過去・未来・海外】Dental and Medical are different ; Advantages and disadvantages.
こんにちは。『アポロニア21』編集長の水谷惟紗久(MIZUTANI Isaku)です。
私は歯科医院経営総合誌『アポロニア21』で、最新の歯科医院経営の情報を20年以上追い続けるとともに、歯科医療の経済的、社会的、歴史的な背景についての調査や執筆をライフワークとしています。
本コラム「Another Viewー医療システムの過去・未来・海外」は、現在、当たり前となっている診療システムや保険制度、自費診療の在り方などについて、過去の歴史や海外の事情などと照らし合わせてみることで、今までとは異なる視点から、医療の新しい景色を探してみようという試みです。
前回③で、「歯科はなぜ医科と別なのか」という理由を18世紀イギリスの事例から探ってみました。
今回は、「歯科と医科が別のメリット・デメリット」というテーマで、米国や日本で発展した歯科医療の背景や、近年の歯と全身の健康の関連への関心に触れたいと思います。
〈19世紀:アメリカ①〉学問と病院が結びついて、近代医学がスタート!
19世紀に入り、欧米では病院と結びついた近代的な医学部が次々に成立していきます。それまでのヨーロッパの医学部は、文字通り「医学という学問を学ぶところ」でした。臨床の技術を習得するには、病院での実習が不可欠だったからです。
もともと病院は、感染症患者、精神病患者、貧困者などを収容し、多くの場合、【隔離することが第一の目的】【治療は二の次】でした。
しかし、19世紀になると新たな技術を病院で実施し、そこで若手医師に実習を経験させるというスパイラルが生まれ、現在に至ります。
最初に病院と結びついて発展した医学部は、イギリスのユニバーサル・カレッジ・ロンドン(UCL、1827年成立)です。ロンドンの篤志病院の医学校と連携して、臨床医学の教育をスタート。これが近代医学の出発点とされます。
〈19世紀:アメリカ②〉歯科が、別の道を歩き始めた…
同時代、アメリカでも1765年にペンシルベニア医学校が初めての医科大学として設立され、その後に近代的な医学部、病院が次々と成立していきます。実は、この時こそ、歯科が他の医療分野と分かれていく重要な分岐点となりました。それらの医学部や病院に歯科が参加しなかったからです。
イギリスで王立外科協会が主導して、最初の歯科医師国家試験(1860年)が実施されたものの、これを受験する歯科医師があまり多くなかったことと合わせ、教育課程でも別の道を歩み始めたのです。
世界最初の近代歯科学校は、アメリカのボルチモア歯科学校(1840年)ですが、医学部に編入されることはなく、歯科医師養成機関が単独で設置されました。
こうして、歯科が医科と別に発展する「医科歯科二元論」の端緒が開かれました。
昭和大学名誉教授の須田立雄氏によると、アメリカの東海岸で歯学は誕生し、中部そして西部へと広がっていったものの、「東部ほど一元論的(*医科と歯科を一体として捉えること)色彩が強かった」とのこと。歯科医学を、東部では「Oral Medicine(口腔医学)」と呼び、西部では「Dentistry(歯学)」との位置付けが強かったようです
アメリカでは、二元論一色ではなかったものの、早くから歯科教育独自の大学化が進んだこともあり、結果的に、医科との区別が進むことになりましした。
〈19世紀:イギリス、日本〉根底には、「歯科」への思い入れも…
医科歯科二元論の成立には、もう一つの側面もあったようです。
イギリスで「医科歯科二元論」のルーツを調べた歯科医師のサラ・ネットルトン氏が、19世紀当時の文献を広く調べたところ、成立間もない近代歯科医療の担い手たちが「歯の健康の重要性」「歯がいかに大切か」をいろいろな機会でアピールしていたことが分かりました。
皮肉なのは、歯の重要性を歯科医師らが訴えれば訴えるほど、「歯は特殊な部位だ」と思われて、そうした特殊な部位を扱う歯科医師も、医師と別ものに見られるようになったことです。
現在も、「歯科の重要性」「口腔と全身の健康」をアピールする歯科医療従事者は多いのですが、やりすぎると誤解されるということでしょうか。
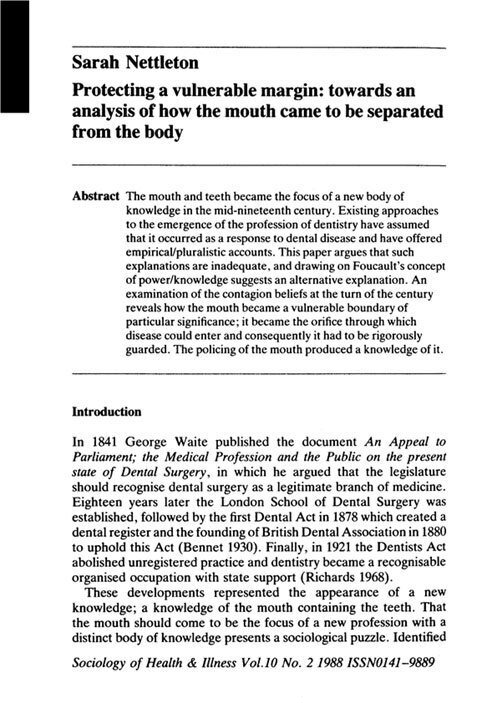
そして19世紀の日本では、「歯科」という名前に強いこだわりを持つ人物が、近代歯科医療の道筋を開きました。
明治8年(1875年)に日本で最初に歯科医術開業試験を受けて歯科医師になった小幡英之介は、「口腔科」ではなく「歯科」という名前にプライドを持っていたことが知られています。
しかし、すでに明治25年(1892年)になると、「歯科では、歯の周囲の病気に対応しにくい」などの理由から、「口腔科」に変更すべきではないかという論議が生まれたという記録があります。
〈20世紀~:イギリス・日本〉歯科医師も全身を学ぶ時代に
20世紀になると、全身麻酔下で行うような大掛かりな歯科治療技術が確立されたこともあり、デンティストの資格で王立外科協会に加盟する人も増加。現在は、指導医含めてイギリス全土で5,500人のデンティストが王立外科協会に加盟しています。
日本でも、歯科医師国家試験に「医科準用」という、医師国家試験からの流用問題が出題される傾向が目立つようになってきました。こうした変化は、現実の歯科医療が医師との連携が進む一方、医師との境界領域での業務も拡大していることに対応するためだと言えるでしょう。
この傾向がさらに進めば、歯科独自の専門教育、資格試験を続ける意義が薄まっていく可能性もあるかもしれません。
〈まとめ〉医科・歯科二元論のメリット・デメリット
19世紀以降、歯科医師は、世界中で内科や外科などの医師とは別個に育成され、保険制度でも別扱いになりましたが、それにはメリット、デメリットもあります。
【メリット】
・歯科医師にしか必要のない入れ歯、被せもの、矯正などの技術教育が行いやすい
・「貴金属を扱う」「入院が少ない」など、歯科の特殊性を反映した医療制度を作りやすい
【デメリット】
・長らく、医療制度上、歯科を保険診療の対象としない国が多かった
・病院では歯科が不採算になりがちで、設置しないところも多い
「歯科」が独立する「医科歯科二元論」には、補綴などの付加価値の高い技術を自由に発展させられる一方、病院中心に発展してきた近代医療と同じ道を歩むのが難しく、20世紀に整備される公的医療制度で給付対象になりにくくなってしまった面も否定できません。
〈展望〉医科と歯科が縮まる方向へ
近年では、がん治療の周術期の口腔管理の必要性から、歯科を設置する病院が再び増加しています。がん患者の治療の前後に、歯科治療・口腔ケアを行うと、退院日数が短縮できるというデータが蓄積され、保険制度においても、口腔ケア・情報提供を行った病院に対しては、特別な加算が請求できるようになりました。
つまり、がん治療を行う病院は、歯科医師や歯科衛生士を配置し、患者に口腔ケアを行った方が、病床の回転率も良く、もらえる保険点数も高いというわけです。
こうした連携は医科、歯科、そして患者にとっても有益なもので、今後がん治療にとどまらず、他の治療においても同様の連携が広がっていく可能性は高いでしょう。
また、国際的にも、保険診療で歯科を給付しようという動きが進んでおり、今後、医科と歯科の距離はいっそう縮まるのかもしれません。
【参考資料】
須田立雄、医歯二元論から出発した我が国の歯科医学の歴史と将来展望、『歯界展望』2023年1月号
樋口輝雄、小幡英之介の受験書類について、日本歯科医史学会誌、27(1)、2008年
この記事を書いた人
水谷惟紗久(MIZUTANI Isaku)
Japan Dental News Press Co., Ltd.
歯科医院経営総合情報誌『アポロニア21』編集長
1969年生まれ。早稲田大学第一文学部卒、慶応義塾大学大学院文学研究科修士課程修了。
社団法人北里研究所研究員(医史学研究部)を経て現職。国内外1000カ所以上の歯科医療現場を取材。勤務の傍ら、「医療経済」などについて研究するため、早大大学院社会科学研究科修士課程修了。
2017年から、大阪歯科大学客員教授として「国際医療保健論」の講義を担当。
【主な著書】
『18世紀イギリスのデンティスト』(日本歯科新聞社、2010年)、『歯科医療のシステムと経済』(共著、日本歯科新聞社、2020年)、『医学史事典
』(共著、日本医史学会編、丸善出版、2022年)など。10年以上にわたり、『医療経営白書』(日本医療企画)の歯科編を担当。
趣味は、古いフィルムカメラでの写真撮影。2018年に下咽頭がんの手術により声を失うも、電気喉頭(EL)を使って取材、講義を今まで通りこなしている。 ★ユーチューブ動画★
【所属学会】 日本医史学会、日本国際保健医療学会
