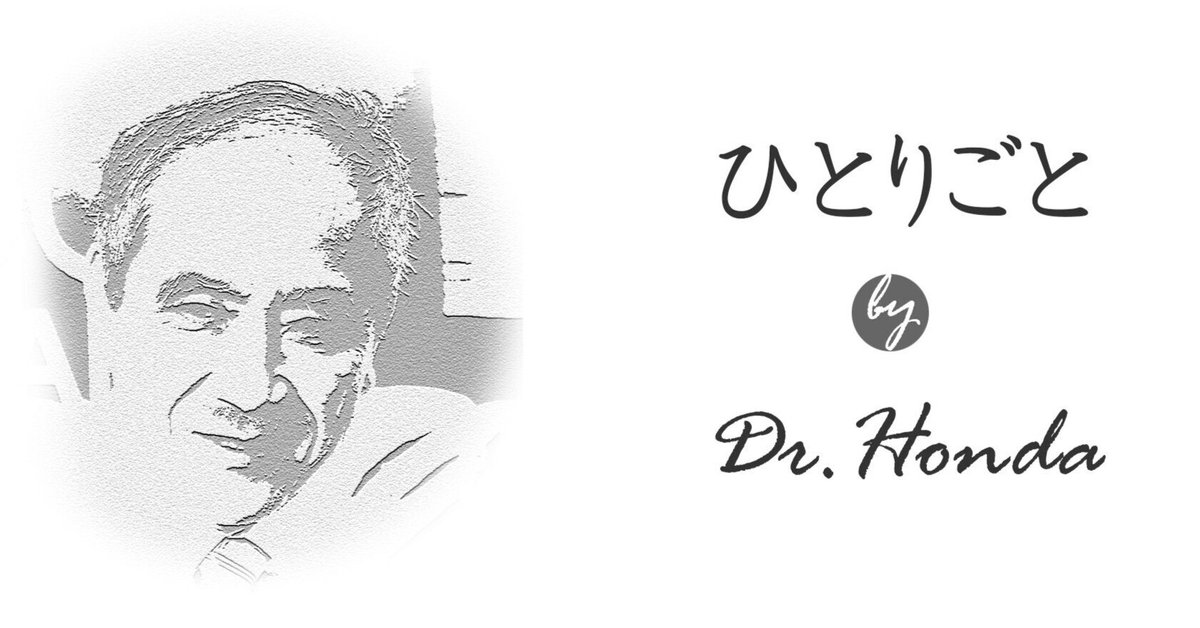
Dr.本田徹のひとりごと(3)2004.12.6
ソクラテスの思い出 :「人は己れの知ることについてのみ智者なのだ」
保健教育からは一見かけ離れてしまうのですが、今回東ティモールへの旅に携えていき、20年ぶりくらいに再読した、クセノフォーンの「ソークラテースの思い出(Memorabilia)」(佐々木理訳・岩波文庫)は、対話法または問答法(訳文では「討論」=ことわけ。古代ギリシア語のDialegesthai)が、教育や自覚形成の上で果たす役割の大切さを、数々の生彩に満ちた実例をもって教えてくれ、飽きさせることがありません。
著者クセノフォーンは言います、 「彼(ソークラテース)の言うところによれば、討論(ことわけ)という言葉は、(人々が)寄り集まって、物事を種類にしたがって<よりわけつつ>、ともに事を議することから出ているのであった。されば、われわれは進んでこれに習熟するように、日頃から大いにこれに励むことが大切である。」(第4巻5章)
つまり、これはNGO活動における計画や振り返り(評価)において、とくに大切にされなければならない、共に学ぶという姿勢、参加型の学習や会得法を述べたものと受け取ることもできます。
2500年近くもの時空を隔てているというのに、<私>の身近に現存している達人という感じを、ソクラテスほど親しく与えてくれる人もいません。そして、彼だったら、現代の世界を苦しめている深刻な政治・社会問題から、家族や個人の悩みや生き方についてまで、どんな意見や助言をしてくれるのだろうか? 少なくともソクラテスの厳しく温かい<吟味>に耐えるだけのことを、自分たちはしているだろうか、という設問が今もって有効であることに、 ただならぬ感動を覚えるのです。
昨年12月、カンボジア市民フォーラムの主催する、復興10周年記念シンポジウムで、ペン・セタリンさん(日本に留学中に、ポルポト政権を忌避して難民となられ、日本に帰化されたカンボジア人女性)と久しぶりにお会いし、東京外国語大学の先生をされながら、泉鏡花など日本の近代文学のクメール語への翻訳・紹介に努めていらっしゃることを知り、驚きと敬服の念を持ちました。「高野聖」などの鏡花の幻想世界に仏教的な観念が通底していて、カンボジア人が読んでも、とてもよく共感・理解できるのだそうです。プノンペンでは、彼女の訳した日本文学の名作が、海賊版も含めてたくさん本屋さんに並んでいると聞きます。セタリン先生と話していてもう一つびっくりしたのが、この頃、プラトンの対話篇(とくに「プロタゴラス」がお好きとのこと)を日本語で読み、ソクラテスの人柄に引き込まれている、と伺ったことでした。「難民になったのは不幸なことだったけれど、日本に長く暮らし、世界中のあらゆる古典を日本語で読めるようにならなければ、ソクラテスについて知ることもなかっただろうから、それだけは運命の転変に感謝しなければいけないかも」と、いたずらっぽく語る彼女を見て、なんてたくましくて、すばらしい人なんだろう、と思ったことです。
ソクラテスの倫理の源泉は「敬神」ということにありました。敬神に導かれて、人が知り得ることの限界を弁え、自己を知り、謙虚に生きることの徳を一方で説き、他方、神の求めと違ったことについては、迫害や死も恐れず、正しいと信じることを誠実に貫き通すという生を彼はまっとうしたのでした。
BC399年のソクラテスの死が、当時の都市国家アテネに与えた道徳的な敗北は、それより5年早くスパルタがペロポネソス戦争でアテネに与えた敗北より、はるかに深刻なものであったと、歴史学者のトインビーは言います。「ソクラテスに対する法の殺人ほど、 ヘレネス(古代ギリシア世界)の心情をすべての都市国家から引き離すのに役立ったものはなかった。なぜならアテネは、ヘレネスの全都市国家のあるべき姿の模範であるようにみずから唱えており、またソクラテスは、自身の生国以外の多くの国家に、友人や賛美者や弟子をもっていたからである。」
(A.トインビー 「ヘレニズム」 秀村欣二、清水昭次・共訳、紀伊国屋書店)
現代の「超国家」アメリカが、古代「ヘレネス」(当時は全世界とも言えた)のリーダー格であったアテネの犯した、傲慢(ヒュブリス)という名の悲劇的なあやまちを繰り返さない、という保証はありません。トインビーがこの本の結論で述べ、求めているのも、国家という神を偶像崇拝して、滅亡の道を辿ったヘレネス文明の失敗を、現代世界が警告として生かすことでした。アメリカの「真の友人」たる日本および日本人は、ソクラテスの勇気と智恵に見習わなければいけない時代が来ているのでしょう。私はバリ島のスコールに降り篭められたホテルの部屋で、クセノフォーンと トインビーを読み返しながら、危機意識とともにそう思い起こしたのでした。
