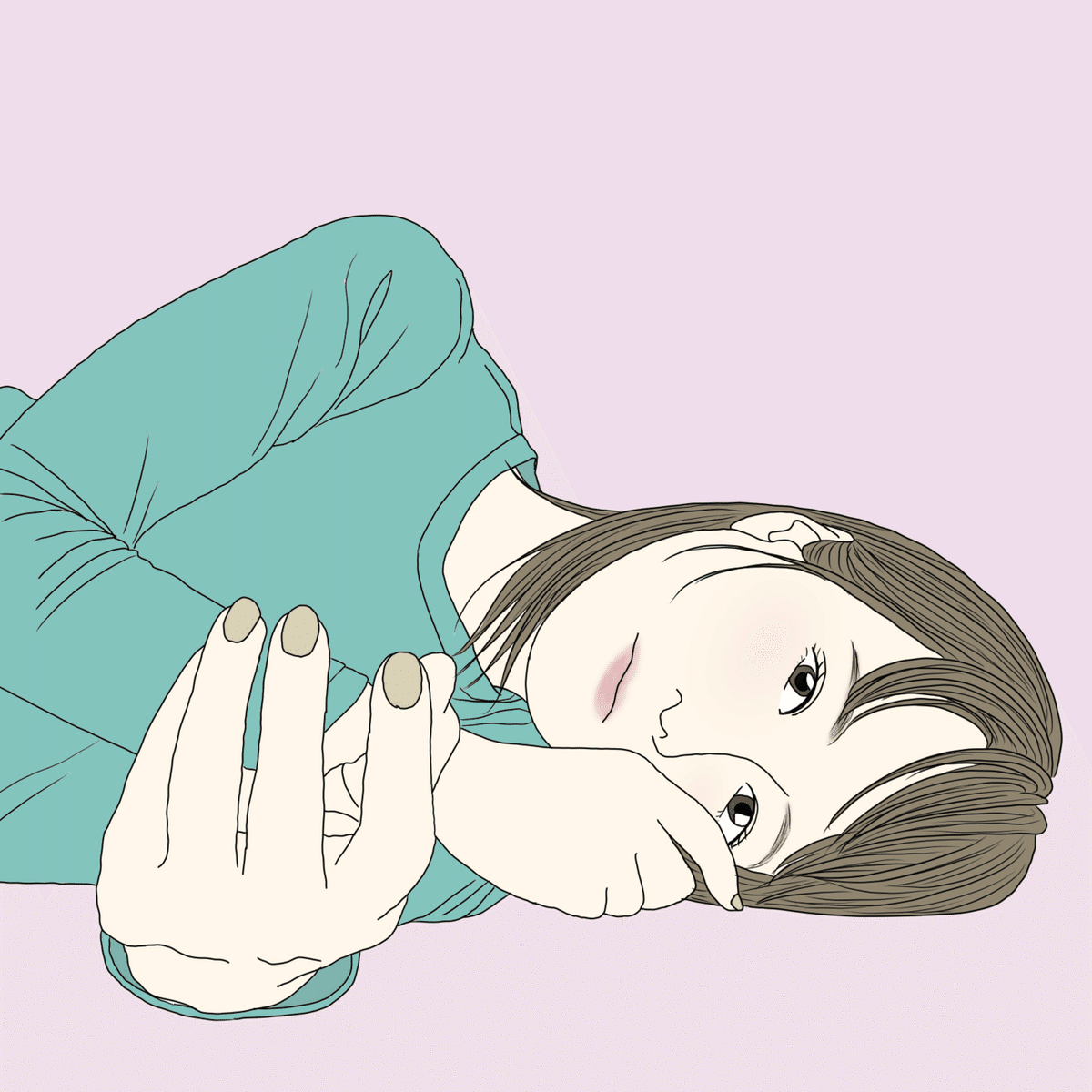妄想日記「三軒茶屋の一室から」
遠藤文香 20歳 大学生
最後の一本だった。三軒茶屋の黄色いアパートの一室、ベランダに置かれた灰皿の前で私は最後のタバコを指の間で持て余している。反対の手で、ポケットの中に手を突っ込むとくしゃくしゃになったレシートが出てきた。ハイライト、レッドブル、さけるチーズ、いつも同じものばかり買うのでいつのレシートだとしても大差ない。私は、再びそのレシートをポケットに戻し室内に視線を移した。カーテンは薄く、部屋の中の様子がよく見える。1DKの室内では、床にあぐらをかき友人たちが顔を赤くしてせわしなく笑っている。写真という共通の趣味を持つサークルの友人たちだが、写真の話題などとうに過ぎてしまった。それと同じく、写真に自分と同じだけの熱量を持った仲間を期待していた私もとうに過ぎ去り、この気だるさの置き場所に困っている。そして、また気だるくなるのだと分かっていても、飲み会に参加している自分が酸っぱかった。
「文香、一本ちょうだい」
ガラス戸の隙間から体を滑らし、友人の奈津子が私の隣に立った。私は、指に挟んでいたタバコをそのまま彼女に渡す。
「え、最後の一本じゃん」
「うん、いいよ」
「えー悪いなあ」
悪い、と口にしながらも、彼女は私からタバコを受け取りライターで火をつけた。彼女に吸われて、パチパチと火の燃え移る音が聞こえてくる。狭いベランダで、彼女の右肩が当たった。酔っているからか、熱い。私の身体がずいぶんと冷えていることに、その熱をもってして知った。
「私、帰るわ。タバコもないし」
そう言うと、奈津子がこちらを見て不服そうな顔をした。
「ええー、困るなあ」
「なんで?」
「だって、文香いなかったら誰がそこのゾンビたち介抱するの」
奈津子の悪気のない一言に、私の心は毛羽立った。同時に、何かを期待していた自分に気付かされて恥ずかしくなった。
「もう大人なんだから、自分で何とかしてよ」
「ふーんだ」
私は、ふてくされ顔の奈津子を放置してガラス戸を開ける。そして「引き留めないんだ」と思った。
溶けた綿あめのような匂いがする部屋に戻り、「帰りますね」と先輩たちに声を掛けると、みんな甘えた声で「なんで」と言って引き留めるふりをした。一人一人をやんわり振り切って自分のトートバックを肩にかける頃には、誰も私のことを見ていない。自分の甘えに気づかないように、私は部屋を出た。
しんとした住宅街を歩きながら、私は今頃あの部屋でどんな会話がなされているのだろうと気になってくる。もしかすると、重大な面白い出来事が起きているかもしれない。私は、遠くの方に見えてきたコンビニに向かって歩きながら、小さく呟いた。
「そんなことは起こらないだろうな」
今までの結果を集計した自分の一言は、私を少し落ち着かせた。
コンビニでいつもと同じものを買い、裏にある公園に入った。家々から漏れるオレンジ色の明かりとは違う、感情のない街灯に照らされているベンチに座り、買ったばかりのタバコに火をつけた。いつもの味わいにホッとして、香りを楽しんでいると突然女性の怒鳴り声が聞こえた。
「ふざけんなよ!!!」
私の身体が一瞬で固くなる。慌てて声のする方へ視線を向けると、公衆便所の前に男女の姿が見えた。私の脳が、どういう状況か把握しようと動き出すのを制止するようにまた女性の声が飛び込んでくる。
「人として恥ずかしくないのかよ!!!」
女性の怒鳴り声に呼応して、男性の声が続いた。
「お前の勘違いだっていってんだろ!!!」
ここまで聞いて「カップルの痴話喧嘩か」と私の鼓動は落ち着いてきた。「いい声だ」と、男性のよく通る声に対して思うくらいには余裕も出てくる。私は、しばらくこの様子を眺めることにした。女性が右手でぐしゃぐしゃと前髪をかきあげ、再び叫んだ。
「私が、今までどんだけ我慢してきたと思ってんの?!!」
「はあ!??我慢してたんならそん時に言えよ!!!」
「言わないでもわかれよ!!!」
「言わなきゃわかんねえだろ!!!」
ある意味息の合った喧嘩に、私は感心しながらどくどくと新しい感情が生まれてくるのが分かった。「いいぞ、もっといけ」「もっと怒れ」「全部吐き出してしまえ」そんな感情が、まるで自分事のように湧いてくる。
「他人のせいにしないでよ!!!」
「お前が勝手に信じるって言ったんだろ!!!」
「そう言わないと嫌われるからじゃん!!!」
「結局、勝手に疑ってキレんのはいつもお前じゃねえか!!!」
「結局、私に甘えて裏切るのはあんたの方じゃない!!!」
そこまで、怒鳴り合ってから二人は突然黙った。肩で息をしている二人の影が、街灯に照らされて揺れている。そうして、男性は投げやりに背を向けてこう言った。
「お前はさ、いいよな!!!そうやって、他人のせいにして自分から逃げられて。一人で、生きてみろよ!!!寄生虫が!!!」
女性の口から嗚咽が聞こえ始める。そして、男性は振り返ることなく公園の出口へ向かって歩き出した。対する私は、自分の怒りに驚いていた。言い返さず、今にも諦めてしまいそうな女性にも、勝ったと思っているであろう男性にも。二人は、私自身の気だるさの化身だと思った。それは、他人に落胆しながらも自分の価値を他人に期待している私でもあり、自分を信じることができず、自分より下らないものの側で「勝っている」と思っていたい私でもあった。私は、走り出した。そして、公園から出る男性の腕を掴み叫んだ。
「ふざけんなよ!!!」
それは、私への怒りだった。
大きく見開かれた男性の目が、驚きと恐怖で染まっている。そうして、次の感情がその目に宿る0.1秒の間。私の気だるさはあの三軒茶屋の一室からもう遠い。