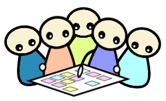【組織開発】良い対話の手順と気配り
こんにちは、組織開発実践コーチの「はやまこ」です。
リアルな「組織開発」実践の「はじめ方」「活用方法」「人材育成」などをテーマに書いています。
良い組織づくりのために「良い対話」はかかせません。
今日は、「良い対話」について考えてみたいと思います
コミュニケーションはできている?
実際の組織開発活動をお手伝いしているとよく聞く言葉があります。
「うちはコミュニケーションできていると思います。雰囲気は悪くないですよ」
あいさつもできているようだし、会話も活発でみなさんの表情も明るい感じです。
でも、何かしら上手くいかないことがあるから、組織開発を導入することになったはずなのです。
コミュニケーションは悪くないのに、メンタルの休職者がいるとか、基本的なミスに気付かないまま進めて大きな手戻りが起きているなど、生産性が向上しない困った現象はいろいろな形で起きているのでしょう。
つまりコミュニケーションは大丈夫という認識だけど、仕事面では何かモヤモヤする状態なわけです。
表面的な関係性は良好だけど、本当に困っていることに向き合う議論は避けているようなチーム状態です。
広く・深くみんなで考えるのが「良い対話」
困った状況に向き合うためには、楽しく仲良く会話ができるだけでは不十分です。
もやもやした対象を「見える化」して、その現象を分解・整理して「言語化」する作業が最初に必要です。
現状認識をあいまいなままで話し始めてしまうと、絡まった糸がもっと複雑に絡み始めてしまうからです。
現状の見える化ができて自分たちを俯瞰して客観視できるようになったら、全員で疑問点やアイデアを書いてみましょう。
「話す前に書く」というのが、効果的な「対話」の基本です。
みんなで書けば、それぞれの考えが言語化されてテーブルの上にそろいます。
それを見ながら話し合いを始めると、「対話」が自然と広く深いものになっていきます。
「良い対話」の「手順」
簡単に手順にまとめておきましょう。
① もやもやした現象に向き合ってチーム全員で取り組む(全員参加)
② 現象を言語化、見える化をして整理する(事実の整理と共通認識)
③ すぐ話しださないで、まず全員で意見を書き出す(全員発言の仕掛け)
④ すべての意見を俯瞰しながら対話をはじめる(広く・深く)
実際にやってみると、これらが簡単なようで意外と難しいのです。
たとえば、結論を急ぐタイプの人がひとりいると、手順がくるって特定の意見を中心にした議論が始まってしまいます。
声の大きな人、影響力の強い人
声の大きな人や影響力の強い人はどこにでもいます。
そういうタイプの方の強い意見で押し切ってしまうと、たしかに結論は早く出ます。
ただし、共感や違和感を十分に認識する前に対話が終わってしまうので、もやもやはくすぶり続けます。
お互いの意見や気持ちを知ることは、もやもや解消と無関係ではありません。
ベテランの方は、頭の中ですぐに答をイメージできますが、それについていけない人もいるはずです。
めんどうに感じても上記の手順を意識して一歩ずつ進めることをおすすめします。
繰り返し練習してスムーズに進められるようになってくると、その良さがじんわり腹落ちしてくるはずです。
リアルな課題で練習しましょう
みんなで歩調を合わせて進めるのが「良い対話」の基本です。
テーマは抽象的な内容ではなく、リアルに困っていることを対象にするのがよいと思います。
誰かに具体的なメリットが生まれるようなテーマが理想的です。
なぜなら、チーム対話を喜べる人がいるとわかれば、メンバーは自然と協力的になるからです。
「違和感」も大切に扱う「気配り」
最後に、
「共感」だけでなく「違和感」を共有することも大事なコツです。
身近な課題でも、きちんと手順をふめば人によって認識に違いがあることがわかってきます。
とはいえ、違和感が残っても「何かを決める」ことを求められるのが現実。
ただ、その違和感を見て見ぬふりするより、そのまま受け入れて共通認識とする方が、もやもやした雰囲気は残りません。
これは、違和感があることを認識したうえでの「コンセンサス」なのです。
だから良い対話には、話し合いのルールだけでなく違和感を丁寧に扱える一人ひとりの「気配り」も大切になります。