
異世界転生のない世界で人生やり直し #1
あらすじ
北海道札幌市に暮らすの兎田恒星(うだこうせい)27歳は、父の死と、医学部受験失敗によって、自宅でニートをしていた。
人生に絶望している恒星を見かねた姉は、荒療治として、恒星を北海道の離島「奥尻島」に無理やり連れていき、奥尻でカフェを経営する宮野のもとでバイトをさせることに。
奥尻島を舞台に、辛い現実と向き合いながらも、恒星はカフェのバイトと、宮野の娘の家庭教師を通じて、少しずつ変化していく。
第一話 異世界転移

自室のベッドの上で目覚めたら、いつものように頭が痛かった。
時計を見る。どうやらまた、2時間ほどしか眠れなかったみたいだ。
頭痛薬に手を伸ばして、近くにあったコーラと共に流し込む。最近は、頭痛薬の中でも、鎮痛成分を増やしたものでないと効果が出ないようになってきた。
時刻は午前1時。街が寝静まる頃に、僕は家を出て散歩にでる。札幌市の7月は、夜は上着を一枚羽織らないといけないくらいにはまだ冷たかった。薬の効果で段々と頭痛は弱くなっていったが、それでも、息のしづらさ、苛立ちは治らない。これを治すには、薬ではない対症療法を取る必要があるのは明らかだが、人間はそう簡単に変化したり、行動したりすることができないと自分にまた言い訳をする。
家から15分ほど歩いた。薄暗く静かな中島公園を抜けると、夜中なのに、店の看板や街灯によって照らされて明るく輝きを放つ、すすきのの繁華街に入っていった。
こんな時間に起きているのは自分だけではないということがはっきりと示され、僕がこんな夜更けにここにいることを認可してくれているような気がするから、どうしてもここへ散歩にきてしまう。
とはいえ、どこか酒を飲みにバーに行くこと、ましてや風俗に行くことはない。そんな金もないし、好きでもないからだ。
7月のすすきのの街を、上下スウェットにサンダル、寝起きの27歳男性がゆったりとした歩調でゆく。
普段入らない遠くのコンビニまで歩いて、中に入った。ほかのコンビニにはない商品や、陳列の方法なんかも細かく確認する。とにかく、もう毎日のようにこの夜のすすきのを徘徊をしてはコンビニに行き、何かを買って買えるという超日常的行動を繰り返している。そんななかで、何らかの変化をつけないと気が狂いそうになるのだ。それくらいでしか、変化をつけることができない自分自身にも腹が立った。
あまりにも微々たる変化と見る者もいるかもしれないが、日々恐ろしいほどに変わらない日々を生きる僕にとっては、大事な変化なのだ。コンビニで増量中だったよもぎ団子を買って帰路につく。僕にとってはこれが1日の大事な気分転換で、なんとか自己を保つためのサプリメントだった。
札幌市の中心部のすぐ傍を流れる豊平川まで歩き、橋の上でさっき買った団子を食べ始めた。
いつものように、後悔の念が、どこからともなく湧き出てきた。もう何千回も思い返しては、もうそんなことを考えてもどうしようもないのに、あのときああすれば、ということを考えずにはいられない。
僕は、27歳にもなって働きもせず、母親から援助を受けながら実家で暮らしている。高校を卒業してから、この状態は続いていて、もう少しで、10年になる。
ーーー回想ーーー
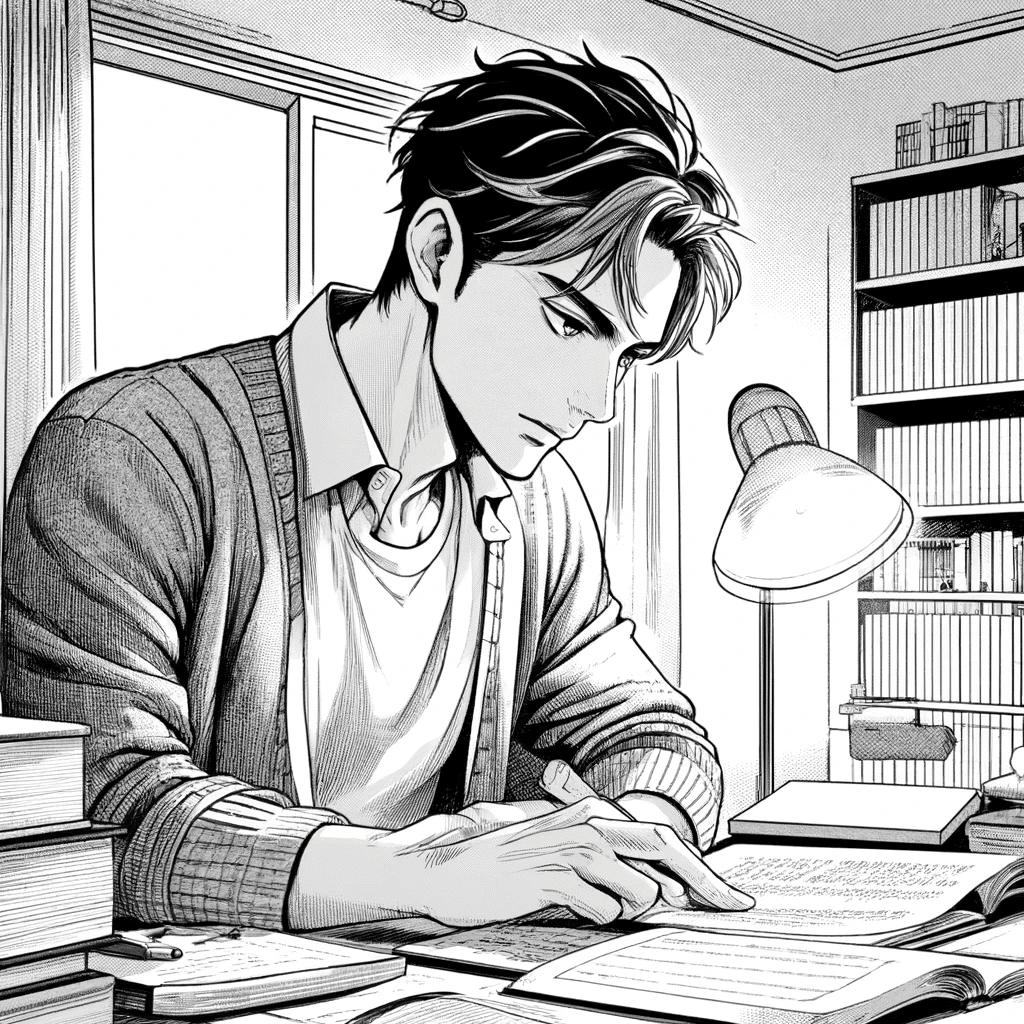
僕は、少し前まで国公立大学の医学部に合格して医者になるため、受験勉強をおこなう浪人生だった。
高校2年の夏から、父親が医療関係の仕事をしていて、姉も看護師だったこともあり、僕は医者を志すことにした。
流石に現役では医学部はおろか、地元の最難関である北大の非医学部にも合格できなかったが、1浪目ですでに地元では最難関とされる北海道大学の非医学部であれば合格できる学力をつけていた。元々高校生のときの僕は、成績がいい生徒ではなかった。むしろ、下から数えたほうがいいくらいのもので、そんな僕が、1年半ほど勉強することで、成績がすごく伸びたことに、周囲の友人は驚き、家族は喜んでくれた。僕も、そんな自分に自信が付いた。
これで、このまま行けば医学部にも合格できると思い、2浪目に入ることを決めた。
2浪目は、国立医学部の2次試験の対策を重点的に行った。センター試験の点数も、医学部に合格を目指す人たちの1つの目標である、9割以上を獲得することができた。
今年は合格できると思って望んだ試験は、不合格であった。
間違いなく、合格できる可能性のある勝負だった。けれど、僕はその勝負に負けた。
2浪目の受験に失敗したことで、風向きが変わった。
この時点で、僕は20歳だった。友人にも1浪している友達は何人かいて、以前は浪人仲間で受験についての話をすることもあったけれど、2浪目に入ってから、他の友達は受験がうまく行ったかどうかにかかわらず、皆大学生になっていた。大半の現役で大学進学した友人は、すでに3年になろうとしていて、就活先についてや、東京に出ていくかどうかについての話をしていた。
僕は、僕だけがみんなから取り残されて、ずっと同じところに立ち続けて、同じ遊びをしているような感覚に襲われた。学生時代は、学業の成績や部活でレギュラーを取ることがみんなのゲームだったように、今では、ほかのみんなのゲームは就職と、結婚といった、次のキャリアを見据えていた。僕だけが、みんなが飽きて放り投げたゲームをしていた。
しかし、いま、非医学部に入学しても、この1年の努力はなかったことになるほうがもっと怖かった。、もう、このときには後に引くにも先に進むにも、苦しいということに気がついた。
僕は、再び浪人することにした。
3浪ともなると、明らかに中高時代の友人とは感覚的なものが離れていることを感じた。友人も僕と話をするとき、僕と話す共通の話題を見つけるのに苦労しているのが容易に理解できた。最近何をしているかと聞かれても、勉強としか答えようがなかったし、僕も、彼らが何を考えているのか少しずつ分からなくなったような気がした。
僕からすれば、未だに大学の生活がどんなものなのか、というのは体験したことがないため、サークルや、1人暮らし、授業や研究について未知で溢れているままだった。
けれど、友人達はそれらについてすべてを知ってしまったような、どこか、無関心であるかのような印象を受けた。彼らも僕のように大学というものに期待はしていたはずだ。けれどきっと、その期待とはまた違ったものが待っていて、それを知ったいま、彼らの興味は別のところにあるのだろうと思う。
きっと僕も、彼らと同じように、やがては大学生活にも慣れて、更にその先のことについて思い悩む事があるのだろうと思った。しかし、僕はどうしたって知らないものは知らない。僕だけが、みんなが飽きたものにずっと憧れつづけている。
3浪に入ってから、これまでのストレスが目に見える形で現れるようになった。もともと痩せていたとはいえ、体重は高校卒業時から10キロは増えた。それと、友人に勧められて吸ってみたタバコにハマり、最初は友人からもらったときだけ吸っていたのに、いつのまにか一人でも吸うようになった。医者になる人間が吸うべきではないのは、100も承知だが、むしろ、その事実もタバコへの手を伸ばさせる推進力になっている気がした。
3浪になると、成績の伸びはそれまでよりも鈍化した。そもそもセンター試験で9割近い得点率だったのを、さらに伸ばすことは難しいし、二次試験も問題によっては絶対に合格できるような回答率を出すときもあったが、そうでないときもあった。実力は確実についており、合格できる可能性がそれなりにあるのも間違いない。もちろん、実力が圧倒的ならば話は別だが、運も絡んでくるのが受験だと言わざるを得ない。実際に東大受験においても、2回試験をすると1回目の合格者の半分は2回目では不合格になるという話もあるくらいだ。
3浪目の結果は、不合格であった。

ここで、僕の中での精神は既に限界を迎えていたのだと思う。1年にたった1度しかない試験に膨大な時間を費やしてきた。そして、その努力は間違っておらず、ある程度の結果も出している。なのに、合格できない。自分は誰かに意図的に落ちるように採点を調整されているのではないかという、疑心暗鬼にかられることすらあった。もう、来年受験しても受かることはできないのではないかと思ったし、もう一年受験勉強を継続させることはできないような気がした。
医学部を受験したのは前期日程で、後期日程では医学部以外の学部を受けることができる。前期よりも後期のほうが同じ学部を受験する場合後期のほうが難易度は上がるため、同じ大学の医学部を受験する場合、前期で不合格だった場合は後期で受かることは難しい。
僕は、後期日程で、医学部ではない工学部などの理系学部を受験して、大学に入ることを親に提案された。親としても、浪人を重ねる僕を心配していたのは明らかだ。とにかく、最低でも北大の非医学部には合格できるのだから、とりあえず大学にいきながら、医学部を目指してもいいのではないかというのだ。
今思うと、この提案を受け入れておけば、と思わない日はない。むしろ、もっと早くにそうしていればとすら思う。けれど、今さら医学部ではない学部に進学しても、そこにいるのは自分より3つも年下の学生ばかり。サークルにも馴染めるはずがないと思った。それになにより、医者になれなかった自分自身を受け入れることがたまらなく嫌だった。
こんなことは、今思えばくだらないプライドだったのかもしれない。家族も僕の考えを尊重してくれた。理解もしてくれた。ここまで受験のチャンスをもらえる家庭はそうはないと思う。だからこそ、合格の報告を伝えたかった。
あと1年だけ。そう家族と話し合い、僕は4浪目に入ることにした。けれど、4浪目でも僕は合格できず、そしてそのあと。。。
ーー回想終了ーー

ふと、強い風が吹いて、我に返った。考えれば考えるだけ、辛さが増えるだけなのに、考えずにはいられなかった。こうして過去あったことを鮮明に思い出しては、満足するところで現実に戻ってくる。
そして、あれほど可能性に満ちて、輝いていた僕の人生は淀み、僕の夢はもう二度と叶いはしないのだという、このどうしようもない現実によって、涙があふれてきた。
「あのとき、こうしていれば、あの頃に、戻れれば」
懐かしい歌の一説を、小さな声でつぶやく。
タバコを1本吸って帰ろうとしたとき、川に目が行った。
橋の真下の、川の中腹で、奇妙な緑色の光が見えた。自然に発生するようなものではないことはすぐに分かった。

僕は、気になって、橋の上から数メートル下の川を覗き込んだ。よく見えなかったので、橋から身を乗り出して、注意深く見てみた。
発光がさらに強まったような気がした。僕は何か不可思議な現象が起きているのではないかと思い始めていた。どうしようもない現実を変えてくれるような、何かが起きてくれるような気がした。
あまりに発光に夢中になっているあまり、僕は足を滑らせて橋から落下した。

「うああああああ」
光の中に吸い込まれるように、川へと落ちた。水面に落ちた時の強い衝撃が身体に走った。
「いってえええ」
目を開けた。川には足がついた。

異世界に飛ばされることなどもちろんなかった。付近には、大きなライトが捨てられていた。発光の原因はこれだったようだ。
きっと、僕の気がおかしかったのと、川の水面に光が反射したため、ただのライトの光が幻想的なように見えていただけだった。少しでも何かが起きてほしい、何でもいいから、とにかく僕を救ってほしかった。
僕は、少しでも何かに期待していたことをとてつもなく恥ずかしい気持ちになった。どれだけ学力が高くても、苦しい現実を前にすると、都合のいいように現象をいくらでも捻じ曲げて解釈するし、自分だけが特別な能力、幸運を兼ね備えていると思わずにはいられない。僕は本当に残念な人間なのだと思い知った。
この世界には、辛い人生を都合よく異世界に転生してやり直すことのできるシステムは存在しなかった。
「なにやってんだろうな、ほんとに。漫画みたいな奇跡なんてのは、あるわけないのにな。」
ずぶ濡れで家に帰った。静かに風呂場へといき、濡れた服を洗濯機に入れ、シャワーに入った。
自室に帰り、少しゆっくりしていると、もう日が昇っていた。母が起きてきて、食事の準備をし始める音が部屋の外から聞こえてきた。
朝食の準備ができたというので、僕は自室の2階から1階へと降りる。まもなくして、姉が家に上がってきた。姉は、実家の真向かいにあるアパートに暮らしていて、食事を食べにうちに出入りしていた。
テーブルに朝食を運び、3人でそれを囲んだ。食べながら、姉は僕に話しかけてきた。父の使っていた椅子は、残ったままになっていた。
「また今日も眠れなくてどこか出歩いてたでしょう? ちゃんと薬飲んだ?」
「飲んだけど、途中で起きた」
「そう。。もうこれ以上強いのだと、危ないしね。その年でその格好で夜中にふらふらしてたら変な人と勘違いされそうね」
会話は、長くは続かない。続けたくもない。姉が心配しているのは、わかりきっている。だけど、僕には今の状態をどうすることもできないのだ。
「ちょっと前もおんなじこと聞いたけどさ、あんた、もう今年受験はしないんでしょ?」
聞かれたくないことを聞かれて、むっとした。
「うん」
「だったら、そろそろ働いたら? 27なんだし、もちろんつらいのはわかるけどさ。」
正論だ。だけど腹が立った。
「わかってるよ」
僕は強く言い返した。いまさら働いたところで、高卒の27歳を雇ってくれるとしたら、低賃金の派遣かアルバイトだろう。医学部にあと少しだった自分が、アルバイトなんてと、そんなことを思う。
いつもなら、姉はこれ以上は追及してこないが、今日は違った。
「お母さんも、この家も、いつまでもいてくれるわけじゃないんだよ? お父さんみたいに、いついなくなるか、わからないんだから。」
「うるさい! わかってんだろうがそんなこと」
僕は姉に、何一つとしてまともな返答ができずに、ただ吠えた。まったくその通りだ。僕だって、自立して、家族を助けるはずだった。けれど、今はもう無理なのだ。何もかもデッドロックされてしまったのだ。医学部に入学することはできないし、今更それ以外の学部に進学しても卒業するころには30を超える。かといって、高卒としては仕事をする気にもなれない。すべての道が、大きな壁で塞がれている。
母は、何も言わず、ただ僕のほうを見ていた。母も55歳。改めて考えると、普通にもう老人の一歩手前といった感じだ。高校生の時の母親の姿と比べると、随分と老けたなと思う。
「もう、この状況じゃ何したって仕方がないって思ってるでしょ。別にあんた健康だし、まだ20代なんだし、医者にはなれなくても、他にできること、色々あると思ってるけどな。地頭はいいんだし。まあ、でも、あんたが辛いのも、わかるけどさ。」
僕は食事をなるべく早く済ませて、自室に戻ることにした。
「はいはい、わかってる、わかってるよ」
「話は終わってないでしょ」
「終わった。今そう俺が決めた。」
「待って、もうこのことはいいから。これ、友達からもらった栄養ドリンク、これだけでも飲んでいきな」
姉が僕が部屋に戻ろうとしたとき、姉は勤務先の友人からもらったというドリンクを僕に手渡した。
僕は何気なく、そのドリンクを飲んだ。普通の栄養ドリンクという感じの味だった。
姉が独り言のように小さく言った。
「もう、これまで色々言ってきたけど、色々言うだけじゃダメなケースもあるわよね。ちょっとだけ悪い気はするけど、あんたと、お母さんのためだからね。」
僕は、姉は何をぶつぶつと独り言を言っているのだろう、と思いながら、部屋に戻りベッドに寝ころんだ。すると突然、強い眠気に襲われた。これはあきらかに自然発生的な眠気ではないとすぐに分かった。僕の視界がぐにゃぐにゃになって、意識を失った。

意識が戻ってきた。まだ頭にモヤがかかっているような感じだ。なんだかひんやりと冷たいものの上にいるような気がして、すこし手を動かしてみた。すると、やはりひんやりして、さらさらとした感触が伝わってきた。
僕は、砂の上にいた。
大分意識がはっきりとしてきた。薄目を開けてみると、青空。そういえば、風もわずかにある。ここは屋外だ。
そして、横を見ると、空の青とは別の濃い青があった。海だ。
自宅のベッドで寝ていたはずの僕は、目が覚めると砂浜にいた。
ここで、僕は状況が異常であることをはっきり認識した。慌てて立ち上がると、少しフラフラした。
見渡す限り、やはり海だ。海水浴場だった。
僕は、異世界転生したのかと思った。しかし、身体は僕のままだった。
「どこだよ、ここ」
続く。
第二話
第三話
