
元銀行員が、美大に入学したワケ
はじめまして。
クラウド会計ソフトのfreee株式会社で働く、関根です。
当社の経営管理本部で財務・経営管理をしています。
この4月から、
武蔵野美術大学 造形構想研究科 造形構想専攻
クリエイティブリーダーシップコース
に入学しました。
コロナの影響もあり、開始が遅れましたが、
先週よりリモートでの授業が始まりました。
簡単に経歴をお話しすると、
・三井住友カード株式会社(2年)
→コールセンター運営企画、事務企画。
・株式会社みずほ銀行(8年)
→国内営業を経験後、シンガポールとタイ・バンコク駐在。融資審査・クレジット分析、日系企業の海外進出支援。
・freee株式会社(もうすぐ4年)
→営業、事業企画、経営管理/財務。
上場準備メンバーとしても携わり、昨年12月、東証マザーズに上場。
って感じです。
さて、本題ですが、
これまで金融の世界で生きてきて、
直近も財務として、資金調達をしたり、ずっと数字を睨んでいたり、お金に関わる、左脳的な仕事ばかりをしてきた私ですが、
なぜ、ムサビで、デザインやアートを学ぶのか
その理由についてお伝えします。
「事業創造×ファイナンス」で、企業を支えたい
これまでの私の職業人生の多くを占めるのが、
財務、ファイナンスと呼ばれる領域です。
お金をどのようにして集めて、
集めたお金をどのような商売に使おうか、
どんだけ売って、何に費用を使うかの予算を決めたり、実績を管理したり、そういったことを
日々悶々と考えています。
ここ数年は、副業で中小企業の資金調達のハンズオン支援や、業務オペレーション改善、事業計画策定などもお手伝いするようにもなりました。
ただ、自分には悩みがありました。
新しいサービスやモノ作りについて、
0→1で発想したり、作ったりする経験や知識が、ほぼ0であることです。
加えて、成長を促進させるためのマーケティングも詳しくない。
そういった「攻め」の領域に関する経験・能力がないことが、企業の支援の幅を狭めているし、どことなく頼りないし、自分のアドバイスや発言もどこか迫力不足なのでは、と感じるようになってきました。
理想で考えるなら、
資金調達が仮に上流とすれば、
調達したお金をもとに、サービスを一緒に企画・開発し、それを販売し、顧客に届けるといった下流まで、一連の流れでワンストップで企業を支援出来ないか
「事業創造」×「ファイナンス」
この2つの両軸で、
日本のスモールビジネスを支援したい
そういったことを考えるようになりました。
「イノベーションの起こし方」と「越境人材」
それから、0→1でサービスを起こすとか、モノを作るとか、そういった内容に関する本を読んだり、イベントに参加したりしていました。
昨年はIDEO Tokyoのワークショップに参加して、
デザイン思考について体験をしたりしました。
ワークショップでは、
新しいサービス・プロダクトを、チームでアイデアを出し合いながら、プロトタイプを作成するまでの一連の流れを体験し、
新しい発想法・イノベーションの創造に関するお作法を学びました。
とても刺激的な内容で、
もっとデザインやアートの考え方、思考、姿勢について学びたい、
そして、とにかく手を動かしアウトプットする機会を作りたい、そう思うようになりました。
それで、
国内外のデザインスクールを調べたりする内に、
以下のブログを発見しました。
ビジネスとデザインの交差点〜 創造科学への道
http://idllife.blogspot.com/
このブログの作者は、佐宗邦威さんという方で、
P&Gでマーケターを経験された後に、アメリカのイリノイ工科大学に留学をされたそうです。
このブログの中に記載があるのが、
今後、イノベーションを創造する上で、以下の重要性について説明してくれています。
1.デザイン、エンジニアリング、ビジネスの交差点で生まれる新たな職業の存在
2.デザイン、エンジニアリング、ビジネスの3つのコラボレーションを促す場作りという新しい価値の存在
3.創り続けることによってWHY(存在意義)を問いかけ続ける究極の姿としてのアーティスト的なイノベーターへの道
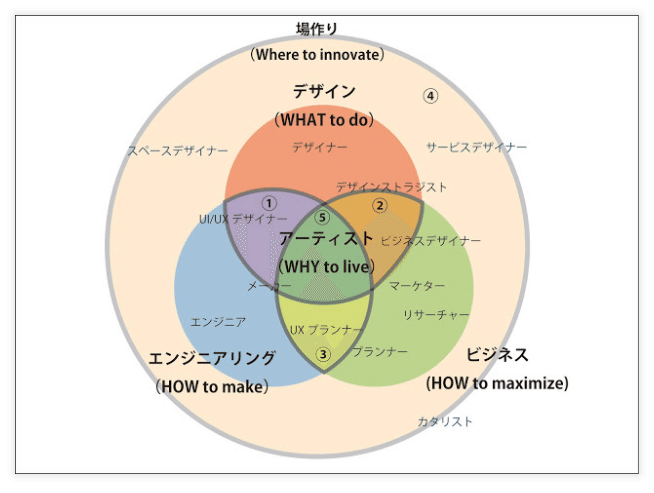
(出典: 上記ブログ: ビジネスとデザインの交差点〜 創造科学への道)
これを読んで、「これだ!」と思いました。
チャートは、「デザイン」、「エンジニアリング」、「ビジネス」で構成されていますが、自分はこのチャートでいうところの、右下のビジネスのところにいるなと。
そこから、上部のデザイン寄りに向かう、つまり、
”デザイン、エンジニアリング、ビジネスの交差点に立つ”ことで、
「ビジネスデザイン」や「デザインストラテジスト」という新たな存在にピボット出来たら良いな、そう思いました。
違う領域への交差点に立つこと、そしてそれを超えていくことを、「越境」といい、それを行う人を「越境人材」と呼ぶそうです。
そして、私は自分のありたい姿を叶えるために、
越境人材を目指すことにしました。
整理すると、こんな感じかな...
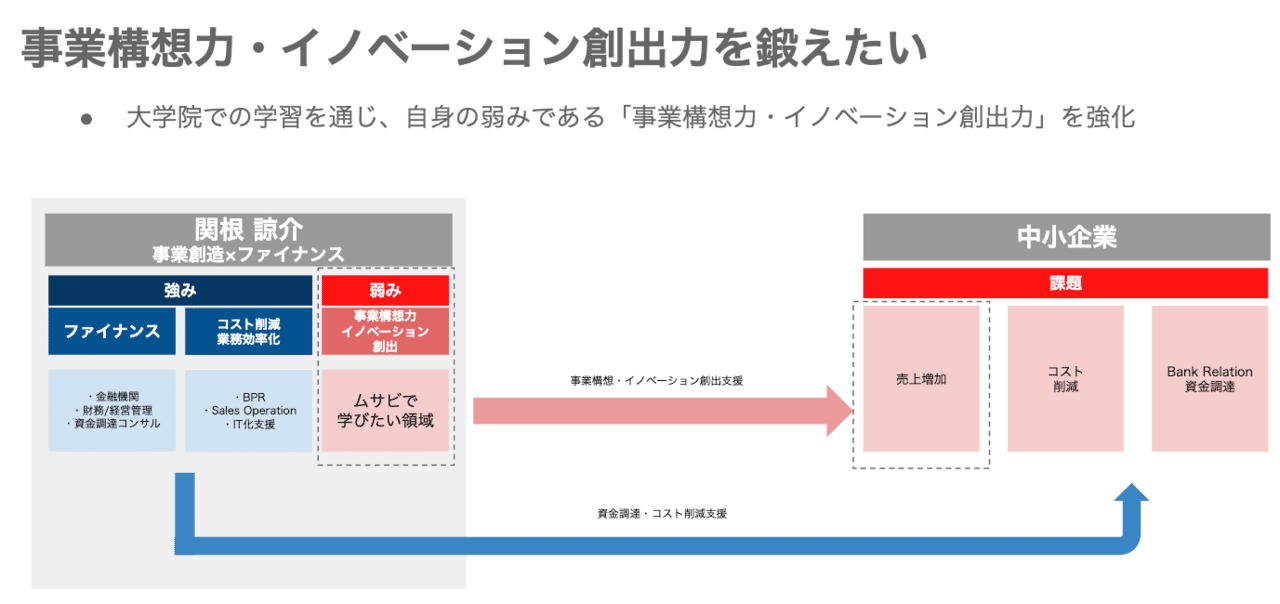
なお、佐宗さんの以下図書も大変参考になりましたので、共有します。
最後に
という経緯で、ムサビに入学することにしました。
国内・海外のデザインスクールは色々調べたりはしたのですが、
なぜ、ムサビを選んだかについては、次回以降お話し出来ればと思います。
また、ムサビでの学びについても、定期的にお伝えできたらと思います。
