
MDGsは、SDGsと本当はどういう関係にあるのか? 【SDGsとは一体、何だったのか?】第3回・中編
●この連載について
今から筆者がお話しするのは、SDGsを世界史の中に位置づけてみようとする試みだ。だが、なぜわざわざそんなことをしようとするのか?
現在すでにSDGs終了後の次期開発目標(ポストSDGs)にかんする議論が動き出している。だが、日本の現状はどうだろうか? SDGsに対する「記号」的なイメージばかりが先行し、開発の最前線の議論や実践と、市井の印象のあいだのギャップも開いている。すでに初期段階から普及段階に移行し、日常に溶け込んでいるという評価もできようが、一時に比べれば人々の関心は薄れ、2021年頃からは冷笑的な反応とそれに対する対抗言説も目立つようになった。
誤解のないように付け加えると、筆者は、SD(持続可能な開発)は必要であると考えている。だが現場や専門的な知見のみならず、そもそも「開発」や「援助」に関する話題は必ずしも一般に共有されているとは限らない。他方で、経緯を踏まえない印象論や陰謀論と結びついた言説も目立つようになっている現状がある。
この国で、「お祭り」が単に忘れ去られていくのはいつものことだ。現状の日本における受容のあり方には問題がある。だが、それどころか人類史にとって「SD」とは何かという根幹までもが、不信と懐疑の対象になってしまうのだとしたら問題だ。
この連載の狙いはそこにある。筆者の関心は、手放しの称賛や冷笑よりも、まずもってなぜこのような状況になったのかを世界史の文脈のなかにたどることにある。そこでこの連載では、「SDGs」がどのような経緯のなかから生まれたものなのか、世界史のなかに文脈づけてみようと思う。
貧困撲滅のための「ビッグプッシュ」
さて前回は、第二次世界大戦後の国際開発規範の変遷が、1980年代に市場メカニズムを重視した構造調整プログラムが貧困を拡大させたことへの反省から、1990年代に「人間開発」の重視に舵が切られ、2000年代初めのMDGsに至って次の3点の要素を持つに至った、ということを確認した。

途上国の貧困撲滅を掲げ、MDGsの旗振り役を担ったのは、世界銀行のエコノミスト、ジェフリー・サックス(1954〜)という人物だ。
彼は次のように論じる。
サハラ以南のアフリカに集中する最貧国は、医療や教育へのアクセスが不十分なため、農業や産業への投資をするための貯蓄が乏しく、にもかかわらず人口が増加し、一人当たり資本ストックが低下し、貧困から脱出することができなくなってしまう。
この貧困の罠から脱出するには、たとえばマラリア避けの蚊帳を大量に供与するなどの思い切った大規模な援助(ビッグ・プッシュ=大きなひと押し)が必要である。
と、このように主張した(このビッグ・プッシュ理論に対しては、開発経済学の分野では有名なウィリアム・イースタリーとの論争がある(ウィリアム・イースタリー『傲慢な援助』東洋経済新報社2009年))。
MDGsにもあった「持続可能な開発」
こうした動向をみていると、MDGsにはまだ「持続可能な開発」を重視する考え方が込められていなかったように思われるかもしれない。
名称そのもに「持続可能な開発」という語を含むSDGsの前身がMDGsであったと聞くと、余計にそう思ってしまうところもあるだろう。
だが、MDGsは「持続可能な開発」に基づいておらず、SDGsになってはじめてそれに基づくようになったのかというと、これも誤りだ。
MDGsの実施をうたったミレニアム宣言では、21世紀における国際関係にとって不可欠な価値観が「持続可能な開発という指針」であり、「持続可能な開発の原則に対する支持を再確認する」と明記されている。
Ⅰ.
6(抜粋). 自然の尊重:全ての生物及び天然資源の管理においては、持続可能な開発という指針にしたがって、慎重さが示されねばならない。それによってのみ、我々が自然から享受している計り知れない富を保全し、我々の子孫に伝えることができる。現在の持続不可能な製造・消費様式は、将来の我々の福利及び我々の子孫の福利のために、変更されねばならない。
Ⅳ.
22. 我々は、国連環境開発会議(UNCED)で合意されたアジェンダ21に盛り込まれた原則も含め、持続可能な開発の原則に対する支持を再確認する。
「持続可能な開発」をめぐる先進・途上国間のズレ
すでに私たちは連載の第2回では「持続可能な開発」概念がどのような経緯で生まれたのかという問いに対して、その成立過程に途上国出身者が関わった点に注目した。
1987年に発表された『ブルントラント報告書』では「持続可能な開発」の要素として次の2つを読み取ることができる。

ただ、とくに争点となったのは①のあり方だ。
途上国のニーズを満たそうとすれば、途上国の工業化は不可欠となる。すでに人為的な開発によって気候変動がもたらされるとの学説が1980年代から報告されるようになり、その対処が検討されることとなっていた。地球温暖化説には、工業化にとって必要な「化石燃料」が関係している。
持続可能な開発を掲げた初の国際会議である1992年の地球サミット(国連環境開発会議(UNCED))でも、そのことは議論を呼んだ。

先進国は①に理解を示しつつも、②には後ろ向きだ。
これに対して途上国は、かつて先進国が産業革命期以降そうしてきたように、これから工業化をする権利を主張し、先進国が環境規制を進める必要を主張した。
つまり、まず工業化と先進国の援助を通して①を主張する。途上国における環境の悪化が、地球環境問題に発展することを防ぐためである。
それに加えて先進国に対しては②を要求する。
途上国と先進国の間で、環境規制に差を設けるべきだというわけである(これが「リオデジャネイロ宣言」第7原則に盛り込まれた「「共通だが差異ある責任」原則」だ)。
つまりここで「持続可能な開発」概念は、サラ・ロレンツィーニの言葉を借りれば「望ましい組み合わせに応じて、個別にカスタマイズする」代物となってしまっているのだ(サラ・ロレンツィーニ 2022 『グローバル開発史』名古屋大学出版会、249頁)。
新興国の台頭と「発展の権利」
このように「持続可能な開発」概念は、途上国の「発展の権利」とも大きな関わりを持っている。
先述のミレニアム宣言に「22. 我々は、国連環境開発会議(UNCED)で合意されたアジェンダ21に盛り込まれた原則も含め、持続可能な開発の原則に対する支持を再確認する」とあるのも、そのことが意識されている。
このような事情から、MDGsには「持続可能な開発」の原則が織り込まれた。
ただ、MDGsに「持続可能な開発」概念が織り込まれているからといって、それがSDGsにおける「持続可能な開発」概念と連続性があると言うことができるかどうかには、議論の余地がある。
それもそのはず、MDGsの実施期間中に国際社会は大きな変動期を迎えることになったからだ。
特に重要な変化は、一部の途上国を指して「新興国」という言葉が使われるようになったことだ。2010年代後半、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカをBRICsと名指すことが一般化し、現在では「グローバル・サウス」とも言われるようになった。
***
新興国は2つの顔を持っている。
一面では先進国を抜き去ろうと経済成長にまい進する、”ネクスト先進国” としての顔だ。そして自国よりも貧しい国々を率いて、みずから開発援助も始めていく。
だがもう一面では、先進国との違いを強調し、新興国・途上国に対する配慮を求める ”先進国による「被害者の会」” としての顔もある。
とくに地球環境問題について、先進国がこれまでさんざん排出した二酸化炭素について、新興国に責任があるとは考えない。

つまり新興国が台頭したことにより、「途上国」という言葉で先進国以外の国々を大くくりにすることは、もはやできなくなってしまったわけなのだ。
地位がずるずる低下する先進国
新興国台頭の背景の一つは2008年の世界金融危機にある。この年からは20か国・地域首脳会合(G20サミット)が開催されるようになり、新興国はますます存在感を強め、先進国の相対的地位は低下していくこととなった。
その影響は開発援助にも現れるようになる。
2000年代後半の開発援助には、従来の貧困撲滅を掲げる規範に変わって、経済成長に重きを置き、民間資金を積極的に活用する動きが目立つようになっていった(詳しくは第5回=「目標17とは何か?」で確認することにしよう)。
2008年に世界同時不況後に経済協力開発機構(OECD)が唱えた「グリーン成長」が、そのあらわれだ。これはテクノロジーの力で環境を解決しながら、経済成長を目指そうというもので、前回紹介した「エコロジー的近代化」路線に近い(ただし、環境産業振興を通して景気・雇用と威信の回復をねらう西欧諸国が前のめりとなるのに対し、石油産業が政治力をもつアメリカは消極的だ)。
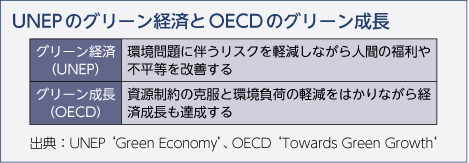
一方その数年後の2011年、国連機関である国連開発計画(UNEP)は、「人間の生活の質を改善し社会の不平等を解消するための経済のあり方」として「グリーン経済(グリーン・エコノミー)」を提唱している。
「グリーン成長」が経済成長に重きを置く概念であるのにたいして、「グリーン経済」は「気候変動、エネルギーの安定確保、生態系の損失の問題に直面している世界情勢の中で、国家間・世代間での貧富の格差を是正することに焦点」がある(平成24年版 図で見る環境・循環型社会・生物多様性白)。

そんな大きなことを言ったところで「そんなの先進国の都合じゃないか」と途上国側は思う。
そもそも先進国の多くは、1970年代に交わしたはずの途上国との援助(国民所得比)の "約束" はいまだ果たしていない。

途上国にとってみれば先進国よりも新興国のほうに頼り甲斐を感じるようになるのも無理はないのだ。

かといって先進諸国は2000年代末の経済危機の余波もあり、開発援助の財政拠出には国内の支持も得られない。民間資金を呼び込もうにも、貧困撲滅という目標だけではなかなか難しいところもあった。
そうこうしているうちに、従来の開発援助の中心であった先進諸国や国連諸機関とは別ルートで、中国やロシアなどが途上国に対する援助に乗り出す動きも活発化していく。2010年代には新興国を含め、インフラは世界全体で供給不足に陥っていたが、厳しい条件の課される欧州のドナーに比べると、新興国の援助はプロジェクト単位の投資に近く、債務負担を別にすれば途上国にとって短期的には魅力的なものに映った。
再定義を迫られた「持続可能な開発」概念
このように2010年代を通して、国際社会の風景は大きく変わっていった。
途上国でもなければ、先進国でもない、あいまいな地位を占める新興国にとって、「持続可能な開発」を自国に対してもそのまま適用することはもちろん望まれない。
『ブルントラント報告書』や地球サミットを経て議論された「持続可能な開発」は、あくまで「開発済み」の先進国と「未開発」の途上国という二分法にもとづいた建て付けになっている。
だが、石油危機以降 "2階建て" から "3階建て" に移行していた国際秩序は、2階部分の国々がいよいよ「新興国」として3階へと梯子をかける情勢となった。
にもかかわらず、経済成長を通した社会問題解決(とりわけ貧困撲滅)というセオリーをこのまま無制限に貫けば、やがて悪化した地球環境自体によって経済成長も社会問題解決も骨抜きにされてしまうかもしれない。
つまり持続可能な開発を「望ましい組み合わせに応じて、個別にカスタマイズする」形で解釈しているようでは、地球全体の収容力が保たれない。
そのことも、地球システム研究の成果により次第に明らかになっていった。
>地質時代「人新世」案、学会否決 社会で浸透も議論に幕 - 日本経済新聞 https://t.co/Tf9RXqskaG |「人新世」は、もともとパウル・クルッツェンが、2000年2月22〜25日にメキシコのクエルナバカで開かれていた地球圏・生物圏国際共同研究プログラム(IGBP)
— みんなの世界史 (@minnanosekaishi) April 16, 2024
MDGsからSDGsへ
このように、たしかにMDGsにおいても「持続可能な開発」は意識されていた。
だが、そこで人々に論じられた「持続可能な開発」は、もはや国際社会の現実に合わなくなってしまっている。
MDGsを推進する先進国においても貧困撲滅から経済成長へ、政府開発援助から民間投資へと、開発援助の軸足をうつす動きがみられたほか、中国やロシアなどの新興ドナーの動きも無視できないものとなっていった。
そのような状況の中、2010年代に入ると、国連事務総長や国連機関の専門家を中心として、MDGsの次の目標(ポストMDGs)が策定される情勢となった。
コロナ禍前によく読まれた ハンス・ロスリング他『FACTFULNESS』(2018年)が高らかにうたいあげているように、世界全体でみれば、たしかにMDGs期間中に絶対的貧困にある人々の総数は減っていった。

Max Roser based on World Bank and Bourguignon and Morrisson (2002). - https://ourworldindata.org/extreme-poverty
だが、これに寄与したのは主に中国における絶対的貧困の激減だ。他地域でも絶対的貧困は改善されているが、統計的な基準を脱したからといって、「基本的ニーズ」の全てが解決されるわけではないことにも注意が必要だ。工業化が環境問題となって、経済や社会に反転する懸念もある。
また、途上国・新興国のなかには、彼らの意向が十分に汲まれないままに、開発政策がつくられることに対する不満も渦巻いていた。特にサハラ以南アフリカ、カリブ海や太平洋の小さな島国、山岳地域にある国々などは、それぞれ特別なニーズを抱える地域も多く残されている。
こうした状況のなか、2010年代に入り、国連主導でMDGsの後継版を策定する動きがはじまったのである。
***
なぜSDGsの提唱国はコロンビアだったのか?
これに「待った」をかける勢力が、2012年に地球サミット30周年を記念して開かれたリオ+20という国連主催の国際会議を前にして現れた。「MDGsの単純な後継版ではなく、「持続可能な開発」を掲げる新しい目標を作るべきだ」というのである。
これを訴えたのがコロンビアの外交官、ポーラ・カバジェロだったことを記す一般書も2020年頃から現れはじめているが、コロンビアは日本でのおおかたのイメージに反し、すでにOECDの加盟国であることに注意を促したい。

つまりこのことは「小さな途上国がSDGsを発案した」という牧歌的なイメージだけでとらえるべきではない。
ここに読み取るべきことは、長年の紛争のイメージが色濃く残る新興国コロンビアにおいて、地球システムの危機に強い懸念を抱く外交官が政府の意をくみつつ、従来の「持続可能な開発」概念への安住を望む途上国に対する困難な外交的折衝を通し、全世界が開発に向かう際の大前提となる新たな惑星的な概念として再定義された「持続可能な開発」概念を掲げる新開発目標をリードしようとしていったプロセスだ。
(後編に続く)
いいなと思ったら応援しよう!

