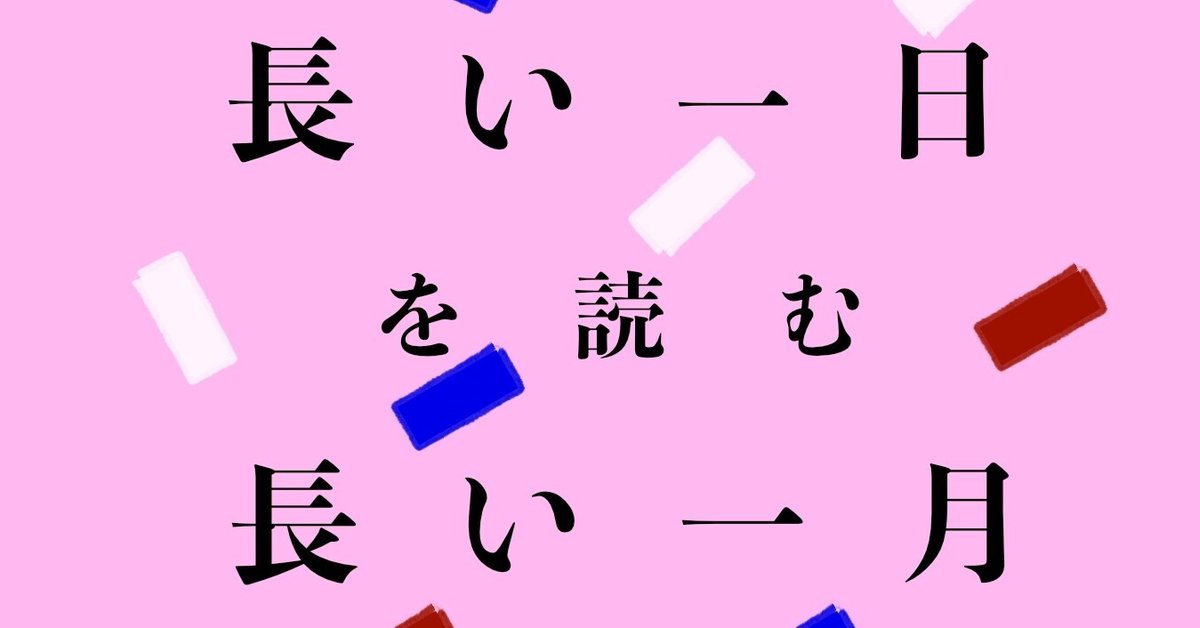
『長い一日』を読む長い一月 〜22日目〜
滝口悠生さんの連載小説『長い一日』(講談社刊)を一日一章ずつ読み、考えたことや想起されたこと、心が動いたことを書いていく試みです。
いよいよ引っ越しが近づいています。第22回は「お別れの日(一)」。
あらすじ
夫婦は転居先の契約を結び、引っ越しの準備を進める。妻は前回の部屋探しのときのチャラい不動産屋のことを思い出す。当時はできるかぎりかかわりたくないタイプと思っていたが、今の家に8年間住んだ後では彼のことさえも少し愛おしく思える。
引っ越しをする家は古い家をリフォームしたものだが、壁や天井は元の建材をあえて残していて、釘の穴や傷など以前に住んでいた誰かの痕跡がそこここにある。家を管理する不動産会社の石毛さんは、住む人がどんどん手を入れいていってほしいと言う。
引越しに向けて感傷的になっているのは夫だけで、妻はいったん決まれば新居での生活にむけて楽しく想像を巡らせる。
引っ越しが近づき、夫婦はお礼も兼ねて大家さん夫婦と食事をともにする。大家さんの家のテレビの録画番組の一覧には、何年か前に妻が仕事で取材されたときのテレビ番組のデータが残っている。
家の時間
この回でも、妻と夫の思考のコントラストが描かれています。決まる前までは迷いもあったが、いったん決まれば前向きに考える妻と、決めてしまってからうじうじと感傷的になる夫。どちらかといえば夫に、わたしは感情移入し、自分のことのように寂しい気持ちになっています。たった3週間くらいですが、この小説を読むという行為を通して、夫婦と大家さん夫婦の8年間が自分のなかに流れ込んできていると感じ、また、わたし自身が暮らしてきた色々な家との時間もそこに織り込まれているように思えます。
仕事で空き家を見ることが多いのですが、人が住まなくなった家はそこだけ時間の流れが早いかのように、どんどん荒廃していきます。ただ、実際の家を見ると、時間の流れではなく「時間が止まっている」という印象を強く受けます。もう少し、実感に即して言うなら「流れていた時間が失われてしまった」という感じでしょうか…
だからこそ、石毛さんの次の言葉にとても感じ入ります。「せっかく古い部分を残した家なので、その時間を続けていくっていうか、先に延ばしていくような、そんな家にしたいんです(p.228)」。
誰かが住むことで、家の時間は続いていく。
人間主体な物言いかもしれませんが、引っ越し前で感傷的になっているということでご容赦いただき、今日はこの辺で終わろうと思います。
生きられる空間は、われわれと感覚的にまじりあうものに生じてくるのである。(『生きられた家』多木浩二 p.125)
