
はじめまして、生成AI活用センターです
はじめまして、生成AI活用センター編集長の白壁です。
当センターは、IT業界で働く有志が集まって2024年4月に発足した、生成AIの活用方法を研究するコミュニティです。生成AIのツールを使う機会は増えていますが、どのような課題を解決できるのか、まだ未知の部分が多くあります。そこで私たちは、エンジニアやデザイナー、コンサルタントが集まり、遊び心を持ちながら生成AIの有効活用シーンを探索し始めました。4月末時点での参加者は30名を超えています。
→今(7月)はなんと130名を超えました!!!
研究で、小さな気づきを発見する
皆さんも、仕事や日常生活で生成AIを使う機会が増えてきたのではないでしょうか。生成AIには多様な使い方がありますが、そのメリットや活用方法がまだよくわからない方も多いと思います。
そこで私たちは、皆の知識やアイデアを集め、生成AIを使ったアイデアや技術を探っていきます。
生成AI活用センターでは、生成AIを仕事、生活、趣味など様々な場面で活用する研究を行います。これをきっかけに、未解決の問題や非効率な点、潜在的な課題を生成AIで解決することにつながる、多くの小さな気づきが生まれることを目指しています。
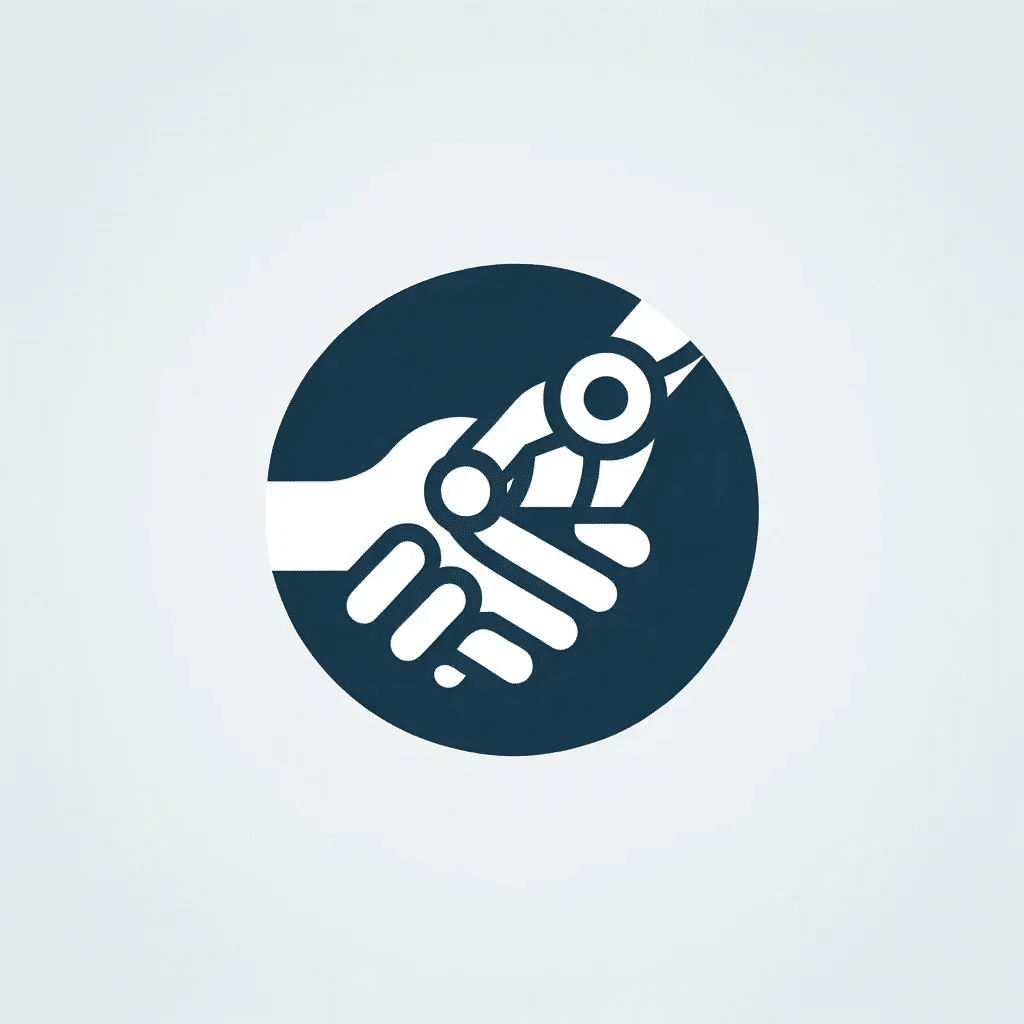
※今後変わります、多分。
とにかく考えて、触って、創ってみる
生活センターの活動は、日常生活で直面する問題や興味深い課題を、AIを使って解決する方法を探ることです。AIをどの程度日常生活に取り入れられるのか、具体的にどのように活用できるのか、そしてAI活用で浮かび上がる新たな課題は何かを探ります。これらの問いに答えるには、とにかく考え、実際に触れ、創造的に取り組んでみる必要があると考えています。

自由に楽しく、遊び心を持って
生成AIで儲けたい!仕事が欲しい!という思いに固執すると、誰でも思いつく発想しか出てこなかったり、研究時間のコミュニケーションが硬くなってしまったりします。
そこで、この問題を乗り越えるため、生成AI活用センターの活動では楽しく、遊び心を持って取り組むことを大切にします。のびのびとしたコミュニケーションを取りながら研究を進めていきたいと考えています。生成AIで思い切り遊ぶ!そんな気持ちで取り組んでいきます。

(編集長白壁のひとりごと)
最近だと全社会のBGMを作ってたりしました。割と完成度高かったです…AI恐ろしや。
<割と有名な音楽系AI>
Suno
Udio
Sonauto
研究開発からコミュニティ運営まで幅広い活動
ざっくりと以下の内容をやっております!各チームでの研究に加え、共有や社外も巻き込んだコミュニティの形成も狙っています!
研究と開発
個人やチームで新しい方法を開発し、仕事や生活を豊かにします。
知識の共有と学習
最新のAI技術や研究成果を社内で共有し、お互いに学び合って知識を深めます。
成果物の発表
研究やプロジェクトの成果をホワイトペーパーやブログ、イベントで広く発信します。
コミュニティ運営
研究員や開発者、AIに興味を持つ社員や社外のメンバーが参加するコミュニティを作り、アイデアや経験を自由に交換して刺激と学びを提供します。社外との交流イベントも行います。
アカデミア研修への応用
ナレッジや研究成果をもとにアカデミア研修のカリキュラムを作成し、講師の育成にも力を入れて専門知識の普及とスキルアップを目指します。
(白壁編集長より)ここの活動詳細は今後どんどん記事化していく予定です。フォローをよろしくお願いします!!!
熱意とユーモアとチームワーク
各メンバーはそれぞれ熱意とユーモアを持って活動してください。一人で進めることもできますが、できるだけチームでで協力し合ってほしい、そう心から思っています。
とは言っても、研究テーマの具体的なイメージが浮かばない人もいるでしょう。ですから、事務局が用意した研究テーマのサンプルを参考にしたり、手を挙げてくれたリーダーがやりたいテーマに乗っかつことをお勧めします。
成果物の発表会やアワードも企画していますので、みなさんが集まれる日を楽しみにしています!
今後は研究成果の連載が記事に
以上、生成AI活用センター(略して生活センター)の活動についてご紹介しました。今後は生成AIを使った、遊びや仕事に関する最新の技術や研究成果をnote記事にして広く共有していきます。今後もどんどん記事を発信していきますので、ぜひnote更新をお楽しみにしておいてください!
(白壁編集長のひとりごと)NoteAIで「エモい」モードで編集したら熱血系文章でした。「エモい」の定義ってなんなんですかね?
