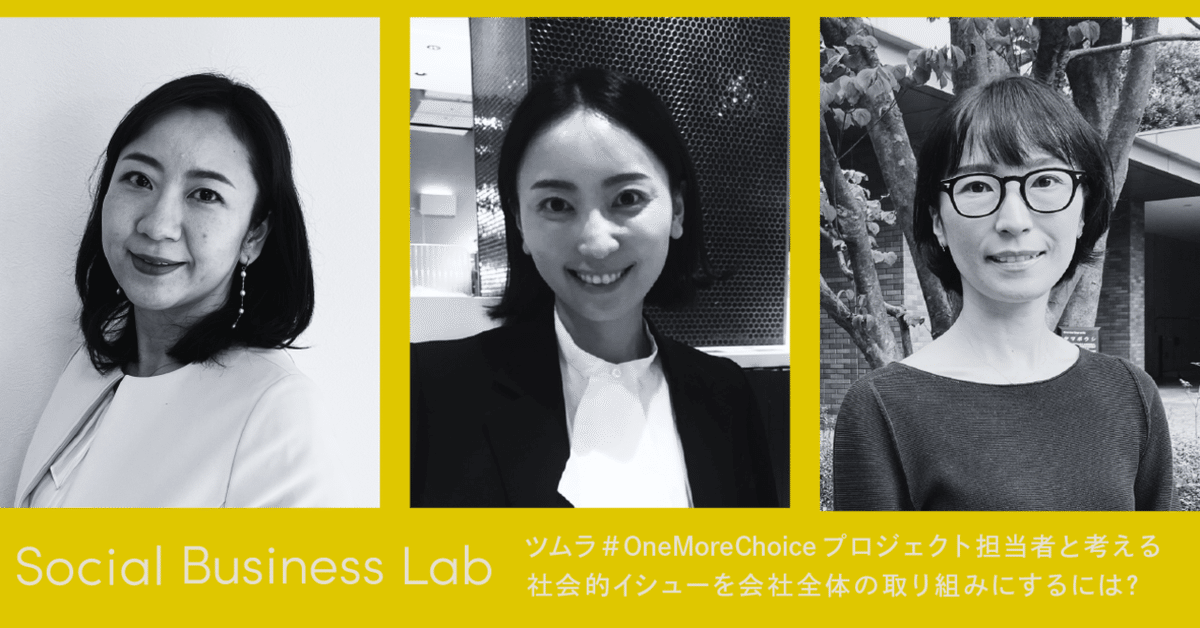
【第2回イベントレポート】「社会的イシューを会社全体の取り組みにするには?」|ツムラ #OneMoreChoice プロジェクト 担当者が語るプロジェクトの裏側 。
こんにちは!Social Business Lab運営事務局です。
わたしたちは毎月1回、SDGsをはじめ、サステナビリティやジェンダー、ウェルビーイングといった社会的なテーマに関連するプロジェクトを、企業の中で担当する「人」にフォーカスし、ともに考え、学びを共有する勉強会を開催しています。
世の中に新たな考え方を提示するような「あのプロジェクトの裏側」に関して、同じテーブルを囲んで話すように具体的に共有していくことで、うまく行ったことだけではなく、失敗や「もっとこうしたらよかった」といった視点、どのように社内を巻き込み、プロジェクトを形にしていったのか?など、プロセスから紐解くことで考え方を知り、それぞれの活動や日々の仕事に活かすことができる場を目指しています。
第2回目のゲストは、漢方でお馴染みのツムラさんが手がける「#OneMoreChoice プロジェクト」の担当者である宮城英子さん、大山尚美さん、髙橋朋子さん。100年以上、女性をはじめ多くの人々の不調に寄り添ってきた歴史ある企業で今回のプロジェクトを立ち上げるには、さまざまなプロセスや葛藤もあったといいます。実際にプロジェクトが生まれた経緯やその過程、今現在考えられていることをお話しいただきながら、Labのメンバーと「すべての人が不調を無理に我慢しなくていい社会」を目指すプロジェクトにはどんな視点が必要だったのか、意見や思いを交わしました。
<第2回目ゲスト>

#OneMoreChoice プロジェクトとは?
誰もが不調を無理に我慢することなく、心地よく生きられる健やかな社会を目指して、#OneMoreChoice プロジェクトを、2021年3月8日の国際女性デーにスタートしました。当社が目指すのは、誰もが心地よく生きられる健やかな社会です。不調の際、治療だけではなく、休む、少しだけ働き方を変える、誰かに相談するなど、それぞれが我慢以外の自分に合った選択ができるようになり、そしてその選択肢を提示できる社会こそが、「隠れ我慢」のない健やかな社会につながると考えています。今後#OneMoreChoice プロジェクトを通じて、健やかな社会の実現に向け取り組んでまいります。
イベントではLabのメンバーが4つの「Social Action Canvas」を軸に、参加者の皆さまからいただいた質問を交えながらお話を伺いました。


未来創造研究所 ふつう研究室 シニアデザイナー

プロジェクトを紐解く
ソーシャルアクションキャンバス
ーまずはプロジェクトについてお伺いしてもよろしいですか?
宮城さん:弊社は医療用漢方薬を主に販売している、漢方薬のメーカーです。これまで皆さんがなんとなく調子が悪いなどの不調症状を抱えている方、抱えたままで悩んでいる方がすごく多くいらっしゃるという現状を感じておりました。そういった中で、私たちがツムラだからこそ社会のためにできることとして始めたのが#OneMoreChoice プロジェクトです。
このプロジェクトでは、誰もが無理に我慢することなく、心地よく生きられる健やかな社会を目指して活動しています。不調を感じている時に休むとか、少しだけ働き方を変えてみるとか。あとは誰かに相談をしてみるなど、症状によっては治療が必要な場合もあるかもしれないんですけれども、それぞれが我慢以外の自分に合った選択ができて、その選択肢が周囲に広がっていく。そうすることで「隠れ我慢」のない、健やかな社会になると考えています。
そして、不調症状を感じている方が年齢性別問わず多くいる中、事前調査の結果をみると特に女性の方が不調症状を我慢されている方が多いということがわかったので、まずはそこから取り組むことにしました。プロジェクトをスタートした2021年には「隠れ我慢」に関する実態調査というものの結果を公表しています。不調を抱えていてもこれくらいなら我慢できるかなとか、仕事や家事に支障が出てしまうといった理由で女性の8割が隠れ我慢をしているといったことを問題提起して、2021年の国際女性デーにプロジェクトを始動しました。
2年目の2022年は、女性が抱える不調症状の中でも多い生理、PMSをテーマに掲げ、「違いを知ることから始めよう」というメッセージを発信しています。辛さには人それぞれいろんな形があると思うんですけれども、実際にヒアリングしながら可視化しました。
また、ツムラこそが#OneMoreChoice を実践していこうということで、社内でもワーキングループを発足して活動を進めています。社員自らが考えて#OneMoreChoice を実践するという状態を目指して、様々な性別や年齢の社員が集まって「隠れ我慢」についてオンラインでディスカッションを重ねています。
わたしたちは常に調査に基づきながら取り組むことを方針にしており、直近では男性の更年期/女性の更年期についての調査の公表をしております。これまで女性だけを対象にしているイメージを持たれることもあったんですけれども、私たちは誰もが心地よい社会といったものを目指しておりますので、性別問わず更年期に生じる症状などにも取り組んでいく予定となっております。
Q. Projectが立ち上がった経緯は? / なぜご自身が取り組むようになったのか
東江(SBLメンバー):まずは、プロジェクトが立ち上がった経緯について知りたいです!
宮城さん:もともと漢方事業なので、広報活動として不調症状の啓発みたいなことは重ねてきていました。生活者の皆さんとお話する中で、不調症状を抱えている方は本当にたくさんいらっしゃることをずっと感じてきたので、何かわたしたちにできることはないだろうか?と考えたのが始まりです。そうはいっても、「社会が求めていること」と「わたしたちができること」とが同じじゃないとあまり意味がない。なので、色々な調査をしたり、グループインタビューや社内でのヒアリングを重ね、「社会が求めてるもの」と「わたしたちができること」、その接点を見出すことを半年以上かけて行いました。
石井(SBLメンバー):広報チームさんがスタートされたんですね。広報としての役割がもともとベースにある中で、「隠れ我慢」というものをトピックイシューに設定してスタートした、という感じですか?
宮城さん:はい、そうですね。実際に皆さんとお話ししたり調べてみたりしたところ、我慢せざるを得ない状況があるとわかったんです。そういった意味でも、単純に不調症状を啓発するのではなく、社会に対してメッセージを発信するようなやり方がいいよねというところに至りました。
東江(SBLメンバー):最初から皆さんの中に「隠れ我慢」の風潮が課題感として共有できていた、というのがスタートポイントとしてすごいなと思います。ツムラさんだからこそというのもあるのかもしれないですけど、何か意識していることや仕組みみたいものってあるんですか?
宮城さん:漢方という特性もあり、「なんとなく不調」という言葉もつくって調査をしたりしていたんです。その言葉自体は社内でも理解が早かったですし、外に発信しても違和感を持たれる感じはなかった気がします。
大山さん:プロジェクトを始めるにあたって、役員からいろんな部署の社員まで本当にたくさんヒアリングをしたんですね。弊社は漢方薬の会社なので女性の MR とかにも色々聞いてみたのですが、やっぱり患者様がすごく不調を我慢しているっていうのを強く訴えていたんです。我慢という薬だけでは解決できないものが世の中にいっぱいあるんだな、というのを実感しました。
石井(SBLメンバー):プロジェクトを拝見していて、ツムラさんだからこそのテーマ設定の納得感があるなと思います。ちなみにパナソニックさんのふつう研究室って、ジェンダーとかセクシュアリティをテーマにしているじゃないですか。それはパナソニックだからこその設定だったんですかね?それとも個人やチームの中での課題意識の強さだったんですか?
東江(SBLメンバー):正直、個人が先行してましたね。私と白鳥さんにとってはすごくセンターにある課題なんだけれども会社の中ではそうじゃないよね、というところから始まっています。
石井(SBLメンバー):(ツムラさんが)ヒアリングをされたとか、ワーキンググループに発展してることを聞いて、テーマ設定の難しさと大事さを感じました。僕たちは学校総選挙プロジェクトを形にしていく中で、個人的な反省として、CCCが若者と社会を繋ぐ理由というか、 CCC だからこそという部分がそこまで強くなかったと思っていて。もっと社内のヒアリングや、会社らしさと個人的な課題感を上手に繋げられたらもっとよかったなと思います。
大山さん:研究部門や生産部門の社員、また日頃あまり接点のない役員からもヒアリングしてみると面白い話が結構出てきたんですよね。熱い想いだとか、会社のこともっとこうしていきたいとか、そういう想いを聞けたのがすごくプラスになりました。
石井(SBLメンバー):やっぱりヒアリングがいきてるな、みたいな実感はありますか?
大山さん:社内での理解に関して困ってる部分も沢山ありますけど、やっぱり共通の想いというのは皆さんにすごく理解してもらいやすいなと感じます。逆に皆さんはどうですか?
東江(SBLメンバー):わたしたちは個人の想いからスタートしているので、そこから会社や社会にすり合わせていく作業を行なっている感覚です。ツムラさんはスタートダッシュがすごく良く、最初から広がっていったような印象を受けてるんですけど、我々はじわじわ…というか、そんな感覚です。石井さんとかはどうですか?
石井(SBLメンバー):僕らが会社とのすり合わせの中で大事にしていたのは、Tポイントと若い人たちとの接点を作ること。この問題意識や必要性は理解されやすかったという背景はあります。なので、若者を対象にしていることへの共通認識は持てていると思いますが、「若者世代の声を社会に届ける」という取り組みのテーマについて「確かに社会的な課題ではあるよね」という理解はありつつ、一方で、何故うちの会社がその社会イシューをやるのか、という点で少し疑問に感じているような方たちもいるんじゃないかな。
高橋さん:うちの会社でいいますと、一番最初に世に出した薬が婦人薬だったんですね。なので、(#OneMoreChoice プロジェクトでは、)調査を経て女性の不調に取り組んでいきましたけど、社内の腑に落ちる感というのは最初からあったように思います。
Q. 社内外の反応は?プロジェクトの評価/継続
石井(SBLメンバー):ウェブサイトもできたり、交通広告もされていたりと、スタートされたばかりなのに展開がすごく大きいですよね。2年目を迎えた2022年になぜそこまで行けたのか、どういう社内の評価があって予算をかけられたのかなどお聞きしても良いでしょうか?
宮城さん:すごく運が良かったといいますか。少しずつ腰を据えて取り組んで、3年ぐらいで少し成果が見えたらすごく嬉しいな、という気持ちでスタートしていたんです。そんな中、プロジェクトを宣言した3月の広告や、プロジェクトの取り組みに対して広告賞をいただくことができて、そういった外からの評価があったのはよかったのかなと思います。企業価値・評価にこう繋がってるよというのが社内でも伝わりやすかったのかと。
東江(SBLメンバー):社内でもうまく広がっている印象があるのですが、活動を評価する上で受け入れられやすい KPI とかってあったりするんですか?
宮城さん:一応ゴールとして掲げているものがあるんですけども、なかなか数値としては出しにくいんですよね。なので、 PR 的な視点での指標。例えば、発信したメッセージが何人に届いたのか、また、高齢の方と比べ若い方の間では企業名があまり知られていないので、どれくらい認知してくださる方がいるのか、といった点は数値としてKPIに入れています。定量的なものと、定性的な評価を掛け合わせながら見てきていますね。ただ、社会課題を解決するだとか、あたりまえになっている「隠れ我慢」の習慣を簡単に変えることは難しくて。3、4年目以降はどう数値で成果を出していこうか課題に感じています。皆さんはどうですか?
東江(SBLメンバー):確かに、最初は分野を広げる、開拓すること自体に価値があったと思います。ただ、会社の中でそれをどうやって事業化していこうかっていう話になったとき、我々はコンサルチームでもあるので、例えば相談を頂けた件数だとか、会社の中で実装できた件数だとか、そういう定量的なものが評価基準になっています。
大山さん:確かに弊社も、誰に情報が届いたかなどの定量的なものも見つつ、社内での「隠れ我慢」も無くしていこうということで、毎年行う社員の健康調査で「隠れ我慢」による業務への影響などが減っているかどうか、というのは定量的に見ている状況です。ただ1年後、2年後にすぐ変わるというものでもない。これまで我慢することがあたりまえになってきた方たちが意識を変えていくってそんな簡単なことじゃなくって。長期的な目線でやっていけたらいいなと思いつつ、会社からは割と短期で結果を出すことを求められる部分もあり、みんなで苦労しております。
Q. Project推進に向けてどんな作戦を立てたか 周囲の巻き込み方/大変だったこと
石井(SBLメンバー):ワーキンググループって、皆さん自発的に応募されてきたんですか?
宮城さん:発足する時は、やっぱり社内制度を変えることなので色んな部門に説明をして回りました。その中の一つとして人事部にも声をかけたりしました。どの部門からも、いい活動だねということで人事部も含め複数部門から興味のある人が参加してくれたっていう形でスタートしました。2年目は、ある程度認知度が上がっていたので公募みたいな感じで募集をかけたところ、現在では20数名の方が集まっています。連絡をくださった中には、20代、30代の男性もいました。さまざまな部門、性別の社員が共感してくれてるんだなってすごく嬉しかったです。
石井(SBLメンバー):プロジェクトの大きなところには生理やPMSなどの課題感はあるけれど、「隠れ我慢」というキーワードをそういった人たちだけのものにしない、いろんな人が自分ゴト化できるようなワードの作り方をされたんですか?
宮城さん:常にそういうことは意識してディスカッションしてきたと思います。生理やPMSを例に挙げても当事者だけの問題で終わらせてはいけない。自分の問題として考えてもらうためにはどういう言葉の使い方がいいかとか、どういうデザインがいいだろうっていうのは常に皆で話してきました。
最後に
ー会社らしさも大事だけど、個人の想いも大事。
Q. 活動をスタートさせるためのヒント
宮城さん:自分の会社じゃないとできないことは何か?ということをすごい突き詰めた上で、本当に生活者の方々が課題に感じてることの中でもまだ誰も取り組んでいないものをうまく抽出して、接点を見出すことですかね。あとは、何よりわたしたち自身の気持ちが乗るような活動にしていくことだと思います。
当事者性の高さなど、個人の想いばかりが先行しているように評価されがちなDE&I領域。
会社らしさとのバランスを保つことが難しいように感じることもありますが、ヒアリングや勉強会を重ね、「役員と現場」、「当事者と非当事者」といったように分断しないこと。また、年齢・ジェンダー等関係なく全ての人が自分ゴト化できるように奮闘する姿に励まされる時間でした。
🗒学びになった4つのポイント

◯社外からの評価を活用
:社会活動につながるアクションは長期目線での取り組みになるためKPIの設定などが特に難しいが、社内で評価を得ていく術の一つとして広告賞やメディアで取り上げてもらうなど、社外からの評価は有効。
◯共通言語の設定
:「隠れ我慢」や「なんとなく不調」など、社内外問わず理解されやすいワードを設定し、共感者を増やしていく。
◯まずは、身内から
:社会を変えるということは、半径3メートル以内に目を向けることでもある。社内に向けての活動・発信は味方を増やす上でも大切。
◯「会社らしさ」と「わたしらしさ」のバランス
:社会活動をサステナブルに続けていくためには、「自社でやる理由×わたしがやる理由」を突き詰めること。
Social Business Labでは、今後も気になるプロジェクトの担当者をお呼びし、ともに学ぶ時間を作っていきます。ぜひTwitterをフォローの上、次回のイベントもチェックしてみてください!
企画 / 編集:Creative Studio koko
ライティング:Ai Tomita
