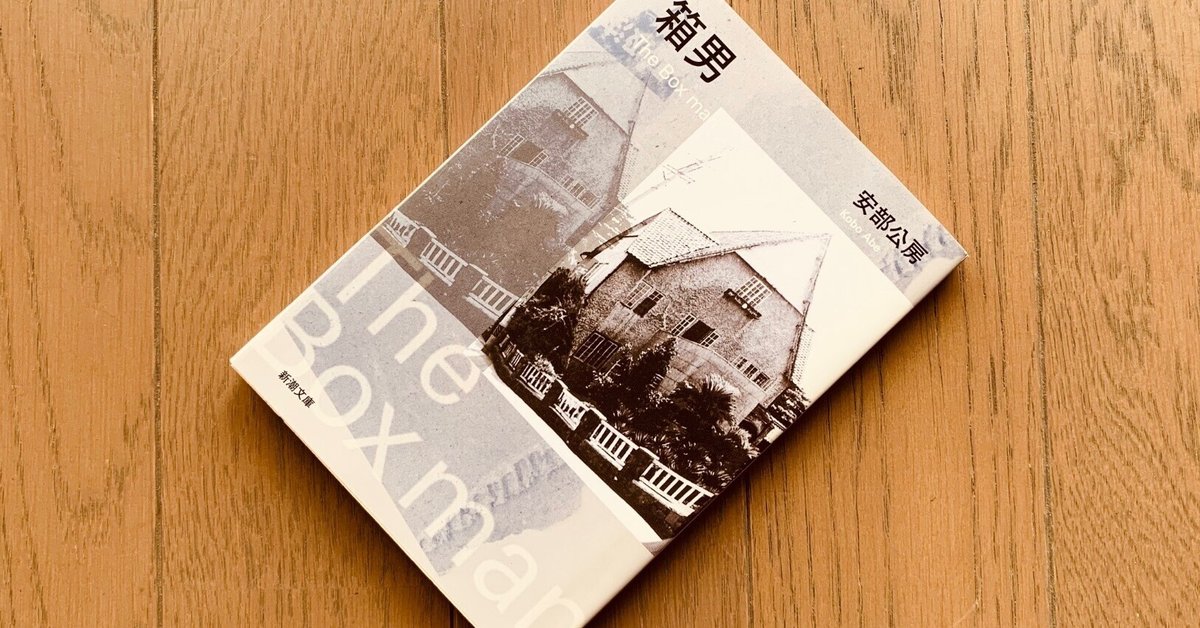
【読書録】『箱男』安部公房
今日ご紹介するのは、安部公房の『箱男』(昭和57年)。私が持っているのは、新潮文庫版。
安部公房は、小説家であり、劇作家、演出家でもある。芥川賞受賞作家でもあり、晩年は、ノーベル賞候補にもなったということだ。
私は、安部公房作品は、まずは有名な『砂の女』から入り、その次に読んだのがこの本だった。
ひとことで言うと、前衛的であり、難解であり、変態的な作品であると感じた。
(以下、ネタバレご注意ください)
この作品のストーリーは、段ボールにすっぽりと入って生活をする「箱男」の話。「見ることと見られること」「覗くことと覗かれること」「匿名性」などがテーマだと言われる。
箱男になることで、他人から見られることなく、ダンボールの穴で切り取られた視界から、他人を覗くことができるのだ。この奇抜なアイデアと独特の世界観は、安部公房作品ならではだろう。
元カメラマンの箱男。贋箱男。軍医、贋医者、看護婦、ピアノの先生。語り手も時系列もころころ入れ替わる。記述スタイルも、新聞記事の挿入、写真の挿入、会話調、供述書調、など、何でもあり。箱男という概念の突拍子のなさ。それぞれ癖のある登場人物の予想できない動き。常人にとっては理解不能で支離滅裂な構成。官能的な描写や少々眉をしかめてしまうような描写も多い。
この作品の評価は、おそらく、大きく二分されるだろう。一部の読者には、生理的に受け入れられないかもしれない。Amazonの書評を見ても、全く受け入れられなかった、という感想を書き込んでいるレビュアーは多い。
他方で、安部公房作品を面白いと感じる読者には、危険な中毒性を与えそうだ。読了直後はお腹いっぱいになっても、暫くすると、恐る恐るまた読んでみたくなるのではないだろうか。私もそのひとりだ。
以下、本作品のうち、特に印象に残ったくだりを引用しておく。
見ることには愛があるが、見られることには憎悪がある。見られる傷みに耐えようとして、人は歯をむくのだ。しかし誰もが見るだけの人間になるわけにはいかない。見られた者が見返せば、こんどは見ていた者が、見られる側にまわってしまうのだ。
彼女を覗きたいという欲望は、たしかに箱の容積を超えかけていた。うずいている歯茎の腫れを、口いっぱいにほおばっている感じだ。
人はただ安心するためにニュースを聞いているだけなんだ。どんな大ニュースを聞かされたところで、聞いている人間はまだちゃんと生きているわけだからな。本当の大ニュースは、世界の終りを告げる、最後のニュースだろう。(中略)ニュースが続いているかぎり、絶対に最後にはならないんだ。まだ最後ではありません、というお知らせなのさ。
仕掛けがあるとも知らず飲み込んだゴム風船が、とつぜん胃の中でふくれ上った感じ。
誰だって、見られるよりは、見たいのだ。ラジオやテレビなどという覗き道具が、際限もなく売れつづけているのも、人類の九十九パーセントが、自分の醜さを自覚していることのいい証拠だろう。
隠す醜さを持たない人間には、他人の醜さだって見えないはずだろう。箱男が専門の覗き屋なら、彼女は天性の覗かれ屋なのである(…)。
よじった腰のくびれめに、数本の細い襞がよった。とくに痩せて見えるわけでもないのに、皮下脂肪の層は薄そうだ。何かを連想させる、なんだろう。そうだ、レンズを拭くためのあの小羊の揉み皮の感触だ。
生物にはそれぞれ個体の縄張りがあって、その境界線を越えた侵入者に対しては、本能的に攻撃反応を示す。(中略)ぼくの経験だと、人間の場合そのラインは、半径二メートル半くらいの位置にあるようだな。(中略)ともかくその監視ラインをくぐり抜けてしまえば、もうしめたものだ。その至近距離では、敵の正体を見破ろうにも、かえって見きわめにくい。役に立つのは、触覚と嗅覚だけになる。
「・・・・・・それじゃ聞くけど、君はいまこの瞬間に、何処で、何をしているんだい?」
「あんたの見ているとおりさ。ここで、あんたと、喋くっているよ。」
「なるほど・・・・・・すると、このノートは、何処で誰が欠いていることになるのかな?(中略)」
「そいつは言いっこなしだろう。それを言ったら、あんたたち自身、ぼくの空想の産物にすぎないことを自分から認めてしまう事になるんだぞ。」
「そう、ぼくが書いているのかもしれない。ぼくのことを想像しながら書いている君を想像しながら、ぼくが書きつづけているのかもしれない。」
どうやら君は、まだなに一つ始まっていない、明後日のことを、すでに過去の事件として記録しはじめる気らしい。
私は死ぬ決心をした。いまさら私に希望を吹き込むような偽善はよしてくれ。口に入れてしゃぶってみるまでは、どんな飴玉でも、けっこう固く感じられるものだ。しかしすぐに嚙み砕いてしまいたくなる。いちど砕けた飴玉は、もう元には戻らない。
ぼくは今、むくんだ声帯を力いっぱい引き締めて、ドア越しに呼びかけてみた。返事はない。身じろぎの気配さえない。ただ夜の静寂が、鉄板にハンマーを打ちつけたような痛みになって、鼓膜に跳ね返ってくるばかりだ。
こんな時代に、月賦の便利さにさからってまで覆面をしたがるのは、ゲリラか、箱男くらいのものかもしれない。
馴れてしまえば、どこにいようと、時間は箱男を中心に、同心円を描いてまわりはじめるのだ。遠景は速く過ぎ去るのだが、近景は遅々として進まず、中心では完全に静止してしまっているので、まったく退屈するということがないのである。
小さなものを見つめていると、生きていてもいいと思う。
雨のしずく・・・・・・濡れてちぢんだ革の手袋・・・・・・。
大きすぎるものを眺めていると、死んでしまいたくなる。
国会議事堂だとか、世界地図だとか・・・・・・。
ここは箱男の街。匿名が市民の義務となり、誰でもない者だけに許された、居住権。登録された一切のものが、登録されたというそのことによって、裁かれるのだ。
観念した。自分の醜さに耐えながら、上衣をとり、シャツを脱ぎ、ズボンを下ろして裸になった。勃起した。だのに、なんの反応もなかった。ドアの向うはしんとしずまりかえったままだった。単に音がしないだけでなく、物質のような静寂がうずくまっているのだ。鍵穴からの視線が黒い光になって突き刺さってくる。視界から色が消えて、明暗だけになる。足の裏から感覚が消えた。よろけそうになったはずみに、小便をもらしかける。小便ではなく、射精だった。途中でこらえることは出来なかった。彼は膝をつき、顔を両手で覆って泣く真似をした。涙が出るわけはなかった。彼の内臓は、夜明けの砂浜のように、一瞬のうちに干上がってしまっていた。
箱を加工するうえで、いちばん重要なことは、とにかく落書のための余白をじゅうぶんに確保しておくことである。いや、余白はいつだってじゅうぶんに決まっている。いくら落書にはげんでみたところで、余白を埋め尽くしたり出来っこない。いつも驚くことだが、ある種の落書は余白そのものなのだ。(中略)
じっさい箱というやつは、見掛けはまったく単純なただの直方体にすぎないが、いったん内側から眺めると、百の知恵の輪をつなぎ合せたような迷路なのだ。もがけば、もがくほど、箱は体から生え出たもう一枚の外皮のように、その迷路に新しい節をつくって、ますます中の仕組みをもつれさせてしまう。
最近、ずいぶん久しぶりに本作品を読み直した。ところどころでショックを受け、混乱した。すらすらと読み進めることができず、何度も立ち止まった。過去に読んだはずなのに、次のページの展開が予想できず、心がざわついた。たくさんの奇抜な比喩に、思わず、うなった。著者の意図を推測しようとするも、あまりに難解で、諦めの境地に陥った。読了後には、とてつもない疲労を感じた。
それでも、若いころに本作品を読んだときと比べたら、本作品から受けるショックや戸惑いや抵抗感は、ずっと少なくなったように思う。年の功かな。
このような作品を読み始めると、ぶっ飛んだ不可解な世界に一気に引き込まれ、現実世界から完全に切り離され、その摩訶不思議な世界観に、頭も心も徹底的に弄ばれる。これこそ、読書の醍醐味なのかもしれない。その意味では、この作品には、何度も、とても素晴らしい読書経験をさせてもらった。もう少し歳を取ったら、またチャレンジしてみようと思う。
ご参考になれば幸いです!
私の他の読書録の記事へは、以下のリンク集からどうぞ!
いいなと思ったら応援しよう!

