
カジュアルでもガチでも、デュエルそのものを楽しむために考えていること
ありがとうございます。サユキです。
カバー画像の「ヴァルモニカ・シェルタ」は、デュエルの遊び方やデッキ構築に迷い悩み考えている自分の姿を想起させるようで、天使と悪魔の囁きに揺れ動くセレトリーチェの様子にシンパシーを感じて選びました。
遊戯王が大好きで7年近く遊んできた身でありながら、まだ大会や交流会に参加したことがないので、デュエルの機会はリモートで遠方の知り合いと、または近場に住んでいる友人と集まって、のどちらかになっています。
当然、人によって遊戯王のプレイスタイルは大きく異なるため、「先攻制圧上等!」「動きは初動で止める」という友人から「誘発ほとんど入れないよ」「強すぎるカードは最後まで取っておく」という知人まで様々。
テーマデッキのデザインが好きな人もいれば、様々なビルダーさんを参考にしながらオリジナルデッキを組むのが生き甲斐な友人もいます。
昔の私はそうしたスタンスが曖昧だったのですが、カードパワーのインフレや考え方の変化に伴い、「いかにお互い楽しいと思える試合をするか?」ということをだいぶ重視するようになりました。
もちろん、こちらも勝ちたい気持ちを燃やしながら決闘するので、最終的な勝利は目指します。
でも、例え試合には負けても、デッキの動きや見せたいシナジーが披露できたとき、出すと歓声が上がるようなカードの降臨に成功したときの盛り上がりには、他では得難いものがあると思うのです。
理想論かもしれませんが、何とかその両立を目指したいという気持ちで、最近はカードを触っています。
いわゆるプロレスデュエルと呼ばれる、互いの動きを見せ合ってそのプロセスも魅せる活動者の皆さんをとても尊敬しているのですが、「そのスタンスを普段のデュエルでも実現したい!」と言い換えられるかもしれません。
(プロレスデュエルに近しい対戦を撮影したことがあり、結果的によい動画が撮れたものの本当に疲弊しました。あれを定期的にされている方々がいかにすごいかが分かります)
前置きが長くなってしまいましたが、普段何を考えて遊戯王に触れているのかを整理しようと思い、筆を取りました。
何かちょっとでも、読んでくださった方の参考になれば嬉しく思います。
前提として
私のデュエルに対する考えは一つの形に過ぎませんし、それ以外の考えが間違っている、なんてことももちろんありません。デッキ構築の理論同様にこの記事も私の一意見で、エゴが強いことも自覚しています。
純粋に勝ちを目指していく上では「それは舐めプだろう」と言われてもおかしくない点もあるでしょうし、そうでなくても人によって同意しかねる点も散見されると思います。
また、コンボ・コンセプトデッキを組むことがまだまだ苦手な未熟者ですので、これまでの記事同様、テーマの純構築やそれに準ずる混ぜ物をしたデッキの話が多くなります。
そんな中でも、皆さんの遊戯王ライフに何かのきっかけを投じる文章であれたら、それに勝る幸せはありません。
デュエルするとき考えていること
身内とやるときは自分のデッキを宣言する
かたや環境トップクラスのデッキ、かたやコンセプトデッキという対面になった場合、双方が合意しているならもちろん良いのですが、そうでない場合はパワーが違い過ぎて悲しいことになってしまいかねません。
なるべくそうならないよう、パワー差で互いが気まずくなることを避ける防衛策です。
例えば【海晶乙女】を使う場合、カードプールを一通り知っている人には「【海晶乙女】だよ」、最近遊戯王を始めてくれた友人には「リンク主体で、アニメのキャラが使ったデッキだよ。強さの個人的体感は中堅くらい」といった伝え方をします。
また、対戦が始まって何のデッキか分かるまでは秘密にしたい友人もいるので(私も昔はそうでした)、そういうときは環境クラス・それほどじゃないけど強い・コンセプトやコンボ優先のデッキ、あたりで大体の強さだけ伝えてすり合わせます。
相手のデッキを予想することでしか摂取できない栄養も存在するので、そこは相手と相談しながら、という感じです。
先攻は1.5〜2妨害で止める
最近のテーマは1枚初動が豊富なのはもちろん、初手要求値が比較的高い代わりに2枚初動ですごい展開ができる、というケースも増えました。
しかし、そうした展開力あるテーマや強力なパッケージを使っていたとしても1.5妨害、多くて2妨害も構えられるようならそこで止めるようにします。
また、最近増えている「1枚で明確に詰ませる」カードは先攻でまず立てないように心がけます(次の項で例を挙げます)。私自身そういうカードたちも好きで使いたいからこそ、自己満足ではありますがそうした制約を自身に課しています(そうした強力なカードたちにも、試合中盤〜終盤には登場してもらいます)。
他方で、前項で挙げたようにデッキを事前確認した上で「互いに環境に顔を出したことがある・現在進行形で優勝報告がある」レベルなら、真剣勝負を楽しむべく最初からテーマのパワーを全力で引き出すようプレイします。
これは自己紹介の記事でも触れたのですが、カジュアルにおける妨害数の話をミソさんがされていて、その中で言及された「先攻1.5妨害」という話にとても共感したので、私もリスペクトしているところです。
(とてもいい動画なのでこちらでも貼ります。迷える方々の参考になると思うのでぜひ)
あるいは(参加経験がないので想像ですが)オフ会や交流会といった場でのデュエルなら、先攻は自分の動きやリソース確保の準備に充てて妨害はほぼ構えない(0〜1妨害)という動きがちょうどよいのかなと考えています。
そう遠くないうちにそうした場にも参加してみたいですし(あとは勇気だけ)、妨害等を構えることに限らず、様々な動き方を自分の中で持っておきたいところです。
テーマのアイデンティティーなカードでも、出すタイミングは慎重に
これは前項と似ていますが、テーマを代表するカードが先攻だとあまりに強すぎる場合、2ターン目以降に回すことを心がけています。
例えば、先ほど言及したような
●ライゼオル・デッドネーダー(効果を発動するたびに破壊を飛ばす)、
●大将軍紫炎(魔法・罠カードの発動を1ターン1枚に制限する)、
●エルシャドール・ミドラーシュ(互いの特殊召喚をターン1度に制限)
といった「1枚で明確に詰ませる」力のあるカードは、プレイするタイミングに注意します。
いずも好きなカードなので使いたいは使いたいのですが、このレベルのパワーカードが序盤から立ってしまうと相手の選択肢を根こそぎ奪いかねないので、彼らには捲り返しや真打登場のタイミングが訪れやすい中盤〜終盤の盤面を任せるようになりました。
また、テーマやパッケージ単位で考えるなら、
●【ヴァルモニカ】を使っていて先攻をもらい、ゼブフェーラを立てられることになっても手札や墓地に「律導(選律)のヴァルモニカ」は構えず、エレディターレ(万能カウンター罠)1枚に留める
●赤き竜ギミックでコズブレやスーパーノヴァを出せるデッキでも、登場は2〜3ターン目に回す。1ターン目に出すとしたら、精霊究極竜など、強力な効果であっても即座にゲームを終わらせるほどではない(無効にはするが破壊はしない等の)ドラゴン族を選ぶ
のように、突破に上振れや多くの手数を要求するパワーカードは、それが例えテーマらしいカードであっても登場を待ってもらうことが多いです。
【ヴァルモニカ】が好きなので彼女たちを例に挙げますが、実際このデッキに関しては、エレディターレの発動後も墓地効果によってリソース回復ができるので、中長期的に戦いたいプレイスタイルにもマッチしていることが分かったのは収穫でした。
「律導(選律)のヴァルモニカ」は素引きしていれば別ですが、先攻で構えられたときの絶望感は凄まじいです。これを構えたゼブフェーラが立っているだけで投了せざるを得ないデッキも少なくないでしょう。
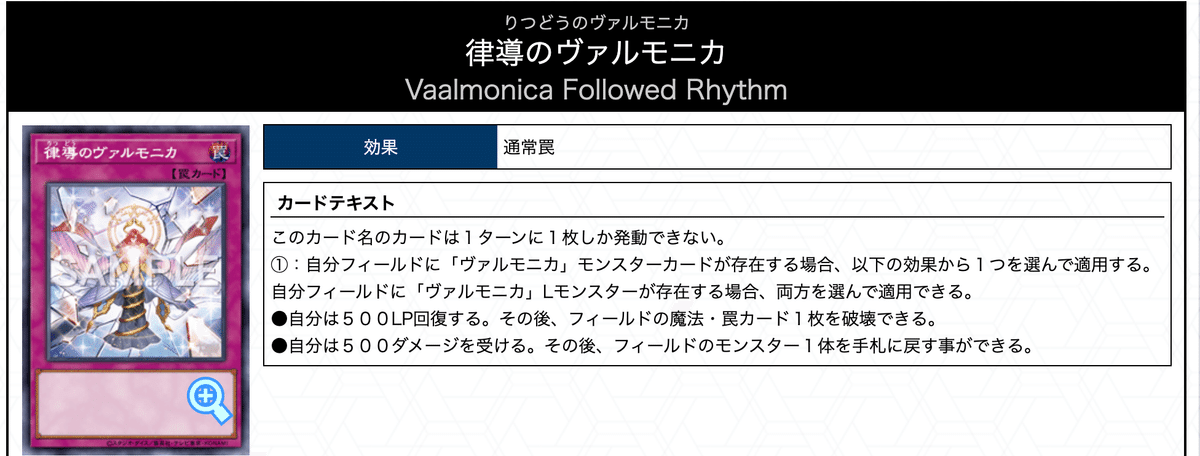
しかし、先攻を取った際に万能カウンター罠のエレディターレを構える展開を試してみたところ、ちょうどいい盤面に感じました。

相手の動きを眺めつつ、こちらの盤面が吹き飛ぶようなカードや爆発的アドバンテージを生むマストカウンターを見極め、そこにストップをかけられるようにしておき、返しのターンをもらいに行く……というイメージです。
ゼブフェーラがいてくれると、響鳴カウンター3個と引き換えに自身の戦闘破壊や相手の全体破壊効果を一度耐えることができるため、そこにカウンター罠を使わされることがないのも偉いです。

無論、相手が力あるデッキだったり、初手からバチバチに止めてくる相手だったりするなら、こちらも律導や選律によるゲームコントロールを目指し、世界の命運を相手には動かさせない鉄の意志を持って勝負に挑みます。
【ヴァルモニカ】、ちょっと癖はありますし初手の要求値も高いですが、かわいらしくて拡張性もあるいいテーマです。今後も研究していきたいですね。
テーマデッキで戦う場合はテーマカードを盤面に残したい
これは周囲の友人もよく口にしているので、価値観としては割とメジャーな考え方かもしれません。
例えば、【M∀LICE】なら最終盤面に立てるLモンスターとして、ネオテンペスト投入がメジャーな型だと思われます。実際非常に強力な動きですし、少ない手数で多くのカードを出力できるテーマですので、ネオテンペストを目指す動きは極めて合理的かつ真っ当なものです。
ただ、私は逆張りなのも手伝って、【M∀LICE】であればテーマ内エースのクリプターと何らかのM∀LICE罠を構える盤面を作るようにしています。

このテーマを使ってるんだ、と一目見て分かりやすい盤面が好きで、テーマの名前を背負ったカードたちに前線を張ってもらいたいという気持ちが強いためです。特にM∀LICEはテーマパワー的にM∀LICEだけでも十分に強く、なおかつM∀LICEカラーのある盤面を高い再現性で作れるから……という点も大きいでしょうか。
他の例として、個人的に昔から好きでずっと使ってきた【クロノダイバー】の研究を続ける最中、
●今のテーマカードだけで理想の先攻盤面を構築する(リダン・パーペチュアを並べる≒レベル4モンスターを4体出力する)ことが極めて困難
●全体のカードパワー上昇により、リダンやパーぺチュアを出すまでに妨害を当てられたり、出した後もすぐ除去されたりしてしまう
●一度崩された後に盤面を再構築することも難しい
という結論に至って以来、長らく彼らの構築を諦めてしまっていました。


有名な型であるRRや幻影騎士団の力を借りれば展開は広がるのですが、EXデッキを圧迫してしまうなどの点が気になっており「何とか別の形はないか?」と考えていたところ、令和を駆け巡る炎と雷・ライゼオルがエクシーズテーマとして登場。「レベル4で固められた展開力あるエクシーズテーマなら力を借りられるかも」ということで、【クロノダイバーライぜオル】を試してみることに。
すると、「エクス・ライゼオル」の規制後でありながらいとも簡単にレベル4モンスターが盤面を埋め尽くし、リダン・パーぺチュアを立たせることなど容易いもの、と言わんばかりの展開力を見せつけてくれました。
ライゼオルを混ぜるもう一つのメリットとして、「ライゼオル・プラグイン」に触りやすくなること。

墓地はもちろん、除外除去されたクロノダイバーXを蘇生・帰還させてくれるだけではなく、デッキからライゼオル罠を素材に供給できるため、リダンを戦線復帰させられるどころか罠を素材にした状態まで用意してくれます。もはや「クロノダイバー・プラグイン」です。
例えクロノダイバー展開を止められてもライゼオルたちが横展開をしてくれますし、その逆もまた然りで、相手の妨害をかなり超えやすくなりました。
とはいえ、ライゼオルにアクセスするための「ライぜオル・デュオドライブ」はX召喚するとしても、あくまで主役はクロノダイバーたち。
彼らのエースであるデッドネーダーには緊急時まで待機してもらい、リダンやパーぺチュア(と時々ダブルバレルくん)で戦うデッキであることには変わりありません。
……すっかり話が逸れてしまいましたが、このように既存のテーマに強力なパッケージを投入する場合も、最終盤面はあくまでそのテーマカードにお任せしたい、という一例でした。
それっぽく言っていますが、前述したように逆張り精神ではあります。
ただ、現代のカードパワーがカジュアルでも上がっている点を
「テーマの色を濃くしても戦いやすくなった」
「出力が控えめなテーマも、カードの組み合わせ次第で戦える可能性が広がった」
と解釈すれば、それはそれで遊戯王のいいところが出ているのかな……と思っています。
妨害を構えているとしても、基本的にはまず相手に動いてもらう
以下の記事でも言及している内容ですが、私はなるべく
相手との複雑なやり取りを楽しみたい
相手のやりたいことを出してもらい、それを返していきたい
そのためにも相手の動きはできる限り通したい
というデュエルを目指しているので、この点を大事にしたいなと思いながら遊戯王に触れています。
もちろん、相手が最初から互いに全力を出したい人・こちらの動きを初手から止めたい姿勢の人であれば、それに応えて最初のターンからしっかり勝ちを目指していきます。
ただ、ゆっくりしたデュエルを楽しみたい人と遊ぶ際や私自身の原則な姿勢としては、構えた妨害の質が高かったり(複数枚除去や万能無効)それらが複数あったりしても、まずは相手のやりたいことを通すことを優先して見守るため、待ちの姿勢で臨んでいます。
【白き森】における「白き森のあくま」、【ARG☆S】【エルドリッチ】等でアクセスすると強い「澱神アポピス」など、カードの種類を問わずに無効化できるカードも増えましたが、相手を妨害するためには基本開きません。
羽根帚などこちらの重要なカードにまとめて触ってくるカード
こちらの盤面が吹き飛ぶ致命的な一撃
1枚で莫大なアドバンテージを稼いでくるカード・コンボ
まで引きつけ、それらが来た場合の防御札として切るようにします。
本記事執筆当時の環境筆頭である【ライゼオル】【M∀LICE】のような明らかなパワーデッキを使っているときでもオリジナルなデッキでも、基本的には変わりありません。
相手にそのデッキの全力やそれに近しい出力を出してもらい、その上で跳ね返したい。突破していきたい。
パワーの高いデッキを握るときも、制圧して勝ちたいのではなく、やり取りを繰り返して勝ちを拾っていきたい。
いわば、ジャック・アトラスのようにエンターテインメントを重視したいスタンスなのかもしれません。
とは言いつつ、動きを通しすぎてチェックメイトされることも多々あり、キングの名は伊達じゃないと思わされるばかり。
頻繁にデュエルしてくれる友人とは試合後の感想戦でそのあたりの考えを話し合ったり、デッキパワーやカードパワーの調整をしたり……そういった時間そのものも、そうした会話を交わせるありがたみも、アナログな遊びの素敵なところだなと感じます。
お互いに楽しめるデュエルができるよう、まだまだ修行の日々です。
あとがき
文章に起こしてみると自分の整理にもなるかなと思って書き始めましたが、自分の脳内や思考を綺麗にまとめて、誰かに届けられるような文章を目指すことの難しさを今回も痛感しながら、この項を書き連ねているところです。
「楽しい」という言葉も非常に広義なもので、何を持って楽しいデュエルだったとするのかは、この先も正解のない世界なのでしょう。
答えも解釈も十人十色な難しい問いではありますが、デュエルが終わった後、勝っても負けても「ガッチャ!」と称え合えると素敵だなと思いますし、私もそうありたいなと常々思っています。
読みづらい点も多々あったことと思いますが、ここまで読んでくださった方々、心よりありがとうございました。
あなたのデュエルがこれからもより楽しいものになりますように。
そして、読んでくださったあなたといつかデュエルができますように!
