
色彩調和論①~1分で読めるAFT色彩検定1級のポイント~
こんにちは。
カラースタイルの三好です。
さて今回から第2単元「色彩調和論」に入ります。
旧テキストと比較すると、それほど変更がなく定番の問題が多い分野です。きっちり覚えて旧テキスト対応のテキストでも十分、可能なので、問題慣れしておきましょう。
ここでは6つの色彩調和論を学びます。
それぞれの特徴が混ざらないようにしておきましょう。
大きく分けると次の通りです。
・ジャッドの色彩調和、4つの原理
・シュヴルールの色彩調和論
・ルードの色彩調和論
・オストワルトの色彩調和論
・イッテンの色彩調和論
・ムーンとスペンサーの色彩調和論
少しだけそれぞれに補足を加えると・・・
・ジャッド(アメリカ・色彩学者)の色彩調和、4つの原理
・シュヴルール(フランス・化学者・織物工場の名誉工場長)の色彩調和論
・ルード(アメリカ・自然科学者)の色彩調和論
・オストワルト(ドイツ・化学者)の色彩調和論
・イッテン(スイス・美術教育者)の色彩調和論
・ムーンとスペンサー(アメリカ・色彩学者夫妻)の色彩調和論
このように国と何している人かは、必ず覚えておきます。
◆ジャッドの色彩調和論◆
今日はジャッドさんをまとめますね。
ジャッドさんは、たくさんの色彩調和に関する本を読み込んで、それをまとめた人なんですね。
たくさん読むと、共通している点などが見えてきてそれらを4つの原理としてまとめたんです。
・秩序の原理
・なじみの原理
・類似性の原理
・明瞭性の原理
この4つです。
2級でも習っているのですが、簡単にまとめると
・秩序の原理は補色色相配色やトライアド、等色相面上で等間隔に並ぶ直線状のグラデーション配色などを指しています。
色立体や色相環から秩序立てて選ばれた色の配色は調和する、という考え方です。

(v4とv16の補色色相配色)
・なじみの原理の代表はナチュラルハーモニー、その他は色相のグラデーションやトーンオントーン配色を指しています。
照明された物体の明暗や自然の中での色の見え方など、人が慣れ親しんだ色の配列による配色は調和する、という考え方

(v10・v11・v12・v13・v14の色相のグラデーション配色)
・類似性の原理は、同一色相配色とか同一トーン配色、ドミナントカラーやドミナントトーン、トーンイントーンなどを指しています。
色相やトーンなど共通要素がある配色は、その共通性で調和するという考え方

(v4・b4の同一色相配色)
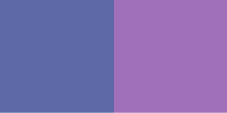
(b20・b22の同一トーン配色)
・明瞭性の原理は、ビコロール配色やトリコロール配色などを指しています。
はっきりとした明快なコントラストがある配色は調和する、という考え方

(v12・v20・v4のトリコロール配色)
出題傾向は、内容を問う文章題や配色からどの原理を指しているかを選ぶものなどがあります。
今日は超超有名人のジャッドさんでした。
本日はここまで♪
