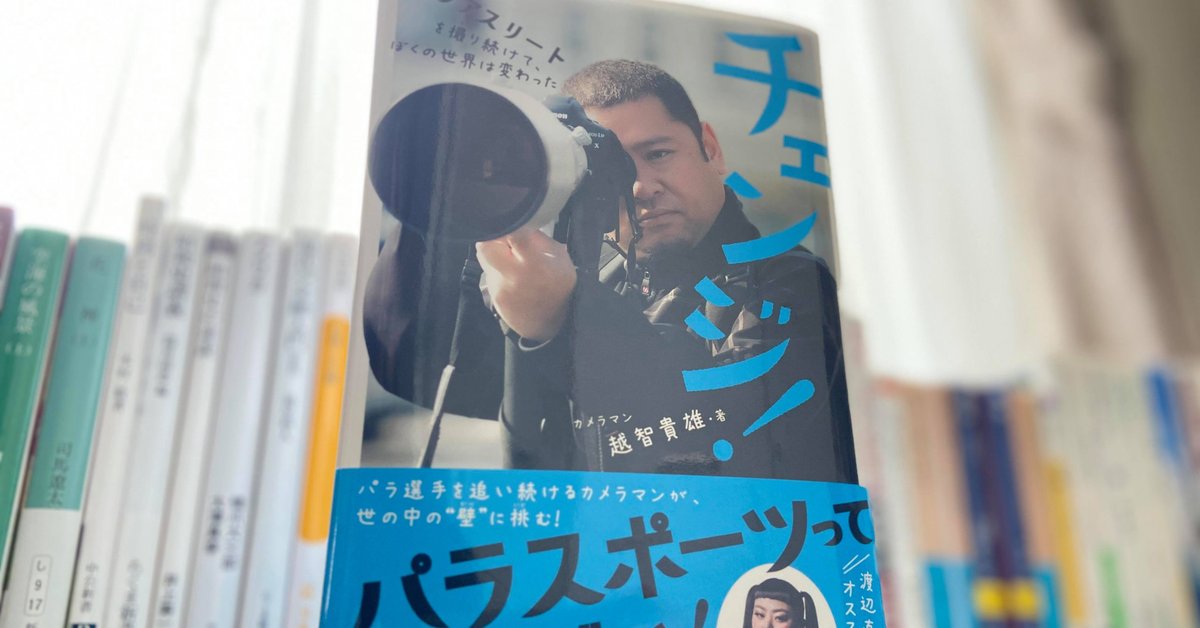
カメラを持つと変身する男 –パラリンピックを撮りつづけて20年–
ひょんなことからカメラマンに
その男は、物腰が柔らかい。「ありがとうございます」「助かります」といつも仕事相手や仲間への感謝を口にし、決して微笑みを絶やさない。少し垂れた眉が、またなんとも言えない「いい人感」を際立たせている。
ところが、ひとたびカメラを持つと別人になる。突然頬を叩く。かと思いきや、素早く頷き、降ってもいないはずの雨を両手で受け止める仕草をし、一瞬天を仰いだかと思えば、矢継ぎ早にカメラを構え、鬼の形相でシャッターを切る。その姿は「獲物を狙うチーター」とも言われる。
男の名は、越智貴雄。2000年のシドニーから連続してパラリンピックを撮影し続けている、日本でも有数のパラリンピックカメラマンだ。
15歳の頃、近所の写真屋さんで、陳列してあった写真立てを壊してしまった。慌てて「弁償します!」と言うと店長は「いいよいいよ」と優しく許してくれた。普通ならそこで話が終わる。だが越智は、「写真に関わる人はみんないい人に違いない」と思い、これを機に写真家を目指すことを決意した。すぐさま父親に「カメラが欲しい」と懇願するも、買ってもらえない。繰り返しお願いすると「テストで100点とったら」という条件が出される。当時の、越智の平均テスト得点は20〜30点。達成不可能と見越しての父からの提案であった。
しかし越智は見事100点を取る。「マークシート式だったんで、これはいけるなと。こういう時、僕は勘が冴えるんです。当時新庄剛志さんが『ミリオネア』という番組で鉛筆を転がして1000万円を取っていて、だったら自分もいけるんじゃないかと信じていたんです」。念願のカメラを手に入れ、そのままの勢いでフォトコンテストに応募すると立て続けに受賞。越智のカメラマン人生が始まった。

カメラを構える前屈姿勢は今も昔も変わらない小学5年生の越智(右)
パラリンピックとのたまたまの出会い
ひょんなことからカメラマンになった越智は、これまたひょんなことからパラリンピックと出会うことになる。大学2年生の頃、2000年のシドニーオリンピックで周辺取材を行う仕事をしていた。すると、越智の写真を見た新聞社から電話があり、「越智くん今シドニーだよね?そのままパラも撮って帰ってきてよ」とお願いされる。仕方なく引き受けた越智であったが、パラリンピック会場で衝撃を受ける。「なんだこれは…!!」。そこには、見たこともないような、美しく、激しく、ワクワクする世界が広がっていた。「なんて面白いスポーツなんだ!」。越智は夢中でシャッターを切った。
帰国後、越智はすぐさま銀座ニコンサロンで、初の写真展「魂の瞬間」を開催。自分が目撃してきた凄まじい世界を、一人でも多くの人と共有したかったのだ。しかし、「なんで可哀想な人にこんなスポーツさせるの」といったようなマイナスの反応が多くあった。ショックを受けた。越智は、「自分が感じたパラリンピックの面白さが写真で伝わっていない」と思った。悔しくて悔しくて、伝わる写真が撮れるまで追いかけようと心に誓った。パラリンピックカメラマンとしては食べていけないので、生活のために新聞配達、バスのツアコン、ブライダルカメラマン、何でもやった。そして貯金をパラリンピック撮影に費やし続けた。気づけば2018年の平昌パラリンピックは、越智にとって10回目のパラリンピックとなっていた。

平昌パラリンピックのアルペンスキー会場での越智
積極的に「受け身」になる
「撮影前まではグルグルゴチャゴチャ余計なことばかり考えるんですよ」と越智は言う。何を撮ろう、誰を撮ろう、どう撮ろう。自分がこれから撮る写真の意義を考えていくと、頭の中の糸がこんがらがっていく。しかし、パラリンピックの現場に来るとすべてが急にパーンとクリアになる。世界最高峰の舞台では何もかもがシンプルで、越智はただ「受け身」になり、寄ってくるものをまっすぐに受信する。いい写真が撮れた瞬間は「金縛り」にあったかのような衝撃がある。
長年密着してきた選手を撮るのも好きだが、撮りたいものが突然天命のように現れることもしばしあると言う。「美術館に行くとお目当ての画家や絵があるじゃないですか。モネとかゴッホとか。でも、突然まったく知らない彫刻を見て、固まって鳥肌が立って動かなくなることがあると思うんですよ。この2つのパターンがあるのが、パラという大きな美術館ですね」。これだからパラリンピックの撮影は、やめられない。
「ずっと写真で『一番』を目指してきたんです。写真以外は何もできないんですけど、写真だけは何故かできるので。神様ありがとう、っていう感じです」。しかし、自分が求めるレベルの写真を撮れず、もがき苦しむ日々が続く。2011年、韓国テグ世界陸上の現場でギックリ腰を起こしてから腰痛が悪化し、その後1年間はまともに歩けず休業を余儀なくされる。痛みをおして現場に行き、若いカメラマンに一番いいフォトポジションを取られたことは今でもトラウマになっている。しかし、腰痛が治ってからは吹っ切れた。
「一番になりたい、ではなく一番になりようがない」「誰かと比べるのではなく、自分が悔いのない写真を撮ればいい」。2012年のロンドンパラリンピックでは椅子に座りながら撮影した。それからは、なぜか憑き物が落ちたかのように、自分で納得のいく写真が撮れるようになった。
「僕、ファインダー越しに人を見ると好きになっちゃうんですよ。あと、その人のことが分かっちゃう。そうするとね、嫌いになれないんですよ」。そんな優しい男が、カメラを持った途端にスイッチが入り「カメラマン」に変身する。「選手からも怖いって言われたり、逆に面白がって選手が僕を撮影するんですよ。僕としてはニコニコしてるつもりなんですけど(笑)」。この緩急こそが、越智という人間の魅力だ。

平昌パラリンピックでアイススレッジホッケーを撮影する越智
障害者ではなく発明家として撮る。
2020年6月、越智は「チェンジ!」という新刊を出した。印象的な言葉が載っている。「練習でも生活でも、自分で考えて工夫をこらし、最適な方法をあみ出すアイデアマンのパラアスリートたちは、まるで発明家のようです」。障害者ではなく、発明家というフィルターを通して撮影をする。だからこそ越智が撮るパラリンピックの写真は、多くの人を惹きつけるのだろう。
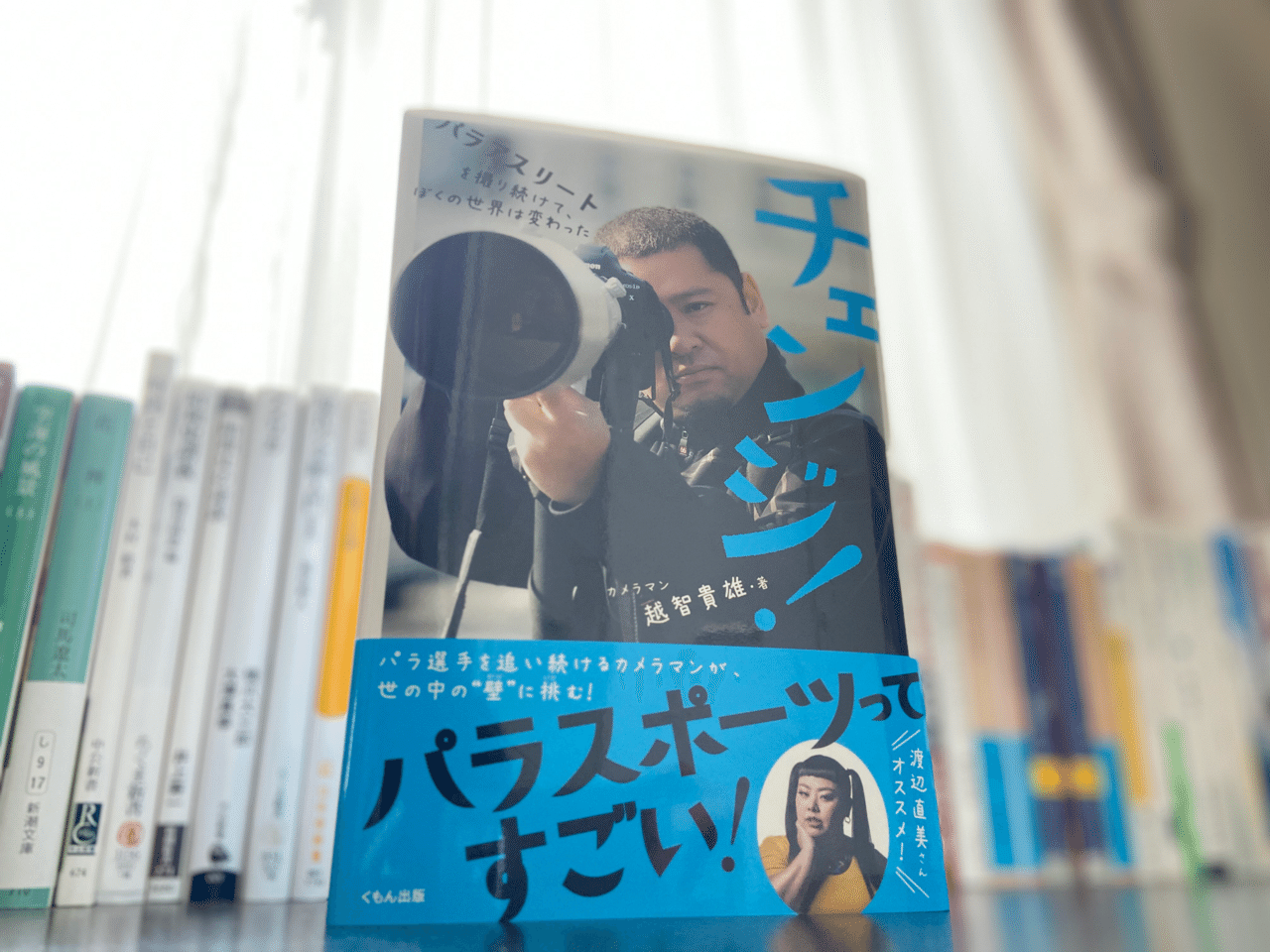
黄金色に染まる夕暮れの平昌パラリンピックスノーボード会場で、カメラを降ろしたままたたずむ越智の姿をみつけた。その先には、走行直後に抱き合う義足のアメリカ人選手と家族がいた。「撮るのがもったいなくて」。越智はいつまでもその家族を、静かに見つめていた。
