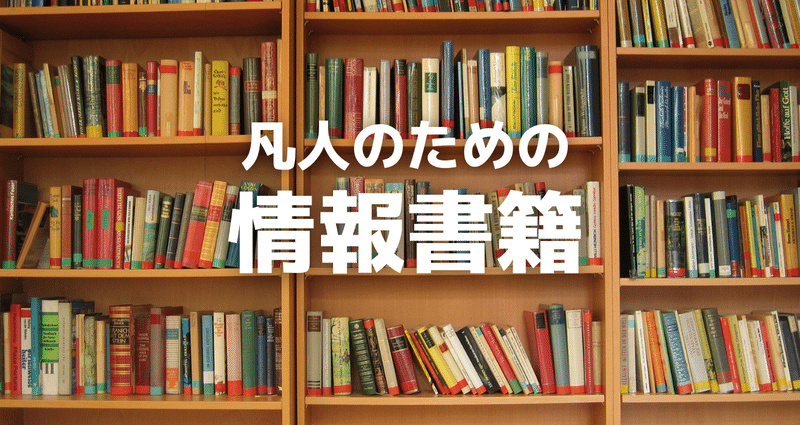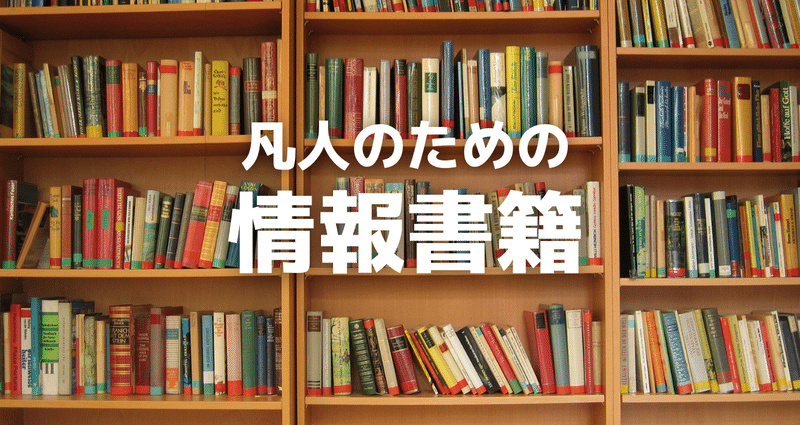【PR】定年後の人生、AIが新たな光を:AI時代の生き方「ひとみん」
変わりゆく日常に、何か物足りなさを感じていませんか?定年退職後、これまでの忙しさから解放され、自由な時間が増えたはずなのに、どこか満たされない日々を送っていませんか?
長年培ってきた経験や知識を活かせる場がなく、将来への不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
「AIからの贈り物」の主人公、佐藤正巳も、定年後の人生に悩みを抱えていました。かつては会社の中心人物として活躍していた彼ですが、退職後はやる気をなくし、毎日を無為に過ごしていました。
AIが教えてくれた、自