
挑戦のスタイルは百人百色~愛と狂気が交差する冒険譚~ MAKERS U-18 9期
自分と本気で向き合う「愛」と「狂気」がこもる5日間。
「高校生なのにすごいね」「本当に高校生なの?」「君は普通じゃない」「AO入試や就活のためにやってるの?」
高校2年の3月、愛媛県西条市丹原町で「〜高校生が企画する〜丹原まるごとマルシェ」というイベントを開催した際、こんな言葉を大人や高校生たちからよく言われた。正直に言えば、嬉しかった。けれど同時に、「なぜ高校生ではできないのだろう?」という疑問が頭に浮かんだ。高校生、高校生……。自分は自分のためでも、ネームバリューのためでもない。ただ丹原という故郷に恩返しをしたい、その一心で取り組んでいただけだった。それなのに「高校生」という枠で見られることが悔しかった。この思いは、マルシェをスタートした日から、MAKERS U-18に出会うまでずっと胸にあった。
僕(るんるん)は愛媛の離島に住んでいて、人が大好きな少年である。僕がどのような人物なのかについてこのnoteでは触れないでおこう。

MAKERS U-18は、4泊5日の合宿プログラムから始まり、同世代の仲間と等身大の自分を見つけるためのプログラムだ。キャッチフレーズは「君の狂気に、惚れている。」まさにこの言葉通り、すべてに愛があふれていると感じる。倍率も15倍以上。9期のテーマは「挑戦のスタイルは百人百色。未だ誰も為し得ぬ道を共に進む」だった。北は北海道、南は福岡、さらにはカナダからの参加者もいた。
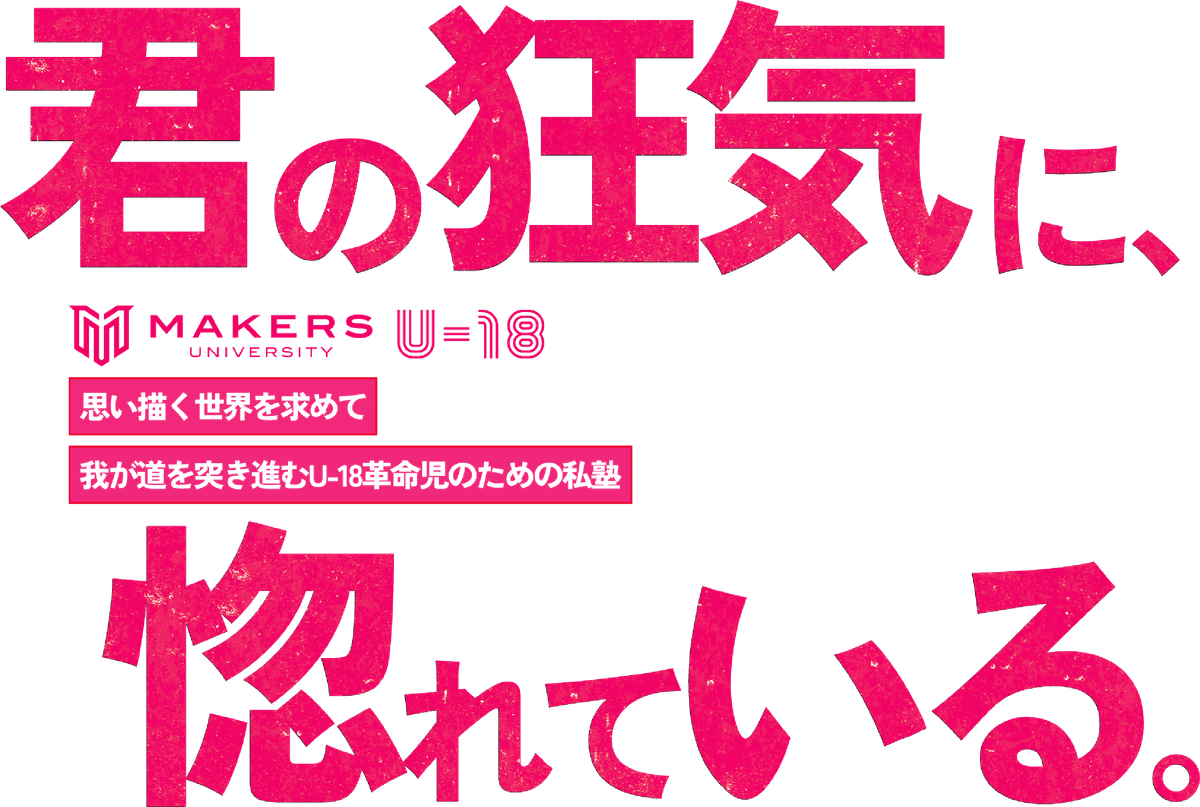
例えば、ジェットパックを作る仲間、キリンの骨に恋した高校生(初恋は人間の骨らしい。)、炭素やカーボンナノチューブが大好きで脱炭素が嫌いな仲間、地元の伝統工芸品・水引を広めたいと思う仲間、魚が好きで全国を旅する仲間など、とにかく個性が圧倒的だ。それぞれが叶えたい夢や野望を持っている。
私たちはU-18、つまり高校生だ。しかし、挑戦することに高校生という肩書は関係ない。お金も技術も経験もまだ不足しているという自覚はある。そんな厳しい現実と理想の狭間で挑み続ける30人が集まり、自分自身と向き合う。そして、何よりも「関係性の土壌を耕す」場でもある。
詳細は、ぜひMAKERSのHPやNoteで確認してほしい。
https://u-18.makers-u.jp
今年、私はMAKERS U-18の9期生として採択された。私のテーマは「幸福度が高く、住民の笑顔が絶えない地域を作りたい」というものだ。具体的には、移住者と在住者の隔たりをなくし、共にまちづくりを進めることを目指している。
私の故郷である愛媛県西条市は、「住みたい田舎ランキング」で1位を獲得したこともあるが、地域には独特の課題が存在する。西条市には移住者が多くいる一方で、古くから続く西条祭りなどの文化的背景から、新しいものを受け入れにくい傾向がある。そのため、地域住民と移住者の間に隔たりが生じ、移住者同士でグループを作ってしまう現状がある。このような課題を解決し、住民が心から「住み続けたい」と思える未来を創ることが私の目標だ。
MAKERSに応募する際、私はこの思いをエントリーシートに次のように表現した。
愛媛県西条市を拠点に、「住んでいてよかった」「住み続けたい」と思える地域づくりに取り組んでいます。西条市は、コロナ禍や企業撤退の影響で地域の活気が失われつつある一方、江戸時代から続く西条祭りや豊かな自然など、地域の魅力を活かせるポテンシャルを持つ街です。しかし、移住者と地域住民の交流不足や閉鎖的な雰囲気が、街の発展の妨げとなっています。
そこで私は、地域住民と移住者が共に楽しめる「丹原マルシェ」や「西条マルシェ」といったイベントを企画・運営しています。これらのイベントでは、地元の事業者や町外からの出店者が参加し、地域内外から多くの来場者を集めました。特に、かつて地域の人々に愛された「丹原七夕夏まつり」の記憶を受け継ぎ、地元の人々に再び笑顔を届けることを目指しました。来場者や出店者から「懐かしい活気を感じた」「またやってほしい」といった声をいただき、多くの人の笑顔に触れることができたことは、大きな励みとなっています。
今後は、移住者や地元企業との連携をさらに深めたイベントを計画しています。特に、移住者が持つ多様なスキルや経験、そして西条市の「ものづくり」の強みを掛け合わせた新しい形のマルシェを開催し、地域の魅力をより広く発信したいと考えています。また、地域住民や移住者を巻き込んだ対話イベントを通じて、双方の意見を取り入れながら、共創型のまちづくりを進める予定です。
さらに、全国の成功事例を学び、西条市で実践できる方法を模索します。特に、移住者が地域に溶け込む工夫をしている他地域の取り組みから学び、それを西条市でどのように活かせるかを探ります。例えば、宮城県石巻市でのインターンや全国のイベントへの参加を通じて得たフィードバックを、自分の活動に取り入れていく計画です。
私が目指しているのは、地域住民と移住者が共に笑顔で暮らし、支え合う持続可能な街の実現です。楽しいイベントを通じて、人と人のつながりが生まれ、それが街全体の幸福度を高め、衰退を止める力になると信じています。これからも、地域の未来を笑顔で彩る活動を続けていきます。

2月22日――
その日はちょうど宮城県石巻で実践型インターンシップに参加していた時だった。しかし、体調を崩し、38度近い発熱で寝込んでいた。そんな中、スマートフォンにメールの通知が届いた。
「MAKERS U-18 コミュニティの仲間になってもらいたい」
その瞬間、心の底から嬉しさが込み上げてきた。思わず涙がこぼれたのを今でも鮮明に覚えている。そして、そのメールは今も大切に保存している(笑)。
ただし、その「合格通知」の衝撃は強烈だった。喜びすぎたせいか、なんとその後熱は39度まで上がってしまったのだった。

3月26日 合宿1日目
みんなに会えるというワクワク感と、どんな人がいるのだろうという不安が入り混じる朝だった。9期生のさほとつばさと東京駅で合流し、国立オリンピック記念青少年総合センター(通称:オリセン)に向かった。ところが、オリセンに到着してみると、その規模の大きさに圧倒され、集合場所もわからず迷子状態に。なんとなく進んでみたところ、運よく正解にたどり着き、無事到着。一番乗りだったのはちょっと嬉しかった。
1日目のプログラムは「90秒自己紹介エレベーターピッチ」から始まった。5人ほどがピッチを行った後、話したい人のところに移動して対話をする形式だ。事前に自己紹介シートで参加者については把握していたものの、実際に目の前で彼らのパッションを感じると、ワクワク感と緊張感が一気に押し寄せた。
夜には、リバネスCEOの丸さんによる公開メンタリングが行われた。その場はわけがわからないほどカオスで、何とも言えないエネルギーに包まれていた。しかし、丸さんの後ろ姿はすごくかっこよく見えたのを覚えている。彼はこう言った。
正解がない中で何を信じるのか。モチベーションではなくパッションだ。
確かにその通りだと思う一方で、モチベーションも重要では?と感じた。この問いに明確な答えはない。けれど、パッションの大切さも確かに心に響いた。結局、答えがないのが答えなのかもしれない。
そんな風に1日目のプログラムが終わったが、面白いのはここからだった。夜、寝る場所に移動すると自然と語り合いが始まった。「自分がどんなプログラムをしていて、どんなビジョンを持っているのか」「これから何をしていきたいのか」――そんな話題が次々と飛び出す。みんなの目がキラキラと輝いていて、この瞬間が何よりも特別だった。この語り合いは夜遅く、3時頃まで続いた。まさに熱い1日目だった。

3月27日 合宿2日目
二日目は、自分が思い描く世界の解像度を高めるプログラムが中心だった。テーマは「移住者と在住者をマッチングさせるための土俵づくり #人の集まりをデザインする」。
「移住者とは?」「在住者とは?」「マッチングとは?」「土俵とは?」「人とは?」「集まりとは?」「デザインとは?」――これらの問いについて、二人一組で話し合いながら、お互いの考えを深め合った。その対話が次第にペアから全員へと広がり、9期生みんなで議論を重ねていった。
このプログラムには講師もメンターもいない。ただただ9期生同士で相互にメンタリングを行い、刺激し合いながら進めていく形式だった。議論を重ねる中で、自分が考えていた「理想の世界」が本当に自分の望むものなのか、疑問や迷いが生まれ始めた。
そのタイミングで、MAKERS U-18の特徴的なプログラム「アニキアネキゼミ」の配属が発表された。このゼミでは起業家がメンターとして伴走してくれる仕組みだ。希望通りに田川ゼミに配属されたものの、最初のゼミでの話を聞いたときに「なんだかふんわりしている……自分が求めているものと違うかも」と感じた。この時点で自分の方向性がわからなくなり、迷いが生じていた。
その後、朝比奈ゼミに移ることになり、田川ゼミは離れることになったが、今では田川さんとも仲良くなり、合宿中の「気まずさ」も笑い話になっている。(田川さん、本当にごめんなさい!笑)ちなみに、田川さんはとても素敵で面白い人であることをここで強調しておく。
夜の語り会は、この日も安定の盛り上がりを見せた。
語り合う中で、自分が応募時に「やりたい」と思っていたことが、本当に自分が本質的に求めていることではないのだと気づいた。合宿を通じて等身大の自分を知っていく中で、その違和感はどんどん大きくなった。この瞬間から、私の「迷走」が始まったのだ。
3月28日 合宿3日目
3日目は「ダイアログセッション」を行った。アジェンダオーナーが問いを立て、それに対して9期生全員で議論を深めていくプログラムだ。この日、自分は迷走中だったこともあり、自然と哲学的な方向に走り出した。
「地域が幸せになってほしい」という自分の思いに立ち返り、「そもそも幸せってなんだろう?」という問いをアジェンダとして掲げた。議論の中心は対話だったが、次々と飛び出す多様な意見に圧倒されつつも、自分の中の「幸せ」の定義を掘り下げる貴重な時間となった。
この日は1日中ダイアログセッションが続き、頭を使い続けたせいか、かなり疲れたのを覚えている。それでも夜になるとお決まりの語り会が始まり、またしても深夜まで話し込んだ。
しかし、この日も迷走は続いていた。自分が何を目指しているのか、何が本当にやりたいのか――その答えはまだ見えなかった。


3月29日 合宿4日目
この日は初めて朝がゆっくりスタート。朝ごはんも必須ではなく、みんな思い思いに過ごしていた。疲れも溜まっていたのか、爆睡している人も多かった。そんな中、僕にとって大きな転機が訪れたのは昼のことだった。
昼ごはんを食べながら、インターンsのだーくんと話していたときのこと。
「るんるん、何悩んでんだよ。自分がしたいことを本気でやれよ。」
彼のこの一言で、自分の中の迷いが一気に晴れた。「なぜ自分は迷走していたのか?」と考え直し、さらに言えば、「自分から逃げていたんだ」と気づくことができた。この気づきは大きかった。本当にだーくんには感謝しかない。
午後は、8期生と9期生のマッチングイベントが行われた。自分の自己紹介をしたり、「こんなことをやりたい」「これなら提供できる」という話をしたりと、自由に交流できる場だった。8期生の皆さんはとても個性的で、興味深い話をたくさん聞けたのが印象的だった。
また、この日は「1on1祭り」とも言える濃密な時間が用意されていた。MAKERS出身のイノベーター15人と9期生が1on1で対話する機会で、地域系の専門家の話や、ジャンルは異なるもののマネタイズやマーケティングの話など、自分が聞きたいことを直接尋ねることができた。非常に刺激的で、自分の考えがさらに広がる時間だった。
夜になると、オリセンでの宿泊最終日ということもあり、みんなで「オール」の語り会が始まった。これまでの活動や未来のビジョンについて熱く語り合いながら、深夜まで笑い合い、語り合い、特別な夜を過ごした。
この日を通じて、自分の中で何かが大きく変わったのを感じた。
3月30日 合宿5日目 最終日
本当にあっという間の5日間だった。「終わりたくない」という気持ちが正直あった。それだけ濃密で、忘れられない日々だった。この最終日は、いくつかのプログラムを経て、最後のプログラム「出航式」が行われた。
「出航式」は、一人ひとりがこれからの挑戦へと旅立つための、ある意味で一区切りとなるプログラムだ。みんなの前で、それぞれがこの合宿で得たものや感じたこと、自分が向かう未来について語った。そして、語り終えた人に対して、全員で応援メッセージを書くという、まるで卒業式のような場だった。
ただし、MAKERS U-18には「卒業」という概念はない。このコミュニティに終わりはなく、挑戦は続いていく。それがまた特別なところだ。
今でも、そのときに書いてもらった応援メッセージに励まされることがある。みんなの思いや言葉が、これからの挑戦の支えになっているのを実感している。
別れの瞬間、僕はふと「また孤独になるのではないか」と怖くなった。愛媛では、ここまで本質的なことを語り合える同世代の仲間に出会うことはなかなかない。多くの場合、「すごいね」といった表面的な言葉で会話が終わってしまう。
しかし、9期生の仲間たちとは違った。本気でぶつかり合い、本質的な問いや考えを共有できる関係だった。それだけに、この場を離れるのが怖かった。心から「また会いたい」と思える仲間との別れは、特別な寂しさを伴っていた。


あっという間の5日間。そして濃厚すぎた日々。
9期生は30人だけれど、僕は「36人のプログラム」だと思っている。それは、9期生30人+インターンsのだーくん、おゆずさん、トミーさんそして運営のめぐるん、TKD、しょうまさんの36人いたからあの愛がこもった9期だと考えているからだ。9期のテーマは「挑戦のスタイルは百人百色。未だ誰も為し得ぬ道を共に進む」。この言葉の通り、僕たちはそれぞれ異なる背景やビジョンを持ちながら、全国各地(国外も含む)で挑戦している。
統括のめぐるんが言っていたけれど、9期という場そのものが、このテーマを体現していたと思う。合宿後も、孤独を感じることなく、LINEやSlackでつながり、Zoomで壁打ちをしたり、相談し合ったり、時には笑い合ったり――そんな関係性が、挑戦を支えている。
「未だ誰も為し得ぬ道を共に進む」のは簡単なことではない。そもそも、僕たちが進む道は誰かが敷いたレールではなく、自分たちで一から敷いていかなければならない。それはとてもしんどい作業だ。敷かれたレールの上を走る方が、間違いなく楽だろう。でも、その苦悩こそが楽しみだと感じている自分もいる。
先日、めぐるんがグループLINEに送ってくれた言葉が胸に刺さった。
「未だ誰も為し得ぬ道なんて、ムズイよ。キツイ。我ながらね。MAKERS U-18という新しい何かを創る身として、毎日吐きそうです。
でも、共に進むなら、不思議とちょっと、イケる気がしてきたんだよね。
創ったものに、いいじゃん。面白いじゃん。そう言ってもらえると、どうなるかわからんけど間違ってない気がする。
最初から正解なんて見えるわけないんだから、目の前の信じられるものを積み上げるしかない。
その道を共に進んでいく。しかも、百人百色のスタイルで。その先にいつかきっと世界が塗り替わる。それがMAKERS U-18だと、改めて信じています。」
この言葉に背中を押された。みんな違って、みんないい。それぞれが作りたい世界を持ち、それに向かって本気で挑む姿勢がある。そして、そんな僕たちが相互メンターとして支え合い、ぶつかり合いながら進んでいく。この仲間たちは、愛にあふれた存在だと心から思う。
9期生のみんな、本当にありがとう。
インターンs、TKD、めぐるん、しょうまさん――そして運営の全員に心から感謝しています。
この5日間で得たものを胸に、これからも挑戦し続けていきます。
合宿はこれで以上!

この5日間で得た経験、気づき、そして出会いが、僕にとって大きな変化をもたらした。しかし、この物語はまだ続く。合宿後にどのような変化が起きたのか、それについては次回、Noteで詳しく記す。
乞うご期待!
MAKER UNIVERSITY U-18 10期生エントリー受付中!
思い描く世界を求めて、我が道を突き進むU-18世代が共に挑み学び合う、合宿から始まる私塾。
この場に集うのは、心の声に従って、我が道を進む同志達。
同じ時代を生きるカオスなU-18革命児との出会いが、君の理想を進化させる。
我が道を突き進む意志がある、新たな仲間との出会いを心待ちにしています。
10期合宿は2025年3月26日(水)-30日(日)。参加費・宿泊費無料、交通費支給。
エントリー・詳細はこちら▶https://u-18.makers-u.jp/
〆切:2025年1月26日(日) 22:00。
