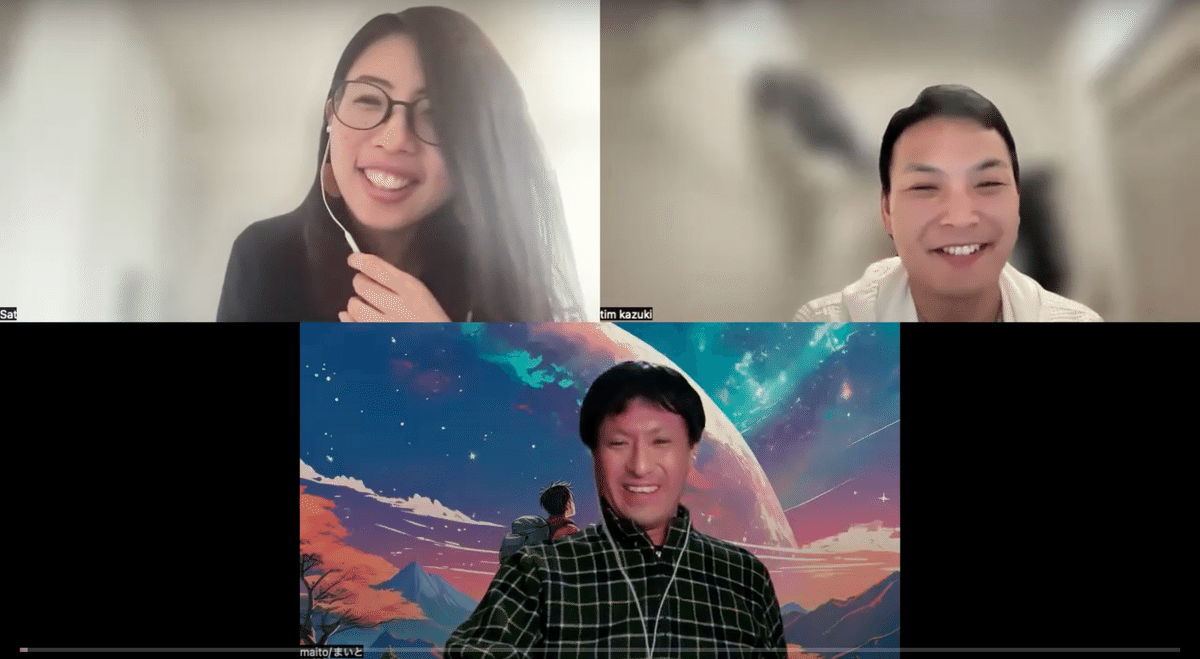なぜ、今自然経営か
(※私的に「サグラダファミリア」は自然経営を感じるのでサムネに)
my story なぜ自然経営なのか
トヨタを筆頭に日本のものづくりはボトムアップの現場力が支えてきたと思う。私のキャリアのスタートは製造業系の組織開発コンサルだった。私は当時製造現場や事務方の人たちと肩を並べながら、課題の分析や目標設定、活動計画づくりを支援していた。傍ら経営者の人たちとも何度も会議し、現場にどう自分たちのビジョンを浸透させていくか、戦略を落としていくかという話もしていた。
自分たちの会社のことは自分たちが一番よくわかっている。当時、経営の全員参画、という夢のようなことを本気で信じていた。今もその気持ちは寸分にも変わらないが、やっぱり当時経営というものが、正解あるものとしか思えなかった。経営者が考えていることがいわゆる正解であって、それをいかに可視化するか、そこをベースにいかに広げるかが組織の使命であるかのように感じていた。ボトムアップということが形骸化して感じられるのも無理はない。正解があるように思っている気持ちを偽って、考えろ、動けと自分や現場に言っていた。根底からその価値観に同意できないと思えたら、それは自分が間違っているのだと思っていた。同じように感じられない、考えられない自分が間違っているのだと。
そんな思い込みから解放してくれたのが、ティール組織であり、自然経営だった。


自然経営とは何か
以下の文章はNotebook LMを使い、自然経営研究会の元理事、山田裕嗣さん、武井浩三さんのこれまでの記事や論文、手放す経営ラボラトリーのDXOのテキストなどを読み込ませて自然経営とは何かを以下に記しました。私の個人的見解に基づくものではなく、それぞれ準拠したドキュメントがある上で確認いただければと思います。
自然経営(じねんけいえい)とは、自然の摂理に沿った経営であり、自然のように変化し続ける経営と表現されます。組織を機械的に捉えるのではなく、生命体や生態系のように捉え、変化を当然のこととして受け入れる考え方に基づいています。
具体的には、以下の3つの要素が重要とされています:
あるがままに委ねる:組織をコントロールしようとするのではなく、自然の流れに身を任せる。
今を起点にする:過去のやり方に固執せず、常に現在の状況から最適な方法を模索する。
すべてが変わり続ける:組織も人も常に変化し続けることを前提とし、変化を恐れない。
自然経営は、組織を運営する上での3つのインフラ(もしくは環境設定)として、以下の3つを重視します:
情報の透明性:組織内の情報をオープンにし、誰もがアクセスできるようにする。
力の流動性:権限や役割を固定せず、状況に応じて変化させる。
境界の開放性:組織の内部と外部の境界を曖昧にし、多様な人々が関われるようにする。
また、活動のサイクルとして、PDCAサイクルではなく、以下の3つのフェーズの循環を重視します:
土壌を整える:組織の基盤となる価値観や文化を育む。
種を植える:新しいアイデアやプロジェクトを始める。
見守る:成長を促し、変化に対応する。
さらに、自然経営は、日本的な組織観を考える上で、河合隼雄の「中空均衡構造」と「中心統合構造」という対比を援用しています。西洋的な組織は中心統合構造を持ち、中心に強い力や原理原則があるのに対し、日本的な組織は中心が「空(くう)」であり、その周りでバランスを取り続ける「中空均衡構造」を持つとされています。
また、自然を「しぜん」ではなく「じねん」と読むのは、明治時代にNatureの訳語として登場した「しぜん」との対比で捉えられます。「しぜん」 は客観的な実体を指すのに対し、「じねん」 は人間が世界の中に等しく存在するという主客未分離な世界観を前提としています。この「じねん」の概念は、組織と個人の関係を考える上で重要であり、西洋的な考え方では自分自身と組織は分離された存在として認識されるのに対し、「じねん」では自分と組織の境目が曖昧に認識されます。
自然経営研究会では、このコンセプトを実践するために、様々な実験が行われました。例えば、代表理事を交代制にする試みも、その一つです。これは、組織内での影響力の固定化を避け、常に新しい視点を取り入れることを目的としていました。また、「実験の場」 として、参加者が失敗を恐れずに新しい組織運営の方法を試せる場を提供してきました。
ただし、自然経営研究会は、ボランタリーな貢献に依存していたため、持続的な創造活動ができなかったという課題も抱えていました。そのため、個人の熱量に依存するのではなく、組織全体として成長できるような仕組みづくりが今後の課題となっています。
近年では、自然経営の概念をさらに発展させ、「生命」と「生態系」を区別して捉えるようになっています。**「生命」は個体として生き残る意図を持ちますが、「生態系」**にはその意図がないと考えられています。自然経営は、当初「生命的な組織」を目指していましたが、実際には「生態系」として捉えられていたと認識されています。今後は、健全な「成長」を目指すことが重要だと考えられており、これは組織の持つ意図に沿った進化を意味します。
また、「組織」という対象だけでなく、「組織づくり」という行為自体にも注目するようになっています。これは、組織を固定的なものとして捉えるのではなく、常に変化し続けるプロセスとして捉えるという考え方に基づいています。
これらの概念を踏まえ、自然経営は、「JINEN Management」 という言葉で海外に発信されるようになり、日本的な組織観を世界に広げる試みが続けられています。
世界的な自然経営の流れ
自然経営が世界的に注目されている背景には、いくつかの要因が考えられます。
組織運営における変化への対応の必要性:
現代社会は、VUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性) の時代と言われ、変化のスピードが非常に速く、従来の「中央集権型」の組織運営では対応が難しくなってきています。
変化の速さに対応するためには、組織の末端で自律的に判断し行動できる「自律分散型」の組織運営が求められています。
「自律分散型」の組織は、権限が現場・末端に移譲され、個人の自律性と相互の信頼を基盤とするため、変化への適応力が高いとされています。
働く人々の価値観の変化:
終身雇用制度が崩壊し、所属の流動性が高まっています。
リモートワークや在宅勤務の普及により、場所の自由度が高まっています。
ミレニアル世代を中心に、お金よりもビジョンや理念への共感、チームへの思い入れなど、働くことの意味を重視する人が増えています。
これらの変化により、「個人」が働くことを「選ぶ」 時代になってきており、組織は個人の変化に対応する必要が出てきています。
技術的な実現可能性の向上:
IT技術の発展により、非対面・非同期での情報共有やコミュニケーションが可能になり、自律分散型の組織運営が以前よりも容易になっています。
オンラインツールやクラウドサービスの普及により、場所や時間に縛られない働き方が可能になっています。
判断基準の多元化:
企業が考慮すべき判断基準が、利益の最大化だけでなく、環境負荷、多様性、人材価値など多元化しています。
これにより、中央で全てを判断することが困難になり、組織全体で課題解決能力を高める必要性が高まっています。
「日本的」な組織への関心の高まり:
グローバル化が進む中で、西洋的な組織運営とは異なる、「日本的」な組織運営に注目が集まっています。
「日本的」な組織は、「中空均衡構造」を持ち、「自然(じねん)」という言葉が示すように、主客未分離な世界観を基盤としています。
このような組織は、個人の自律性を尊重しながらも、全体としての調和を重視するという特徴があり、多様な創造性を許容できる可能性があります。
海外では、日本文化の精神性や、コレクティブウェルビーイング(集団としての幸福)への関心が高まっています。
日本的な組織は、個人のウェルビーイングよりも集団のウェルビーイングを重視する傾向があるため、「生きがい」の概念が注目されています。
「自然経営」という概念への関心:
「自然経営」は、自然の摂理に沿った経営であり、組織を生命体や生態系のように捉え、変化を前提とする考え方です。
近年では、自然経営の概念は、「生命」と「生態系」を区別して捉えるようになり、より実践的なコンセプトとして進化しています。
自然経営の概念は、「JINEN Management」として英語で海外に発信されており、世界的に関心が高まっています。
これらの要因が複合的に作用し、自然経営は世界的に注目を集めるようになっています。
上記の中でも、「日本的」な組織への関心の高まり、に特に注目したい。私自身オランダに住む環境の中でも、生きがいをはじめとした日本の文化・コンテンツへの関心が高いことも感じている。(そしてみんないつか日本に行きたいといっている(笑))なぜそこまでの関心を持っているのかを聞いても、満足がいく答えには辿り着かないのだが、日本人が持つ自然との関係性や物事を自然(じねん)的に捉える姿勢などに惹かれているように感じる。懐かしさのような、温かいもの。いのち。そのようなことを直感的に感じ取られているように思う。
また、西洋思想と東洋思想の違いでよく取り沙汰されるのが、個人主義が集団主義かという議論だと思う。上記のコレクティブウェルビーイングは西洋の文脈で理解しやすいように言語化されたものと解釈する。つまり今の世界的状況は、世界観の統合が起きているということではないだろうか。その状況下で「自然(じねん)」は元から、「個人」も「集団」も、「自律」も「共生」も、統合されている世界観を示しているように思う。
山田裕嗣さんとの対話

先日、山田裕嗣さんのスペインのティール型経営を実践している企業への訪問に同行した。その際、自然経営についてどう感じているか、今後どうしていきたいかについて話をした。(以前もラジオ出演いただいていたのでその内容も紹介しておきます)
裕嗣さんがまずライフミッションとして日本的な経営を世界に発信しようということを感じた。生きがいも禅も、西洋的解釈から世界に広がり、日本に逆輸入される形をとっているが、そのプロセスにおいて形式的になり本来的意味を失っているところも否めない。自然経営については私たち日本人起点でその心を大事に広げていきたい思いは私も持っているなと感じた。
そのためには私たち自身が海外に積極的に出ていく必要がある。裕嗣さんがおっしゃっていたことだが、海外との違いに触れて初めて自分たちのことを理解するというプロセスがあるので、その交流の中で、言語化を図っていこうと改めて思った。
自然経営は無意味?経営者は選択しない?
ただある意味ショックだったのが、裕嗣さんの中で自然経営研究会の功績が思った以上に評価されていなかったことだ。中心がないばかりに継続性のある活動ができず、価値を生みにくい。「熱量」があるときは盛り上がるが、一度失えば活動は断ち消えてしまう。人のつながり、ネットワークは拡大し、そこから派生的に様々なイニシアチブに繋がっている側面はある。自然経営の実践は「実験」には適した場ではあるが、価値創造、いわゆる企業活動には向かない、という印象があるのではないだろうか。
ーーーー以下NotebookLMによる自然経営研究会の功績まとめーーーー
自然経営研究会は、2017年12月から活動を開始し、2023年1月31日に解散したため、足掛け5年2ヶ月続きました。
その活動期間中、自然経営研究会は、以下の様な功績を残しました。
新しい組織のあり方の探求と発信:
「自然(じねん)経営」 という言葉を提唱し、その概念を広めました。
「自然(じねん)経営」 を 「自然の摂理に沿った経営」 、「自然のように変化し続ける経営」 と定義し、その考え方を普及させました。
「機械的な組織」 と 「生命的な組織」 という対比を用いて、組織の捉え方の違いを示しました。
「あるがままに委ねる」「今を起点にする」「すべてが変わり続ける」 という3つの要素を重視し、組織運営における重要な考え方を提示しました。
「情報の透明性」「力の流動性」「境界の開放性」 という3つの組織インフラを提唱しました。
活動サイクルとして、PDCAではなく、「土壌を整える」「種を植える」「見守る」 という3つのフェーズを重視しました。
河合隼雄の 「中空均衡構造」と「中心統合構造」 という対比を援用し、日本的な組織観を考察しました。
「しぜん」 ではなく 「じねん」 という言葉を使うことで、主客未分離な世界観を表現しました。
新しい組織運営の実践と実験:
「実験の場」 として、様々な新しい組織運営の方法を試す機会を提供しました。
月1回の定例イベント (Monthly Conference) を開催し、延べ459名が参加しました。
多様な分科会 を立ち上げ、様々なテーマについて議論を深めました。
Facebookグループ を活用し、761名が参加するコミュニティを形成しました。
Slack を活用し、84名が参加する実務的なコミュニケーションの場を設けました。
代表理事の交代 という実験を行い、組織内での影響力の固定化を避けようとしました。
チーム制 を導入し、自律分散的な組織運営を目指しました。
未来のシナリオを描く ワークショップを実施し、組織の未来を共有する試みをしました。
コミュニティ形成と人材育成:
新しい組織のあり方を模索する人々のつながりを顕在化させ、多面的なつながりを生み出しました。
多くの参加者にとって、新しい組織のあり方を探求する上で、大きなきっかけ となる場を提供しました。
「ティール組織」 が日本に紹介されたタイミングで、新しい組織運営に関心を持つ人々が集まる「場」となりました。
これらの活動を通じて、自然経営研究会は、新しい組織のあり方を模索する人々にとって重要なプラットフォームとなりました。しかし、一方で、継続性のある創造活動ができなかった という課題も残りました。 今後は、自然経営の概念を進化させ、組織が持続的に成長できるような仕組み作りが課題となっています。
自然経営の社会的意義
自然経営研究会の活動を総括すると、組織が自然経営を選択する意味がなんなのか改めて捉えたくなった。経営のトレンドとして、利益追求や資本拡大を中心に据えた組織づくりは長くは続かないということがだんだんわかってくる中で、人間中心的な組織を志向する流れはすでにあると感じている。
ただ、自然経営はさらにその先にコンセプトの中心がある。先に紹介した自然経営の定義の中でも「生命体組織」と「生態系組織」について言及があったが、自然経営はいわゆる生態系組織についても包括するような概念であると思う。
自然になぞらえて考えてみよう。生態系の中では私たちひとりひとりには私たちの意志を超えて役割が付与されていて、そのありのままの機能を発揮していくことで、循環が起き、生態系自体が繁栄していく。そこでは永遠に続く命はなく、時が来れば朽ちていくものもあれば生まれるものもある。
このプロセスは原理原則で、抗えるものでも敢えて選択するものでもない。そのため、「自然経営をしよう!」と意図してするものなのかというと少し違和感があり「組織ってこうなるよね」「人ってこうなるよね」をありのまま受け入れていくと自ずと自然経営の実践になるのではないかと思う。
ホラクラシー経営、ティール組織、ヒューマノクラシー、エフェクチュエーション、冒険する組織。自然経営を単なる経営のトレンドと同じ文脈で捉えるのか、それとも人の手からあるがままの姿に組織という生き物を還していくのか。
私は後者であると思っている。私たち人間が自然や宇宙の一部であることを前提にその原理原則に身を委ねていく感覚は、母なる地球の愛や自己受容につながり、深い安心感・幸福感を覚える。
だからこそ、敢えて自然経営の社会的意義を紐解いていく意味を感じている。
自然経営を世界へ。自然に還ろう。
おまけ:武井浩三AIに聴く「自然経営の効果測定」
たけちゃんAIに自然経営の効果をどう測定するかを聴いてみました。
ーーーー以下たけちゃんAIの回答ーーーー
自然経営の効果を測る方法については、以下のような視点で取り組むことが効果的だと考えられる。
1. 定性的評価
自然経営では、単なる数字の成果ではなく、組織や個人の成長、信頼関係の深化など、質的な側面を重視することが多い。これには以下の方法が含まれる:
対話やフィードバックの質の向上
メンバー間の信頼や共感がどれだけ深まったかを、定期的な対話やアンケートを通じて測る。自己成長の実感
個々のメンバーが自分の成長や自己実現を感じているかをヒアリングする。
2. 定量的評価
自然経営の成果を数値化する方法もある:
離職率の低下
自然経営の実践によって、離職率がどのように変化したかを追跡する。意思決定のスピードや効率性の向上
意思決定のプロセスがスムーズになり、業務が効率化したかを測定する。新しいプロジェクトの創出数
メンバーが自主的にプロジェクトを立ち上げる頻度を確認する。
3. 経済的指標
自然経営の施策が売上や利益にどのように影響したかも一つの指標となる。ただし、短期的な利益追求ではなく、長期的な視点での安定性や持続可能性を評価するべき。
4. 外部からの評価
外部のステークホルダー(顧客、パートナー企業など)からの信頼度や満足度も重要な指標になる。【15†source】【16†source】
5. 自然経営特有の指標
共感資本社会の実現度
メンバーや関わる人々が「共感」を基盤に活動しているかどうかを測る取り組み。組織構造の柔軟性
自然経営の仕組みが組織内でどれだけ浸透し、変化に対応できているかを確認する。
これらを組み合わせて、自然経営がもたらす影響を多面的に評価すると、より具体的な成果を測ることができる。組織の特性や目指すビジョンに応じて適切な指標を設定するのが鍵だ。
この後、それって日本一大切にしたい会社やウェルビーイング経営などいろんな経営モデルと似ているね、という話から、「異なるアプローチだけど
アウトカムはやっぱり共通だよね」という話になった。たけちゃんAIが叩き出した共通のアウトカムイメージは
①従業員の幸福度
②顧客満足度や信頼の向上
③組織の持続可能性や社会的価値の創造
というところ。
ただ私は究極、こうやって従業員とか顧客とか、主語を切り分けるのではなく、組織の中も外も、社会全体も調和し、繁栄していく自立共生の状態を目指していくことなのではないかと思っている。
それって「Conviviality(自立共生)」を次の指標にするということなのか。
evOrgで自然経営探究プロジェクトを始めます
evOrgで来年から自然経営を探究していくプロジェクトを始めていきたいと思います!まいとさんやティムさんと対話し、「自」の起源から自然(じねん)とは何かを捉え直したりと、自然経営には無限に広がるフロンティアを感じるので、引き続き探究活動を始めていきます。目標は今のところ論文を出すことですが、これもいい意味ですでに揺らぎ始めています。それこそ自然(じねん)のあり方と、「実践」「実現」を大事に、この冒険を楽しみたいところです。もし、このプロジェクトに参加してみたい方、私やお近くのevOrgメンバーにお問い合わせください!