
子どもの才能の見つけ方・向き合い方
こんにちは。さなぎです。
先日、こちらの本を読みました。
「世界一やさしい才能の見つけ方」
1つ前の「世界一やさしいやりたい事の見つけ方」も良書でしたが、こちらは子育てにも活かせそう。実際この本を読み終えたあとに息子の様子を観察して関わり方を少し変えてみたところ、のびのびとしております。
「ほんまかいな」と思われるかもしれませんが、今回の記事ではわたしが意識したことをまとめてみようと思います。
ぜひ最後までお付き合いください。
親は長所より短所に目を向ける
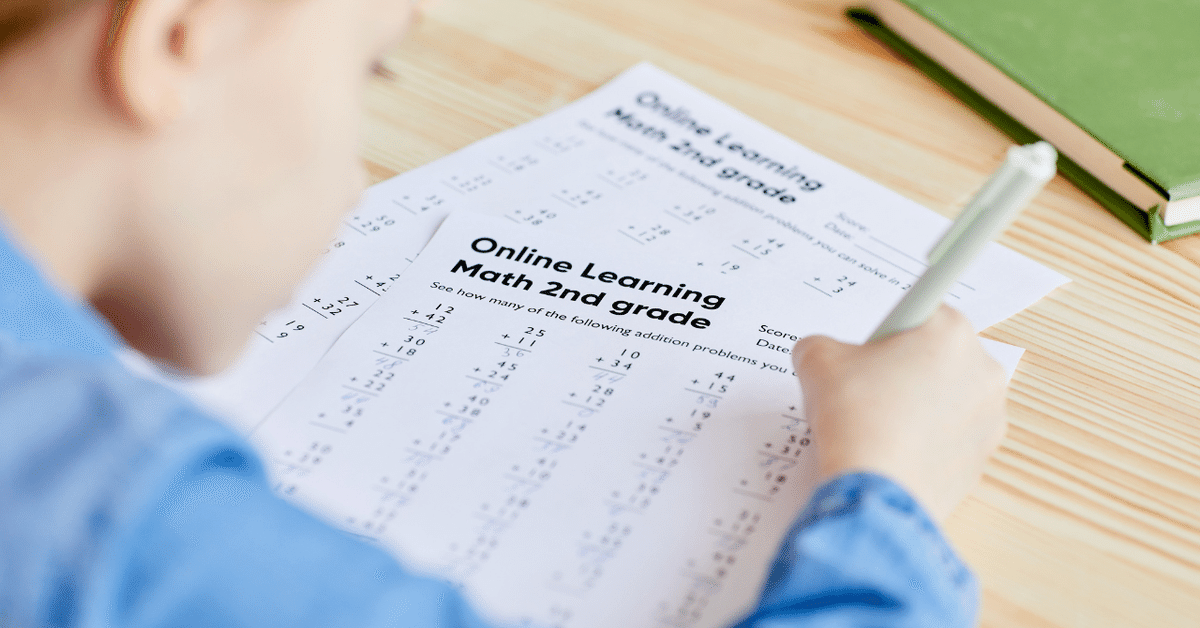
親というものは子を想うがゆえ、どうしても口を出してしまいます。
特にテストの点数。どうしても点数という目に見えて分かるものでついこう言ってしまいます。
「(95点だったのに)あと少しで100点だったね」
「(97点だったのに)あと1問合ってたら満点だったね」
「(マラソン大会で3位入賞をしても)あと少しで1位だったのにね」
小さい頃からずっとこう言われてきました。
少し不器用だった妹はこう言われていました。
「(90点を取って)すごいじゃん!よく頑張ったね!」
「(70点を取って)次は頑張ろうか」
「(マラソン大会で順位がよくなくても)よく走り切ったね!」
同じ親から生まれ、なぜこうも扱いが違うのだろうか。わたしは点数を取らないと生きていたらダメなのか…といつも感じていました。
お金をかけてもらい強豪の進学塾にも通わせてもらいました。そこではわたしなんかよりずっとずっとずーっと頭のいい、モンスター級・レベチの子がたくさんいました。
でも「わたしには無理…」となかなか言い出せませんでした。
期待をしてくれていたのは嬉しかったけど、ちょっと重かった。
この時からかな。自分の気持ちを出せなくなったのは。のちに妹が学校に行けなくなり、自分の進路選択にも影響を与えました。ちょっとだけ「あの時に波に乗って勉強をしておけばよかったかな?」と後悔もあったり、なかったり。

時はすぎ、親になったわたし。
息子が小学校1年生のころは同じように声をかけていました。
「大丈夫、キミは出来るよ」
「(97点を取って)あと少しだったね」
「(80点を取って)なんでこんな悪いの?」
今となっては大反省。猛省。土下座したいくらい🙇♂️
もはやその声かけがクセになってしまっていた気がします。
気づいたのは5年生の中盤。テストがあることを言わなかったり、隠しているのを発見。
”怒られるから言えなかった”と息子から告げられ、やっと「これは違う」と思えた。遅かったなー。
本文中にはこうありました。
“短所は指摘され続けると自信を失ってしまう“
分かっていたのに無意識にやってしまっていた。もちろん甘やかすことがいいことではありませんが、もう少し良い声かけがあったのかなと思っています。
環境を変えることで花開くことがある

小学5−6年生では完全に息子は学校に対して戦意喪失していました。環境を変えようと中学受験の勉強もしたのですが、どう考えても難しそう。
彼は読解力が少し低いため、問題文を理解するのが難しかったのです。
諦めモードの中、たまたま見つけたN中等部の文字。
N中等部では学年まぜまぜ(いわゆる無学年制)で過ごします。一般的にいう中学校のようにクラスという単位もなく、誰かと必ずいないといけないわけでもない。キャンパス内であれば作業はどこでも構いません。グループワークもランダムだから自分から動くのが苦手な子でも自然と参加することが出来ます。
お昼ご飯はみんなスマホ&イヤフォンで自分の世界。
午後はそれぞれがプログラミング学習をします。
息子が得意なのが3Dモデリング。特に授業という授業はなく、自分の好きな作業を時間内に行います。彼は海外YouTuberの動画を見ながらとにかくトレースする日々。
どんなに難しい部分もトレースし続けました。機械系が苦手なわたしからすると「もうここはすっ飛ばして次に行こうぜ!」な部分もエラーを見つけて修正して乗り越える。
この粘りは彼の才能なのかもしれませんね。
乗り越えているからこそ、たいていの作業はもう知っているそう。勝手に基礎から鍛えられていたようです。
息子は1日に3.4時間はその作業をしています。
そのトレースされた作品たちは「え、これ中学生がトレースしたの!?」レベルのすごいものに。ありがたいことにちょっとした大会に選出されました。
本文中にはこうありました。
”あなたは社会不適合者ではありません。今いる環境に不適合なだけ。”
息子にとっては一般的な中学校に不適合なだけだったのかもしれません。
彼の希望は大都市でプログラミングを仕事にしたいそうですよ。
その夢、叶えようね!
短所は長所を見つけてから踏み込む

さてさて。ここまで聞くと「環境変えて成功した。よかったね。」と終わりそうですが、そんなに現実は甘くありません。
彼は将来的に海外もいいなと考えているそう。
海外で働くには必要なものがあります。
“大学の卒業資格“
そう。大学は行かないとね、ビザがなかなか難しいじゃないですか。
なのでわたしたちは常々こう伝えています。
「今はいろいろな大学がある。もちろん新しく設立されるZEN大学もその1つの選択肢かもしれない。最近は総合型選抜もあるしね。でも出来たらそれらは第2・第3の選択肢にしよう。自分の実力で大学を選べる側になれば強いと思わない?」
この思考は特に夫が強く持っています。
彼は中学校の内申点が悪かった。学力の順位はいつも1桁台にいたのに、内申点の影響でいけるはずの高校に進学が叶いませんでした(当日点を足しても足りなかったらしい笑)。
運動も勉強も出来た。あまり目立つタイプではなかったけれど、そのあと大学は国公立大学に進学。どうやらあの時の苦労が忘れられないそうなのです。
対してわたしはゴマすりが上手で、リーダータイプ。学級長などを歴任し、内申点はほぼ満点に近かった。でも失敗が怖くてほどほどの進学校を選んだ。
そう。わたしは高校を選べたんです。
夫の気持ちはよく分かります。確かにわたしは高校入試とても楽でした。
現在、なかなか学力テストで点数を取れない息子。
テストを隠すので対策が出来ませんでしたが、不運にも(?)今回見つけてしまいましてね。
本人の許可を得て、解答の過程を見せてもらいました。
『分かっているけれど、答え方が違う』
ウイスク検査で出た「読解力」の部分が邪魔をしていたのです。
それはもう…気の毒になるほど笑
わたしはこう伝えます。
「今ね、見させてもらったんだけど、考え方は合ってるよ。でも答え方が違うからバツだらけなの。一回さ、ガッツリついて確認してみる?嫌なら無理には言わないよ。」
息子はこう言います。
「なんでいつも間違ってるか分からないから教えて」
ようやくヘルプらしきことを聞けたので、現在わたしもガッツリ介入して一から数学を見直しています。ちょっと面白い傾向も見えたのでまた記事にしようかなと思います。
わたしたちの考えはこうです。
短所ではなく長所に注目してみる
↓
環境を変えたら長所が見えた
↓
長所を掘り下げたら伸びてきた
↓
次は短所をやわらかく改善していく
今はこの最終段階に来ています。
これをね、どうしてもみんな逆でやっちゃうんですよ。そうすると本人は自己肯定感が下がるし、親もキリキリカリカリしてしまう。
本を読んで「そうか、順番か!」と気づけました。良かったーー!
というわけでちょっとした気づきがあった息子。きっとこれから変わっていきます。本人の許可のもと、noteに残していこうと思うのでぜひお付き合いくださいね☺️
今回はここまで。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
