
【2/3】【フランスチーズ留学】学校でのチーズ作り
皆さまこんにちは、hideです。
前回に引き続き学校(ENILEA)でのチーズ作りについて紹介したいと思います。
本日はMorbier(モルビエ)を例に、実際にどのような工程を経てチーズを作っているのか紹介していきます!
(今回と次回は話がかなり専門的になるかもしれません…)
Morbier作りの工程

①朝7時前に学校のチーズ工房に集合
⇒学校に到着したら作業着に着替えて工房へ向かいます。工房は「Pâte Molle(ソフトチーズ)」「Pâte Pressée(ハードチーズ)」「Yaourt(ヨーグルト)」の3つに分かれているので、当日は「Pâte Pressée(ハードチーズ)」の工房に集合。

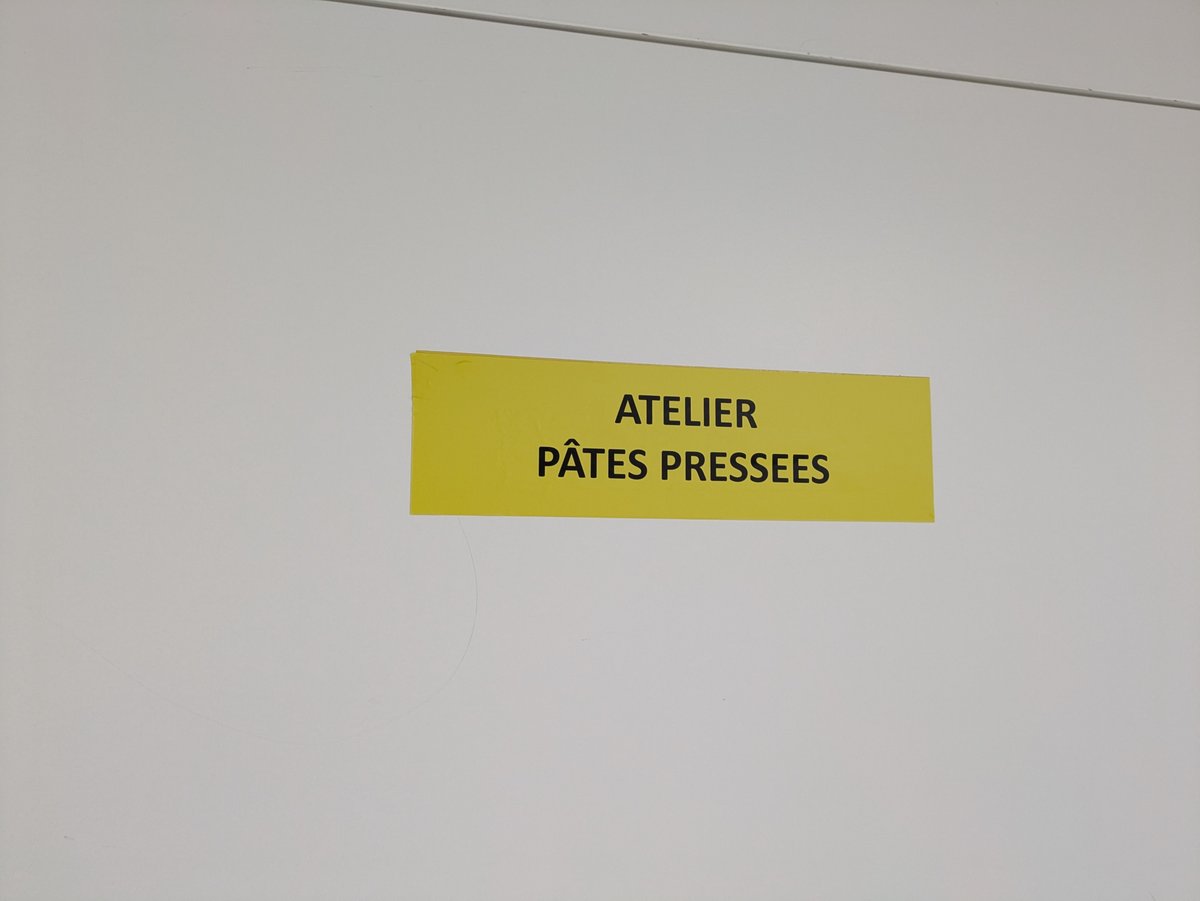

右手奥に見える機器がSoutirage(ホエー排出機)になります ※後述
②その日作るチーズのDiagramme(表)を確認して、作業の流れを確認

Diagrammeの見方として、それぞれどんな意味があるのか示すために黄と緑と青で囲ってみました。
黄:作業の手順
緑:Entrantと呼ばれ、作業の途中で加えるもの
青:Sortieと呼ばれ、作業の途中で発生するもの

③Arrivée LAIT Entier cru AOP
以降はDiagramme通りに作業を進めます。
一行目ではLait entier cru(無調整乳)を加えると記載してあるので、工房内に4つあるCuve(槽)に牛乳を満たします。


余談ですが、牛乳関連の仏語ボキャブラリーとして下記があります。
lait entier:全脂乳
lait demi-écrémé:低脂肪乳
lait écrémé:脱脂乳
④CHAUFFAGE, ENSEMENCEMENT
まずは40℃近くまで牛乳を熱します(CHAUFFAGE)。
次に、左の枠内を確認すると「Streptococcus thermophilus」や「Lactobacillus bulgaricus」等の乳酸菌を牛乳に加えてねと書いてあるので、これらを接種、つまり牛乳に加えます(ENSEMENCEMENT)。


フランスでチーズ作りに関わる人以外はあまり必要のない情報ですが、乳酸菌のENSEMENCEMENT(接種)には下記の2種類があります。
Morbierは1)Ensemencement directになります。
1)Ensemencement direct
⇒市販の乳酸菌を、直接牛乳に加える方法
⇒一貫した品質と安定性がある
⇒使いやすく、管理が簡単
2)Grand levain
⇒乳清(ホエー)を培養し、次のチーズ作りに使う方法
⇒伝統的な製法で、地域の風味が出やすい
⇒手間がかかるが、独特の味や複雑な香りが生まれる
⑤EMPRESURAGE, ENSEMENCEMENT
この工程ではPrésure(レンネット)と呼ばれる凝乳酵素を牛乳に加えます(EMPRESURAGE)。
AOPの規定により、この工程で使用されるPrésure(レンネット)は牛や羊の胃から抽出される酵素になります。
また、この工程でも乳酸菌の接種を実施します(ENSEMENCEMENT)


⑥COAGURATION
この工程では牛乳が凝固するのを待ちます。

⑦DECAILLAGE
この工程では牛乳が凝固した後、Tranche-caillé(トランシュ・カイエ)という器具でカード(凝固した牛乳)を細かくカットする作業をします。
Tranche-cailléを行うことで、より多くのホエー(乳清)を排出し、チーズの最終的な水分量を調整します
※うまく説明できてないかもしれませんが、カードとホエーの違いは下記の通りです。
カード:牛乳が凝固したもの
ホエー:残った半透明の液体のこと


Tranche-caillé(トランシュ・カイエ)。
これによりカード(凝固した牛乳)は細分化される。

トレーナーさんがCuve内をかき混ぜてしている様子
⑧BRASSAGE(1回目)
この工程では、カットされたカードをかき混ぜる作業をします。

⑨DELACTOSAGE, CHAUFFAGE, BRASSAGE(2回目)
まず、牛乳にEau de délactosage(脱乳糖水=チーズ製造や乳加工の過程で発生する副産物)を加えます(DELACTOSAGE)。
上記の工程の理由として、「乳糖が多すぎると酸性が強くなりすぎ、チーズの食感や風味に影響が出る」「脱乳糖水を加えることで、pHの急激な低下を防ぎ、穏やかな発酵を促す」等があります。
次に、再びCuve(槽)を熱し(CHAUFFAGE)、かき混ぜる(BRASSAGE(2回目))。


本日はここまで。
次回で残りの工程を紹介できたらと思います。
長い文章って読むのって結構根気いりますよね…自分もそれを分かっててなるべく写真多めに、文章簡潔にを心がけているのですが、結果的にかなりボリューミーとなってしまいました…
最後まで読んでいただきありがとうございます!
ではでは
