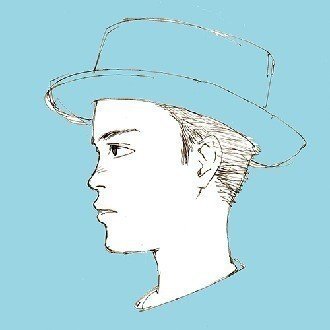2017年3月の記事一覧
猫に乗る【掌編小説】
大きく吸い込んだ息をゆっくりと吐き出すと、私の体はだんだんと小さくなっていく。セーターが縮んでいくみたいに。部屋の天井が段々と遠くなり、テーブルの脚が視界に入ってくる。緑色のカーペットの毛並みは草原のようにどこまでも続いているし、開けっ放しの掃き出し窓から春の砂まじりの風が吹き込んでくる。
四月の空はどこかマゼンタがかった淡い水色だ。
白い毛に包まれた脚が目の前に現れる。リオネルの前脚だ
Hey! TAXI!【掌編小説】
夜の日比谷通りを流していた私は、大きな荷物を持って手をあげる中年のサラリーマンの前で車を止めた。
「世田谷まで。急ぎでやってくれ」
彼は乗り込むやいなやそう私に告げると、せわしなく腕時計を覗き込んでいる。
「そんなにお急ぎですか?」
私は客のそんな素振りを気に掛けて尋ねた。師走の大通りは大渋滞だ。車であふれかえっている。世間は未曾有の好景気に湧いていて結構だが、急いでタクシーに乗り込
蝶の図書館【掌編小説】
「ご専門は文学ですか? それとも歴史学?」
「いいえ、博物館学ですよ」
館長の問いに私はそう答えた。
「ほう、それは初めて耳にする学問です。博物館を研究していらっしゃるのですか?」
「左様です。世界各地の博物館を調べ、訪問し、記録し、分類する。それが私の研究なのですよ」
入館録に名前を書きながら答える私の言葉に、館長は大きく頷いた。メガネの奥の目が柔らかく微笑んでいる。いかにも人当た
ワイングラスとバターナイフ【掌編小説】
ホントにおどろいたなあ。
君がこの店の場所を忘れてるなんてさ。去年だって一昨年だってここで食事をしたじゃないか? 僕はちゃんとこうやって、今年も夜景のキレイな席と大きな花束と気の利いたプレゼントを用意して三十分も前から待ってたっていうのにさ。
君ときたら「ごめんなさい。どこだったかしら?」なんて。
電話の向こうであまりにも申し訳なさそうな声を出すものだから、僕はもう怒るのを通り越して
スイート・リフリジエイター【掌編小説】
あたしが眠ろうと思って目を閉じると、あいつが低いうなり声をあげているのがわかる。
ベッドの中で頭からシーツをかぶって、ぎゅっと目をつぶって耳をふさいでいても、わかってしまう。
キッチンの隅にたたずむそいつは、お日様の出てる間はおとなしくしているのに、あたしの家族がぐっすり眠ったあとで、ゆっくりと動き出す。
ネズミよりも狡猾に。泥棒よりも用心深く。
何も考えていないふりして、実はア
ロスト・アンド・ファウンド【掌編小説】
私が若い頃に働いていた骨董屋には、曰く付きの売り物があった。座面に深い緋色のクッションの付いたダイニングチェアだ。一見して洒落たデザインだし、ものも良い。店に出しておけばひと月と経たずに買い手が付いた。
だが、不思議なことに買い取られてから数ヶ月経つと、客がまたうちの店に持ち込んでくるんだ。難しい顔をしてね。私が理由を聞くと客はもごもごと小さな声で、何となく座り心地が良くないとか、思ったより
村の雪神様【掌編小説】
木枯らしが吹いてしばらく経って、湖の水が凍り付いても、雪はまだ降らない。
──年の瀬までに雪が降らねえとうんまくねえなぁ。凶事がおこるぞ。
──昔も降らねえ年があった。そんときゃ米どころか稗まで取れねえで難儀した。
──そういや吉田んところの倅が流行病にかかっただろう?
──倅だけじゃねえ、嫁もだ。それで腹の子が流れた。
──なんとか年を越すまでに降ってくれればいいが。
座敷で火鉢
お母さんはある日突然、郵便局になった【掌編小説】
お母さんはある日突然、郵便局になった。
何を話しかけても「ここは郵便局です」しか言わないし、時々ポストのマネをして手紙をバクバク食べる。
お母さんに食べられた手紙はどこにいったのか、まったく分からない。
噂を聞きつけた近所の人達が、沢山の小包をもって私の家の前に並んでいる。お母さんは慣れた態度で小包を受け取り、それをどこかに放ってしまう。もちろん小包がどこに行ったのか、誰もしらない。