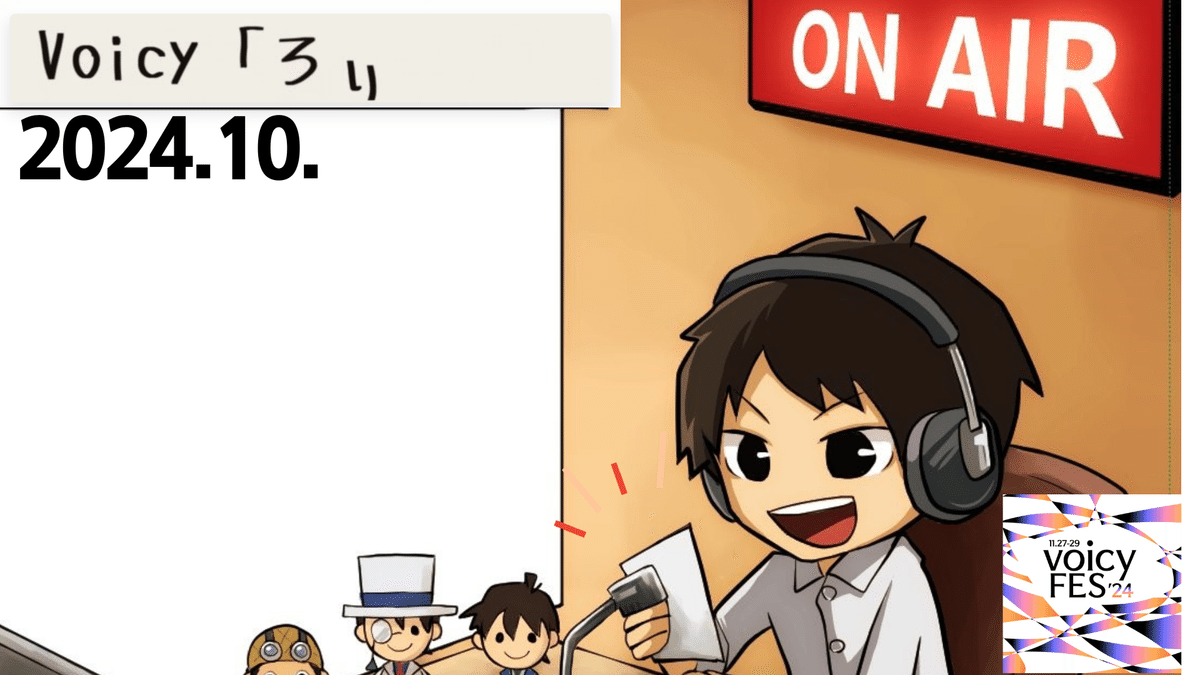冤罪生み出し判定テスト
どうも、しんたろーたりーと申します!営業マン歴13年、ナンパ歴14年の経験を活かし、voicyのパーソナリティをさせて頂いております。本日も「ろりラジ」で話したことを文章にしていきたいと思います。
今日は、Twitterで目にしたあるツイートについてお話ししたいと思います。
そのツイートは、裁判における「感情と司法の在り方」について言及していたものです。内容を要約すると、裁判官が判決を下す際に「自分の娘がこんな目にあったら」と置き換えて考えるべきではないか、という意見でした。
これを見て、僕は本当に怖いなと思ったんです。
裁判という場が何を求められているか、という基本に立ち返ってみましょう。
裁判は感情ではなく、事実と法律によって公正な判断を下す場です。「自分の娘がこんな目にあったら…」という感情論は、司法の場においては持ち込むべきではないんです。それが裁判の本質だからです。
例えば、警察でも同じようなルールがありますよね。「身内の捜査をしない」という原則です。これには理由があります。感情が捜査の公正さを損なう危険性があるからです。同じように、裁判でも「一切の私情を排する」ことが最重要なんです。
だからこそ、裁判官が「自分の娘だったら同じ判決を下せるのか」と問われたら、答えは「下さなければならない」なんです。自分の家族が被害者であろうと加害者であろうと、判決は全く同じ基準で行われるべきです。それが司法の中立性であり、公正さなんです。
この感情の排除、簡単なことではないですよね。でも、だからこそ司法は「プロフェッショナルな判断」が求められるんです。個人的な思いや情に流されることなく、法の枠組みの中で冷静に判断を下すこと。それが司法の役割であり、その枠組みがあるからこそ社会の信頼を得ているんです。
「感情を捨てる」というと冷たい印象を受けるかもしれませんが、それは決して感情が悪いという話ではありません。ただ、司法の場において感情が入り込むと、判断がぶれる可能性がある。それは被害者にも加害者にも不公平をもたらします。
今日お伝えしたいのは、司法の本質的な役割について理解を深めてほしいということです。「感情が入らない」ということは、冷たさではなく、公正さの証です。裁判という場は、感情に流されることなく、公平に事実を見つめる場所でなければなりません。
また次回も、こうした社会の在り方について考えるテーマをお届けしたいと思います。ありがとうございました!
【ろりラジ切り抜き動画】 #2896 冤罪生み出し判定テスト pic.twitter.com/2Whl6xQNfB
— しんたろーたりー📻voicy┃10万時間しゃべるボク (@ryuka121212) December 25, 2024