
100日後に年越すオレ 71日目「ね:寝ずの番」
”いろは順”エッセイの二十日目、本日は”ね”です。
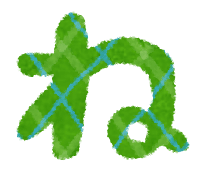
"ね”で選んだ題材は、「寝ずの番」。僕の敬愛する中島らもの短編小説であり、また映画化されている作品でもあります。まずはそのあらすじから書いていきたいと思います。
そもそも「寝ずの番」は、通夜などで故人を寂しがらせないために遺体の傍に居て、弔問客と思い出話に花を咲かせたりしながら飲みつつ夜を明かすことを言います。僕も昨年ちょうど祖母の兄、つまり大叔父が亡くなった時にちょうど沖縄に帰っていて、途中までではありますが親戚の人達と「寝ずの番」を経験したばかりです。人生においてそこまで多くはないですよね、その機会は。
さて中島らも作品の「寝ずの番」に話を移すと、六代目笑福亭松鶴がモデルである落語家の橋鶴師匠が無くなり、その後一番弟子やおかみさんが次々と亡くなり、その度にその通夜の寝ずの番を弟子たちが行うというのがざっくりとしたあらすじですが、その中で師匠の死体を担いで「死人のかんかん踊り」をする、というくだりがあるんですね。これは何かというと、落語の大ネタである「らくだ」の噺のオマージュなわけです。モデルとなった笑福亭松鶴師匠は、この「らくだ」の当代一の名手として名を馳せていて、あの立川談志師匠がそれを生で聞いて舌を巻き、松鶴師匠の追悼文でそのことを触れていた、というのは有名なエピソードです。
松鶴師匠の弟子には著名な人たちも多く、仁鶴師匠や鶴光師匠、そして本題になる鶴瓶師匠が居ます。それくらい多彩な弟子たちを見るに、松鶴師匠の懐の大きさが分かるのではないでしょうか。(まあ鶴瓶師匠の落語「癇癪」ではかなり短気なのかも、とも思ってしまいますが💦)
さてここからが本題です。今日、笑福亭鶴瓶師匠の落語会2020、東京初日を見てきたんですね。鶴瓶師匠の落語会は実はここ三四年ほど毎年見に行くことが出来ていて、いつもの赤坂actシアターで今回も見ることが出来たんですが、コロナ禍のなかでこうして見ることが出来て安心してたんですね。何せ先週の札幌会場も中止になっていたので。
記念すべき東京初日、今日の演目は、「癇癪」と「らくだ」でした。それもあってこの稿に「寝ずの番」を選んだわけですけどね。
まずは毎回恒例、「TSURUBE BANASHI(鶴瓶噺)」からスタート。要は鶴瓶師匠の漫談のようなもの。今年はこれまで以上に長くて、恐らく40~50分くらい喋りっぱなしだった気がします。残念ながら会場はキャパの半分しか入れていないこともあり、やはり満員大入りの時と比べるとどうしても一体感というか笑い声の厚みが寂しかったのは事実。特に今回二階席から見ていたので猶更感じてしまった気がします。もちろん内容は変わらず面白かったんですけどね。
一席目の「癇癪」は、古典の作品を鶴瓶師匠が私落語(新作落語)として、主人公を松鶴師匠に変更して作った噺。松鶴師匠がこういう人だったんだ、と聞き手にも伝わる一席です。実は今回の落語会のパンフレットでは神田伯山師匠が文章を寄せていたのですが、その名文の〆が松鶴師匠と鶴瓶師匠を重ね合わせて見えた、というもの。図らずも今回の演目とリンクしていて嬉しかったのだ、と鶴瓶師匠は語っていました。
お仲入りを挟んだ後は、二席目。それこそ松鶴師匠流を語り継ぐのだという意気込みの「らくだ」でした。しかも今日のサゲは鶴瓶師匠オリジナルの物。これには会場で一度拍手をしてしまった全員が驚きました。まだ続く?あ、こう来たか、と。
「らくだ」という話は前半はくすぐりが多くて笑っていられるのですが、後半に入ってくると結構笑いが減っていくんですよね。でもそういうところもしっかりと笑わせる仕掛けがなされていて、最後までダレずに楽しむことが出来た気がします。
なお鶴瓶師匠の「らくだ」に賭ける思いは、2004年のインタビューで既に感じることが出来ますね。
そんな鶴瓶さんの「らくだ」。ご本人いわく「笑福亭の”らくだ”として洗練させていきたい」という決意表明をされていたので、今後も長らく鶴瓶師匠の十八番として口演されるんじゃないかと思います。楽しみですね~。


