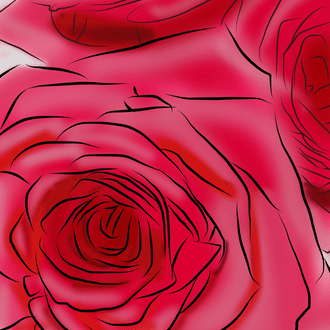マイズナー・メソッドの基礎
声優や演技の勉強を始めたばっかりの時って、どう台本から役を作っていくのか難しく感じませんか?
そんな中、演技を勉強している人なら耳にしたことはあるだろうマイズナー・メソッドについてまとめてみました!
自分の学習noteです!ではさっそく…
そもそもメソッド演技って?
「メソッド演技」と呼ばれている演技方法については、
「物語の中で、役として本当に気持ちを動かす」という、
スタニスラフスキーシステムを基にした、俳優の役としての気持ちの動かし方と、
その方法が1940年代のアメリカで盛んに研究され、
<リー・ストラスバーグ>
<ステラ・アドラー>
<サンフォード・マイズナー>
という方たちが、それぞれ確立した、方法や方式の流れを受け継ぐ演技法が「メソッド演技」と呼ばれています。
メソッド演技とは|たちばなしんたろうのブログ
スタニスラフスキーシステムとは?
コンスタンチン・セルゲーヴィチ・スタニスラフスキーが創り上げた
俳優の教育法である。
<コンスタンチン・セルゲーヴィチ・スタニスラフスキー>
1863年1月17日 - 1938年8月7日
ロシア革命の前後を通して活動したロシア・ソ連の俳優で演出家。
ロシア演劇の代表的人物の一人。
スタニスラフスキーシステムの概要
「自分の脳内で脚本に基づく仮想世界を構築することで、身体表現や感情のリアルを引き出していく」ことを目指したものである。
人間の脳は本当に体験しなくても、ドキドキしたり、すっぱさを感じたりすることができます。
これを利用して、俳優が演出家や共演者とともに創り出した台本通りの脳内映像を、スタート!の合図に合わせて再生することができれば、俳優が気持ちを「造る」のではなく、演じる「役」として自然に感情がわきおこり、その「役」があたかもその場に生きているようなリアルな演技が生み出せるのです。
スタニスラフスキーシステムとは|たちばなしんたろうのブログ
日本での勉強方法は?
マスターをして、実際に使えるようになるには現状では
・ワークショップ
・本
の2通りではないだろうか。
ワークショップは先生を選ばないとお金の無駄になってしまう可能性があるので、今後もう少し調査していきたいです。
本はいくつかおすすめを見つけたので、読んだらnoteにまとめて行けたらと思います。
●俳優修業 第1部 第2部|スタニスラフスキイ 翻訳されたものだから日本語で理解しにくいかもしれないが、内容はすごいらしいので、勉強するなら是非読んでみたい
完訳版もあるが、長くて難しそうなので、短そうな1950年代ん方にチャレンジしてみようかな
●スタニスラフスキーへの道―システムの読み方と用語99の謎 |レオニード アニシモフ 結構精神的な話のものが多いので、本当の相性が問われるものが多そうな予感をレビューから感じます。
スタニスラフスキーシステムのまとめ
演技をよりリアルにするために、心理学(フロイト心理学)の要素を取り入れ、役作りをしていくための学習カリキュラムであるのではないだろうか。
フロイト心理学って?
「意識は氷山の一角」フロイトの無意識論
フロイトは、人間の行動にはすべて心理的な裏付けがあり、それは「無意識」だとしました。
心理学の三大巨匠!フロイト・ユング・アドラーの学説を知る
1:リー・ストラスバーグ
スタニスラフスキー・システムはその後アメリカに持ち込まれ、リー・ストラスバーグがこれを基にメソッド演技法を確立させました。
<リー・ストラスバーグ>
1901年11月17日- 1982年2月17日
オーストリア=ハンガリー帝国(現在のウクライナ)出身のアメリカの俳優、演出家、演技指導者。
メソッド演技法を確立。
1966年には、ロサンゼルスにアクターズ・スタジオ・ウェストを設立した。1969年にはニューヨークとロサンゼルスにリー・ストラスバーグ劇場研究所 (The Lee Strasberg Theatre and Film Institute) を設立した。
リー・ストラスバーグの関連本
●メソードへの道 |リー・ストラスバーグ
2:ステラ・アドラー
彼女はスタニスラフスキーに演技法を指導された唯一のアメリカ人だった。
<ステラ・アドラー>
1901年2月10日 - 1992年12月21日
彼女はグループ・シアター(英語版)の重要なメンバーだったが、スタニスラフスキー・システムの指導法を巡るリー・ストラスバーグと意見の相違は、グループ・シアター解散の一因になった。
アドラーとストラスバーグとの根本的な違いは、俳優の感情の引き出し方にあった。
ストラスバーグは常に、「感情の記憶」、すなわち五感を使って俳優個人の過去の記憶を引き出す方法の、強力な提唱者であった。
一方アドラーは、俳優が文章から学び、想像した状況を信じることが出来れば、脚本にある感情が自然に表面化すると考えた。
ステラ・アドラーの関連本
●魂の演技レッスン22 〜輝く俳優になりなさい! |ステラ・アドラー
3:サンフォード・マイズナー
<サンフォード・マイズナー>
1905年8月31日-1997年2月2日
<リー・ストラスバーグ> 、<ステラ・アドラー> らとともにグループシアターの創設者の一人
数々の優れた舞台や映画に出演するが、1964年からは教師に専念した。
サンフォード・マイズナーの関連本
●サンフォード・マイズナー・オン・アクティング |S・マイズナー、D・ロングウェル
人物歴史まとめ
上記の本の感想をまとめている人がいたので参考までに↓
マイズナー・メソッドはスタニスラフスキーシステムの流れを汲んだグループシアターでの演技指導の一つである。
3人の代表的な指導者がおり、その中でそれぞれの解釈で指導している。
それぞれの主張があり、正解はないので自分に合う人の意見を少しづつ取り入れて行ったほうがいいのかもしれませんね。
劇薬に近いものかもしれないので用法・容量にはご注意ください!(盲信しすぎて、監督と喧嘩しすぎないように)
マイズナー・メソッドはサンフォード・マイズナーによる指導の流れを汲んでいる。
マイズナー・テクニックとは?
*第一段階:繰り返し・レペテション(リピートエクササイズ)
日常で出来るのに、芝居になったとたん出来なくなる「相手の言ったことをきちんと聞いて、相手に伝える」と言うことを学びます。
*第二段階:打ち込める作業・アクティビティ(ひとつの行動を達成する)
一人が何か作業をします。 もう一人は外からドアをノックして入ってくる。その後は一段階と同じ。ただし、一人は作業をしながらやります。こうすることで相手と作業の両方に集中しますから、その“空間全体に集中する感覚”が養われます。
*第三段階:理由と目的・感情準備
第二段階に加えて、作業をする人も、ドアから入ってくる人も“個人的に重要な理由と目的”を持って行う。
*第四段階:関係性と共通の出来事・LAC /Life altering circumstances (日常生活の転換事件)
第三段階に加えて、互いの関係性と共通の出来事を組んだ相手と打ち合わせをします。ある意味即興に近いのですが、2のアクティビティの人と転換事件をたった今味わった人との間で行われるレペテション。
*第五段階:キャラクタリゼーション
第四段階に加えて、その人物に必要な特徴を持って練習する。“普段の自分に無い癖”を取り入れるということです。
*発展:シーンスタディー・シーンに向けての稽古
台本の中のト書きは無視し、台詞の中から“詳細な状況設定をリサーチし府に落とす”。
台詞を読む場合は原則黙読です。声に出すとしても棒読み。表現や抑揚を考えずやる。
相手との読み合わせも棒読み。ただし、相手を見ながら言う(聞く)。
練習後半になって状況設定もほぼ把握できたなら、台本と無関係なことをやりながら練習する。
まとめ
HOWTOではなく、感覚を掴めるまでやる練習な気がします。
頭でこのテクニックはこう使うというより、天才的な俳優が持っている感覚を学習できることを目指している気がします。
Q&A(先生に聞ける機会があれば個人的に知りたいこと)
・マイズナー・メソッドはどう学ぶのか?
・普段一人の時どんな練習をすればいいのか?
・一人でできる練習はあるのか?それとも人と練習をするのが主流なのか?
・おすすめの本はあるのか?
・ワークショップを受けるときののポイントは?いい教師の見分け方
・声優になりたい人にマイズナー・メソッドはあっているのか?
気になる疑問や質問がありましたら、コメント欄に書いていただけると聞ける機会が来たときに一緒に質問してきます!
いいなと思ったら応援しよう!