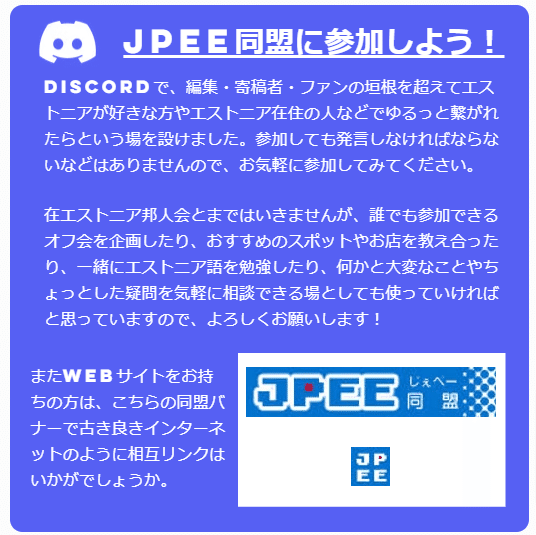JPEEエストニア・アンソロジーについて
エストニアに住んでいる誇り高き同人オタクとして年の瀬に『JPEEエストニア・アンソロジー』というのを毎年出しています。この2024年度版でVol5、5年目となりました。
一方言っだしっぺである私がこの冬で「脱トニア」したので、一旦今回のVol5を以てこのアンソロ同人誌スタイルでの発行は区切りをつけることになりました。発起人として一応毎回冒頭「はじめに」を書いているのですが、今回ラストだしせっかくだから2ページくらい長々と書いちゃおっかな!と思って書き溜めていたのが、Vol5(サンプル)はただでさえ私のインタビュー記事まで載っているので全体通して自分語りが過ぎてちょっとイタイかな…と思い、通常通り1ページ分量に抑えました。
もはや自己紹介これでよくね?と思ってインタビュー記事だけ公開させてもらった。
とはいえ書いたものももったいないので、我らのJPEEエストニア・アンソロジーを振り返る記事をここに書いておこうと思います。
はじめに
JPEEエストニア・アンソロジーとは
「エストニアに関する同人アンソロジー。普段なかなか知ることのできないエストニアの(ニッチな)魅力をたっぷりお届けします。」
を売り文句に、JPEE編集部とエストニアに縁のある日本人または日本語話者による「テーマ:エストニア」(のみ)の自由な同人アンソロジーです。読み物やイラスト、マンガなど好きなフォーマットで各人が語っています。
BOOTHで頒布中のPDF版やKindle版はフルカラー、冊子版は表紙カラー本文モノクロでお届け中です。公式ショップでVol1のPDFが無料で読めます。
JPEE編集部とは
エストニアの首都タリンにて同人活動を行う(おそらく)唯一無二のサークルです。エストニアと日本文化を繋ごう!という高尚な目標のもと今日も元気におうちに引きこもっています。
JPEEアンソロの軌跡
同人オタクの恩返し
JPEEエストニア・アンソロジーはコロナ禍の2020年の年末に始まりました。ロックダウンのため年内に予定していたイベントが軒並みキャンセルになったため(私が)同人オタク熱と暇を比較的持て余していたこと、ネットで(イベント中止のため)日本の同人印刷所さんが危機に陥っているというニュースを見たこと、一方でオンラインでの様々な活動が盛り上がっていたこと。遠い異国ながら、今までお世話になってきたしこれからもなるつもりだった同人誌文化の危機に、微力なりに何かできないかなと考えた末に発足したのがエストニア・アンソロジーでした。
実は最初は本当にそれだけで、そんな大層なものにするつもりはありませんでした。兎にも角にも何かしら印刷物をつくろう!が先だったので、原稿さえそろえばよい。ただあまりペラペラでもあれなので、私がメインで何かを描いて、せっかくなので友人知人にちょっとだけネタをもらったり描いてもらえるとうれしいなと思っていました。
マイナー勢の嘆き
というのもまでタリン在住の日本人たちと話した中で、次のような声を聞いていたからです。曰く、ネットで転がっているエストニアの情報は(当時は特に)E-residencyとかスタートアップのキラキラ系ビジネス記事か、オンライン投票のやや政治寄りの記事、後は北欧のおしゃれなんちゃらみたいな情報ばかり。もっと制度や気候や、日常の様子とか、エストニアで生活できるかな、の判断に必要そうな情報がほとんど落ちていない、と。ならばと来たばかりのころは皆ブログを始めてみるけれど、そのうち飽きて更新しなくなってしまう。けれどもこうやって集まれば、あれやこれやと小さいネタはあるものだー。
私自身はあまりエストニアの情報を事前にネットで調べたことはなくあまりピンと来なかったのですが、まぁそういうなら皆にブログ1記事分くらいはなにかひねり出してもらおうかなと。それでブログや文章を書いていると知っている友人知人にまずは声をかけ始めました。
同人誌って何?
概ね感触はよかったのですが、そこで思わぬ壁にぶち当たりました。
「アンソロ同人誌だそうと思うからなんかエストニアネタで寄稿して!」
と突然声をかけたところで、一般人は「は?」となります。それはそう。
勝手に自由帳に漫画を描いたり勝手に漫画賞に応募したり勝手にネットで趣味のサイト作ったり勝手にオフ会してあれよあれよという間に同人誌をつくっていた私には全く盲点だったのですが、普通の人間はそんなほいほい同人誌作ったりしない。そもそも同人誌って何?狂った人間が仕事や人生の大事な時間を削って作り出す狂気の産物。うーん説明したくない。
そこで私は決意しました。エストニア・アンソロジーにもう一つのミッションを付け加えました。
同人人口を増やそう。ジャパンが誇る(?)同人誌文化とはなんたるかを、ここ北ヨーロッパから広めていこうと。

同人沼へようこそ
そもそもこちら(欧州)にはおそらく同人誌文化がないんだなというのはそれまでのイベント参加を通じてなんとなくわかっていました。
ファンアートということでイラストやグッズがメイン。すべてがグレーゾーンだという大前提ですが、日本だとグッズ系は同人結構厳しい目が向けられると思います。ところが逆にこっちでは本の形態で出すほうがちょっと大丈夫?ってなるらしいです。(あくまでらしい。正面から聞いたのはドイツ人アーティストだけだったのでドイツ特有の事情も何かあるかもしれません)
もちろんイラストやグッズも悪くはないけど、同人誌のよさってやっぱり「狂気」だと思うんですよね。ストーリーや起承転結がある分こいつなんでこんなものを作ってしまったん…????みたいな手の込んだ手遅れ感がよりわかるのがよいというか。
とまぁそういう「こちら」の事情はわかっていたつもりでしたが、別に国とか地域とかじゃなくてそもそも日本人も皆が皆同人誌作っているわけではないことをすっかり失念していました。TLを見ていると常に誰かが原稿している気がするんですが、別に世間一般としてそんなことは全くない。
そして私はまず「同人誌」なるものの布教をも始めました。
「こうやって紙に残すだけでもいいものですよ」「印刷したら1冊差し上げますね」「気軽に!ほんとに気軽な気持ちで大丈夫です!」
結果、同人誌って初めてだけどやってみたいです!といってくれる参加者が出始めました。
エアコミケ
同人誌の醍醐味の中には「原稿ハイ」と「脱稿めっちゃハイ」と「現物の匂いを嗅いだり紙のツルツルを味わうハイ」と「よくわからんけど売れてしまったハイ」と「感想をもらえてしまってビタビタするハイ」といくつものHighがあると私は思います(ハイがあれば谷間もあるわけですが)。
一般郵便物も規制かかっていた当時、現物は日本で印刷して実家からタリンまで送ってもらうとしても1~数ヶ月かかる想定だったので、取り急ぎ「よくわからんけど売れてしまったハイ」くらいは同人誌初チャレンジである参加者たちにも味わってほしいな…ということで急遽新刊発行をエアコミケに狙いを定めました。
エアコミケは冬コミが中止になったことを受け、ならばせめてオンラインで開催しようという取り組みです。
もともとのコミケにサークル参加しない参加者でもエアコミ参加サークルとして参加できたため、究極の目的は印刷版の発行とはいえど、とりあえず電子版だけでもここに間に合わせられればより多くの人の目に留まるチャンスがあります。この広いインターネッツ世界の中にはうっかり「お、ちょうどエストニアについてめっちゃ気になってたんだよ!」みたいな変な、いえ稀有な人材と出会えるかもしれないので。
そういうわけで「締切は1ヶ月(未満)後です」とかいう無茶ぶりでなんとかできあがったのが『JPEEエストニア・アンソロジーvol1』です。ちゃんとエアコミにも間に合わせました。
それどころか心配していたような原稿の遅れは一切なく、年末差し迫る忙しい時期にもかかわらず皆きちんと原稿を送ってきてくれました。SNS上で度々アンソロのトラブルを観測していた私はこれにはかなり驚きました。
もしかしたら極道入稿を繰り返す同人オタクのほうが異常なだけで、一般的な社会人学生諸氏は「締切」を設定したら守るものなのかもしれません。
JPEEプロジェクトの今後
5巻目を迎えて
前述したようにそもそもは日本の同人印刷屋さんになにかオーダーをしよう!というのが原初の目的だったのでシリーズ化などは特に考えてなかったのですが、編集作業をまるっと投げていた(だってインデザが使えるっていうから)編集担当のしんぷぅ氏がさらっと表紙にVol1っていれてたり、「じゃ来年のテーマは」とかいう言葉が参加者から出たりして、気づけばなんやかんやと5年も続いてしまいました。

毎年年末に「やべぇそろそろ『あの時期』じゃねぇか」と思いついたように募集をかけ、編集部権限で我々に締切は適応されないという合言葉を胸に活動してきました。
毎回いつもの手順を忘れKindleやBOOTHの登録に戸惑い、かと思えば同じく5年の付き合いであるタリンの印刷所さんがいよいよ現物ができてからInvoiceを発行しだすなどそれなりの軌跡や思い出がたくさんあります。
エストニアで読める日本語の発行物はそれだけで珍しいと手に取ってくれる日本語勉強中のエストニア人たち、俺のいとこが今エストニアに住んでいるんだよと興味を持ってくれたドイツニキ、せっかくなら現地の人とお話をと連絡をくれた大学の先生、ネットで感想をくれる匿名ネキ、それから全然興味も関係もないだろうに手に取ってくれるフォロワーのみんなさん達…アリガト
JPEE編集部の活動として、年末の新刊発行のみならず、英語版の作成を試みたりオンラインオフライン問わずイベントに参加してみたりもしました。
そこで声をかけてもらったことも複数回、普段あまり他者と交流のない編集部員にとっては貴重な外部との関わりを提供してくれました。
上のAnimatsuri参加記録でも描いたのですが、やっぱり継続というのはそれだけでそれなりの力にはなるんだなぁとしみじみ思った次第です。
同人文化を広めよう
いつかかっこいい名前を考えようと言っていたものの自分たちの中でも『JPEE』の名称がすっかり馴染んでしまい、結局そのまま行動制限が解除され各国でリアルイベントが復活し、海外旅行(遠征)にも行けるようになりました。

JPEEエストニア・アンソロジーは最初のうちはオンライン版を中心に、それから日本の印刷所で印刷し、オンラインプラットフォーム、オンライン即売会などを通じて頒布しました。またリアルイベントの復活やヨーロッパでのイベント活動などを通じ、現在JPEE冊子はエストニアの印刷所で(時々日本の頒布ように日本でも)印刷されています。タリンでの日本文化イベントを中心に英語版も少部数ながら頒布しています。
アンソロの他にも、エストニア語や日本語を学ぶ小冊子、マンガの描き方やレポマンガを作成したり、タリンでお絵かき会をやったり高校生にマンガ教えにいったり、海外イベントに出張したりして、「同人文化(というか広くアニメっぽいお絵かきや日本のマンガの描き方)を広める」という第二の目標にも、微力ながら貢献できたのではないかと思っています。いつかエストニアから漫画家がデビューするかもしれない。
何よりJPEEエストニア・アンソロジーの活動を通じて想像よりも多くの、それも様々な人々と関わることができたのは思いも寄らない収穫でした。間違いなく私のエストニア生活の中で一つ大きな割合をしめていた活動でした。今後はともすれば孤独に陥りがちな海外生活の中でライフハックとしても効能を主張していきたい次第です。

また同じようなことを始めるかもしれないし、ノコノコ戻って来る可能性もないではないし、エストニア在住日本人会が突然爆盛り上がりするかもしれないし。Vol1(2020)~Vol5(2024)まで、楽しんでもらえると嬉しいです。
宣伝
最新刊
リアルな声がたくさんつまったエストニア・アンソロジーVol5は12月31日中(エストニア時間)公開予定です!!!後でリンク貼っておくので読んでください。BOOTHとKindle版が出ました。それまでは過去の無料公開を御覧ください。
2月のコミティア
製本版Vol1~5を2月のコミティア(東京)に持っていく予定です!日本のリアルイベント(創作系)は初参加なので今から楽しみです。
Discord
JPEEのゆるゆるDiscordサーバーです。画像下のリンクからどうそ。