
(26)できるだけ少ない知識で解きたい人用「後置表記法(逆ポーランド表記法)では,例えば,式 Y=(A-B)×C を YAB-C×= と表現する。次の式を後置表記法で表現したものはどれか」
#基本情報技術者試験 #平成24年 #春期 #問4 #逆ポーランド表記法 #後置表記法
後置表記法(逆ポーランド表記法)では,例えば,式 Y=(A-B)×C を YAB-C×= と表現する。
次の式を後置表記法で表現したものはどれか。
Y=(A+B)×(C-(D÷E))
ア YAB+C-DE÷×=
イ YAB+CDE÷-×=
ウ YAB+EDC÷-×=
エ YBA+CD-E÷×=
後置表記法(こうちひょうきほう)、またの名を逆ポーランド表記法のルールは知っておかなきゃいけない。
名前が長いので、以降逆ポと書くよ。
たとえば、普通はA+Bって書くんだけど、逆ポだとAB+と書くのがルール。
他の例だと、
普通:A+B-C → 逆ポ:ABC-+
普通:A+B×C÷D → 逆ポ:ABCD÷×+
普通:(A+B)×C÷D → 逆ポ:AB+CD÷×
というように書く。
逆ポの考え方は、計算に必要な2つの値を先に並べておいて、後からどんな計算をするのか(+とか×とか)の記号を置く、という感じ。
だから、例に出したAB+CD÷×の場合は、
まず、AとBの値を取り出して、+が登場したから足し算をする。
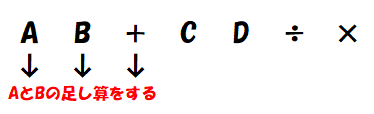
つぎに、CとDの値を取り出して、÷が登場したから割り算をする。

さいごに、足し算の答えと、割り算の答えで、掛け算をする。

というやり方です。
逆ポの前置きが長かったけど、これをふまえて解いてみます。
問題は、普通の式Y=(A+B)×(C-(D÷E))と同じ計算がされるのは、次の逆ポの式のどれでしょう?というもの。
アのYAB+C-DE÷×=から調べてみます。
まず、両端のYと=は気にしないようにする。(普通の式のY=の部分だから)
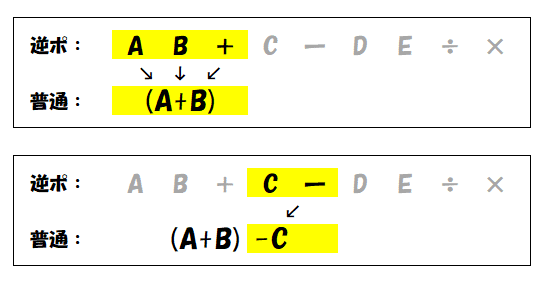
まだ途中だけど、(A+B)-Cってなった時点で、問題文の式とちがう。だから、アはもう消えた。
次はイ。AB+までは同じなので、その続きから見ていく。
イは、YAB+CDE÷-×=という逆ポ式。
両端のYと=を無視して、AB+CDE÷-×にしたところから解読スタート。
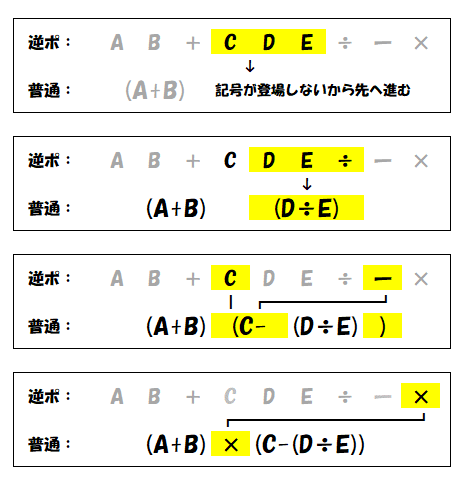
問題分の式と同じになってしまった!
普通式に読み替えるのが大変だったから、イで見つかってよかったよかった。
CDEと値が続いてしまって、記号が出てこなかったところが少しむずかしい。記号が登場しないときは、ひとつ進むところがわかりにくいね・・・
