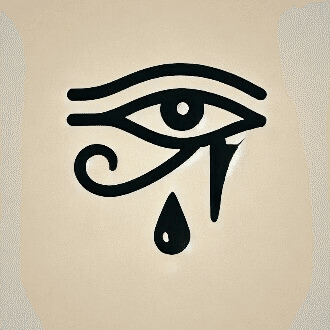🪐ロゼッタ軌道
天文学では、ロゼッタ軌道は、各軌道周期の間にペリアストロンシフトがある場合に発生する。逆行性のニュートン・シフトは、中心質量が点状の重力源ではなく、伸長している場合に起こることがあり、その結果、非閉鎖軌道になる。相対論的な順行性シフトは、大質量の重力源からの相対論的効果によって起こる。コンパクトなレンズ状の棒(箱状の棒とは対照的)を持つ棒渦巻銀河では、棒の形態は、棒と一緒に回転するロゼット状の軌道をたどる星によって支えられている[2]。
中間の速度でブラックホールに接近する天体は、複雑な軌道パターンを描き、ホールまでの距離が近くて遠い、ハイポトロコイドとして知られる振動パターンを描く。2020年、欧州南天天文台の超大型望遠鏡による観測で、いて座A*の周りを恒星S2がこのパターンで周回していることが初めて明らかになった[3][4]。
量子力学では、ロゼッタ軌道は球対称(1/rを除く)ポテンシャルの解である。
天文学におけるロゼッタ軌道: ロゼッタ軌道は、天体の軌道がペリアストロン(軌道上で中心天体に最も近づく点)で毎回シフトする現象です。これは、中心質量が点状の重力源ではなく伸長している場合に起こる可能性がある逆行性の「ニュートン・シフト」によるものです。このような伸長は、天体が非閉鎖軌道、つまり完全な楕円や円ではなく、その形状が周期的に変化することを意味します。相対論的な影響による順行性シフトもあり、これは重力の強い大質量天体近くで起こります。
棒渦巻銀河におけるロゼッタ軌道: 棒渦巻銀河では、中心部にある棒状の構造が星のロゼット状の軌道によって支えられています。これらの星は、棒の形態に沿って一緒に回転しながら、複雑なループやスパイラルパターンを描きます。
ブラックホール周りのロゼッタ軌道: 中間の速度でブラックホールに接近する天体は、非常に複雑な軌道パターンを描きます。このような軌道は、ハイポトロコイドとして知られ、距離が近くなったり遠ざかったりする振動パターンを示します。2020年には、欧州南天天文台の超大型望遠鏡を使って、いて座A*の周りを恒星S2がこのパターンで周回していることが明らかにされました。
量子力学におけるロゼッタ軌道: 量子力学では、ロゼッタ軌道は球対称(1/rを除く)ポテンシャルの解です。これは、原子内の電子が核の周りを周回する際に見られる現象で、電子の軌道が単純な円や楕円形ではなく、より複雑な軌道パターンを描くことを示しています。

いいなと思ったら応援しよう!