
石積み部の活動を振り返る(2022年3月~2023年12月)
前書き
これは筑波大学吹奏楽団の団員による,吹団あどべんとかれんだー2023 の23日目の記事です。遅刻ぎりぎり……。
私は筑波大学吹奏楽団で3年間クラリネットを担当し,先日12月10日に行われた第90回記念定期演奏会をもって引退しました(ご来場いただいた皆さま,本当にありがとうございました)。ゆえに,今回のアドカレでは吹団の活動を振り返る記事でも書こうかと思っていたのですが,それではどうしても個人的な話が多くなりますし,団員に対する感謝の気持ちなどはやはり対面で伝えたいと思いましたので,直前でテーマを変更することにしました。
では代わりに何を書くか。できれば吹団の関係者にも,外部の方にもそれなりに楽しんでいただける記事を書きたい……。そう考えた時,私にはぴったりの題材があることに気付きました。

そう,石積みです。
というわけでこの記事では,私の吹団活動のもう1つの側面ともいえる,石積み部の活動についてお話していこうと思います。
創設
そもそも吹奏楽団の活動と「石積み」に何の関係があるのか。まずはそこからお話していきます。
吹団には,練習後に団員が活動場所(筑波大学の文化系サークル会館。略称は文サ館,文サ)の外にたむろして長時間おしゃべりをする,という風習(?)があります。特に2021年~2022年にかけては,COVID-19 の感染拡大のために活動後の集団外食等が厳しく制限されていたため,屋外で充分な距離を取って言葉を交わすということは,団員同士が親交を深めるための最も効果的な手段だったのです。
そんなわけで,文サ館の入り口前には日々団員たちが集っていたのですが,そこには古びた外観の建物からそのまま切り出したような,コンクリートブロックの破片や石ころがたくさん転がっていました。当初の我々は,一般的な大学生がそうであるように,それらの石には殆ど関心を持っていませんでしたが,流石に何もない場所で何時間も話していると手持ち無沙汰になってくるため,おしゃべりの最中に石を足で弄んだり,サッカーのまねごとをしたりすることが徐々に増えていきました。そうすると不思議なもので,我々はいつの間にか,特段意識をしない迄も,なんとなく石の存在を気にかけるようになっていたのです(他の団員がどうなのかは知りませんが,少なくとも私はそうでした)。
そして2022年の3月1日。
その日は珍しいことに,活動が終了すると殆どの団員がさっさと帰宅してしまい,文サ館の下に残っているのは私と友人の2人だけでした。
くしゃみをすれば内容を忘れてしまうような薄っぺらい雑談の途中,私が足で弄んでいた石に注目し,「それを積んだら面白いのではないか」と提案したのが私と友人のどちらだったのかは,どうしても思い出せません。1つ確かなのは,「日頃なんとなく気にかけている存在」にとどまっていた石を積極的に活用するという発想は,この日我々が会話を交わす中で初めて誕生したものだった,ということです。
そして私は,その発想に基づいて実際に石を積み,気まぐれでその画像をTwitter で発信しました。
#文サ下石積み部 pic.twitter.com/AoWjlLbS1O
— 道の上 (@road_klis21) March 1, 2022
#文サ下石積み部 というハッシュタグは,特に意図のない単なるジョークだったのですが,このツイートに対する反応が予想以上に多かったことや,私が当時趣味を求めていたこと,何よりこの日に行った石積みが想像以上に楽しかったことから,私は今後も「石積み部」を名乗って石を積み続けることを決意します。
ここに,文サ下石積み部が誕生しました。
黎明期
最初の頃は「石積み部」を名乗りつつも,コンクリートブロックやその破片を積むことが多かったように記憶しています。


とはいえ,毎回同じような素材ばかり積んでいると,どうしても飽きが出てきます。そのため私は,文サ館の周辺を歩き回って石を収集するようになりました。十分な数の石があれば,それらを組み合わせることで様々な作品を作ることが可能になり,毎回新たな楽しさを味わうことができるようになります。
これ以来,学内で見つけた「良い感じ」の石を文サ下に集めることは,すっかり私の習慣になりました。現在文サ館の外には大量の石が転がっていますが,それらは殆どが私が個人的に収集したものです。

石積み部の活動は吹奏楽団の活動が終わった夜中から始まるため,日付が変わる前に帰宅したいと思えば取れる時間はせいぜい2時間です。しかし,4~6月頃の私は難易度の高い作品を積み上げることにこだわっていたため、2時間を目いっぱい使ったり,数日を費やしたりして1つの作品を積み上げるということが頻繁にありました。今思い返すと「暇かよ」以外の感想が出てきませんね。

このくらい,今だったら15分もあれば積めるなぁ……。
とはいえ,1つの作品に多くの時間をかけていたのは初期の頃の話です。石積みに慣れてくると,そこまで時間を費やさずともそれなりに見栄えがする作品を作れるようになりました。7月~9月頃は,新たに仲間に加わった色とりどりの石たち(もちろん比喩です。石の色はだいたい白か灰色か茶色です)を1時間程度で積み上げることが多かったです。


「物立て」への浮気
3年目の浮気ならぬ半年目の浮気といったところでしょうか。9月末,私は初めて石以外の物を立て,その楽しさを知ります。

様々な物を通常ではありえない角度で立てるという営みは,(意外に思われるかもしれませんが)石積みよりも簡単であり,そのくせ見た目のインパクトは抜群です。これ以来,私は石以外の物(特にパイプ椅子)も積極的に作品に用いるようになります。
研鑽と試行錯誤
ここまで結構細かく石積み部の沿革を見てきましたが,これ以降は何か新しいことをやるというよりも,「より多く,より多様な形の石を,より独創的に,より速く積む」ことを目標に,ひたすら石積みのカンを磨き,新たな積み方を探ることになります。修行の時期ですね。


石以外の物もどんどん立てちゃいます。
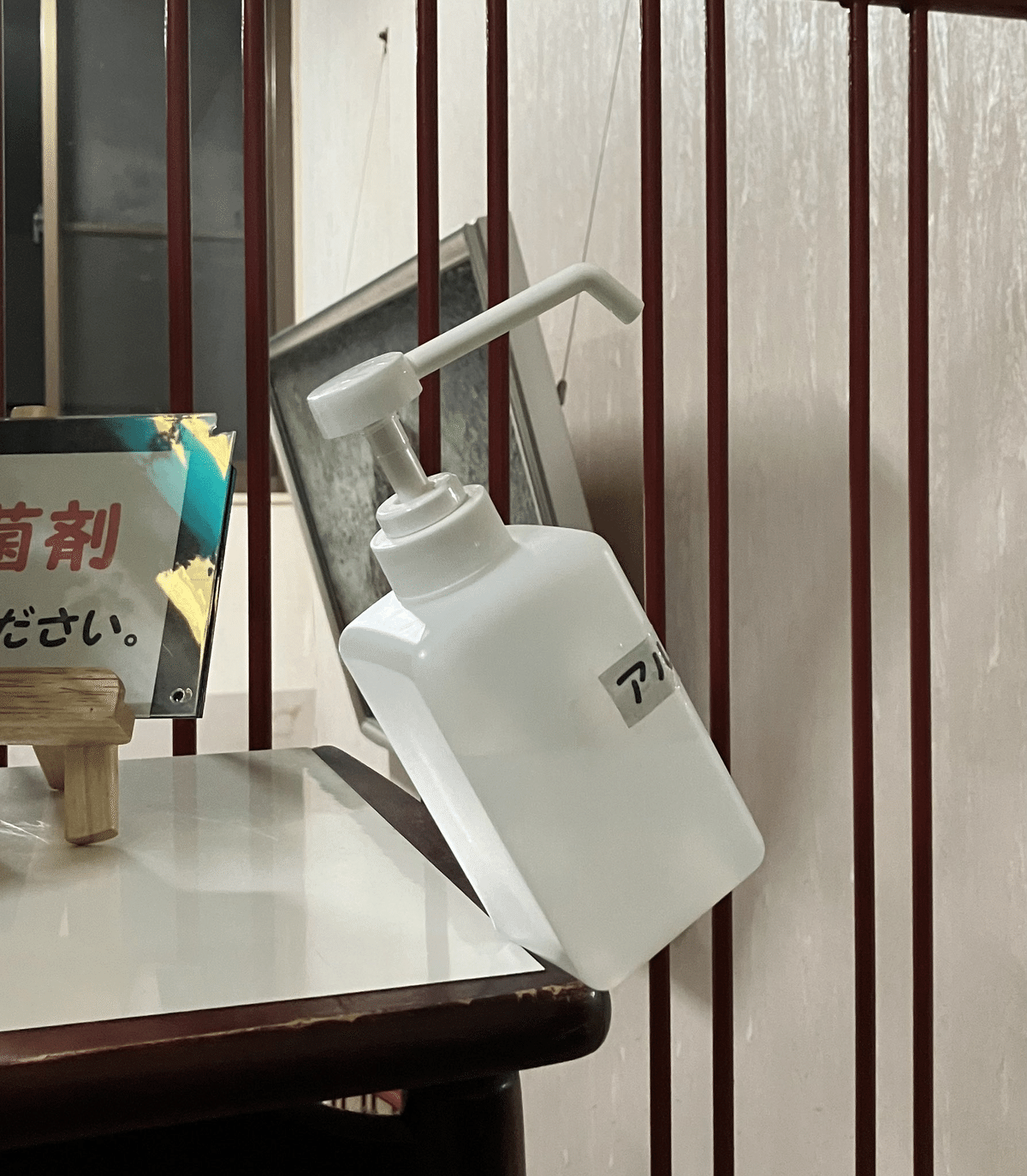

そうこうしていたら,いつの間にか時は2023年の3月1日を超えていました。文サ下石積み部は(あまり石を積んでいない時期もあったにせよ)2年目に突入することになります。
2年目の石積み部
活動2年目となっても石積み部の活動に特に変わりはなく,相変わらず唯一の実動部員である私は,ほんの少しだけ慣れた手つきで色々な石を積んできました。もちろん今も積んでいます。
ただ,強いて2年目の新たな方向性を挙げるとするならば,(1) 石積みと物立ての融合,(2) 難易度の高い作品への回帰,という2点があると思います。
(1) の方向性は読んで字のごとくです。石の上に物を立てたり,立てた物の上に更に石を乗せたりすることで,自然物と人工物が一体となった作品を作ることを目指しました。


(2) の方向性は,調子に乗って30分程度で積める作品ばかりを公開していた,一時期の自分に対する反省から生じたものです。かつて数日かけて作っていたような作品は,経験を積んだ今なら数十分で完成させられます。しかし,それで満足することなく,今の技術でも完成に数日かかるような作品を追求することこそが,石積み部のあるべき姿なのではないでしょうか……?
このような考えから,特に2023年の春学期の時期には,難易度の高い作品に取り組むことが多かったです。最近はまた簡単な作品に傾いている気がするので,そのうちもっと凄い作品を積み上げてやろうと思います。


その他にも……。

既存のパズルを積んだり……。

石とデカい木の棒を組み合わせたり……。

不安定な足場の上に石を積んでみたり……。などなど,とにかくいろいろな作品を作りました。
「より多く,より多様な形の石を,より独創的に,より速く積む」だけでなく,石以外の物や環境の要因も組み合わせることで,見た人により大きな驚きを与えられるような,そして何より自分がより楽しめるような作品を作ること,それが現在の私の目標です。
吹団の引退と今後の石積み部
さて,前書きでも述べたように,私は既に吹奏楽団を引退しています。
もしも吹奏楽団に所属していなければ石積み部が誕生することはなかったでしょうし,私がここまで長く石積みを続けられたのは,私の作品を凄いと言ってくれたり,時には一緒に石を積んでくれたりした,吹団の仲間たちがいたからこそです。本当にありがたいものですね。
と,少し湿っぽい雰囲気になりましたが,吹団を引退するからといって,石積み部も一緒に引退するということはありません。だってこんなに楽しいこと,やめられるわけないじゃないですか! 吹団は引退の時期が決まっていますが,石積み部にはそのような規則は無いので(なぜなら,部員は私しかいないからです),可能な限りいつまでも活動を続けたいと思います。
今後は文サ下だけでなく,大学内の様々な場所で,そこで見つけた石や物を積んだり立てたりする予定です。道の上の今後の活動にご注目ください。
文サ下の石は特に回収せず,このまま残しておこうと思います。いつの日か私の「意志」が受け継がれ,新たな文サ下石積み部の部員が誕生することを願っています。
