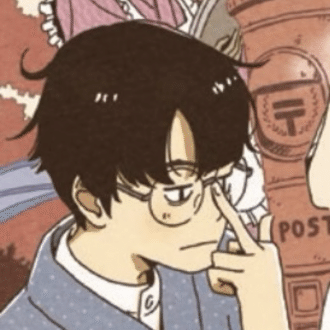note連続小説『むかしむかしの宇宙人』第66話
前回までのあらすじ
時は昭和31年。家事に仕事に大忙しの水谷幸子は、宇宙人を自称する奇妙な青年・バシャリとひょんなことから同居するはめに。幸子は父親の周一と関連のある謎の女性と出会う。
私と主人は板橋で酒屋を営んでおりました。主人は以前大きな酒造店で番頭をしておりまして、そこを独立してから自分で店を出していました。
人あたりもよく働きものだった主人は、近所の方々からも大変好かれておりました。若くしてそこに嫁いだ私は、心の底から主人を頼もしく感じていたものです。
戦争のせいで店の経営は厳しかったのですが、どうにか生活はできましたし、待ち望んでいた子宝にも二人恵まれ、充実した日々を送っていました。
しかし主人はその後満州へと出征し、私は子供二人を抱えて途方に暮れました。空襲がはじまったこともあり、私は主人が大切にしていた店を泣く泣く閉め、実家のある埼玉へ疎開することにしたのです。
疎開先の暮らしは思い出すのも辛いものでした。子供を食べさせるために、毎日畑で鍬をふり続けました。
栄養失調で手と足がむくみ、疲労と空腹のため何度も気を失いかけました。あの当時は子供を飢えさせないことだけしか考えていませんでした。静子さんも同じ気持ちを抱きながらあなたを育てたんだと思います。
そして、終戦を迎えました。
近所ではちらほら男性が復員してきました。毎日神棚に祈り続けたおかげか、幸いにも主人の戦死公報は届いていません。
主人さえいれば、どんな困難な時代でも生きぬける。主人の生還だけを今か今かと待ち望みました。
ところが、現実は残酷でした。その後、主人がシベリアに抑留されたという知らせが届いたのです。
戦争が終わったにもかかわらず、日本に戻れない。そんな馬鹿な話があるんでしょうか……目の前の景色がぼやけ、意識が遠のくようでした。
何日か泣き暮らしたあと、やっと決心しました。主人は、死んだのではありません。いつか無事に帰ってくる。それを励みに心を奮い立たせました。
生活の糧を得るために、私は東京に戻りました。東京の自宅は空襲で焼けてしまったので、近くの母子寮に住み、主人のお得意先だった小料理屋さんに頼んで働かせてもらうことにしました。
早朝から夜中まで働き続けても、給金は雀の涙ほど。酒に酔った客に未亡人だと侮られ、しつこく誘われたことも数えきれません。そんな卑劣なふるまいにも、わらってやり過ごさなければならないのです。
そんなとき唯一のなぐさめとなったのが、シベリアから届いた主人の手紙でした。帳簿と同じあの懐かしい字……
大切に何度も読み返しました。手紙一枚がこれほどありがたいものだとは、それまで考えすらしませんでした。
終戦から二年ほどすると、ソ連からの引き揚げが本格的に行われるようになりました。
主人が帰ってくることを想像し、私はおかしくなるほど喜びました。再び家族が一緒になったときのために、時間が少しでも空けば、店の新しい物件を探しに出かけたものです。
しかし、そんなときでした。あの知らせが届きました。主人が収容所で亡くなったという知らせが……一体、何が起きたのか、詳しいことは何もわかりませんでした。
主人が死ぬわけがない。何かの間違いだ。何度も何度もたしかめました。でも、それはまぎれもない真実でした。
主人との再会だけが生きる支えでした。そのかすかな希望だけにすがりつき、必死に耐えてきたのです。
でも、それが呆気なく消えた……生きる気力がうすれていくのが、自分でもよくわかりました。私は、その場で卒倒しました。
それから、病にかかりました。結核でした。
長年の労苦と、主人の死による精神的な衝撃が原因だったようです。仕事どころか、起き上がることすらままなりません。
小料理屋も辞めました。枕元で子供が泣きわめこうが、何の感情も起こりません。絶望のあまり、もう生きることが嫌になったのです。
子供と一緒に青酸カリを飲み、自殺するしかない。古ぼけた天井を眺めたまま、そんなことを漠然と考えていました。
そんなときでした。水谷さんが我が家を訪問されたのです。シベリアで主人と一緒の収容所にいたと彼は言いました。
水谷さんは仏壇に手を合わせ、祈り終えると、一枚の写真をくれました。それは、私たち家族の写真でした。
主人の遺品でした。その写真には、いたるところに補修した箇所がありました。それを目にした途端、涙がとめどなくこぼれました。
主人がどれほど私たちを想っていたか。どれほど日本に帰りたかったか……その色あせた一枚の写真から、それがひしひしと伝わりました。
写真だけではなく、一緒にあの人に戻って欲しかった。水谷さんがいるにもかかわらず、その無念さで私は嗚咽しました。
しばらく泣いたあと、水谷さんがさし出したハンカチで涙をぬぐいました。突然、泣き出したことを謝罪すると、水谷さんは黙り込みました。
あまりに深刻な面もちに、私は固唾を吞みました。そして、水谷さんはこう切り出しました。
「申し訳ありません。三井を殺したのは私です」、と。
いいなと思ったら応援しよう!