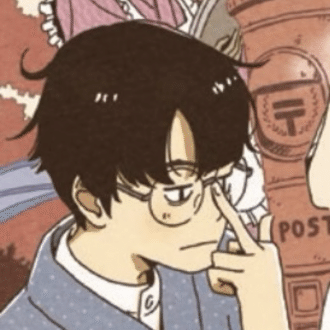note連続小説『むかしむかしの宇宙人』第74話
前回までのあらすじ
時は昭和31年。家事に仕事に大忙しの水谷幸子は、宇宙人を自称する奇妙な青年・バシャリとひょんなことから同居するはめに。銀行をやめた幸子は新たな職を得た。
お母さんの誕生日会の翌日、わたしは杉本学園に赴いた。窓口で入学条件を訊いていると、ばったり美加子さんに出くわした。
用件を伝えると、美加子さんはからからとわらった。
「学校なんて通う必要ないわ。それよりあなた、私の店に来てちょうだい」
「お店ですか?」
「そうよ。花嫁修業で洋裁やりたいなら別だけど、仕事をしながら技術を学ぶのが一番だわ。
まあ、教員の私が言う台詞じゃないけどね」
彼女がおどけるように舌を出したので、ついふき出した。
「実は、ちょうど新しく店を出したばかりで経理ができる人を探していたのよ。
もちろん洋服の仕立ても、デザインも勉強してもらうわ。
お給金はあまり出せないけれど、学校で授業料払うよりはいいでしょ。どうかしら?」
突然の提案に驚きをかくせなかった。でもよく考えれば、これほど魅力的な話はない。ファッション業界で働ける上に、銀行での経験もいかせる。
「やります。やらせてください」
わたしの反応に、彼女は口角をきゅっとあげた。
「じゃあ、早速来週からお店に来てちょうだい。私の連絡先を渡しておくから何かあったら連絡して」
手渡された名刺を目にして、わたしは仰天した。『杉本美加子』と書かれている。
「もしかして、杉本って……」
「ああ、言ってなかったかしら。私は理事長の姪よ」
あっけらかんと答え、美加子さんはにやっとわらった。
こうして思いがけずもわたしは、その翌週から杉本洋装店で働くことになった。
店の場所は、銀座のみゆき通り。まさか憧れの銀座が仕事場になるとは夢にも思わなかった。
洋装の世界は、銀行とは何もかもが違った。中でも最も異なったのが、その店内だった。
色あざやかな洋服が整然とならび、その中でも最も素敵な洋服がショウウィンドーに飾られていた。
洗練されたその洋服に引き寄せられ、女性たちが詰めかける。しかめっ面したおじさんばかりの銀行とは、まさに正反対だ。
やがて、美加子さんがこの業界では指折りのデザイナーだとわかった。
職場の人たちに、美加子さんと知り合ったきっかけを訊かれ、「ワンピースの作り方を教えてもらうために、美加子さんのところに押しかけました」と答えると、
「私たちからすれば、ディオールに押しかけるのと同じことよ。あなた、いい根性してるわね」と、みんなが呆れてわらった。
この店では、二階が作業場だった。そこで何人もの人間がどたばたと働いている。そのすべてが女性だった。
彼女たちはオート三輪のようにやかましく、自己主張も激しかった。ここも、銀行の行員たちとはまるで違う。でもそのにぎやかさが、やがて心地よさへと変わった。
経理の仕事のかたわら空いた時間で洋裁の勉強をした。
仕事が終わると百合子さんの家を訪ね、洋裁を教えてもらった。洋裁をかじりだしてはじめてわかったのが、百合子さんの腕前の素晴らしさだった。
どんな複雑なデザインもちらっと見ただけで、またたく間に縫い上げてしまう。これほどの技術を持った人は、そうそういないだろう。
百合子さんはわたしに教えられることが余程嬉しいのか、「静子さんに教えていたころを思い出すわ」と涙ぐんだ。
彼女のおかげで、わたしの腕前もみるみる上達した。
仕事にもなれてきたころ、デザイン画を描きなさい、と美加子さんに命じられた。
そのデザイン画を見せたところ、主任デザイナーに、なかなか見どころがあるから、デザインの方もやってみたらとすすめられた。
そこで翌日から経理の仕事と並行して、デザインもやることになった。いつの間にか、しがない銀行の行員からデザイナーの卵になっていた。ほんの短期間で、人生が大きく変わっていったのだ。
あるとき忘れ物をしたので店に戻ると、美加子さんが以前と同じく机に足をのせ、雑誌をめくっていた。いい機会なので、思い切って訊いた。
「どうしてわたしを雇ってくれたんですか?」
杉本洋装店は高い技術を持った職人の集団だった。とても素人のわたしが就職できる店ではない。美加子さんは足をおろし、微笑んだ。
「私が最も得意なことは洋裁の才能を見抜くことよ。だからあなたが凄いんじゃないの。私が凄いのよ」
ひねくれた自慢がおかしくてついわらった。すると、美加子さんは小さく息を吐いた。
「でもね、一番の理由はあなたが買いものかごの取っ手に結んでいたはぎれよ」
「はぎれですか?」
「ええ、あなた、以前私が話した親友のことを覚えてる?」
「はい。覚えていますわ」空襲で亡くなったという女性のことだ。
「彼女もそうやって余ったはぎれをかばんに結んでいたわ。贅沢が許されない時代だったけど、彼女はできる限りの範囲で自分のおしゃれを楽しんでいたのね。
あなたの買いものかごを見て、とても驚いたわ。まるで彼女が生き返ったみたいで_」
と、美加子さんは目を細めた。
「この世界はそんな人が生き生きと働ける場所だと思うの。彼女は残念ながらこの世を去ったわ。
だからあなたにはこの世界で働いて欲しかったの。ちょっと個人的な理由だったわね。迷惑だったかしら?」
「いいえ」と首をふり、わたしは笑顔を向けた。
「光栄ですわ」
話し終えると、バシャリが機嫌よく言った。
「おお、そうですか。良かったではないですか。まさかあの下品な女性がそれほどの人物とは想像できませんでしたね」
「ほんとね」わたしはふきだした。
その後、わたしは仕事の内容を夢中で語り続けた。バシャリはふんふんと聞いていたが、やがて話も途切れると、ふいに空を見上げた。
その視線をわたしも追った。雲が一面を覆っているせいか、星ひとつ見当たらない。
「あそこにあなたの星があるのかしら?」
「いいえ」バシャリが苦笑した。「アナパシタリ星は次元も時空も違う空間に存在します。
方角という概念はありません。空を見上げるというのは一種の象徴的動作ですね。故郷を想うとき、人は空を見上げるものですよ。それは地球人も宇宙人も同じです」
わたしは覗き込むように訊いた。「そろそろ自分の星に帰りたい?」
「そうですね……」バシャリはため息を吐いた。「地球に不時着してからかなりの日数が経過しました。
さすがに里心がついたようです。ですがこれほど探索しても、ラングシャックが発見できません。近頃、幸子はちっとも協力してくれませんし……」
と、うらみがましい目を向けてくるので、うっと息が詰まった。バシャリの言うとおり、最近ラングシャックさがしをさぼっていた。協力しなくちゃ、とは思うものの、どうもやる気がでなかった。うしろめたさをはぐらかすように、明るく励ました。
「心配いらないわよ。きっとあと少しで見つかるわ」
「そうですかねえ……」と、バシャリは肩を落とした。「何だか自分の能力にまで自信をなくしました」
「どうして?」
「いくら地球は感情密度が薄いとはいえ、これほど強く念じているにもかかわらず、ラングシャックが見つかりません。
私は宇宙飛行士です。アナパシタリ星の宇宙飛行士は感情実現能力がずばぬけて高い人間しかなれません。
ですがここまで発見できないとなれば、自分の能力が低下したのではないかと不安になります……これでは宇宙飛行士失格です……」
いつになく気弱な発言だ。最近のバシャリは本当に元気がない。まるでわたしと性格が逆転したみたいだ。何か力づける言葉を、と考えたとき、ふと閃いた。
「そうだわ。明日、荒本さんのところへ行ってみたらどうかしら。あなたも最近研究会には顔を出してないんでしょ? もしかしたら何か情報があるんじゃないかしら?」
作者から一言
感情実現能力とは、想いを叶える力です。想像を現実にする力ですね。超光速で宇宙船を動かす宇宙飛行士は、極めて高い感情実現能力が必要になるというわけです。
いいなと思ったら応援しよう!