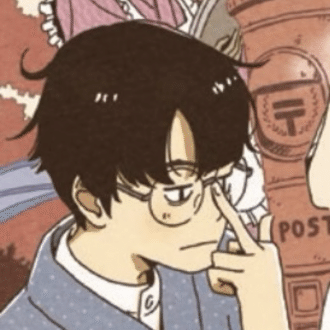note連続小説『むかしむかしの宇宙人』第72話
前回までのあらすじ
時は昭和31年。家事に仕事に大忙しの水谷幸子は、宇宙人を自称する奇妙な青年・バシャリとひょんなことから同居するはめに。友人の星野が小説が完成したと訪ねてくる。
15
数日後、わたしは目黒川沿いの道を歩いていた。銀行から帰っているように装うためだ。
バシャリが出迎えに来ることもあるかもしれないと、退職した翌日からこうしている。
近頃は職さがしを中断していた。公園をぶらついたり、図書館で本を読んだりして時間をつぶしている。仕事を見つけなきゃ、と焦る気持ちはあるのだが、どう頑張ってもその気力が起こらなかった。
「おおっ、奇遇ですね。幸子ではないですか」
バシャリがわざとらしく駆けよって来た。一瞬ドキリとしたが、念を入れてこの道を歩いていて良かった、とほっとした。
「何が奇遇よ。わかってて来たんでしょ」
「さすが幸子。鋭い洞察力です」
バシャリがべらべらとしゃべる今日の出来事に、適当に相づちをうちながら帰り道を歩いた。
「ただいま」と家の戸を開けると、だだっと健吉が駆けよって来た。いつになく興奮しているみたいだ。
「おお、準備は万端ですか、健吉?」
バシャリが靴を脱ぎながら言った。健吉は何度も首を縦にふった。
「準備?」と疑問を含みながら居間を見て仰天した。
部屋が色紙で飾りつけられ、花瓶には黄色の綺麗な花がささっていた。ちゃぶ台の上ではビールやジュースの瓶が整列している。
そして、お父さんが居心地悪そうに座っていた。バシャリが手もみしながら言った。
「さあ、はじめますか」
「一体、これは何なの?」
何かのお祝いだという見当はつくけれど、それが何かがわからない。
「お誕生日会ですよ」
柱の日めくりカレンダーを見る。お父さん、健吉の誕生日ではない。当然、わたしの誕生日でもない。
「もしかしてあなたの誕生日なの?」
バシャリはふきだした。
「幸子は相変わらず愉快な人ですよ。アナパシタリ星人に誕生日などありません。誕生時空連結点はありますけどね」
会話が長引くことを懸念して、誕生時空連結点に関して尋ねるのは控えた。
「じゃあ、誰の誕生日?」
「静子ですよ」
「お母さんの?」
再び、カレンダーに目を向ける。11月29日、たしかにお母さんの誕生日だった。バシャリが説明した。
「昔、私はケケロカマカマ星という星を訪れました。そこでは地球と同じく誕生日を祝う風習が存在しました。
ですが、地球とはひとつ異なる点がありました。そこでは生存する人間ではなく、死者の誕生日を祝うのですよ。
地球でいう弔いの意味があるのかもしれません。地球とまったく逆の行事なので、そのことを周一に教えたら、もうすぐ静子の誕生日だから、誕生日会をしたいと言ったのですよ」
「お父さんが……?」
余程恥ずかしいのか、お父さんの顔が赤くなった。バシャリが続ける。
「はい。だから私は考えました。天国の静子が喜ぶことは一体何か、と。
答えは簡単です。娘の幸子が楽しむ姿を見せることです。
特に、幸子は近頃ふさぎがちでしたから。今日はたくさん幸子に喜んでいただくことにしようと計画を立てたのですよ。さあ、今日は祝いの日ですよ」
と、軽快にビールの栓を抜いた。
健吉がわたしにコップを渡し、おぼつかない手つきでバヤリースのオレンジジュースを注ぐ。「ありがとう……」と言ったものの、まだとまどいが消えない。
みんなに飲み物が行き渡ったところで、バシャリがうながした。
「さあ周一、乾杯の音頭をお願いします」
「俺がやるのか?」と、お父さんが自分を指さした。
「当然です。周一はこの家の主です。つまり円盤にたとえるならば船長でしょう」
お父さんはまだしぶっていたが、しかたなさそうにコップをかかげた。「乾杯」
「乾杯」と、バシャリが陽気にコップを合わせた。わたしもとりあえずコップに口をつける。
甘いオレンジの味が喉にすべり込む。それが合図だったかのように、じわじわと嬉しさがこみ上げる。
「周一、ご存じですか? この前銀座という土地を訪れたのですが、とある洋菓子屋の店前に、巨大な頭部を所持した今にも首がもげそうな少女の像が祀られていたのですよ。
しかも、舌を出して体温調整をしているのです。いやあ、あれには仰天しました。
あんな奇怪な像は宇宙でも非常に珍しいものですよ。あれは邪神像でしょうか。
地球は、異教に関しては非寛容な星だと考えていましたが、邪神信仰が街中で行われていても、日本の統治者は放置しているのですね。実に、寛大な国ですよ」
バシャリは上機嫌でしゃべりだした。お父さんと健吉が静かに聞いている。その光景が、子供のころに描いた理想の情景と合わさる。
すると、バシャリが話題を変えた。
「周一、そろそろあれをお願いします」
お父さんは頷くと同時に奥の部屋に向かい、やがて重そうにミシンを抱えてきた。
「お母さんのミシンじゃない。どうしたの?」
わたしが二人の顔を交互に見ると、バシャリは不敵な笑みを浮かべた。
「さあ、幸子、ちょっとミシンを動かしてください」
「何言ってるの? これ、壊れてるのよ」
「まあ、そう言わずに。試しにお願いしますよ」
バシャリが強引にミシンの前に座らせたので、わけもわからずミシンを踏むと、ダダダダダという音が響いた。
動かなかったはずのミシンが直っていた。バシャリが歓声をあげた。
「周一、すごいではないですか。ちゃんと動きましたよ」
お父さんが満足そうに頷いた。
「お父さんが直してくれたの?」
「ああ、上手く直って良かった」
なぜ今になってミシンを修理したんだろうか。「どうして_」と口を開きかけた寸前で「幸子、座りなさい」とお父さんが神妙に言った。
わたしが正座すると、お父さんがちゃぶ台にあるものを載せた。杉本学園のパンフレットだった。
「おまえが銀行を辞めたことは聞いた」
ぎょっとして飛び上がった。秘密にしていたのに、なぜ知られたのだろう?
「どっ、どうして知ってるの?」
いいなと思ったら応援しよう!