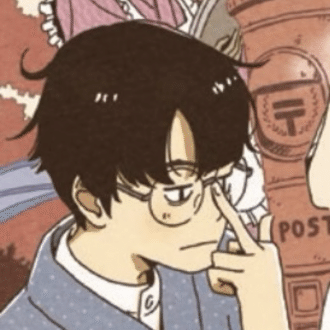note連続小説『むかしむかしの宇宙人』第61話
前回までのあらすじ
時は昭和31年。家事に仕事に大忙しの水谷幸子は、宇宙人を自称する奇妙な青年・バシャリとひょんなことから同居するはめに。二人は空飛ぶ円盤の観測会に出かける。
12
マルおばさんの家に醤油を返しに行くと「さっちゃん、これ持っていきなさい」と、マルおばさんが大きなみりんの瓶をくれた。
角田のおじさんの得意先がくれたそうだ。
その瓶を抱えながら家に戻り、「ただいま」と玄関の戸を開けると、壁にかけたワンピースが目に入った。
ほんと、夢のようだったわーー
昨日の自分の姿を思い返した。荒本さんや星野さん、それにあの三鳥由起夫にも褒められた。
あれほど人に褒められた経験ははじめてだった。そして、はじめて自分自身で服を作った。あの感触が、数日経った今でも手に残っている。
知らず知らずのうちに手の力がゆるみ、瓶がずり落ちそうになったので、あわてて持ち上げた。
その様子を見ていた割烹着姿のバシャリが、呆れた面もちで言った。
「幸子、何やってるんですか?」
「うるさいわね」と、恥ずかしくて顔をそむけた。
出勤準備を終えたお父さんが、部屋から出てきた。玄関の前で足を止め、ワンピースに目をやる。
一体、何を言われるのかとわたしはどきまぎした。バシャリが説明した。
「周一、それは幸子が作った服ですよ」
「幸子が……」と、お父さんがゆるりとわたしを見やった。
バシャリが声を弾ませた。「その服を身にまとった幸子は、大変素敵でしたよ。見られなくて残念でしたね」
お父さんは、再びワンピースに目をやった。そして、
「……それはたしかに残念だったな」
とぼそりと言うと、仕事に出かけていった。
わたしは呆然とした。とてもお父さんの発言とは思えない。やっぱり以前とは違う。わたしだけでなく、お父さんも以前とは少しずつ変わっているんだ……
どこかあたたかな気持ちで出勤すると、わたしはいつものように男性行員の机に仕事道具をならべた。
特に関根課長の机は、置き忘れがないか念入りに確認した。数日前、こっぴどく𠮟られたからだ。
就業時間になり、男性行員たちがやって来た。課長も気だるそうに席に座ると、おもむろに新聞を読みはじめる。
わたしはすぐさま給湯室に向かい、お茶を淹れた。差し出す頃合いを見定めるため、課長の様子をうかがう。
すると、突然課長が新聞を凝視した。紙面に古ぼけた眼鏡を近づける。
それからこちらを見た。その表情には驚愕の色が浮かんでいる。あまりの不気味さに、うっかり後ずさりしてしまった。
課長はもう一度新聞に目を落とし、「水谷、ちょっと来い」と低い声で呼びつけた。何事かと眉をひそめながら近づくと、課長は新聞をつきつけた。
「これはおまえじゃないのか……?」
指さした箇所に三鳥由起夫の文字が見えた瞬間、ぞっとした。昨日の空飛ぶ円盤観測会の記事だった。三鳥さんの隣に、バシャリとわたしがならんでいる。
頭が、まっ白になった。新聞に載れば、銀行の人間の目にふれる。当然だ。あのときは周りの空気に吞まれ、そんな単純なことにも気づかなかった。
一変したわたしの形相を見て、課長はどなり声をあげた。
「銀行員たるものがこんな怪しげな集会に参加するとは、一体、何を考えとるんだ!」
「申し訳ありません」すぐさま頭を下げた。
「空とぶ円盤研究会? おまえはあんなものを信じとるのか?」
「いいえ。とんでもないです」
首がちぎれるほど横にふった。あまりの騒動に他の行員たちが集まる。関根課長の腰巾着である、木谷係長が訊いた。
「関根課長どうかしましたか?」
課長は鼻でわらった。
「水谷がこんな会に入っていてね」
と、新聞を渡した。一読した係長は、嘲笑をまじえたままわたしを見た。他の行員たちも同じ表情を浮かべる。
無理もなかった。銀行と空飛ぶ円盤ほど世界が異なるものはない。まさに水と油だ。そんな中、若手行員の向島さんが何気なく言った。
「でも、あの三鳥由起夫と一緒に写っているんだからすごいもんだ」
関根課長はあからさまに顔をゆがめる。
「小説なんていうのは実際の社会では何の役にもたたんよ。だいたい共産主義も小説から生まれたものだ。君はアカか?」
「いいえ、違います」と、向島さんは必死に否定した。
「あんな連中がちやほやされているなんて日本もどうかしておる」
以前から抱いていた不満を吐き出すような口調だった。
「そうですか……」
向島さんは一瞬、不服さを匂わせたけれど、それを上手く押し包んだ。
そのときだ。ようやく新聞が回ってきた西園さんが、感激の声をあげた。
「水谷さん、この服よく似合ってるじゃない。素敵よ」
場違いな発言に一同がハッとした。
「どこが似合っとるんだ」課長がにらみつけると、西園さんはしゅんとした。課長は新聞をとりあげ、ばんばんと叩いた。
「いくら普段着とはいえこの下品な服装はなんだ。おまえは月光族か? 銀行員としての自覚がなさすぎる」
頭の中でざわりと音がした。仕事上ではいくら罵声を浴びせられようが、愛想わらいを浮かべてやり過ごせた。
でも、丹精込めて作った洋服をけなされることは、我慢ならなかった。
「……どこがいけないんでしょうか?」
怒気を含んだ声が口端からもれた。全員の視線が、瞬時にわたしに寄せられる。その反応で、自分がとんでもない発言をしたことに気づいた。
課長は、ぽかんとした。
最下層の女性行員が口ごたえをするという事実を上手く飲み込めないのか、無言のままだ。
だが、やがてふつふつと怒りが込みあげてきたのか、眉間がぴくりと動いた。そして憤怒の表情に変わると、奥歯をぎりぎりとかみしめる。その恐ろしさにすくみ上がった。
「幸子、さがしましたよ」
突然、大理石のフロアに大声が反響した。声がした方角に目を向け、わたしは唖然とした。バシャリが大きく手をふっている。別れたときと同じ割烹着姿だ。
いいなと思ったら応援しよう!