
日本初の病棟型ホスピスへの取り組みを始めた淀川キリスト教病院で、27年間6000人の看取りを経験して思うこと。田村恵子さんインタビュー
本noteでは、ホスピス特化型メディアとして、ホスピスの見学レビューや業界の動向をレポートしています。
今回は、ともいき京都の代表を務められている田村恵子さんへインタビューをしました。
日本で初めて病棟型ホスピスに取り組み始めた大阪の淀川キリスト教病院にて27年間看護師を務められてきた田村さん。
本記事では、田村さんが看護師として患者様に接してきたご経験やホスピスに対してのお考えなどをまとめました。
ぜひ最後までご覧ください。

ともいき京都代表 田村恵子さん
1987年から2014年までの計27年間、淀川キリスト教病院に看護師として勤務。この間、約6000名を超える看取りに向き合う。
2008年にはNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」に出演。ホスピスでのがん患者の看取りと家族への看護の様子が放映され、大きな反響を呼んだ。
ー本日はよろしくお願いいたします!まずは田村さんがホスピスに関わるようになられた経緯についてお聞かせください。
看護師の資格を取得してから、勤めた病院でのある女性Aさんとの出会いが、その後の私の看護師人生に大きな影響を与えてくれました。
Aさんは、肝臓がんを患っていました。
しかし、当時は患者に対して病名を告げるということはしていませんでした。
ですから、Aさんはなぜ自分がなかなか退院できないのか分からず、常に苛立っていらっしゃって、私も意地悪をされたりとても大変な思いをしていました。
後日、Aさんの息子が「母に病気のことを伝えたいのだけれど、どうしたらいいか」と私に尋ねてきました。
私も看護師の立場ですから、どうしたらいいか分からず、主任看護師に相談をしました。ですが、「病院の方針で、告知するのは難しい」と言われてしまいました。
私は、「息子がお母さんに伝えたい、と言っているのになぜ…?医療者がダメだという権利はあるのだろうか」と納得することはできませんでしたが、当時の私になす術はありませんでした。
それを聞いた息子さんは、「そうであれば、母をホスピスに転院させたい」と、ほどなくしてホスピスに移っていかれました。それが淀川キリスト教病院でした。
当時、私はホスピスというものを知らなかったし、そういう場所が大阪の中にあるとは知りませんでした。それから私はホスピスのことを勉強するようになりました。
そして後日Aさんのお嫁さんから、「ホスピスに移った母はすごく穏やかになり、行ってよかった」という話を聞きました。
私はとても驚きました。あんなにも激しかった方が、なぜそこまで穏やかになれるのか、と気になり、当時あまり推奨されていなかったのですが、「ホスピスにお見舞いに行きたい」と申し出て、お見舞いに行かせていただくことにしました。
Aさんには歓迎されないどころか、きっと怒られると思って、覚悟して向かいました。
ところがAさんはすごく歓迎してくれて、「来てくれて本当にありがとう。ここではみんなに良くしてもらって毎日幸せなの」と人が変わったように穏やかな表情でした。
まるで何かの魔法にかかったように変わったAさんを見て、私はホスピスについて本格的に勉強をするようになりました。

ーAさんとの出会いと、彼女の変化が田村さんにとって衝撃的だったのですね。それから淀川キリスト教病院に就職されるまでにはどのような経緯がありましたか。
それからホスピスについて勉強をして、本もたくさん読みました。しかし、ホスピスの本質的なことは何も分からなかったのです。
「これは自分の身をもって体験するしかない」、と思い淀川キリスト教病院へ就職することにしました。
就職したからといってすぐにホスピスで働くことはできませんでした。初めの2年間は外来と救急外来で勤務をしながらホスピスの勉強をしていました。
当時は病院内に「ホスピスで働きたい」という看護師さんが沢山いたので手を挙げ続けても、働ける保証はありませんでした。
ですが、「行けないかもしれないけど、諦めたら確実に行けない」と思っていたので諦めずに仕事を続け、2年後にホスピス病棟で働けることになりました。
ーホスピスに入るまでに2年間しっかり準備されていたのですね。ホスピス病棟で実際に働き始めてからのギャップや葛藤、また田村さんが患者と接する中で意識されていたことなどは何かありましたか。
ホスピスは患者さまをリカバーさせるための場所ではないので、薬の投与などできないことが最初はとても歯痒かったです。
患者様の容態を見ていると、「こういう薬を投与すればちょっとは延命できるだろう」ということがわかるのですが、ホスピスの場合は何もしないんですよね。
ですから、入って半年くらいは悶々としていましたし、ホスピスに配属になった看護師さんはみんな同じ気持ちのようでした。
このようにホスピスでは積極的に治療をしないので、「ホスピス」と聞くと、「死」に向かっているイメージをどうしても持たれるかもしれません。しかし、私たちは逆です。
痛みや息苦しさなどの症状で自分のことができなくなっていく患者さんを前にして「この方に何をしたら、より穏やかに過ごしていただけるのだろう」ということを常に考え続けていました。
どうしたら患者さまが毎日を穏やかに「生」きられるかを考えて毎日接するようにしていますし、それが私たちのケアの目標です。
容態が刻一刻と悪化して、家族や本人と会うたびに嫌なことを言わなければならない状況が続きますが、どれだけその人に関心を寄せて寄り添えるか、その人のことを考えて誠実な態度で看護ができるか、という「人」がとても大事なのだと感じます。
その中で、私が意識していたことは、同一視せずにケアに入るということです。苦しい、悲しいという感情の一つひとつに同一視していたらこの仕事は続かないですから、私の中でストレスにならない程度の距離を取るようにはしていました。
一方で、「何があっても私たちがそばにいますよ」というサインは常に送り続けてきました。
きっと、私たちのそういう気持ちが患者さまに伝わって、Aさんのように表情が変わったり、笑顔になったりされているのだと私は思っています。
ーそうですよね、私もホスピス見学に行って一番見るのは「どういう人がケアしてくれるのか」という「人」の部分です。少し質問の毛色が変わりますが、今病院にも自宅にも行き場がない"看取り難民"が非常に多い問題がありますが、田村さんはこの問題をどう捉えていますか。
人々が自分の「死」に対しての考えを持っていないことが一番の問題だと私は捉えています。
ホスピスや病院の病床数が足りないわけではないんです。
実際に今空いている病床に、”看取り難民"と言われる方々が入ったら、その数はだいぶ改善されると思います。
大体の人はみんな、「死」はいつかは来るとは思うけど、と考えることから逃げていますよね。そして、自分の死生観が確立されていない。
この現状が変わらない限り、これからいくら施設が増えても難民は増え続けるし、自ら難民に向かっていると思います。
これは幼少期からの教育にも改善の余地があると思います。
もっと「生死」について考える時間を設けなければ、大人になってから「じゃあ今から考えましょう」と言われて考えられるようになることはないのですから。

ー確かに私たちは最期の時間をどう過ごすか、正面から向き合えている方は少ないですね。田村さんは実際に「死」に対してどう考えていらっしゃいますか?
「死」は誰しにも必ず訪れるもの、そして「死」は人生の通過点だと思っています。
「人は必ず死ぬ」、それはこれまで6000人以上ものお看取りを経験してきてひしひしと感じることです。
ちょっと気を抜いたら、人はこぼれ落ちるように亡くなっていきます。
「気になるけど、寝てるから明日また声かけよう」と思って、翌朝来たらベッドが空っぽという体験を数えきれないほどしてきました。
私自身が「死」を経験したわけではないので、恐怖感がないわけではありませんが、これまで患者さんへの看護を結構頑張ってきましたから、みんなウェルカムって言ってくれるかな、なんて思っていますけどね。
ーそうですね、きっとあの世では今よりももっと忙しくなりますね。では最後に田村さんに現在のご活動について教えてください。
私は現在、NPO法人ともいき京都の代表と大阪歯科大学大学院看護学研究科(仮称)開設準備室の室長として臨床・教育・研究に従事しています。
ともいき京都は、がん患者や家族が対話を通じて生きる知恵を育み、支え合うコミュニティづくりを目指す団体で、誰もが緩和ケアの恩恵を受けられるようにという思いを込めて活動をしています。
私たちは誰もが、苦しんでいる人がいたら役割に応じて、手を差し伸べられるようにしないと、これから迎える多死社会には追いついていけないと思っています。
今後もこのともいき京都での活動を通してコミュニティでお互いをどう支えていくかをミッションに掲げて活動を続けていきたいと思っています。
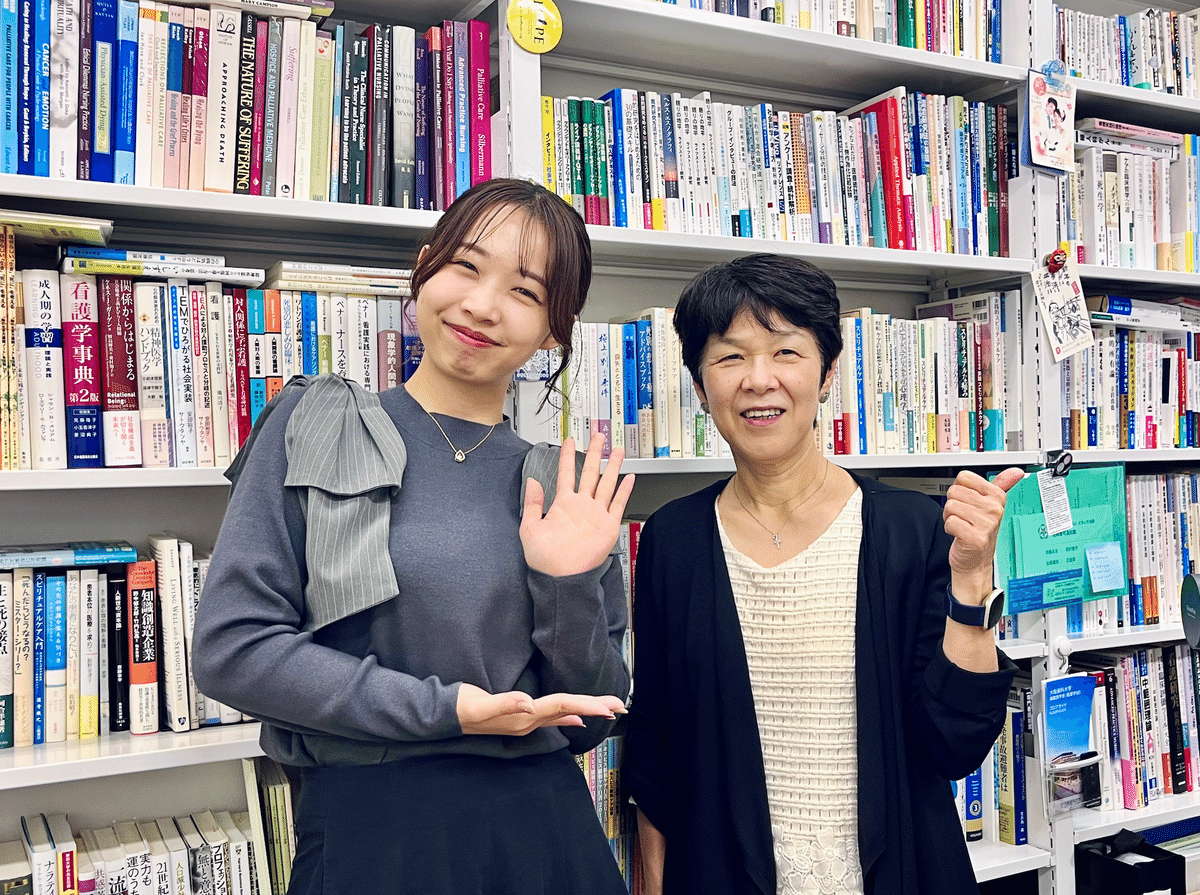
ーーーー
以上、ともいき京都代表 田村恵子さんへのインタビューでした。
2025年7月4日〜5日には田村さんが大会長をされる「第30回日本緩和医療学会学術大会」の開催もあるので、興味がある方はぜひご参加ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━
このnoteではホスピス業界の最新情報や実際の見学レビュー、
インタビュー記事などホスピスに特化した情報を発信していきます!
私は「自分の家族を預けられる」ホスピスを立ち上げ中です。
そのための情報収集など細かに行なっているので、ホスピス選びに悩んでいる方は、無料相談を受け付けています。
下記メールアドレス宛にお気軽にご相談ください。
→ info@nokos.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━
他の記事はこちら↓
