
新環境の壊し方 バカムラルフィ(紫ルフィ)
紫ルフィの変遷
光の速度で…

紫ルフィが登場したのはワンピースカードゲーム第5弾新時代の主役、2023年8月下旬です。
4弾環境終盤で生き残ったのは白ひげ、レベッカ、ゾロ、ルッチ、ドフラでした。特に白ひげとゾロのデッキパワーが高く、これらに戦えるかどうかという視点で環境が形づくられていました。
ここに投下されたのが紫ルフィです。先行を取ってドン加速し4ドン、7ドンのキャラを展開する。相手の追いつけないまさに光の速度で高パワーのキャラを展開し4弾環境のデッキをなぎ倒していきました。
環境初期では注目された赤紫ロー、青黒サカズキ、黄エネルを軒並み蹴散らして去年の9月の店舗予選は紫ルフィを握れば突破できると言わしめるほどの実力を見せつけます。
様々な型とフルパワー型

去年9月の店舗予選では様々な型が存在しました。
麦わら型、film型、インペルダウン型、キッド型、W7型…
紫ルフィが流行ったことによりさまざまな型が考案されました。ほかの環境デッキに勝てるかという視点に加えて紫ルフィミラーに勝てるかという点が色濃くみられていました。
その中で生き残ったのはフルパワー型。サーチを入れて安定性を向上させるのがいままでのデッキでは定石とされていましたが、これを採用せず各型の強いカードをぶち込んだデッキタイプになります。
この型が流行ったのは紫という色の貧弱さに由来します。この時点まででの紫単色のリーダーはあまり評価されておらず、唯一カードパワーのある百獣海賊団はこのころサーチがありませんでした。このためサーチの評価が低くなり、結果的にフルパワー型が注目されました。
そして暗黒時代へ

しかし、そんな紫ルフィの天下も長くは続きません。アグロサカズキとか言われた、ヒナや犬噛紅蓮等を採用した青黒サカズキの流行により紫ルフィの時代は終了します。ここから環境は紫ルフィに勝てるかという視点から青黒サカズキに勝てるかという視点にシフトしていきます。紫ルフィはほかのデッキに勝てるが、青黒サカズキに勝てないという点が致命的でだんだんと分布が減少していきました。
そして青黒サカズキが禁止された後も赤紫ローやCP0の黒ルッチが流行り環境には顔を出すことができません。いろいろ勝てるデッキはありますが、tier1に勝てずtier3,4どまりでした。
突然のチャンス
ここで神から与えられた3つのチャンス。
①スタートデッキと9弾による強化
あたらしいカードが増えて紫ルフィが強化されました。スタートデッキは紫ルフィ用のカードであるということは言わずもがな、9弾の新カードに関しても黒紫ルフィだけでなくほかのデッキにも使える効果にしてくれた結果紫ルフィが強化されました。
②赤紫ローと黒ルッチの弱体化
赤紫ロー自体の禁止と黒ルッチの弱体化が今年の9月から施行されました。単純ではありませんが、不利だったデッキが2つ環境から姿を消したことになります。
③大型環境の到来
新たなる皇帝が発売されていざ蓋を開けてみると、大型主軸のデッキが増えました。9ルフィ10ルフィ8モリア主軸の黒紫ルフィ然り、10ドフラ8キッド主軸のボニー然り、10ティーチ主軸の黒ティーチ然り、特に10シャンクスが強い赤シャンクスは評価が高くこのデッキが環境の中心となりつつあります。
環境デッキ、特に赤シャンクスに勝てるという点で紫ルフィの個人的な評価が高いです。大型中心の環境になり簡単に4コスト7コストが処理されないという点が5弾環境初期の再現です。握るなら今しかない!ということで今回は紫ルフィについて解説をしていきます。
シャンクスには勝てるけど、ドフラには勝てないよん
紫ルフィはなぜ強かったのか
先ほど言ったように、紫という色自体は貧弱です。ではなぜ紫ルフィは強かったのでしょうか。
それはリーダー効果とゲームシステムの噛み合いの良さに由来します。ワンピースカードゲームはデュエルマスターズと同じようにドン(マナ)をためてだんだんと強いカードを使えるようになっていきます。基本的に4ドン使ったら3~5ドンくらいのカードを除去したりできるようになっていますし、4ドンのカード2枚を使うより8コストのモリアを使ったほうが強い場合が多いです。こういうところは1ターン目からソリティアを始める遊戯王と違いますね。このようなゲーム性において相手よりも多くのドンを使えるということは強さに直結します。相手は紫ルフィよりもドンの枚数的に弱いカードを使うことを強要されてしまい、結果序盤にひっくり返せない盤面差を作りだされ捻り潰されます。
また、簡単すぎることも強い理由であり弱い理由でもあります。基本的に相手に合わすデッキタイプではないので簡単でした。先行を取ってリーダー効果を毎ターン使い4ドン7ドンと手札にある一番コストの大きいカードを順番に使うだけで勝てます。(このせいで青黒サカズキ視点では何を出してくるかわかりやすく、簡単に紫ルフィは負けます。)
またコンボデッキでないことが再現性を高めています。紫の強いところがドン加速ですが、終盤は役に立ちません。ドン加速用のカードとそうでないカードの2種類を搭載することが紫のデッキの足かせとなりますが、これを紫ルフィは入れる必要がないです。1種類、プレイする用のカードを入れておけば簡単にデッキが回るのです。
アドバンテージをどこで稼ぐか
紫ルフィがアドバンテージをどこで稼ぐかという問題です。これは「生き残ると強いカードを早めに出すこと」がポイントです。
ドン加速を行うことで早めに大型のカードを出すことができます。現在ワンピースカードでは登場時効果、起動メインが強いカードが評価されています。アタック時効果は次のターンまでそのキャラが生き残る必要性があり、また大型だと出すタイミングが遅いことから使える回数が少ないです。
これを紫ルフィは克服しており、相手より多いドンのカードを使用することで相手の処理漏れを狙うことができるようになっています。
単純に4ドン6000のカードが4ターン生き残れば毎ターンのアタックで2000カウンターを4枚以上要求することができるようになっています。強そうでしょ?強いんですよ。
勝てるデッキと勝てないデッキ
これを踏まえると勝てるデッキと勝てないデッキが明確になってきます。ズバリ「4ドンで4ドンを、6ドンで7ドンを除去できるかどうか」「高パワーで殴れるか」という二点でしょう。
紫ルフィが先攻を取った場合リーダー効果を使用すれば1,4,7,9というドンカーブで進行していきます。対戦相手は2,4,6,8というドンカーブになります。紫ルフィのアドバンテージの稼ぎ方が、いかに序盤に出したカードが生き残れるかということに依存するなら4ドン、6ドンのカードを処理できるかどうかが勝敗に直結します。4ドン7ドンを処理するカードは多々ありますが、5ドン8ドンを使って処理することが多いので、当然もっと少ないドンでこれらを処理するのは難しくなっています。これを赤紫ローとエニエスロビーありのルッチはやってきましたが、現在の環境ではこれに代わる除去デッキが出て来ていません。
また、高パワーで殴れるかという点も大事です。紫ルフィはリーダー効果によって少ないライフで戦うことになります。相手視点リーダーにドンを付けて高パワーで殴ると盤面で負けるし、展開を優先すると毎ターン5000でしか殴れず紫ルフィは簡単にライフを守れます。このジレンマを解決してくるのが赤ゾロ、ベロベティ、青ドフラです。特に青ドフラに関してはかなり不利寄りです。
バカになれ
いろいろ理屈を捏ねましたが情報を整理しましょう。
・不利対面が減って現在環境が追い風となっている。
・簡単なデッキなので回しやすく再現性が高い。
・強化が来ていて相手がまだ慣れていないカードプールで戦える。
手札にある一番コストの高いカードを使ってれば勝てる、そんなバカになって勝てるデッキ握り得でしょう?
構築

デッキレシピです。軸は麦わら軸になっています。4ドン6000のゾロ十郎を強く使うという観点で組んでいます。そのほか各カードの詳しい採用理由は採用非採用カード解説で語っています。
プレイ方針と考えること
先攻を取って、4ドン7ドン9ドンの強いカード(一番コストが大きくてカウンターレスのカード)をたたきつけてください。非常に簡単で、バカムラルフィといわれる所以です。
先攻を取った場合
4ドンでゾロ十郎を出したいです。手札を減らさずに4ドン6000を立てられることも強いですが、ゾロ十郎から7ドンのカードにもつながることで安定性がかなり高まります。最初にゾロ十郎を出せるとそれ以降の動きの良しあしにつながります。(ウソップはゾロ十郎がないときよう)
7ドンではルフィ太郎を出したいです。ゾロ十郎ではルフィ太郎およびルフィ太郎から出す5コスト以下の麦わらで足りないパーツを探しに行きます。7ドンのルフィ太郎で出して強いカードとしてはゾロ十郎>サン五郎>ジンベエという順になっています。大体どれかがあるのですが、5以下ということに引っ張られすぎないようにしてください。相手は次のターン6ドンなのでサン五郎やジンベエは処理されるケースが最初よりも高いです。また、ゾロ十郎は手でかさばるデメリットを内包しているので早めにプレイすることをお勧めします。(サンジは7ルフィ太郎が)
次のターンはリーダー効果なしで8ドンか9ドンになっています。7ルフィ太郎も9ルフィもどちらを使っても強いですが、判断基準をゾロ十郎が手札にあるかどうかにゆだねてください。カウンターレスがかさばることが死に直結するデッキなので早めにこのカードをプレイしてください。逆にゾロ十郎がない場合は9ルフィを使ったほうがいいです。
後攻を取った場合
5ドンで出してほしいのが5キッドか4ゾロ十郎です。5サンジでもいいですが、この二つのほうが恩恵が高いです。5キッドは6000ブロッカーとして活躍してくれるのと、ドン加速を2回使えばいいようにしてくれる。(8ドンターンにドンマイナスを緩和してくれるので次のターンドン加速をしなくてもよくなる)ゾロ十郎は手札にかさばるのを防ぐためです。次のターン以降にプレイするカードがあるなら5キッドでいいし、ないならゾロ十郎を使ってください。
8ドン以降は先行と同じです。考えやすくていいね!
その他
その他のプレイ方針についてです。まだライフについて触れていなかったと思いますが、基本的に7000以下の攻撃は守ってください。相手の最初の攻撃を受ける癖がついてしまっている人が多いですが、このリーダーはライフの価値が非常に高いです。最初に受けなきゃよかったと思うことが最初に多々あると思うので、ライフは基本すべて守ってください。特に手札1枚で守れる攻撃は全部守りましょう。また7000の攻撃は1回は守ってもいいでしょう。
また、6000のキャラは終盤以外守ってください。4ドン6000のキャラが評価されているのはリーダーにアタックされるときよりも1000カウンター得できるからです。お得に守ってください。
それと重要なのが、ローはむやみに使わないこと。①1ターン目②後攻に(ドンが余るときに)パーツが足りない場合、この2パターンのいずれかに該当しない場合は使わないでください。相手のカウンター値を少しでも削るためにローは使わないで攻撃に回しましょう。
最後にカウンター値計算。7ドンを超えたタイミングで次のターン死なないかどうかを考えてください。死ぬなら相手のキャラを殴るかブロッカーを立てるし死なないなら相手のライフを詰めてください。紫ルフィはカウンター値計算が白髭の次に簡単なのでこれができるだけで勝率が上がります。具体的な場面でカウンター値計算の例を出しているのでよかったら見てください。
有料部分について
有料部分では採用非採用カードについての解説、各対面の解説、最新の構築について書いています。サンプルを載せておくので気になったら読んでいただけると幸いです。
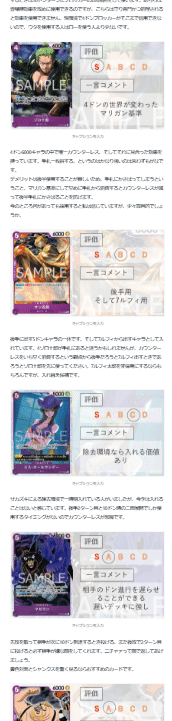
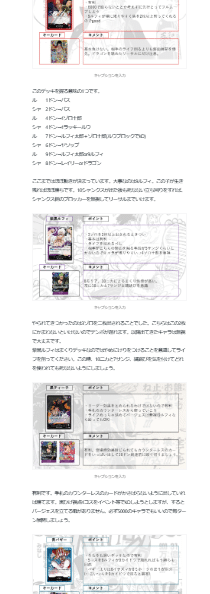
ここから先は
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
