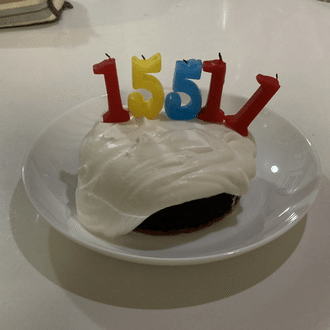人生フルーツ
繰り返し観るドキュメンタリー映画がある。「人生フルーツ」だ。建築家で自由時間評論家の津端修一さんと、英子さんの夫婦の日常を綴っている。
なんとなく調子が悪い時、気分が沈んだ時、この作品を観る。樹木希林さんのナレーションが心地よく、画面の中に流れる時間が穏やかで、音楽が荒れた心に沁みる。なにより、このご夫婦の生き方が好きだ。静かな暮らし。自給自足の野菜と果物。肉や魚は、バスと電車を乗り継いで市場へ行き、40年以上も親交のある人たちから買う。コンビニで買い物をしたことが一度もないの、と笑う英子さんは、日常の料理の他にお菓子や保存食を作り、畑仕事をし、機織りもする。修一さんも、毎日のように知人にハガキを書き、庭仕事、畑仕事に精を出す。ゆったりとした暮らし。
最初わたしは、この作品が90歳と87歳(2015年の撮影当時)の老夫婦の、ほんわかしたスローライフの暮らしぶりを撮ったものかと思っていた。違う。そうじゃない。過去のエピソードが重ねられるにつれ、凡人には理解しがたいほどの信念を持った人たちの生き方だとわかった。流されない。目的地には、どんなに遠回りしても辿り着く。むしろ、時間をかけることによって、最良の結果を導き出す。意思は強く、いや、激しく、熱い。やると決めたら徹底して貫き通す。ブルドーザーで切り開くような大仕事ではなく、小さなことから、歩を緩めずに進み、ていねいに暮らしている。修一さんの「時をためて、コツコツ、ゆっくり」という言葉に、何度も何度も背筋に一本の支えをもらう。人は、一度にたくさんのことをできるわけではない。焦らなくていい。けれど、強い意志で、最後まであきらめないこと。そんな声がする。
台湾での出版記念パーティで、インタビューに答える修一さんは「彼女はね、僕の人生最高のガールフレンド」と、照れ笑いをする。手を繋いで写真を撮る時も「恥ずかしい。ふふふ」。いつも穏やかで、口調は優しい。まさに好々爺である。しかし、その内面にある情熱の凄まじさ。『内助の功』が薄っぺらい表現にしか聞こえないほどの、英子さんの支えがあってこそ、修一さんの存在があるのだ。
作品の終盤、修一さんに「お仕事」を依頼した、佐賀県の精神科病院で働く人たちが出てくる。二人の暮らしぶりに感銘を受けた彼らは「経済中心の社会で揉まれ、本来の自分の心を見失った患者さんたちに、どんな生活の場を提供したらいいのか。人間らしい暮らしとは何か。住居や作業所など、新しい施設を作ることになったので、知恵を貸して欲しい。」と相談の手紙を書き、津端家を訪れる。その時の修一さんの嬉しそうな顔。スケッチブックを前に、サラサラとラフスケッチを描いていく。そして、数日後には全体の構想図が出来上がっていた。その素早さ。この時のやり取りは、引退した建築家が余力でやっている、という感じがしなかった。本気の仕事だ。その証拠に、病院側の人が言うのだ。「いま仕事があるとか、自分がすべきことがあるときには、すぐ動ける(ようにしていた)。だから、道具も古びてなかったし、スケッチブックもすぐ持って来られた。構造(構想?)もすぐに説明できる。常にそういう態勢にいたわけですよね。だけど周りの人はそれを津端さんに求めてないから、それを出してないという…」
これにはもう、稲妻で打たれたようなショックを受けた。90歳の人が、である。この心がけこそが、仕事をする人の在り方だ。わたしはこの15年、ただ忙しさの中で一生懸命だったけれど、仕事に対しては、気を抜いて生きてきたのだ。だからそれを忘れないように、くじけそうになった時こそ、これを観る。癒されて、励まされて、勇気をもらう。
やはり、この夫にこの妻あればこそ、という英子さんの言葉も心に残る。庭に置かれた鳥の水浴用の水盤が割れて、「気に入ってたのに」と嘆く娘を諭すように英子さんが言う。
「いいことだけを考えて、悪いことは言わないの。」
※この作品は樹木希林さんの追悼企画として、CSの「日本映画チャンネル」で2019年10月に放送(放送日はこちら)されます。TSUTAYAで借りることもできるようです。
※写真はこちらのサイトからお借りしました。この作品を主題にした堀川とんこうさんのエッセイを読むと、作品の背景もよくわかります。)
いいなと思ったら応援しよう!