
モーツァルトの自動作曲システム
ここのところ、猫の話ばかり続いている。
ハンネを、猫横丁工房あたりに替えようか。
そう思ったが、たまには音楽の話もしたい。
ということで、当面はこのままでいこうと思う。
さて、見出し画像は、ヨーロッパ旅行のお土産に頂いたティッシュペーパー。
このティッシュ、恐れ多くて、本来の用途に使えない。(ばちが当たる)
なので、普段は猫が届かない高さの壁に飾っている。(霊験あらたか^^)
今日の話題は、モーツァルト。
数々の名作を残したモーツァルトであるが、彼が自動作曲システムを開発していたことはご存じだろうか。
それについて、ある楽曲投稿サイトのトピックに書いたことがある。
数年前に閉鎖されたサイトで、もう見ることはできないので、少し書き直してこちらに出すことにした。
以下、少々長いが、よろしければお付き合い願いたい。
最近は、全くの素人でも、PCを使って楽曲制作ができる環境があります。
実は18世紀後半の西欧には、それに近いシステムがありました。
それは音楽のサイコロ遊びと呼ばれるものです。
フレーズをいくつか作って、それぞれに番号を付けておきます。
後は、サイコロを順に振って、出た目に対応するフレーズをつなげていくだけ。
市販のループを並べて曲を作るのに似ていますが、並べる順番はサイコロが決めてくれます。
従って、音楽的センスは必要ない、というメリットがあります。^^
このさいころ遊びは、福笑いに似ています。
出来上がったフレーズの並びは、たいてい変な音楽になるから。
それを、プレーヤー同士で笑い合う。
当時の貴族の間で流行した遊びだったのでしょう。
とは言いましても、ゲームとしての面白味のためには、もう一つ必要なことがあります。
ちゃんとした音楽も、時にはできてくれることです。
理想を言えば、どのようなつなぎ方でも音楽として流れるようなフレーズを一揃え用意できれば、商品として差別化できます。
それは非常にセンスが必要で、そう簡単には作れない。
たぶんそのためと思いますが、販売元は有名音楽家の名前をかたって売っていたようです。
例えば、モーツァルトの名前で販売されたものが、今でも数種類残っていて、全て偽作とされています。
例えば、その一つがこれ。
ところが、モーツァルト直筆のさいころ遊びのスケッチが、発見されていたんです。
それについては、野口秀夫氏のHPで詳しく紹介されています。
「音楽の遊び ハ長調 K.516fの演奏法と作曲の背景」
それによりますと、モーツァルトはサイコロを使う方法ではなくて、知り合いの名前の文字(アルファベット)をキーにして、それに対応させたフレーズを並べて作曲する方法を考案しています。
詳細は、上記の野口秀夫氏の記事をご覧頂きたいですが、モーツァルト直筆のフレーズ一覧だけ、見やすく書き直してみました。
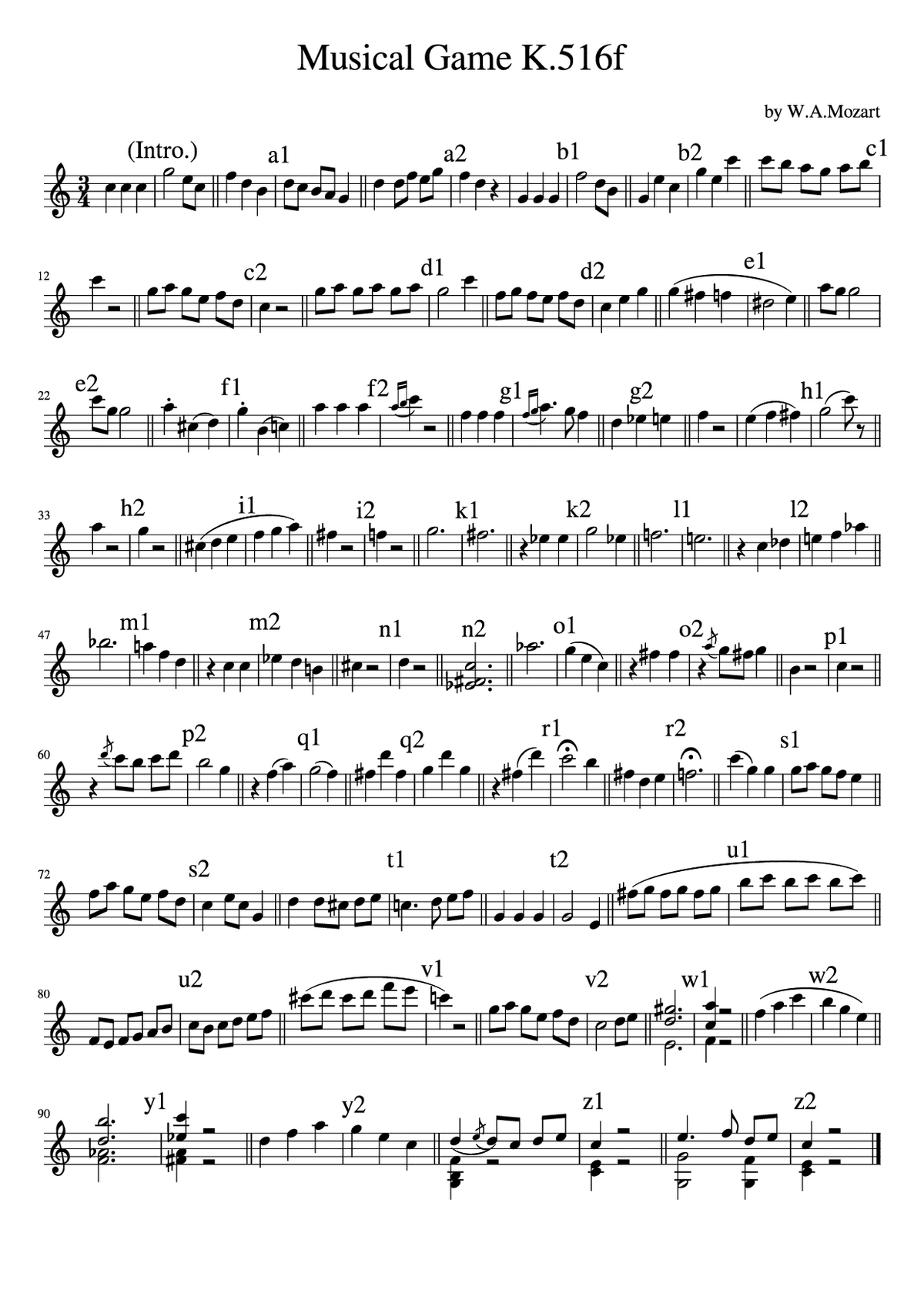
さて、これを使ってどうやって作曲するのでしょうか。
ここではblue but greenさんのハンネをお借りして、実際に作ってみます。作り方は至って簡単です。
まず、お名前からスペースを取って最後にzを付けます。
bluebutgreenz
次にアルファベット順に並べ替えます。
bbeeeglnruutz
同じ文字がある場合、一つ残して残りを抜き出し、後ろへ回します。
eは3つあるので、2回抜き出します。
beglnrutz + beu + e
各文字に番号1と2を交互につけます。
後で出てくる同じ文字には、前と違う番号を付けます。
b1 e2 g1 l2 n1 r2 u1 t2 z1 b2 e1 u2 e2
最後に元の名前の順序に戻します。
アルファベットだけ見れば、ブルグリさんのハンネの並びと、最後に付けたzに戻っていることが確認できると思います。
b1 l2 u1 e2 b2 u2 t2 g1 r2 e1 e2 n1 z1
モーツァルトは、jとx以外の全てのアルファベットに対して2通りのフレーズを作っています。
2通りあるのは単調さを避ける工夫です。
上のb1とかe2の数字は、そのどちらのフレーズを使うかを表します。
上でアルファベット順に並べたり、順繰りに番号を付けたりしているのは、そのどちらを使うか、決めるための工夫です。
zは必ず最後にきますから、最後はエンディング用のz1とz2のどちらかになります。
また、最初の2小節だけはフレーズが決まっています。上の楽譜でIntroと書いたフレーズです。
インプットした名前に対応するフレーズは、3小節目から始まります。
こんなシステマチックな作り方を思いつくあたり、モーツァルトもヲタク的性格だったのかもしれません。^^
出来上がった曲を、オルゴール風の音色を使って、自動演奏してみました。
聴いてみると、さすがモーツァルトが作っただけあって、実にモーツァルトです。^^
ただ、繋がりにやや難がある感じです。
メロディーだけなので、コードを付けるなどの工夫をすれば、うまくつながるかもしれません。
とすると、この作曲法は素人向けとは言えないですね。
それより、コードを勝手に付けたら、その時点でモーツァルトの作品と主張できなくなります。
アレンジになるのでしょうね。
このシステムの特徴は、インプットする名前によって、全く違うオリジナル曲ができることです。
しかも作曲がモーツァルトというのは、何と素敵なことではありませんか。
あなたも、ご自身のお名前で、作ってみませんか。^^
