
なぜ「おきつあー」をしたいのか
2025年1月25日と26日に予定している「おきつあー」(ぜひ来てください)
なぜこのようなイベントをしたいのかと聞かれたら、もちろん「興津という土地に対する愛着やその魅力に魅了されているから」なのですが、このイベントやリサーチに託したい思いを「おきつあー」をしたいと思わせてくれた2冊とともにここに記させてください。
※興津関係ない2冊です
↓↓↓ 参加申し込みはここからどうぞ! ↓↓↓
土地の見えない構造や可能性を探す楽しさ
1冊目:『東京の地霊|《ゲニウス・ロキ》』 鈴木博之 2009年 ちくま学芸文庫

三井財閥と久能木一族が争った一等地・日本橋室町、薄幸の皇女の影をひきずる林野庁宿舎跡地、天海僧正が京都を模した上野の山…。どのような土地にも、時を経ても消えることのない歴史・記憶の堆積、「地霊(=ゲニウス・ロキ)」がある。それは、土地に結びついた連想性と可能性を生み、その可能性の軌跡が都市をつくり出していく。江戸から平成まで、近代の東京の歴史は、そうした土地の歴史の集積として見ることができるだろう。数奇な変転を重ねた都内13カ所の土地を、新しい視点から考察し、広く話題を呼んだサントリー学芸賞受賞作。
気鋭の建築史家、鈴木博之。彼は都市の歴史を研究する最中、ドライに史実を整理していくだけでなく、そこを所有していた人物の嗜好や時代背景までも考察し、その土地の”性質”とでもいうような特徴を本書で考察しました。
どのような土地であれ、土地には固有の可能性が秘められている。その可能性の軌跡が現在の土地の姿をつくり出し、都市をつくり出してゆく。(中略)都市の歴史は土地の歴史である。
ところが一般には、都市史と言われるものの大半が、実は都市そのものの歴史ではなく、都市に関する制度の歴史であったり、都市計画やそのヴィジョンの歴史であることに、かねがね私は飽きたりなさを感じていた。都市とは、為政者や権力者たちの構想によって作られたり、有能な専門家たちによる都市計画によって作られたりするだけではない存在なのだ。現実に都市に暮らし、都市の一部分を所有する人たちが、さまざまな可能性を求めて行動する行為の集積として、われわれの都市はつくられてゆくのである。

・鹿鳴館の生みの親・井上馨や、”最後の元老”西園寺公望の別荘があったこと。
・日本の柑橘の聖地・カンキツ研究拠点があること。
・地球の内部を掘り進める探査船”ちきゅう”の母港になっていること。
・チャールズ皇太子(国王)の座布団をつくった職人がいること。
このような興津にまつわるあれこれは、それぞれ偶然に起こった出来事なのでしょうか。仮に、何の関係もない偶然だったとしても、一個一個がなかなかに濃ゆいと思いませんか…?
このような興津の土地の歴史の集積を、”興津の地霊”として見出すことができれば、きっとも面白いんじゃないか。
そしてこれから先、具体的な土地の歴史やその土地を愛した人々を無視した”事業計画”みたいな凡庸なマスタープランに沿ってまちづくりをするのではなく、その地霊にあやかって継ぎはぎするように街の将来を描けていけたら…
興津はそんなことを夢想させてくれるほどに、いろんな可能性に満ちているし、おきつあーでは参加していただいた皆様、そして企画をした自分たちも興津の地霊に触れ合える機会になればいいなと思っています。
実際に体験したことから考察する面白さ
2冊目:『Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture(メイキング 人類学・考古学・芸術・建築)』ティム・インゴルド 金子遊・水野友美子・小林耕二訳 2017年 左右社
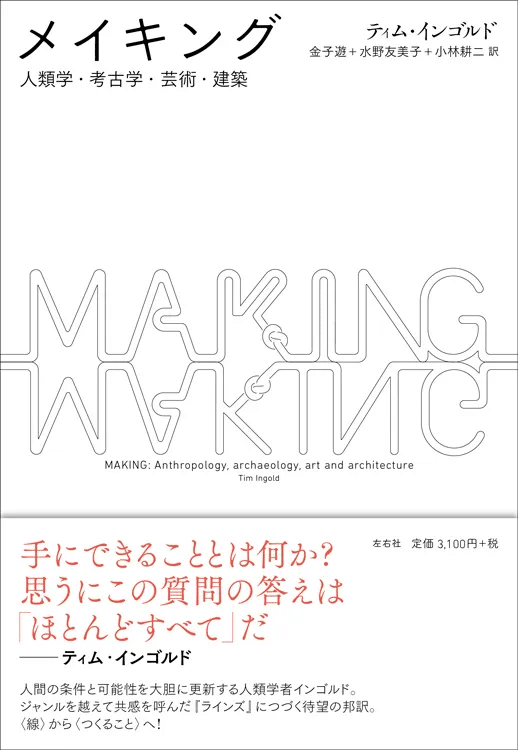
人類学と考古学、芸術、そして建築。
これら4つのAをすべて、世界を探究する技術として捉えなおしたならば、どんな風景が広がるだろう。そのために石器を試作し、浜辺を歩き、ある1体の彫像を1週間観察する。そんな授業を続けてきたインゴルドが送る、文化人類学の冒険の書!
フランスからアフリカまで産出する石斧が、ほとんど同じ形状をしているのはなぜか?
ゴチック建築の傑作、シャルトル大聖堂は、設計図なしにどうやってつくられたのか?
この物質世界のなかで、生きているとはどういうことか? それは風に吹かれる凧とどう違うのか? 無数の刺激的な問いから、インゴルドは人間の根本的な条件と可能性を見つけだす。 知るのではない、狩人になるのだ──。
『メイキング』とともに過したものだけが、その意味を知る!
イギリスの社会人類学者ティム・インゴルド。時計、建築、あるいは石器など過去に作られたものが”なぜ” ”どのように”つくられたのかを様々な角度から検証することで、インゴルドは人間根源の可能性を追求していきます。
そしてインゴルドは文化人類学者として、”何かを知る”ためには実際に体験して自身の内側から学習することの重要性を説きます。
物事を知るためには、それが自分自身の一部になるように自己がそれに向って成長しなくてはならない。それから、自分のなかでそれを育てあげなくてはならない。
端的にいって、わたしたちは見ること、聴くこと、感じることを通して学ぶ。それは世界が語りかけてくるものに注意を払うことだ。
学問の殿堂のなかで、論理の直感に勝るものだとされる。専門知識は常識をしのぎ、事実に裏付けられた結論は、人びとが日常の経験や慎み深い知恵から得る知識をしのぐとされる。長いあいだ、人類学の任務はこのような学問の殿堂をくつがえすことにあった。それは次のように仮定するところからはじまる。もしこの世界がどうなっているのか何か知っている人がいるとしたら、それは祖先がしてきたように自分の生を次の世代に捧げてきた人たちであろう、と。

そしてここから派生した興津にある様々なもの・ことはどんなものがあるでしょうか…
・石垣から染み出してくる水
・いくつもある細い路地
・海沿いのバイパス
・雰囲気のある古い洋風住宅
今の興津あるものが自然発生にしろ人為的にしろ「なぜ生まれたのか」を探ってみると、その答えは、本の中にあるのではなく”街”の中にあります。興津を実際に歩いてみて見える・感じることと、これまでの興津の歴史を重ねることで、街に対する解像度がぐっと増すのではないでしょうか。
そうした体験・観察・考察の繰り返しでこれからのまち ―興津に限らず― の将来を描いていくことができるのではないでしょうか。何か正しいことや仕組みに沿って街を作っていくのではなく、生身の人間が感じたことや見つけたことをちょっとずつ組み合わせたり、編み込んでいくような…。おきつあーにはそんな期待を込めてみたいと思っています。
なんやかんや書きましたが結局のところ…
【街の歴史や成り立ちを、いろんなものが絡み合った結果として面白く見てほしい!】
おきつあーでやりたいことは、上のことに終着する気がします。いろんな先人たちがまとめてくれた資料や専門書を分解して、”まちのおもしろさ”を見つけることを難しいことじゃなく、娯楽として誰かに届けばいいなと思っています。
おきつあー、来てね✌

