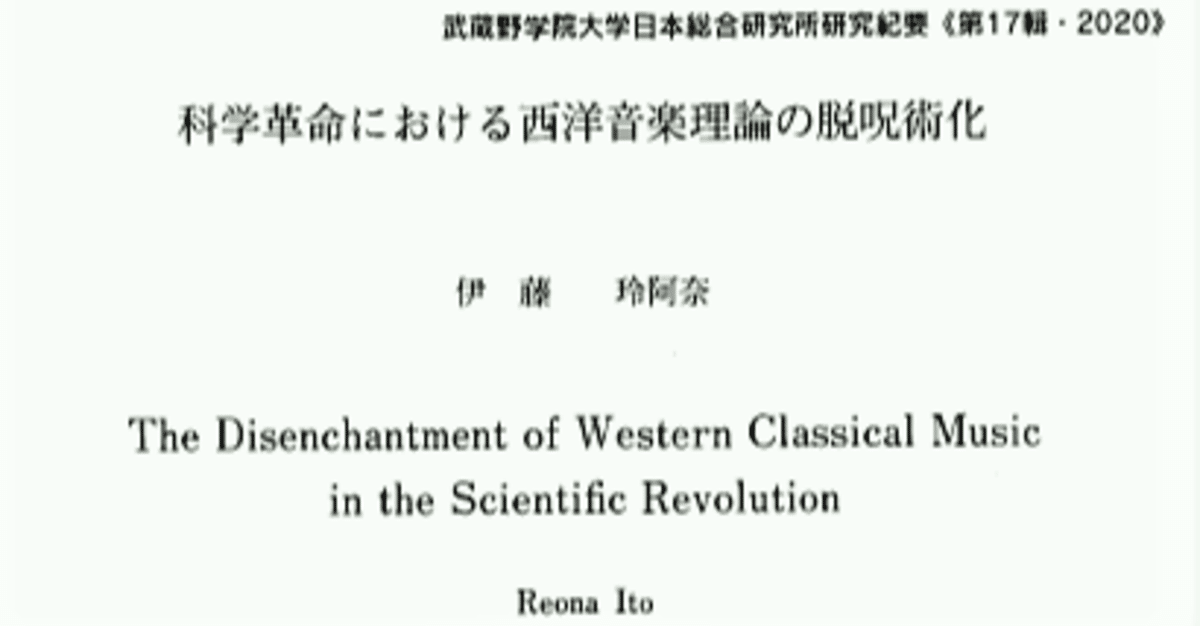
【論文公開2】科学革命における西洋音楽理論の脱呪術化
2020年、私は初の著書となる『「宇宙の音楽」を聴く』(光文社新書)を世に送りだしました。コロナ禍でニューヨークが完全にロックダウンされた折に執筆したものです。
執筆にあたっては自分の過去に行った研究成果を、かなり引用しました。ここで公開する学術論文もそのひとつです。
noteではこれを含めて二つの論文を公開していますが、いずれも私が大学院にて客員准教授、日本総合研究所にてスペシャル・アカデミック・フェローを勤める、武蔵野学院大学の研究紀要で発表されました。
今回公開する論文は、『「宇宙の音楽」を聴く』第1章~第3章第1節を執筆するにあたっての土台になったものです。熱心な読者の皆さんへの便宜をはかるため、大学側に転載許可をもらったうえで全文を公開しています。(読みやすさを考慮して、一部で改行など表記法の変更を加えましたが、本文そのものは紀要掲載時のままです)
ただし、論文はある程度の専門家を読者として想定しており、学術的な厳密さを重視した硬い文章ゆえに、たいへん読みにくいです。講演や著作における私のいつもの調子とは落差が激しいことはご諒解ください。
論文タイトル&キーワード
科学革命における西洋音楽理論の脱呪術化
伊藤 玲阿奈
The Disenchantment of Western Classical Music in the Scientific Revolution
Reona Ito
【キーワード】科学革命 近代合理主義 デカルト ラモー 音楽理論 機能和声
1.はじめに
1.1 本論文の目的
16~17世紀に進展した科学革命は、西洋古典音楽(クラシック音楽)の音楽理論にも決定的な変化をもたらした。この小論では、近代合理主義の祖であるルネ・デカルトに特に注目しながら、実際にどのような変化が起こったのかを総合的に記述することを目指す。そして、そこからどのような意義が見出されるのか、筆者なりの見解を呈示することになるだろう。
1.2 混乱を招きやすい術語について
本論の前に、重要な術語の中でも読者を混乱させる恐れがあるものについて、先に説明を加えておく。
まず「科学革命」について。
本稿では、クーンに提唱された通約不可能性で特徴づけられる有名なパラダイム(ただし後期クーンにおいては「専門母型」の術語があてられる)の転換による科学革命ではなく、コイレによって提唱されバターフィールドが歴史概念として定着させた方を一貫して指す(注1)。すなわち、英語では常に定冠詞を伴い “The Scientific Revolution” と表記される、およそ1550年から1700年の間に知の方法が大きく変貌を遂げて近代科学が成立した事象である。その定義については後述する。
「自然学 physica」(もしくは「自然哲学 philosophia naturalis」)も現代人が混乱しやすい概念だ。
科学革命期において、現在の自然科学にあたるものは「自然学」「自然哲学」呼ばれており、哲学の一分野であった。科学革命によって誕生した新しい自然学に対して、単に知識を意味したラテン語の scientia を充てるようになったのは後世である。したがって、コペルニクスもニュートンも自らを「哲学者」と任じていた。「科学者」の語の登場は1834年まで待たなければならない(注2)。
科学革命前の古い自然学の基礎になったのはアリストテレスによる自然学体系である。彼は、この世界のすべての存在物はいくつかの元素 elements から成り立っていると考える。月下(地上)界は火・空気・水・土の四大元素、そして天上界はエーテルと、全部で5つの元素がある。そして、火なら “熱い” 、水なら “冷たい” のように、それぞれの元素に固有の性質を措定した(注3)。ここから、それを引き継いだ中世のスコラ哲学では、物質や諸現象をその性質に還元することで物理現象を説明することが盛んに行われたのである(注4)。
しかし、肉体を動かす力のように、どの性質にも還元できない現象については「qualitas occulta(“隠れた性質”・occulta は「隠された」の意)」として、自然学の範疇からは除外された。また、天然磁石が鉄を引き寄せる磁力といった、感覚不可能な現象一般も occult と呼ばれる(注4)。
このようなアリストテレスに依拠したスコラ学に由来する「オカルト」の定義は、現代のそれと違うので注意せねばならない。本稿においても「オカルト」はこのスコラ的定義に従う。オカルト思想 philosophia occulta は科学革命期にスコラ哲学が否定されるとその存在意義を失い、新しい自然学(近代科学)によって吸収され、それが発展するにつれて現在のような軽蔑的なニュアンスの言葉に変化することになった。
ここに筆者が「脱呪術化」というマックス・ウェーバーの有名な術語を使用する理由がある。音楽理論においても、中世末期からルネサンスを経て科学革命期と進むにつれて、「宇宙の音楽」に代表される超感覚的な qualitas occulta の要素が排除されたからである。無論、“音楽の脱呪術化”とは象徴的な用法であって、その実質的な意味は、ウェーバー本人の言による「(世界を)主知化し、合理化する」という定義に準じている(注5)。
また、「ハルモニア」「調和」「ハーモニー」「和声」は基本的には同義であるが、前二者は古代からの形而上的宇宙論的音楽観に基づく広義の意味で、後二者は実際に鳴り響く音の集積という現在使われている狭義の意味で用いる。
以上を了解して頂いたうえで、本論へと移りたい。
2.前史
最初に、科学革命による変化を明示するために、それ以前の音楽理論について簡潔に振り返ることから始めよう。
2.1 古代・中世(14世紀まで)
天動説の完成者であるプトレマイオスは、『ハルモニア論 Harmonica』を著し、古代のさまざまな音楽理論を集大成した人物でもある(注6)。
しかしながら彼は、師アリストテレスの衣鉢を継いで経験主義的音楽理論の祖となったアリストクセノスを痛烈に批判し、数を真実在とするピタゴラスの思弁的な音楽理論を支持していたため、『ハルモニア論』の第1巻と第2巻において彼は、音律や音程など音の響きに関して数比をもって処理する姿勢を貫き、さらに第3巻では音楽と霊魂や諸天体の対応関係までが考察され、ハルモニアの本質へ形而上学的に迫ることになった(注7)。
古代から中世の変わり目に書かれたボエティウスによる『音楽教程 De institutione musica』は、プトレマイオスの形而上学的解釈を受け継いで、非常に有名な音楽の三区分――「宇宙の音楽 musica mundana」「人間の音楽 musica humana」「道具の音楽 musica instrumentalis」――を確立する。
このうち「宇宙」と「人間」は理性でのみ把握できる“聴こえない”音楽で、その原型はプトレマイオス『ハルモニア論』の第3巻にある。実際に鳴り響く音楽は「道具の音楽」なのだが、これは最下位に置かれた。感覚より観念を優先させるピタゴラス-プラトン的伝統で、音楽とは宇宙の調和(ハルモニア)の真実について知的に考究する哲学と見なされており、演奏家は理論家(つまり哲学者)に劣後する存在であった(注8)。
ボエティウスは中世における絶対的な権威の一人として音楽理論に君臨する。オックスフォードやケンブリッジでは18世紀に至るまでリベラルアーツの授業で『音楽教程』が使用されたという事実からも、その影響力が推察できる(注9)。
しかしながら、中世末期、アリストテレスの “再発見” を準備した12世紀ルネサンスを境に変化が起こる。
この再発見によって、それまで知られていた論理学関連の著作に加えて、形而上学や自然学などアリストテレスの哲学著作の全貌が体系的に明らかになったことで、それを取り入れたトマスやオッカムに代表される盛期スコラ哲学が13~14世紀に花開いた(注10)。それに伴って、音楽理論でも感覚をより重視するアリストテレス―アリストクセノス的伝統が顕在化し始めたのである。
その代表的論客グロケイオ(c. 1255~c. 1320)はボエティウスの三区分法を否定、聴こえる音のみを音楽と考えるに至っており(注11)、国安洋はそれを「音楽概念のコペルニクス的転回」と称している(注12)。
それでも実践面を考慮すれば、マショーなど実際の14世紀音楽はピタゴラス以来の完全協和音程のみを認める作法で作曲されているので、ハーモニーの観点では古くからの理論がまだ有効だったといえる。ただし、リズムや記譜法に関してはヴィトリがアルス・ノヴァを創始したように、演奏実践に即した革新があった。
2.2 ルネサンス期(15~16世紀)
15世紀に入ると、イングランドでピタゴラス以来の理論では不協和音程とされる3度と6度の採用が始まり、デュファイらブルゴーニュ楽派によって大陸でもフォーブルドン fauxbourdon の和声テクニックとしてそれが常用されたことで、音楽理論とそれを支える音楽観(美学)に大きな変革が起こった。
バルトロメ・ラモス(注13)を例にとると、彼はピタゴラス音律では調子が外れてしまう3度・6度をいかに美しく響かせるか研究し、ボエティウスらが説くモノコードの分割法から離れた独自の分割法を考案した(注14)。
これに関してラモスは、主著の『実践的音楽Musica practica』(1482)において「(ボエティウスによる分割法は)有益で理論家を楽しませるものではあるが、歌手が理解するには面倒かつ困難である」(注15)ことが考案の動機であると語る。同時に、「鼠と像が一緒に泳げるような、ダイダロスとイカロスが一緒に飛べるような」(注16)理論と実践の統合を目指す立場を明確にしている。
また、15世紀の代表的理論家ティンクトーリス(c.1435~c.1511)の定義においては、音楽は「歌唱と楽器演奏とを熟知すること」、ハルモニアは「調和した音から生ずる甘美さ」とされるのである(注17)。
このようなルネサンス期の新しい音楽理論に共通しているのは、耳に心地よく響いてくる音そのものをハルモニア(調和)としてそれを追求する態度が見出せることで、長尾義人による「もはや中世の観念的・抽象的な音楽観から離れた、現象として体験されたものに即して獲得される知として音楽を捉えようとする姿勢」という指摘はまことに的確である(注18)。要するに、アリストテレス-アリストクセノス的伝統が理論・実践両面において優勢となったこと、そして実践が理論に優先するようになったことを意味する。
そのような経験・現実主義が台頭した一方で、15世紀に流行した神秘主義やオカルトへの傾倒(1.2参照)が音楽理論に与えた影響も見逃せない。
それらを流行らせた中心的人物の一人は、メディチ家に庇護されたプラトン・アカデミーのフィチーノである。プラトン全集やプロティノスなどの正統的な古典のほか、ヘルメス文書など神秘主義文献も彼によって翻訳され、キリスト教以前の旧約時代における古代の秘儀のように受け入れられた。そのフィチーノが1489年に著した『三重の生について De triplici vita』は人の健康をテーマにしており当時広く読まれたが、その内容は神秘主義・オカルト思想を含んでいる。特に第3巻では惑星の動き(占星術)が音楽や健康に与える影響が論じられており、16~17世紀において音楽の影響力について議論する上での基本資料となった。
また、先ほど触れたラモスにしても、『実践的音楽』で音楽の旋法・身体・惑星の関係について言及している(注19)。この傾向は科学革命期に入っても続き、この時期に重要な音楽理論書を書いたツァルリーノ・ケプラー・メルセンヌなどはすべて惑星と音楽を結び付けた考察を残した。
いずれにしても、このような考え方は現象から超越したところに真実在を措定する(新)プラトン主義と相性が良いのに対し、アリストテレスを基礎にした自然学に依拠する限りではオカルトとなる。それは経験・現実的な態度で理論と実践の統合を目指す新しい音楽の流れと矛盾するように見えるが、次の点を見逃してはならない。
第一に、当時の主だった音楽理論は大学や修道院で自由七学科を身に付けた教養人によって発表されている。とすれば、音楽における惑星や霊魂への言及は驚くに当たらない。自由七科のうちの数学的四科が算術・幾何・音楽・天文で、音楽と天文学は仲間であることを思い出せば、占星術にしても数学的操作に基づいた運命論であることは容易に察しがつくだろう(注20)。音楽を数で追求しつつ霊魂や宇宙にまで知を巡らすピタゴラス・プトレマイオス・ボエティウスの学統と基本的には同種なのだ(プトレマイオスは占星術でも業績を残している)(注21)。
そして、哲学と神学がすべての学問の上位に君臨しているから、形而上的な議論が当然付いてまわる。このような教育体系が続いていたわけだから、聴こえない「人間・宇宙の音楽」の伝統から急に完全に抜け出すことは困難であったろう。つまり、現代と変わらない音楽観へと徐々に変化していく移行期であり、音楽を宇宙の顕現とする解釈はもうしばらく生き残り、現象と体験から音楽を解釈する新しい態度と併存することになったのである。
第二に、超越者もしくは超越的現象への希求が結果として科学革命を進展させたという事実である。科学史家・中山茂が指摘する通り、何らかの科学的法則を発見するにも、眼前の現象と体験のみに囚われていると上手くいかないもので、現象の背後への想像力や好奇心こそが原動力となる(注22)。
ケプラーの第三法則が発表された『宇宙の調和 Harmonices Mundi』が最たる例で、その業績は、宇宙が調和的な数比に従って運動していると信じるケプラーがその信念を証明するため、真摯に研究に取り組んだ結果であることが伝わってくる。すなわち、経験的データを超越した存在を前提にしているのである(注23)。
以上をまとめれば、ルネサンス期は実際に鳴り響く音が音楽行為の対象として認められ、そこに快を求める感性が根付き始めた時代であって、現在の音楽観への転換期にあたる。3度・6度が不協和音程から不完全協和音程として処理されるようになったのを代表例に、リズム論や記譜法に遅れてハーモニー論にも変化を促し、音楽理論全体について思弁的性格が薄れていくことになった。古代文藝復興に伴った神秘主義やオカルトの流行など、プラトン的な形而上への志向は依然として残ったものの、それが形而下における諸現象への丹念な観察を重視する新しい潮流との(今の我々から見れば)奇妙な共存関係を築いた状態で、時代は科学革命期、すなわち近代へと突入するのである。
3.科学革命における音楽の脱呪術化 ~デカルトの重要性
科学革命については、自然に存在する対象物や自然現象の過程に対する操作、物質世界へ数学的手法を適用することによる計量・定式化とされるのが一般的である(注24)。しかし、先ほどケプラーの例で見たように、それだけでは業績を測れないことも多いため、「西洋における古代理論系から近代的な理論系への転換・交代という局面で規定される」とする村上陽一郎のやや緩やかな定義が妥当であろう(注25)。
近代的理論系とはすなわち近代科学であるわけだが、その理論的枠組みを作り上げた人物の一人がデカルトである。コペルニクスからニュートンに至る自然哲学者は科学の成立に貢献したとはいえ、それは主に実践面での業績が主であり、純粋理論(純粋哲学)を形成して発展を下から支えたという観点では、デカルトは最大の功労者であると筆者は考えている。また、デカルト座標の考案に代表されるように、実践面から見ても申し分ない。
本章では、デカルトが近代合理主義を確立して、科学の理論的枠組みの祖となった哲学史的な経緯は既に周知の通りであるので詳しく触れず、彼が音楽理論に与えた影響について論述する。なぜなら、デカルトこそが音楽理論の分野においても近代を開始した人物だからである。
3.1 『音楽提要』にみる音楽理論家としてのデカルトの革新性
デカルトの処女作が音楽理論であることは専門家を除いてはあまり知られていない。22歳の彼が執筆した小論『音楽提要 Compendium Musicae』がそれである。この小論が「音楽の目的は快を与え、我々のうちに様々な情緒をひき起こすことである」(注26)という一文から始まることに端的に示されているように、デカルトもまたルネサンス期に起こった新しい態度を保持している。ただし注意すべきは、デカルトの場合はそれが独自の構想に基づいていることである。
デカルトが21歳の時、アリストテレスを否定し、数学を使って自然学を探求するアイディアの持ち主だったベークマンと出会い、知的影響を受ける。「[デカルトはこれまで]数学と自然学とを緊密に結合した人に出会わなかったということである」(注27)と、ベークマンは誇らしげに日記に書いている。
さて、『方法序説』第1部での回想から分かる通り、若き日のデカルトはそれまでのスコラ学では真理探究の基準・方法としては不十分であることを憂い、確実な学問の基礎付けを遂行することを生涯の目標と定めていた。それを果たすうえで彼が用いたのが数学である。誰にでも直観的に把握可能なその明証性ゆえにデカルトはラ・フレーシュ学院に在籍していた最初期から数学、特に幾何学を愛した。そして、直観的明証性をもつ幾何学、数の代わりに文字列で方程式を構成する代数学、そして文字の規則である論理学の三つを統合してすべての事象を計量的に説明する普遍数学を構想し、それは後にデカルト座標の解析幾何学として結実することになる(注28)。
このような数学と自然学を合体させようとするベークマンの影響下でこの時期に手掛けた研究の一つが「弦の振動とその法則における比例的調和」で、それがリズムと音律について論じた『音楽提要』へと発展したのである(注29)。その意味することは、いくら音楽の目的を快と定めていても、あくまでもそれは知的な感動として捉えられており、数学的根拠による論証が可能であることを前提としているということだ。実際に、まずは快の原因を数的比例関係に還元したうえで、それを音楽に適用していく形で論証を進めている。しかも、音楽によって惹起される快すなわち情緒に対して、デカルトは抑制されるべきものとして否定的な見解を持つ(注30)。
したがって、デカルトの音楽論をバロック音楽における情緒説の基礎とする通説は表面上では間違いないにせよ、その本質には音型を幾何学的に捉えるハンスリックのような近代の形式主義音楽美学に通じるものを内包しているのであり、そこにそれまでに無かった革新性が見られることは佐々木健一が指摘する通りである(注31)。また、国安洋のように、響きの甘美さではなく、快(=情緒・感情)を音楽の目的に据えたことから、近代感情美学の祖とする見方もある(注32)。
以上から、デカルトは音楽理論家としては相対的に知られていないが、実は彼が最初に達成した歴史的業績はこの分野にあることが分かる。すなわち、スコラ学に代わる新しい学問の基礎付けを目指した普遍数学の構想による“数学-自然学”の音楽への適用、そして感情(快)を音楽分析の表舞台へと引き出したことである。これらはもちろん前節で記述したルネサンス期音楽理論家の基本的態度を踏襲したうえでの革新であって、デカルトの天才は若年時から発揮されていたことを再確認させてくれるものだ。
3.2 音楽理論におけるデカルト哲学の射程
次に、デカルト哲学全体が音楽理論に与えた影響を俯瞰してみよう。
デカルトがスコラ学に代わる新しい学問体系を根拠づけられる確実な原理としてコギトを据えたことから、彼以降の哲学の主流は、人間の意識を分析することでいかに世界についての知識を得られるのかを研究する認識論へと移ったことは哲学史の常識である。そして、彼が考案した明証性・分析・総合・枚挙からなる「四つの規則」に従って、客体たる世界への“数学―自然学”を適用する(普遍数学または普遍学の構想)ことから近代科学は始まる。
要するに、主観(コギト)と客観(世界)の一致が問題になるのがデカルト以後の近代哲学であって、客観性を求められる現在の科学や学問の体系にしても基本的にはこの路線に沿っているのだ。
さらにデカルトにおいては、存在を精神と物質に分ける二元論のもと、すべての物質世界は機械であるとする機械論的自然観が展開される。物質は延長として定義され、精神は世界に居場所を持たない。コギトはまったく純粋な知性であり、この三次元の世界に“存在しない存在”になってしまうのである。このような物質と精神の峻厳な区別はデカルト哲学最大の欠陥であるとはいえ(心身問題)、それによって物体の背後に“隠れた”性質すなわちqualitas occultaを消滅させ、古い自然学では説明のつかなかった“オカルト問題”を克服することには成功した(注33)。
このようなデカルトの理論は科学革命の純粋哲学的支柱となり、自然に存在する対象物や自然現象の過程に対する操作、物質世界の数学による計量・定式化を躊躇なく推し進めることに貢献する。科学の名のもとに、あらゆる現象が数字や物理法則へと還元 reductionされる習慣がここから始まったのである。
それは当然ながら音楽理論を根本から変えるように作用した。音楽が客体として数量的・即物的に捉えられるようになると、それが主体にとってどのように作用するのか、どのような意味を持つのかが問題になるからだ。ここに、人間の感覚(経験)に信頼を置かずとも、神から与えられた理性で音楽を追求していれば良しとされる時代は完全に終わりを迎えるのである。代わりに、感官を通じた音そのものを分析して、その作用と意味を追求するのが音楽理論家の仕事になっていく(注34)。
言いかえれば、鳴り響く音楽を客体として要素還元の対象とする態度であり、器楽のみを対象としていたデカルトの『音楽提要』はその象徴といえる。ここにバロック期以降の器楽の発展や絶対音楽概念の萌芽を見ることは間違いではあるまい。(彼の音楽観に形式主義的美学が内包されていることは既に述べた。)
以上みたように、科学革命期において近代科学の理論的祖型を構築したデカルトは、音楽理論においても、フィチーノやケプラーが固執した「惑星の音楽」のごとき神秘主義やオカルト思想の痕跡を消し去ることに貢献し、客体としての音響の合理的記述への扉を開いた。すなわち、「近代哲学の父」は「クラシック音楽の脱呪術化の父」としても位置づけることができるのである。
3.3 その後の脱呪術化の進展
そのようなデカルトの遺志を継いで、音楽の脱呪術化を理論面で決定的にしたのがジャン=フィリップ・ラモーである。
18世紀前半から中盤にかけて理論書を次々と発表したラモーは、当時ソヴ―ルによって発見されたばかりの倍音音列(注35)を観察して、1)長三和音は比例計算ではなく自然に基づくこと、2)オクターブの音を同一と見なし、和音の転回形の概念を提起したこと、3)根音バスを提唱し、音楽分析の基礎となる和音連結の法則を明らかにしたこと、などの理論的発見を成し遂げた(注36)。これをもって近代和声学がスタートする。
ラモーがデカルトの影響を受けていることは、同時代人の指摘がある(注37)。それは、観察される自然倍音をもとに音楽現象を数学的に記述・証明しようとする姿勢(“数学-自然学”)によく表れているし、ラモーの理論書の中で最も重要な1722年に書かれた通称『和声論』の正式名称は『自然の諸原理に還元された和声論 Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels』で、「還元」の語が使われていることからも如実に伺われる。音響における経験データの複雑な集合体を、自然(倍音)の法則に支配される合理的な体系にまで還元した理論という意味だから、まさしくデカルトやニュートンそのままである(注38)。科学革命期の新しい自然学の手法が音楽理論にもたらした変化を教えてくれる好例といえよう。
何はともあれ、このラモーの発見が世界で他に類例のない調性音楽の隆盛を促し、それが19世紀末にリーマンによって機能和声論として体系化されて、現在でも全世界の音楽学校における楽理教育の雛形となった(注39)。少なくとも音楽理論上は(調性音楽である限り)譜面の上にあるすべての音符に対して一定の客観的な説明が可能になったのである。
こうしてみると、西洋音楽理論の脱呪術化は、科学革命期にデカルトから始まり、ラモーによって決定的な一歩を踏み出し、リーマンによって完成したとみて良いだろう。
4.意義
世界史をみると、自然を加工する思想・技術を進展させた科学革命期を境として、西洋文明は地球上の他の文明を圧倒し始める。それは19世紀から20世紀にかけての帝国主義において、力による征服としての圧倒がピークを迎えた。しかし、科学技術、政治、軍事による征服だけではなく、文化面における浸透力も同様であった。
たとえば我が国では、明治12(1879)年に音楽取調掛を設置した時から西洋クラシック音楽の受容がスタートするが、明治20(1887)年の東京音楽学校への発展的解消を経て、そのわずか15年ほど後には滝廉太郎という天才を輩出している。しかも、明治45/大正元(1912)年には、山田耕筰が日本人最初の交響曲『勝鬨と平和』を作曲し、当時の西洋人職業作曲家にまったく劣らない作品に仕上がっているのである。
これはまぎれもなく、クラシック音楽というものが当時すでに万人が学ぶことの出来る合理的な体系となっていた証左として重要だ(時代としてはリーマンによる機能和声論の確立期にあたる)。だからこそ、遥か極東の島国においてもクラシック様式に基づいた独自な音楽が生まれるし、島国からの留学生もきちんと理論を消化すればそれなりの作品を仕上げることが可能になる。
もしもクラシック音楽理論が、科学革命期以前のようにキリスト教神学と結びついた非合理的かつ形而上的なままであったなら、このような事態にはならなかったであろう。デカルトの『方法序説』冒頭で宣言されている通り、理性(原文では「良識 bon sens」)は民族・人種・宗教などの相違に関係なく、人間であれば誰しも平等に与えられている。そして、その理性を用いつつ共通の手続きを踏んで、誰でも同じ答えへとたどり着くものを客観として正解とし、それを求め続けるのが近代合理主義や科学の土台なのだ。
理論や美学の点で合理化を経たクラシック音楽も同様である。家元制度や口伝などが残る日本の伝統芸能においては、いまだ外国人による一流を輩出していないことと比べると、この意義がより明確になろう(もちろん、そのことが悪いなどと価値判断をしている訳ではない)。現在のクラシック音楽界は東アジア人抜きでは考えられず、最近ではムスリム圏からも世界に通用する音楽家を生み出し始めた。ここに、科学革命期に端を発する脱呪術化の大きな今日的な意義があるのである。
注
1 野家啓一 (2008) 『パラダイムとは何か』講談社学術文庫 p. 316 ~ 317
2 村上陽一郎 (2010) 『人間にとって科学とは何か』新潮選書 p. 14 ~ 15
3 アリストテレス『天体論』の第4巻に詳しい。
4 Millen, R. (2002) The Manifestation of Occult Qualities in the Scientific Revolution. Osler, M. J., & Farber, P. L. (Eds.), Religion, Science, and Worldview: Essays in Honor of Richard S. Westfall (Edition 1), Cambridge University Press. p. 185 ~ 187
5 ウェーバー, M. (1999) 『職業としての学問』(尾高邦雄訳)岩波文庫 (1919) のp. 33を参照。なお、ウェーバーは「脱呪術化」を宗教社会学においては別の特別な意味で使用するが、ここでは1919年の有名な講演で示された主知主義的合理化という一般的な意味で用いる。濱島朗ほか編『社会学小辞典 増補版』有斐閣双書 (1983) の「呪術」及び「呪術からの解放」の項も参照せよ。
6 津上英輔 (1997) 『諸天体の構造的調和 プトレマイオスの宇宙調和論』 今道友信[編]『精神と音楽の交響 西洋音楽美学の流れ』所収 音楽之友社 p. 48
7 津上 前掲書 p. 49
8 国安洋(1981)『音楽美学入門』春秋社 p. 190 ~ 195
9 Gouk, P. (2002) The Role of Harmonics in the Scientific Revolution. Christensen, T. (Ed.), The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge University Press. p. 225
10 伊藤邦武(2012)『物語 哲学の歴史』中公新書 p. 92 ~ 94
11 椎名亮輔[編著]三島郁・筒井はる香・福島睦美[著](2017)『音楽を考える人のための基本文献34』アルテスパブリッシング p. 83 ~ 89
12 国安 前掲書 p. 197
13 本稿ではBartolomé Ramos de Parejaの綴りに従ったが、文献によってはBartolomeo Ramis de Pareiaとも綴られている。また、生年を1440年頃とするのは全文献で一致するが、没年は1491・1522・c.1500など一定しない。
14 グラウト, D. J. & パリスカ, C. V. (1998) 『西洋音楽史 上巻』(戸口幸策・津上英輔・寺西基之共訳)音楽之友社 (1996) p. 203
15 Herlinger, J. (2002) Medieval Canonics. Christensen, T. (Ed.), The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge University Press.のp. 178に所収されたC. A. Millerによるラテン語から英語への抄訳を筆者が日本語へ訳した。
16 Christensen編による前掲書のp. 7に所収されたC. A. Millerによるラテン語から英語への抄訳を筆者が日本語へ訳した。
17 椎名 前掲書 p. 99
18 長尾義人(2004)『近世人文主義の音楽論』根岸一美・三浦信一郎[編]『音楽学を学ぶ人のために』所収 世界思想社 p. 38
19 Gouk 前掲書 p. 226
20 中山茂(1992)『西洋占星術 科学と魔術のあいだ』講談社現代新書 p. 148 ~ 150
21 中山 前掲書 p. 54 ~ 63
22 中山 前掲書 p. 149 ~ 151
23 村上陽一郎(1986)『近代科学を超えて』講談社学術文庫 p. 29 ~ 30
24 Gouk 前掲書 p. 224
25 村上 『近代科学を超えて』 p. 33
26 国安 前掲書 p. 205
27 伊藤勝彦(1967)『デカルト 人と思想11』清水書院p. 31 ~ 32より。ただし本書の原文では「数学と物理学」となっていて、後者はおそらくphysicaの訳だろうが、ここでは「自然学」の訳が適切であることは1.2からも明らかなので、筆者の判断でそのように変更した。
28 伊藤勝彦 前掲書 P. 43 ~ 44 もしくはデカルトの『方法序説』第2部か『規則論』第4部を参照。
29 伊藤勝彦 前掲書 p. 32
30 国安 前掲書 p. 205 ~ 206
31 佐々木健一 (1997) 『耳から知性の音楽 デカルトにおける美と音楽の快』 今道友信[編]『精神と音楽の交響 西洋音楽美学の流れ』所収 音楽之友社 p. 154 ~ 155
32 国安 前掲書 p. 205
33 伊藤勝彦 前掲書 p. 146
34 椎名 前掲書 p. 60 ~ 66
35 Green, B. & Butler, D. (2002). From Acoustics to Tonpsychologie. Christensen, T. (Ed.), The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge University Press. p. 249
36 アラン, O.(1969)『和声の歴史』(永富正之・二宮正之共訳)白水社(1965)p. 79 ~ 81
37 Paul, C. B. (1970). Jean-Philippe Rameau (1683-1764), the Musician as Philosophe. Proceedings of the American Philosophical Society, (Vol. 114 No. 2) p. 140
38 Lester, J. (2002). Rameau and Eighteenth-Century Harmonic Theory. Christensen, T. (Ed.), The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge University Press. p. 759
39 『標準 音楽辞典』(1966)音楽之友社 「和声学」の項より p. 1453
主要参考文献(上記以外)
デカルト, R.(1997)『方法序説』(谷川多佳子訳)岩波文庫(1637)
本論文の初出
武蔵野学院大学日本総合研究所研究紀要《第17輯・2020》p. 207~215・大学側の転載許可済み
執筆者プロフィール:伊藤玲阿奈 Reona Ito
指揮者・文筆家。ジョージ・ワシントン大学国際関係学部を卒業後、指揮者になることを決意。ジュリアード音楽院・マネス音楽院の夜間課程にて学び、アーロン・コープランド音楽院(オーケストラ指揮科)修士課程卒業。2008年のプロデビュー以降もニューヨークを拠点に、カーネギーホールなど各地で指揮。2014年「アメリカ賞」(プロオーケストラ指揮部門)受賞。武蔵野学院大学客員准教授。2020年11月、光文社新書より初の著作『「宇宙の音楽」を聴く』を上梓。タトル・モリエイジェンシーのnoteで『ニューヨークの書斎から』を連載。
いいなと思ったら応援しよう!

