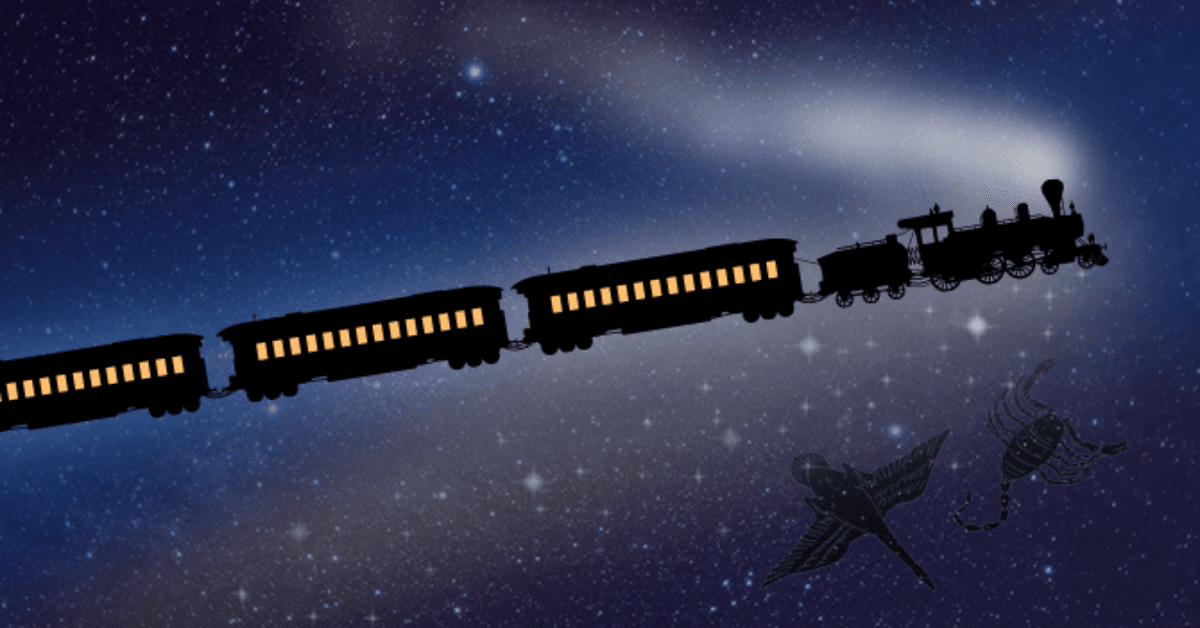
【いつかの夜】 短編 黒田 勇吾
あの年の冬はこの街にも初雪が12月に降った。
いつもの年なら、1月になってから降ることが多かったのだが、なぜあの年は早かったのだろう。
12月の24日のクリスマスイブの日、僕は仕事を早めに片づけて、会社から駅の近くのデパートに走った。と言ってもすでに午後の6時をまわっていて、空を見るともう真っ暗で、星も見えない。おそらく冬雲が垂れ込めていているのだろうが、何かの前触れを告げるようにやけに静かだった。予約していた君へのプレゼントを混雑しているレジで受け取ると、近くの駅から電車に乗った。20分ほど乗っていつもの駅で降りて改札通りを抜けて、北口に出て、繁華街を通りすぎた。街は煌びやかに光り輝いてにぎやかだった。音楽が鳴り、店店に飾り付けの光が虹のように眩しく輝いている。
すれ違うみんながどこかに急ぎ足で歩いているようだった、ぼくと同じように。
風が時折吹いて、その冷たさは耳を痛くさせたが、
背広の襟元のマフラーが暖かだった。それは先週君が編んでくれたばかりのものだった。左手に持った少し重たいプレゼントは、いつか君があのデパートに行った時、これいいわね、と何気なく呟いてたことを覚えていて、買ったものだった。手袋を今日は忘れてきたので、両手に冷たい風が当たり、冷えてきた手が痛くなるほどだったが、あまり気にならない。
左側に線路を見ながら、あと五分ほどで家に着くことが何故かもったいない気がして、ゆっくりと歩き始めた。
一度だけ電車が通っていった。見るとたくさんの人を乗せた電車も何故かゆっくりと走っているように思えた。
その電車が通り過ぎたあとに、目の前にちらほらと白いものが流れ始めた。思わず空を見上げると、真っ暗な空の向こうから、転々と雪が落ち始めてくるのが、見えた。一粒が顔に当たった。電車が通り過ぎた後の静寂な道に、それはだんだんと数を増やして柔らかなスピードでそして音もなく降り落ちてくるのだった。少しずつ道路が白化粧をし始める。
初雪なんだ、何年振りだろう、イブの夜の雪。
立ち止まって空をゆっくりと見上げたかったが、やはり歩くことを止めずに踏切を左側に見ながら歩いた。その交差点の角を右に回って百メートルほど歩くと大きな白い屋敷の向こう側に僕らの住んでるアパートはあった。
階段を上って二階に上がり、玄関の扉の前に立って鞄を置いた手でいつものようにチャイムを3回鳴らす。そしてプレゼントを抱えてあらためてひとつ深呼吸をした。。僕はもちろん部屋の鍵を持っているのだが、それが僕が帰宅するときの君との約束事だった。チャイムは3回鳴らす。
30秒ほど待ってもいつものように君はドアを開けなかった。
おかしいな?と思って、ぼくはプレゼントの箱を置いて、カバンから部屋のカギを出して、ドアを開けた。中は真っ暗だった。急いで部屋の灯りをつけ、居間に入ると、部屋は片づけられて炬燵の上には何もない。
おそらく料理を作って君は僕を待っていると勝手に思っていた自分に腹が立ってきた。隣のダイニングキッチンのテーブルの上に、折りたたんだ小さなメモが、おいてあるのを見つけ、急いで開いてみた。胸の鼓動がせわしなくなった。
何も書いていない、、。
無言?何も告げることなくいなくなる?
よくわからない感情の中で、自分にいろいろと問いかけてみた。
別れるなんて気配は少しもなかったのに。
何でだろ?なんでなんやろ?
思いつくことが何も見当たらない。
僕はしばらくテーブルの側に立ち尽くしていたように思う。
携帯電話などがまだなかった時代だった。
そして、ふと思い出した。プレゼントを入り口に置いたままだった。
玄関を出ると、プレゼントの箱は地べたにおかれてそこにあった。まだよくわからない、という混乱の心が、乱れている。もう一度、玄関に入ろうとしたとき、しげさん、おかえりと階段を上ってきた君の笑顔が見えた。
「ごめん、今日私の仕事が遅うなって、ほんでもってデパートでとりあえずケーキとチキンだけ買うて今帰ったんや、ごめんな、おそうなったわ」
僕は玄関の前に立った君を抱きしめた。その拍子に僕の持っていたプレゼントが地面に落ちた。君はしっかりと抱えたケーキとチキンの入った大きな紙袋を右手に持ちかえて、ちょっと、ちょっと、どうしたん?と戸惑った笑みを見せた。
僕は何も言わずに君を抱きしめた。そしてなぜだかわからず、なみだが零れはじめた。そのままずっと僕は泣きながら君を抱きしめつづけた。雪が通路まで入り込んで降り始めて、風は強くなっていった。
~~了~~
花は咲き 花は散り 夢は散り ふたたび夢は咲く 2023年12月07日夜
