
2025年から始めるWeb3の基礎—初心者向け完全ガイド
こんにちは、りかる(@recal.jp)です。
私は、普段Instagramやこのnoteを中心に、より豊かな生活に役立つ情報を毎日発信しています。
最近では、QOL向上のため、新しいテクノロジー
(Web3 / NFT / メタバース / AR,VR / AI)などについてご紹介しています。
<私がWeb3について学ぼうとしたきっかけ>
私のWeb3の入り口は、NFTの売買から始まりました。
NFTを売買していると、インターネットの発展と共に、誰もがクリエイターとして価値を生み出せる時代が到来してきたと感じています。
近年話題になっているブロックチェーン技術や、Web3.0の概念が普及してきたことにより、クリエイターがファンから直接報酬を受け取れる仕組みを形成できたり、ファンとのコミュニケーションがより密になるなど、さまざまな可能性が開かれ始めています。
インターネットが出た時もそうでしたが、世の中に新しいテクノロジーが生まれる時は、怪しいと思われて使われなかったりするものです。
いまWeb3は、そういう意味で「新しい時代の入り口」に立っている状況といえるかもしれません。
まずは「知らないことを知る・勉強する」ということから学びが深まります。
この記事ではWeb3について、初心者にも分かりやすく解説しています。
学びがあった、気づきがあったという方はスキ、フォローで応援よろしくお願いいたします。
Today's technology and web3?
「2025年から始めるWeb3の基礎—初心者向け完全ガイド」
Web3(ウェブスリー)は、インターネットの新しい形として注目を集めています。
特に、ブロックチェーン技術を基盤とした分散型の仕組みが特徴です。
年末年始のゆったりとした時間を活用して、Web3について学び始めるのは理想的なタイミングです。
本記事では、Web3の基本的な概念から実際の活用方法まで、中学生にもわかりやすく解説します。
Web3とは?
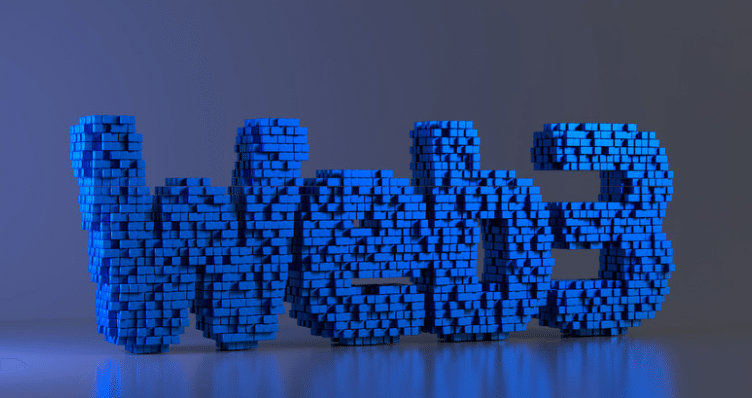
Web3は、インターネットの次世代モデルと考えられています。
現在のインターネット(Web2)は、GoogleやFacebookなどの企業が中心となって運営されていますが、Web3では「分散型インターネット」がキーワードになります。
Web3の特徴:
分散型の仕組み
データは一箇所に集中せず、複数のサーバーやネットワーク上で管理されます。ブロックチェーン技術
ブロックチェーンはデータの改ざんが難しいため、高い信頼性があります。ハッキングするのが難しい。ユーザー主導のエコシステム
中央管理者がいないため、ユーザー自身がデータや資産をコントロールできます。
Web3で使われる技術
Web3の世界を支える重要な技術について紹介します。
これらの技術を知っておけば、あなたもWeb3の理解が深まります。
1. ブロックチェーン

ブロックチェーンは、取引データを記録する技術です。
すべてのデータは「ブロック」として保存され、改ざんが難しい仕組みになっています。
例えば、ビットコインやイーサリアムといった仮想通貨がこの技術を利用しています。
2. スマートコントラクト

スマートコントラクトは、契約内容をプログラムで自動実行する仕組みです。
例えば、売買やレンタルの条件が満たされると、手動操作なしで取引が完了する仕組みです。
3. NFT(非代替性トークン)

NFT(非代替性トークン)は、デジタルデータに唯一無二の証明をつける技術です。例えば、絵や音楽、動画といったデジタル作品に「これが本物で、所有者は誰か」を証明する役割を果たします。
これにより、アートや音楽がデジタル資産として認められ、取引が可能になりました。従来、インターネット上のデータは簡単にコピーできましたが、NFTを使うことでそのデータがオリジナルであることを保証できます。
NFT市場は急成長を遂げており、デジタルアートだけでなく、ゲーム内アイテムやスポーツの記念品など、さまざまな分野に広がっています。
Web3を学ぶメリット
1. 新しいスキルが身につく
Web3関連の技術や知識を学ぶことで、未来のキャリアに役立つスキルを得られます。その中でもプログラミング開発やデジタル資産管理など、実用性の高いスキルが人気です。
2. 自己管理の意識が高まる
Web3では、自分の資産やデータを自分で管理することが基本です。これにより、セキュリティやプライバシーへの意識が自然と向上します。
3. 未来の技術を先取りできる
Web3はまだ発展途上の技術ですが、今から学ぶことで先行者利益を得るチャンスがあります。
Web3を始めるためのステップ
Web3を効率よく学ぶために、以下のステップを試してみましょう。
ステップ1:基礎を学ぶ
Web3の基本用語や技術について調べましょう。無料で学べる動画や記事、オンラインコースが多数あります。
おすすめリソース:
YouTube(「Web3 入門」で検索)
無料オンラインコース(CodecademyやUdemyなど)
ステップ2:ウォレットを作成する
仮想通貨やNFTを管理するためのウォレットを作成します。初心者には「MetaMask」がおすすめです。
ウォレットを作ったら、少額の仮想通貨を購入して送受金の仕組みを体験しましょう。
ステップ3:実際にWeb3サービスを使ってみる
NFTマーケットプレイス(例:OpenSea)でデジタルアートを見たり、分散型アプリ(DApps)でサービスを試してみましょう。
ステップ4:興味のある分野を深掘りする
NFT、DeFi(分散型金融)、メタバースなど、自分が興味を持った分野をさらに詳しく学びましょう。
学ぶ際の注意点
セキュリティを最優先に
仮想通貨やNFTはハッキングの対象になりやすいので、パスワード管理やウォレットのセキュリティを徹底しましょう。無理な投資をしない
初心者は、まず学ぶことを優先し、少額の取引から始めましょう。信頼性のある情報源を利用する
怪しい情報や詐欺プロジェクトには注意が必要です。公式サイトや信頼できるプラットフォームを活用してください。
まとめ
年の始まりは新しいスキルを身につけるのに最適な時期です。
Web3を学ぶことで、未来の技術を先取りし、自分自身の可能性を広げることができます。
ブロックチェーンやNFT、スマートコントラクトなどの基本を押さえ、少しずつ実践していきましょう。
2025年には、Web3がさらに身近なものとなり、あなたの知識が役立つ場面が増えるはずです。今から学び始めることで、Web3の未来を一緒に築いていきましょう!
[PR] What is ZEXAVERSE ?
私はWeb3業界を盛り上げようと、Web3のパイオニア「ZEXAVERSE(ゼクサバース)」のPRをしています。
「ZEXAVERSE TOKYO(ゼクサバース トウキョウ)」では、精巧な3Dスキャン技術によるリアルな3DアバターNFT発行サービスが実体験できる「ゼクサゲート」はじめ、メタバース&NFTの最先端を体験できます。
ZEXAVERSE TOKYO(銀座マロニエゲート内にて)
・国内最大級のメタバース&NFT体験型店舗を運営。
・ZEXAGATE、KATWALK mini S(キャットウォークmini S)、
NFT Counter(NFTカウンター)、Scan Studio、VRゴーグル販売など、メタバースやNFTを最大限体験できるサービスを提供しています。
詳しくはこちらの記事にまとめていますので、ご覧ください。
ZEXAVERSE TOKYO(ゼクサバース トウキョウ)でオリジナルメタバース空間や独自のNFT発行サービスが実体験できる国内最大級のメタバース&NFT体験型店舗の記事なども書いています。
最後までお読みいただきありがとうございます。
これからも心の赴くままに、志高く生きたいと思います。
そして、関わってくださったすべての方に、感謝する気持ちを忘れず自分の人生を突き進みます。
また次の記事でお会いしましょう☺︎
いいなと思ったら応援しよう!

