
『人之彼岸』レビュー
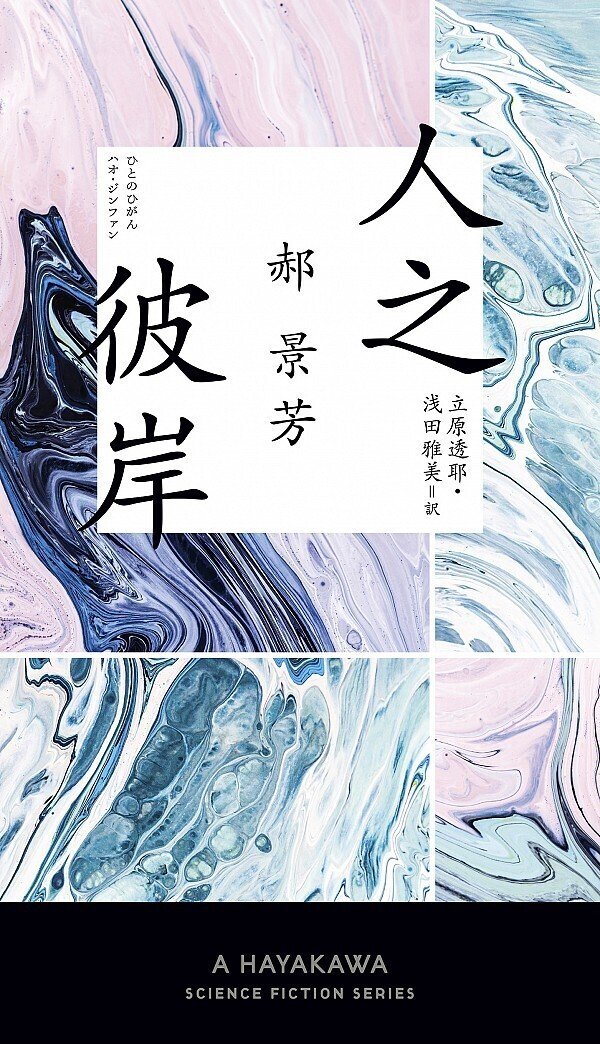
『人之彼岸』(ひとのひがん)
郝 景芳(ハオ・ジンファン)(著)/ 立原透耶・浅田雅美(訳)
◇
『折りたたみ北京』で、『三体』に続いてヒューゴー賞を中国SF界にもたらした郝 景芳(ハオ・ジンファン)さんの短編集です。
彼女は1984年に天津市で生まれ、清華大学で天体物理を学び、その後、経営学と経済学の博士号を取得。なるほど『折りたたみ北京』の著者らしいプロフィールです。けしてどっちつかずではなく、理系と文系の両方を専門にしている作風が素晴らしい。
境界線があいまいで、純文学のようであったりSFであったり、思考実験であったりする「作品」たちが良い感じです。
この本には、そんな彼女の書いた、主にAI関係の短編6編と、エッセイが2編収録されています。
まずは、AIについての興味深いエッセイが二本。
どちらも、SF作家がAIについて質問されるような内容が的確に書かれています。内容を一言レビューしますと……
エッセイ
・『スーパー人工知能まであとどのくらい』 浅田 雅美/訳
アルファ碁についての解説から、今後「スーパー人工知能」が生まれるまではどれだけの進歩が必要か。といった、よくある内容ですが、これがまたとてもうまくまとめられていて非常にわかりやすく書かれています。
・『人工知能の時代にいかに学ぶか』 浅田 雅美/訳
こと学習に関してはAIのほうが人間よりはるかに優秀で高速です。そんな時代に、人間の子供はどう学習していったらよいのか? という、学校に通う子供を持つ親御さんは興味ありまくりの内容じゃないかしらんとおもいます。
どいうかんじ。
この二本のエッセイで気に入ったポイントは沢山ありますが、特によかったのは、この二本目83ページあたりに書かれている
一般的に、子供を人工知能と比較すると、次のような特別な長所がいくつかある。
・ 一部で全体を総括する
・注意力が散漫になる
・飽きる
・間違う
・感情に依存する
・逆らう
という一文。これ、人間の子供が持っている長所なんですよねw
この後、なぜそれが長所かということをわかりやすく説明してくれています。これで、彼女がAIについてどう考えているかよくわかってきます。
そして、その後に収録されている6つの短編も、その考えを推し進めて書かれているというわけ。
では、続けてざっと、今度は短編小説の一言感想を書いてみますと、
短編
・『あなたはどこに』 立原 透耶/訳
AIによるエージェントシステム『分身』を開発している主人公、彼は彼女の服にも『分身』AIを仕込ませ、デートに遅れる言い訳をさせるのだが……。
・『不死医院』浅田 雅美/訳
死に瀕した母親が運び込まれたのは、末期の重病も治してしまうという高度医療病院。一切の面会を謝絶して謎の治療を行っているという、一目母親に会いたいと望んだ男はその病院の秘密に触れてしまう……。
・『愛の問題』浅田 雅美/訳
AI開発者の父と、早くに亡くなってしまった母と、その家にやってきたAI執事と息子(兄)と娘の関係性の話。世界のAI達が自発的に接続しているパルテノンというシステムの概念が面白い。
・『戦車の中』立原 透耶/訳
AIによる補助システムが組み込まれた戦車同士が出会い、相手の戦車に人間が入っているかを図霊測試験(チューリングテスト)するお話。
・『人間の島』浅田 雅美/訳
新天地となる惑星を見つけ、ブラックホールを潜り抜けて辛くも地球へ帰還した探査チーム。しかし地球では100年の時が過ぎていて、人類はゼウスというスーパーインテリジェンスに頼り切る生活をしていた。旧人類として時を超えてやってきてしまった彼らと新人類(+AI)の軋轢のドラマ。
・『乾坤(チェンクン)と亜力(ヤーリー)』立原 透耶/訳
世界を統べる万能AIと、三歳の少年の交流。かわいらしいお話。だいすき☆
◇
と、いうわけで、私としては最後の短編『乾坤(チェンクン)と亜力(ヤーリー)』がめっちゃお気に入り。かわいいんですよねーw
寓話めいたお話にもしっかりとスジの通ったAIに対する理解が背景として感じられてとてもよいかんじです。
この感覚、少なくとも私が感じたり想像しているAIと人間の未来に非常にマッチしていて、最初に書いたようにAIの未来について人に聞かれたら、まずはこの短編集を渡してあげようとおもいますw
そういえばこれ、短編集といいつつ表題作がありません。エッセイも入っているからでしょうか?
『人之彼岸』という、まさにAIと人間の未来に絡めたタイトルがハマる、そんな本なのでした。
※そして、このような本が一般に出版されるようになった中国のSF許容率の高さというか、テクノロジーに対する理解と豊かさが、正直「いいなあ」と感じてしまうのでありましたー。
―――
いいなと思ったら応援しよう!

