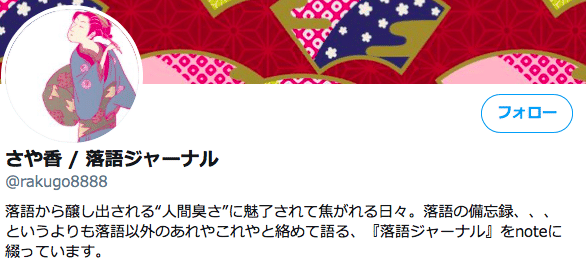落語はポップでもキャッチーでもない。
「さや香さんって“キャッチー”だけど“ポップ”ぢゃないよね」
と、以前とある人に言われたことがある。
ふーん。笑
「そだね!間違いナイトプ~ルぅ~っ!パシャっパシャっ☆」
とでも返しておけば、わたしに不足な“ポップ”は多少でも補うことができたのだろうか。
たしかに『EXIT』は“ポップ”で“キャッチー”だと思う。
カタカナ語故の定義の曖昧さは否めないものの、
『ポップでキャッチー』=『大衆ウケしやすいわかりやすいもの』
と考えれば、なるほど『EXIT』はその条件を満たしている。
「スキ、キライ」
「おもしろい、おもしろくない」
は完全に個人の好みの問題だからそこについて深く言及するつもりはないのだけども、彼らの今の人気ぶりをみたときに、“『EXIT』というパッケージ”は相当よく作り込まれているなと感心する。
アレは、“練りに練った戦略勝ち”なのだ。
かたや落語界はどうだろう。
そもそも落語自体がポップでもキャッチーでもない。
「いいえ、落語はポップでキャッチーなジャパニーズカルチャーよ!」
と言えちゃう人がいるならば、きっとその人は落語に相当詳しい“落語の内側”の人なのだ。
“落語の外側”の人からすれば、落語なんてバリバリにアンダーグラウンドのサブカルチャーである。
ヴィレッジ・バンガードもびっくりなサブカルっぷりである。
(そして、コロナ明けのヴィレバンはもっと落語コーナを拡大充実させて良いと思う)
「落語に少しは興味あるんだけど、どこからどう入っていいかわからないんですが。」
と思っている人々は物凄く多い気がする。
で、頑張って入ろうとしてみても、ちょっと入り方を間違えると、初めて末広亭を訪れたときのわたしのように春は訪れなかったりする。
“落語側”からしてみれば、
「寄ってらっしゃい!見てらっしゃい!いつでも誰でも大歓迎!ようこそ、ここへ!遊ぼうよ!パ・ラ・ダ・イ・ス♪」
くらいに、両手広げてウェルカムな精神で待っているものの、
“落語の外側”の人からしてみれば、
「友好的に両手広げて、ようこそ!とか言ってるクセに鍵付き貞操帯履いてるぢゃないかよぉっ!胸のりんごなんて剥けやしないよっ!」
くらいに、ガードの堅さ・・・というか“その向こうへ行き(イキ)にくいなにか”を感じるのだ。
落語は『能動的参加型芸術』である。
ゴレンジャーなどのヒーローショーやディズニーランドのジャングルクルーズもきっとこれに近い。
自発的に前のめりで関わっていかないと、楽しみを掘り起こせない。
噺家と観客とでその空間を完成させるという、かなり特異な『無形瞬間芸術』である。
そして、落語初心者がその世界に最初の一歩を踏み込むにあっても、かなりの積極性を要する。
先程“ガードが堅い”という表現を使用したが、言い方をかえてみると
“受動的な姿勢では簡単には必要な情報が入ってこない”
ということだ。
それこそまさに、落語がポップでもキャッチーでも無い所以である。
落語は浮き世のあれこれを題材にしておもしろおかしくストーリー展開をしてゆく話芸なのに、非常に浮世離れした世界で成立している。
そこも落語の不思議な魅力のひとつである。
が、やはり受動的詐取の構えでいる“落語の外側”の人からしたら“大衆ウケしにくいわかりにくい”世界である。
たとえば、“落語の外側”の人が、落語ににわかに興味を持ち始めた時に得る情報としての『演目一覧(ネタ帖)』なんて絶望的にわかりにくい。
落語ファンは自分が訪れた寄席のログとして記し、また演芸小屋や噺家は宣伝として配信し、オンライン上にも頻繁に漂っている情報のひとつである。
しかし、ある程度の演目と噺家さんを知らなければ、単純な文字の羅列としてしか認識できないから、
「“ブンナナモトユイ”って楽しいの?“コンヤタカオ”って美味しいの?“コトブキゲンナシ”ってラーメンズの持ちネタだよね?」
状態である。
また、演芸小屋もどこに行けばいいのか、特に首都圏の人は迷うかも知れない。
よくわからないから、まずは自分の家の近く寄席に行ってみようか、となる。
そして、
「そーいえば、『ガッテン!』の人は、ホントは『ペヤング』の人では無くて人気の落語家さんなのよね!もしかしたら、今日の寄席に出てくるかもしれないわ♪ワクワク!」
なんて思いながら、鈴本演芸場にいそいそと出かけてしまうかもしれない。
喜劇すぎる悲劇だ。
そんなこんなで落語界隈はいろんな事情が色々と細かくてわかりにくい。
「じゃあ、わかりにくいなら丁寧に説明いたしましょう!」
と張り切っている情報サイトや書籍もあるのだけども、いかんせんその量と煩雑さが災いして、受動的には吸収できない『読ませる情報』になってしまっているものが多い。
丁寧に説明しようとすればするほど、わかりにくさに拍車がかかるというパラドックス。
多分ここが関門となってなかなか入り込めないから、本当は“シンプルでわかりやすく面白い世界”であるはずの落語が難しい世界に感じられ敬遠されてしまうのだと思う。
明らかに、受動的な初心者には『見せる情報』が有効的である。
だからこそ『笑点』はお茶の間でウケたし、『EXIT』は若者の間でバズった。
やはり『アイコン的なわかりやすさ』というのは大衆の視線を集めるためには必要なのだ。
『EXIT』の秀逸な点はダーゲット層を『若い女性』に定めていることである。
OLブーム、女子大生ブーム、女子高生ブーム。
高度経済成長期以降、ブームの対象となったのも、またムーブメントを巻き起こしたのも、いつの時代も「若い女性」であった。
流行はいつの時代も若い女性から始まり拡散してゆく。そして若い女性に刺さると、必然的に老若男女に広がるように世の中の仕組みはできている。
そこにダイレクトに狙いを定めて発信された『EXIT』の“キャラ設定”“ネタの内容”“ワードチョイス”などは、林家ペーパー師匠の“視覚効果を狙ったピンクカラー”くらいに秀逸な正攻法なのだ。
(あ。だから兼近氏のヘアカラーはピンクなのかっ・・・!?←)
だから、昇々さんや鯉八さんのようなシュールな新作落語も「若い女性」に届けば、もっともっと盛り上がるのにと思う。
『ZAZY』がウケる時代なら、確実にもっとウケるハズ。
(あ。ZAZYの衣装もピンクだっ・・・!!!←)
ところが、悲しい哉、落語ファンの人口区分は、
定年前後以上のおじさま・・・70%
アラフォー以上のお姉さま・・・20%
その他・・・10%
※さや香調べ
で構成されているのだ。
どうにかして、ポンキッキーズ世代より年上の“10代20代のタピオカ世代の女の子”にまでダイレクトに届けば良いのにと思う。
セミヌードでシーツにくるまり『anan』の表紙でも飾ると若い女子により届くのだろうか。←
もっと、若者文化に馴染み深いライブハウス とかでたくさん高座を打てばいいのにね。ネイキッドロフトでもトーク会だけでなく、落語をもっともっとすれば良いのかも。
そういった点では、志の輔師匠には、『下北沢』『本多劇場』『渋谷』『PARCO』という若者が敏感に反応しそうなワードを纏っているイメージが強い。
『笑点』や『成金』に好意的でない往年の落語ファンが少なからずいることは知っているけども、彼は、彼岸と此岸を分かつ三途の川に架け橋を築いた功労者だと思う。
彼らは、大衆から見て非常に“わかりやすい”のだ。
うん。そして確かにあの頃の『でんぱ組.inc』もわかりやすかったのだ。
「生きる場所なんてどこにもなかった」という直接的な歌のタイトルは、メンタル弱めな引きこもり気質のオタクたちにわかりやすく響いたのだ。
「こんなかわいくてキラキラしたアイドルが実は僕と同じ境遇や気持ちで居たんだ」って思ったら、励まされて好きになっちゃうよね。
あ。誤解していただきたくないのは、
「落語界ももっと“キラキラ、チャラチャラ、ウェイウェイ、ポンポーン!”しなよ」
と言いたいワケではない。
ただ、落語界をもっと発展させるためには、「いつの間にか気付かぬうちにわたしの胸に落語がありました」とひとりでも多くの人に言わせるように、受動的な大衆に『わかりやすさ』を提示していかなくてはいけないんぢゃないかなと思う。
どんな業界でも、その『わかりやすさ』を『だれ』に『どう』示してゆくかを真剣に緻密に考えることが、ヒットへのカギになるのだと思う。
今の世に、『すゑひろがりず』みたいな古語を常用している人なんて居ないように、時代とともに、言葉も文化も価値観も変わる。
日本の素晴らしい古典芸能や日本の美しい伝統工芸が、廃れるか繁栄するかは、古いしきたりにとらわれ過ぎずに歴史ある良いところを守りながら若い世代への訴求力を高めつつ、時代の変化の波に上手く乗れることにかかっている。
“落語の外側”から入ってくるのに多少難儀するが、 “落語の内側”はシンプルでわかりやすいのに、知れば知るほど奥深く、様々な楽しみ方がある無限の可能性を抱えた宇宙である。
知的好奇心が旺盛で、自学自習が好きな自閉の気がある学者や研究者肌の人には堪らない世界だと思う。
・・・それでも、やっぱり未だ、落語はポップでもないし、キャッチーでもないんだけどね。
そして最後に・・・
今回の文章で『EXIT』と打つたびに、『EXILE』と打ち間違えそうになっていたわたしが居たことをここに記しておこう。
note編集部さんに
「#エッセイ 記事まとめ」 で
取り上げていただきました。
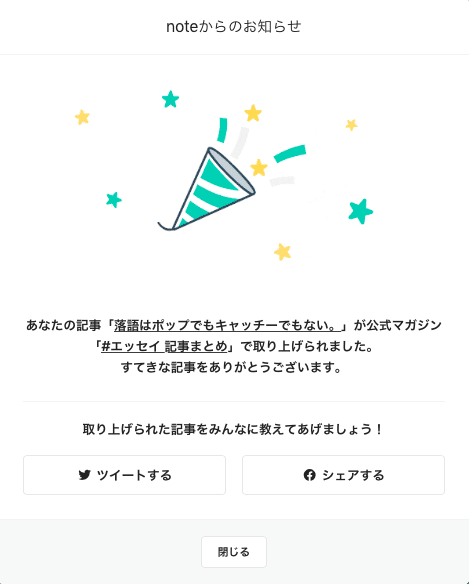
こちらもnote編集部さんに
「#おすすめ」 で
取り上げていただきました。
『わかりやすさ』の重要性を訴えているヤツの文章が、情報を盛り込み過ぎて、まさかのわかりにくい文章に仕上がりました。この哀愁に同情を覚えてくれた人は、『♡』を押して、Twitterフォローしてくれると嬉しいです。
いいなと思ったら応援しよう!